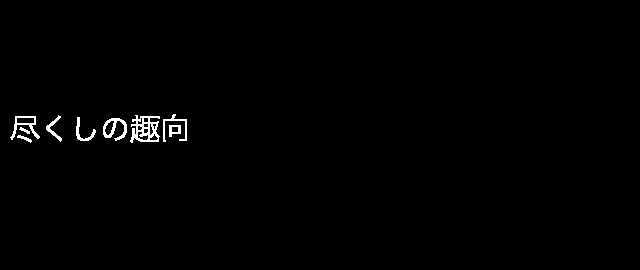1 網羅と同類--集成の原理
たとえば豆腐料理で有名な店に行くと、懐石風のコースに出てくる皿がすべて豆腐を素材にしていたりする。すると私たちは「お、豆腐尽くしだね」などと言う。よく考えてみるとこの言い方はおかしい。「尽くす」という語の本来の意味は「尽きた状態にさせる」こと、つまり「余すところなく全て出しきる」ことであるはずだ。とすれば、「豆腐の在庫をすべて出しきる」か「知る限りの豆腐料理をすべて出しきる」のでなければ「豆腐尽くし」とは言えないはずだ(どちらにしても食べきれないが)。しかし実際には私たちは「出された料理のすべてが豆腐を使っている」ならばこれを「豆腐尽くし」と呼ぶのである。ここから私たちは二つの「尽くし」の型を区別することができる。それぞれを「網羅」と「同類」と呼ぶことにしよう。たとえば『動物尽くし』という本があったとして、すべての動物を残りなく取り上げているものは「網羅」型の尽くしであり、数は少なくとも取り上げている事例のすべてが動物の類に属するものであるなら「同類」型の尽くしである。この二つはいずれも編集の原理となるものだが、その根底にある志向は異なるだろう。そして日本の「もの尽くし」のほとんどが本来の語義を離れて同類型であるのは、多分それを好む理由があるのだろう。だがそれはいったい何か。
すべてを網羅したいという欲求は確かに私たちにある。辞書や事典、全集やカタログは網羅を目指す。網羅しきれないまま世に出るのは、たいがい経済的あるいは物理的な外部条件による。考えてもみよう。一画家の全作品を網羅するカタログ・レゾネや既知の全漢字を網羅しようとした康煕字典などの編集作業は、想像するだけで気が遠くなる。だから現実には「おおむね網羅」や「主なものの網羅」で足れりとすることが多い。けれども残りなく所有したいという欲求が編纂の動機であることに変わりはない。その背後にあるのは、世界のすべてを知りたいという欲求である。これは博物学や歴史学や自然科学などの根底にある欲求でもあるだろう。網羅型集成においては「全て」ということそのものが価値である。項目の一つ一つがいかなる価値を持つかは問題ではない。康煕字典中の個々の文字の間に価値の優劣はない。動物図鑑であれば、ほとんどの人が関心を持たないような動物までも貴重な動物と同じ待遇で掲載していることが要求される。個々の動物の価値よりも、欠落なく「尽くしている」ことに網羅の意義があるのだ。
もっともどれほど膨大な動物図鑑といえども、存在する動物の全個体を記載するわけにはいかない。そこで網羅の場合には、何らかの基準で「全てを尽くしている」ならばよいということになる。ここに編者の網羅の基準、つまり対象をどのように把握しているのかという、物の見方が重要になる。たとえば動物図鑑であるなら、編者はまず動物を何らかの基準で分類し、さらにそれを下位分類してツリー状の系統図を作り、すべての末端の項目について必ず一つ(雌雄老幼を問わず)図像を載せるというやり方をとるだろう。もし分類された項目に図例がなければ、それは網羅から落ちた空白である。読者がこの分類に納得し、かつ空白がなければ、この動物図鑑は必要な観点での網羅を尽くしたことになる。分類基準はなんでもいい。時代別、地域別、サイズ別でもいい。逆にこの分類がでたらめだと、読者は「これで網羅ができるのか」と不安になるだろう。
同類の集成は全体ではなく共通の特徴への関心から始まる。私人のコレクションはこれが多い。たとえば馬の好きな人が馬に関する事物の収集を始めると、馬の絵や写真から書籍、置物、さらには馬の名を冠したウイスキーから果てはぬいぐるみやキーホルダーにまで及ぶかもしれない。網羅の場合はあらかじめ全体の枠が見えており、それゆえ集成はあるとき全体に達して終わりがくるが、同類の場合はこれで全体を尽くすという限界がない。馬面の人の顔や一瞬でも馬の登場する映画や漫画にまで広げれば収集の範囲はいくらでも広がる。それは和歌の世界の縁語に似ている。連想関係(縁)がある言葉というだけの条件では、縁語はいくらでも増やしていくことができる。ある語の縁語の全体はあらかじめ決めることができない。
網羅は「全て」であることに価値がある。それゆえ個々の品目は等価である。しかし同類の集成では個々の品目に価値の差がある。たとえば「珍重」という言葉があるように、珍しいものはそれだけで価値をもつ。それゆえ収集家はありふれたものを売り払って珍しいものを購入することがある。美術品の収集の場合は「名品」であることが関心の中心となることさえある。つまり「名品」と呼びうるものの集合を作ろうとするわけである。これは一種のアンソロジーの形成であるといってもよい。アンソロジーは全体をめざす網羅とは異なる関心で作られる集成である。アンソロジーにおいては、作品一つ一つの価値が重要であり、したがって編者の眼力が問われるだろう。その代表が百人一首であり、日本の王朝が国家事業として力をそそいだ勅撰和歌集であった。これらは歴史上の全作品を網羅するものではもちろんなく、一作家、一時代の作品を網羅するものでさえなく、編者の視点から名作と思われるものを集めたアンソロジーであった。
美術館のコレクションを例にとろう。ボストン美術館の日本美術コレクションをみると、その収集の方針は時代様式別に典型的作品を揃えることのようである。これによって、ボストン美術館の所蔵品を見るだけで、日本美術史の全体を様式史の観点から把握することができる。即ち、編集の原理は網羅であり、編者の観点は様式史として美術を見ることである。膨大な日本美術の全体は、時代別の様式にもとづいて分類され、観客はこの分類に従って全体を構造的に理解することになる。これに対し、ある日本の私立美術館では、泰西名画と古典日本画と世界の現代美術とが脈絡もなく同居している。全体的知識を与えるのが美術館だという考え方に立てば、これはまるででたらめである。しかし編集の基準がないわけではない。どうやらそれは、それぞれの分野で作家が有名であることである。多分創立者である富豪がコレクションを始めたとき、「名品」を揃えようと思ったのだろう。しかし本当の名品はなかなか市場に出てこない。そこで「有名作家」の作品なら名品とみなしていいだろう、という方針をとったのだと思われる(ひょっとしたら「値段」が高ければ名品とみなそうと思ったかもしれない)。つまり有名作家という同類で作品群は一括することができる。これはアンソロジーのひとつのやり方である。個々の作品の価値が高ければ、全体とか構造とかいう観念は必要がないのだ。
こうして収集あるいは編集の基準には網羅型と同類型がある。たとえば馬を主題に展覧会を企画し、すべての馬の種を画像によって提示するならこれは網羅型である。集められた絵画の全てに馬があればこれは同類型の「馬尽くし」になる。両者はどう違うのか。網羅型の場合、個々の作品よりも、その作品群が属する世界の構造を明らかにすることに主眼がある。だからこそ、まず「全体」という枠組(例えば生物学的種差の観点から見た馬の世界)が設定され、ある原理に従って分類され、規則に従って配列され、空白がないように埋めつくされるのだ。空白がないとは、世界が正しい秩序で構築されていることの証明である。個々の画像に要求されるのは、芸術的巧みさよりも、馬の種差を明確に示すことであろう。網羅の場合は個々の事例を超えて、全体としてどのような秩序が見えてくるのかが重要である。観客や読者がそこに一つの世界を構造化して認識することができれば、その集成は成功なのである。
これに対し、名品や馬絵画のアンソロジーの場合、観客の関心は「名品を見ること」「馬の絵を見ること」にある。そこでは「名品の世界」や「馬の世界」の全体は問題にならず、眼前の作品の一つ一つの出来ばえや面白さが問題になる。名品や馬といった共通課題に個々の品がどれだけ答えているかが関心の対象となるのだ。「もの尽くし」とは一定の課題のもとで編者の「眼鏡に叶った」事例を多数集めたものである。事例の価値は(面白さは)観客又は読者の期待や予想との相関で決まってくる。そこから、期待に見事に応えたり、期待を超えたり、意表を突いたり、予想を裏切ったりといったゲームの面白さが価値の中心となることもある。職人尽絵の作者と読者、豆腐尽しの料理人と客の関係にはそれがみられる。近松の『心中天の網島』の「橋尽し」の詞章もそうだ。聴衆は大阪の橋の名の数々が、掛詞によっていかに道行の言葉に詠み込まれていくかを固唾を呑んで聞き入っている。橋の名というのは課題であり、制約条件である。これを見事に切り抜けて行く近松の言葉の芸がここでは鑑賞されているのだ。
この関係を利用したゲームの一つに、中世に流行した連歌がある。初期の連歌には賦物という課題があった。たとえば源氏五十四帖の巻名(桐壺とか明石とか)を詠み込む、あるいは国の名(大和とか武蔵)を詠み込むというのがその規則である。これらは「源氏尽し」「国尽し」の歌づくりだといってもいい。掛詞を使って「夢の浮橋」といった難しい言葉を巧みに詠み込めば、会衆からやんやの喝采をうけるだろう。会が終われば百韻の歌巻が残るけれども、それは全体として作品とはみなされない。注目されるのは、鮮やかに課題を切り抜けた個々の句作の手並みなのである。
2 曼荼羅と散らし--配列の原理
網羅と同類とでは項目の配列に違いがある。配列にも、時間的秩序とでもいうべき順序と、空間的秩序である配置(レイアウト)とがある。
網羅の場合、項目の順序は明確な基準に従うのが常である。項目間に価値の差がある場合には、それは序列という形になる。たとえば相撲の番付。もっとも、必ずしも常に価値の序列が配列の順序に一致するわけではない。日本の場合、映画や演劇の出演者リスト(クレジット)は、主演者はたしかに冒頭に来るが、主演以外でもっとも格の高い者は最後に置くという決まり事がある。項目の一つ一つに価値の差がない場合は、機械的に全てを並べうる基準に従う。五十音順が一番普通かもしれない。時代順もある。地名であれば北から南へということもある。これらの場合はむしろ、内容に関わらず外的な指標のみで配列することで、個々の項目間に価値の序列を見ないという編者の態度を表現しているともいえる。動物図鑑などの場合には生物学的分類が配列の基準となる。たいていの編者は近代的生物学の観点から動物の世界に秩序を見出しているからだ。この場合網羅的提示は、同時に編集が示す秩序によって、編者の抱く世界像の表現となる。
では同類の場合の順序はどうか。たとえば「職人尽絵」の配列になにか基準はあるのだろうか。少なくとも、そこには編者の職業観を表現するような秩序はみられない。いわゆる「順不同」である。むろん編者の好みや意図によって、恣意的な秩序に従って配列することもできる(というか、ふつう編者はその「順序」をどうすべきかに心を砕いているだろう)。しかし、見るものはその順序を「恣意にすぎない」ものとして、つまり一種の偶然とみなして、そこに意味を見出そうとはしないであろう。見る者の関心は一つ一つの面白さにあって、全体の構造や秩序には興味がないのだから。そして編者の順序の決め方は、多くの場合、世界の構築よりも出現順序の演出効果を意識したものとなるだろう(序破急とか意表をつくとか)。では豆腐尽しの料理が懐石の形式で出てくる場合はどうか。これは豆腐料理の世界としては順不同だが、懐石としては順序正しい。ここに構造の引用というものがあるのだが、これについては次章に述べる。
平面上のあちこちに要素を配する空間的配置では、網羅と同類の配列原理の違いはさらに見やすい。網羅の典型として曼荼羅がある。これは世界の全体を記号的に再現するものであり、図像の一つ一つが仏教の観点から見た世界の要素を、その大きさが個々の要素の重要性を、その配列が全体の秩序を表現している。それは作者の世界観の表現であり、これによって作者は世界に秩序を付与しているのである。これに対し、紋尽しや花尽くしの意匠では、何がどこにあるかはほとんど偶然としか思えない。内容に従う序列もなければ、外形特徴からくる順序もない。むしろあえて秩序を感じさせまいと配置を計算しているかのように見える。曼荼羅のような配置の意味が明確なレイアウトとはデザイン原理が違うのである。このような意図的に秩序を排したデザインを日本では「散らし」と呼ぶ(だから「紋尽し」は「紋散らし」ともいう)。ちょうど木の葉が地上に散り敷いたときのような、人為を感じさせない配置である。これは一つの美意識と言ってよい。それは「偶然」あるいは「自然」の不作為の再現が目指されているのである。
このような偶然の装いは、網羅された要素の配列にさえ用いられることがある。私は源氏物語絵巻の断片を貼った六曲の屏風を見たことがある。屏風の各面には四ないし五の絵と文章の組合わせが貼ってあり、それぞれに「明石」とか「若紫」とかの題がついている。全部で二十七あったから、多分もとは六曲一双で五十四巻の全てを網羅したものなのだろう。私が驚いたのは、その配列が桐壺巻から始まる物語の順序に従わず、でたらめであったことだ。この作者には源氏物語の構造を正しく再現しようという意図がない。源氏はデザインの一素材にすぎないのだ。しかもよく見ると、絵を描いた紙と文字を書いた紙とは、ある場合は横に並べ、ある場合は縦にずらし、その組み合わせ方も一貫していない。各面に何巻分を貼るかも一定していない。つまりこれは源氏尽しであり、源氏散らしの屏風なのである。だからこそ、元来一双の屏風を分けて一隻だけ飾っても差し支えないのだ。源氏物語の全てを網羅する必要はないのだから。このように、本来は秩序をもって配列されたものを、わざと分断し、散らしてしまうのは、実は日本では珍しいことではない。たとえば古今集の写本を寸断し、その断簡を散らして貼り交ぜにしたり、ときにはたった一つの断簡だけを表装して鑑賞するのは古来の慣習である。これは曼荼羅を寸断して個々の仏像を拝むようなものだ。そこには信仰はあるかもしれないが、曼荼羅の表わす思想はないと言うべきだろう。とすれば古今集の断簡を飾る者は「古今集」という全体が何を表現しているかは、関心の外なのだろうか。そうではない。古今集は全体で一つの美の世界を構築しているが、その断簡は古今集の歌の事例を示しているのであり、事例とは部分で全体を代理するものである。さらに古今集は「歌の道」という人為的世界の全体を代表している。それゆえ床の間に飾られた古今集の断簡は、いわば歌の道という風雅の世界から送り込まれた全権大使となるのである。それは現代の空間を一挙に古典の場に変える。これを媒介に主人と客とはともに「風雅の場」で対面していることを意識するであろう。
網羅の思想は全体を構造化して提示しようとする。例示の思想はいくつかの事例で全体を代表させようとする。前者では全体は明示的に現前し、後者では全体はただ事例によって代理される。例示は全体の構造をではなく、それが属する世界の特徴(雰囲気とか様式とか)を直接触れさせる。事例は偶然に選ばれたものと見えるほうがよい。選択に編者の意図が入り込むとき、見るものは世界そのものよりも、編者の世界観を見ることになるからだ。偶然に選ばれた事例が複数あるときそれらは同類であり、それらの間に秩序はない。とすれば、事例の配列はまた秩序をもってはならない。配列になんらかの秩序が見て取られるとき、そこには編者の意図が現れてしまうからだ。個々の事例は、あくまでも同じ世界に属する同類という以上の意味を帯びてはならない。もっともよい配列は偶然を原理としたもの、すなわち「散らし」である。
「散らし」という配置は秩序を表現しない。その代わり、部分が全体と同じ特徴をもつことができる(フラクタル図形のように)。曼荼羅を切断すれば、それはもはや曼荼羅ではない。世界が表現できないからだ。曼荼羅を複数接合すれば無意味になる。一つで既に世界の全体であるのに、複数化すればそれぞれの世界が「全体の一部」に格下げされ、相対化されてしまうからだ。しかし散らされた模様の屏風や着物を切断しても、その断片の模様は依然として「散らし」である。また断片を無作為に接合して巨大化しても、これまた依然として「散らし」である。見えない全体を代理する部分である。人はそこに世界の全体を見るのではなく、いわば世界に触れるのである。散らされた要素が実は全体を網羅していることはあるだろう。先にあげた源氏物語の貼り交ぜ屏風は六曲一双で五十四帖の全てを尽くす。しかしその配列が「散らし」の原理に従うとき、見るものは子細に全体を検討したりしない。ただ「源氏物語」の世界に触れるための媒体として受け止めるのである。だから半分の一隻になっても、さらにそれを寸断しても、その意義は変わりがない。
職人尽の最初といわれる「東北院歌合」の五番本では判者を含めて十一種の職人しかいない。はじめから職人の職種を網羅することなど考えていないのだ。作者である貴族にとって、職人の世界は異世界であり、この世界をいくつかの事例によって代表させればよかったのだ。読者(これも仲間の貴族階級が想定されていただろう)はここに確かに俗なる世界が(雅の世界のパロディという形式で)表現されていることに興じたのである。
世界に触れるという経験では、世界全体の構造(分類や秩序)はどうでもよい。その世界の雰囲気とか感触とかが確実であればよい。だからこそいくつかの典型的事例でよいのだ。その配列も、断片らしく順不同、散らしでよい。職人尽も順序になんの秩序もない。職人尽は後代になるほど職人の数が増えてくる。しかしいくら増えようと、決してそれは全体には至らない。多数の事例であって、網羅ではない。読者は依然として、一つ一つの番いの組み合わせ方や歌や絵に籠められた趣向を楽しんだのである。それは目的地のない旅人が、途上で出会う光景の一つ一つを楽しむのと似ているだろう。出会いとは常に偶然なものであり、あらかじめ予期できるようでは面白くない。「もの尽し」の面白さはまさに偶然の出会いの面白さにある。そこで楽しまれるのは、作者の世界観などではなく、細部の趣向である。
3 世界と趣向--構造の引用
歌舞伎の作劇法では、昔から「世界」と「趣向」という言葉がある。「世界」は台本のコンテクストとなる周知の物語であり、「勧進帳」は「義経記」を、「仮名手本忠臣蔵」は「太平記」を世界としている。新作を作る場合、座主や作者や役者が顔を揃えてまずこの世界を決めることから始める。これを「世界定め」という。「趣向」とはこの「世界」に新たに導入される工夫であり、観客の意表を突くような着想が望ましい。たとえば曽我兄弟の物語を世界とする場合、孝子武人の鏡とされる曽我五郎を色男にして吉原に遊ばせよう、扮装も荒事のいかにも強そうなものではなくすらりとした着流しで、しかも病人のような鉢巻きをさせてみよう、というのが趣向である。ただし滅法強いという曽我五郎の基本特徴は変えられない。そこで色っぽい五郎が大もての吉原で啖呵を切る「助六」が誕生する。もととなる「世界」はいわば古典正統の世界であり、趣向はここに俗なる諸事象(とりわけ吉原文化)を重ね合わせることである。いわば観客は吉原尽しの舞台の向こうに、聖なる武人の仇討ちの世界を透かし見ることになる。助六が実は五郎であることが明らかになるときの操作を「見顕し」という。「見顕し」とは、悪人と見えたものが実は善人、身近な庶民と見えたものが実は高貴な人といった二重構造が明らかになる仕掛けである。これが面白いのは、聖と俗、あるいは雅と俗といった価値の序列をまるでパロディのように切り崩すからである。
同様の不謹慎な仕掛けに「見立て」がある。聖なる世界や雅の世界を見立てによって俗な世界に置き換える趣向は江戸文化の一つの特徴である。石川淳はこれを「やつし」あるいは俳諧化の操作と呼んだ(「江戸人の発想法について」)。石川はもっぱら文学の例を挙げるが、これは江戸文化全般に見られる傾向である。たとえば春信の浮世絵において中国の「瀟湘八景」は江戸の「座敷八景」となり、「遠帆帰帆」は「手拭かけ帰帆」となる。翻る手拭いが瀟湘の舟の帆に見立てられているのだ。作者による「やつし」(俳諧化)の操作は、聖地を遊廓に、名士を庶民や遊女にとその姿を世俗化する。見るものは「見立て」の操作によって、俗なる事象に聖なる意味を読み込んで楽しんだのである。
釈迦が入寂するとき、横たわった釈迦を取り囲んで菩薩や羅漢から動物たちまでが嘆き悲しむさまを描いた涅槃図という形式がある。伊藤若沖はその形式を借り、釈迦は大根に、その他人物禽獣のすべてを野菜や果物に置き換えた「果蔬涅槃図」を描いた。若沖は青物問屋の元主人である。一八一五年の展覧会の目録には「青物尽ねはん像」と記されているそうだから、これは江戸時代にはもの尽しの絵と見なされていたわけである。狩野博幸氏によれば「大根は、禅家においては“仏”のイメージを示すものであった」という(若沖展図録、二〇〇〇年)。釈迦が大根なら他の菩薩や動物だって青物になるだろうと考えたのが、青物尽しの趣向のもとだろう。若沖の意図はパロディではなく大まじめだったとする研究者もいるが、本当のところはわからない。ただ有名なこの絵が江戸時代の人にどう受け取られたかは容易に推察できる。よく知られた涅槃図という聖なる絵画形式を引用しつつ、聖者を野菜にやつして「見立て」の趣向を楽しむものとみなされたであろう。
貴族の風雅な歌合を俗な職人にやらせてみようというのも同種の趣向である。職人歌合というフィクションは、この雅俗を重ね合わせる趣向を楽しもうという貴族によって創られた。こういう趣向が生きるためには、職人歌合の外形はできるだけ本物の歌合と同じにしなければならない。そこで彼らには「月」と「恋」という典型的な歌の題が与えられ、作法に従ってもっともらしい歌が読まれ、判者が設定されて本物同様の規範にしたがって批評と判定がなされる。つまりあたかも職人たちがおおまじめで歌合をしたかのように作られる。ただ一つの異様な条件を除いて。それはどの歌も作者の職業を反映していることである。内容においてその職業を想起させるか、言葉において職業独自の用語を掛詞などで織り込んでいる。これは実際に職人が歌を作るときにはありえない。題を与えられて歌を詠むときには、個人的生活に関わりなく和歌としてよい歌を詠もうとするのが習いである。このとき参照すべき世界は、古歌の中の風雅な世界であって、日常の現実ではない。むしろ日々のなりわいなどは、排除すべき世俗的話題であり、風雅な歌の道にはふさわしくないものなのだ。そのふさわしくないことを、だからこそわざとやってみようというのが趣向なのである。外形は雅のふりをしつつ、いかにして俗な内容や言葉を組み入れることができるか。歌の場合には掛詞という便利な操作があって、二つの世界を表と裏に同時に持つことができる。絵の方は三十六歌仙などの歌仙絵の形式が借用される。俗なる職人たちがあたかも聖なる歌仙のように描かれるのである。こうして職人歌合という趣向では、歌の道という雅の世界と職人の俗の世界とがどのように重なるかが見どころとなる。
歌合は貴族の風雅なイベントの代表であるから、やつしや見立てに絶好の題材である。一五世紀の御伽草子『十二類合戦物語』は十二支の鳥獣が鹿を判者に月を題として歌合を催すところから始まる。やがて話は多くの鳥獣を巻き込んだ合戦となり、最後は狸の出家遁世と和歌への執着を語って終わる。人間界の雅・武・聖の世界が動物によって演じられるわけで、まさに俳諧化の趣向といえる。この絵巻は、しぜん動物尽しの絵となる。さらに奇をてらう趣向としては、家具に歌を詠ませる調度歌合などもある。現在でも落語の大喜利などで、誰かに成り代わって一言などといった趣向があるが、私は昔の貴族たちも集まっては職人だの動物だのに成り代わって歌を詠むという遊びをしていたのではないかと想像している。この操作はパロディに近い。
若沖の「果蔬涅槃図」にせよ職人尽にせよ、春信の「座敷八景」と同じ構造をもっている。それは参照される原形を古典の雅の世界に採り、その項目を俗なる事象に置き換える操作である。それは歌舞伎における世界と趣向の操作に似ている。観客ないし読者は現前する俗なる光景の背後に、聖あるいは雅の世界を重ね合わせるのである。ただし歌舞伎における世界と趣向の操作と必ずしも同じでないのは、参照される世界からその構造を借用する点である。横たわった釈迦を中心とする涅槃図の構図、あるい歌合という形式、そして「帰帆」や「夕照」といった八景の構成。このとき、構造を構築する個々の項目は俗なるもので一貫させる。すなわち、青物尽し、職人尽しといったふうに。目に入る俗な項目が全て同類であるとき、構造だけが聖であり雅であることがいっそう際立つだろう。こうして聖俗、あるいは雅俗の対立が鮮やかになる。懐石料理の形式で出される豆腐尽しが趣向として成功しているのも同じ理由による。それは単に聖なるもののパロディではなく、聖なる世界の構造と、俗なる世界の同類の集成という二つの制約条件に応えた作品なのである。逆に言えば、同類の集成を提示するにあたって、その内部的秩序(五十音順とか価値の順)ではなく、外部の、それもまったく無関係な世界から構造を借用しているわけである。野菜を並べるのに涅槃図の形式は必要ではないし、実際八百屋はそんなことはしない。職人を並べるのに歌を詠ませる必要はないし、まして歌合を演じさせる必要はない。つまりもの尽しは、内部の秩序に意味がないため、散らしの配列をとることもできるが、趣向として外部から配列の秩序を借用することもできるのである。その場合、この種の趣向の常として、日本では聖なる世界、風雅の世界から構造を借りてくる。それは「見立て」や「やつし」と同じく、価値の異なる二つの世界をわざと重ね合わせるという、われわれの伝統的文化手法からくるのである。