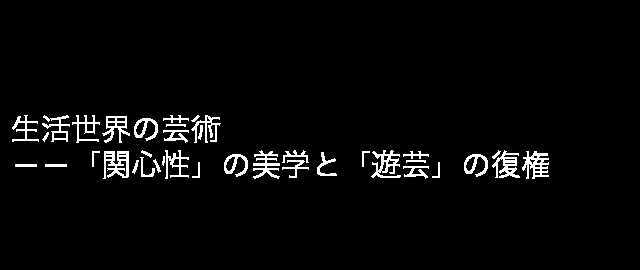久しく日本の芸術関係者たちは政府や自治体が予算面でも制度面でも芸術支援に熱心でないのを嘆いてきた。長い紆余曲折を経て、2001年にようやく芸術支援のための法案が議会を通過した。しかしこのとき違和感を持った人は少なくないだろう。それは「芸術」だけを支援するものではなかったからである。まず名称が「文化芸術振興基本法」であり、その対象には「文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術」だけでなく「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」を、また「雅楽、能楽、文楽、歌舞伎」に加えて「講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能」を、さらには「生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をいう。)、国民娯楽(囲碁,将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等」までが含まれていた。さらにこの法は、芸術家の創作活動を支援するだけでなく、アマチュアの趣味的活動の支援を定めていた。第二十二条は高齢者・障害者等が行う文化芸術活動に必要な施策を講ずることを求め、第二十三条は青少年の文化芸術活動の、第二十四条は学校教育における体験学習の、第二十七条は各地域の市民に身近な文化芸術活動の場の充実を図ることを求めていた。これは「芸術」の範囲を娯楽やアマチュアの趣味にまで拡大しようということなのだろうか。それとも芸術は娯楽的文化の一部に過ぎず、国が振興すべきは芸術を含む娯楽的文化のほうだということなのだろうか。いずれにせよ、ここには従来の芸術/非芸術の区分が曖昧となった現状が反映している。
18世紀西欧に誕生した「芸術」という観念と制度は、20世紀の終りに「芸術の終焉」論が盛んになったことからも明らかなように、制度疲労を迎えた。しかし「芸術」という言葉とこれにまつわる制度はなくなるどころか、新たな政策や民間支援の対象となり、人々の芸術への関心はむしろ拡大したとさえ言える。ただ、そこで語られ、想定される「芸術」が、旧来のものよりも広がってきているのである。専門家が「芸術の終焉」を語る一方で、一般人はむしろ「芸術」に意義を見出し、それを身近なものにしたいと望んだ。このとき人々の語る「芸術」と専門家の使用する「芸術」の語のずれが生じたのだ。「芸術」という制度を社会現象の一つとして見るとき、私たちは「芸術」の再定義を、あるいは少なくともその範囲の再考を行わねばならない時期にある。
芸術が滅びないのは一般の人々が芸術になんらかの存在理由を見出しているからだ。ではそれは何か。昔から西洋においても中国においても言われてきたのは道徳教育効果である(didacticism, l'art pour la vie)。日本では本居宣長が「もののあはれを知る」ようになる効果をあげた。これは美への感受性や他者の心への共感能力を高めるというものである。ほかにもいろいろあるけれども、共通しているのは、芸術は人の心を動かすことによって何か(認識とか思考法とか)を変えるということである。とすれば芸術家は人の心を動かす専門家であるということになる。じっさい、現代の一般人が芸術に期待しているものは、なによりも感動であるといってよいであろう。
だがこの論法には問題がある。第一に、現代芸術はほとんど感動を目的としていないという現実である。このことは現代美術館や現代美術展に行ってみればすぐわかる。第二に、感動を与えて人の心を動かすのは芸術の専門家による作品に限らないということである。
1993年アメリカのカリフォルニア州で強姦殺人の裁判があった。その法廷で、被害者の母が自分でビデオを編集して被害者の19年の人生を20分ほどにまとめ、エンヤの音楽と自分のナレーションをつけて陪審員に見せたところ、死刑の票決を得た。これに対し、殺人事件の審理は理性的に行われるべきであり、感情に訴えるこのようなビデオを見せることは適当ではないという批判がおきた。実際この審理方法については改めて裁判で争われたのだが、結局最高裁はこのビデオ使用を合法とした(日本の裁判員制度でもこのようなビデオが被害者側の意見陳述に利用されるのではないかと言われている)。ビデオを編集した母親はプロではない。またこれを「芸術作品」と呼ぶことにはためらう人のほうが多いだろう。しかし一流の作家が同じ素材を小説や映画や演劇に仕立て上げても、おそらく母親のビデオをしのぐ効果を陪審員たちに与えることは難しいだろう。ただのフィクションとしてなら不幸な物語に涙を流して感動する人も、現実に一人の人命を奪うかどうかを託された陪審席では感情に流されまいとする意志が働くことが知られており、むしろ感情の誘導を意図した作為的表現には反発さえ起きるからだ。けれども、母親が見せたものは「作品」としてではなく、全て「事実」の記録として受けとめられ、陪審員たちはその事実性に心を動かされたのである(エンヤの使用は被害者の愛した音楽だからと説明された)。このことが示しているのは、人に感動を与えて心を(そして考えを)動かすのはプロの芸術家による「芸術作品」に限らないということである。
母親の法廷用ビデオを「芸術」と呼びがたい理由はいくつかある。第一に、もともとこれが私的記録にすぎないということである。芸術とは見知らぬ他者からなる公共世界に向けて発信された作品であり、芸術家の創作であるというのが私たちの通念である。だから抽斗のアルバムの中の写真は持ち主には大切な人生の思い出であるとしても、公共性もなく創造性もない私的記念物にすぎない。個人的にはかけがえのないものかもしれないが、普遍性をもつわけではないから芸術的価値を問われたりすることはない。ときにそれらを臆面もなく他人に見せる人もいるけれども、たとえば年賀状に印刷された子供の写真を私たちはふつう「芸術」とは呼ばない。作品としての美的レベルが低いからというより(実際たいがいは低いのだが)、近代の「芸術」という制度の中にその席がないからである。私たちの文化では年賀状は「社交」の一部である。お辞儀がどれほど優雅でも、葬儀のスピーチがどれほど感動的であっても、私たちはそれを「芸術」には分類しないことになっている。同様に法廷用ビデオは「証言」であって、「芸術」ではない。
第二に近代的芸術観は芸術を何かの手段としないという自律性を特徴としている。近代に「芸術」という制度が立ち上がってほどなく、芸術は宗教の普及や政治的啓蒙や道徳教育のための手段ではなく「芸術のための芸術」であるとされた。芸術の存在理由を何かの「手段」であることに求めると、当然ながらその「目的」の方が重要であるということになってしまうからだ。芸術は何ものにも奉仕しないという宣言は、芸術以上に重要なものは認めないという一種の信仰の表明でもあった。もとのフランス語(l'art pour l'art)やその英訳(art for art's sake)では「芸術のための芸術」であるのに日本で「芸術至上主義」と訳されたのは、芸術の上に主人を作りたくないという動機をよく示している。しかし母親の証言ビデオは明確な目的を持っている。制度上の目的は陪審員の票決のための判断材料である。だが母親の目的は娘の人生を客観的に要約することではなく、陪審員から被害者への同情と加害者への怒りを喚起することにあっただろう。つまりプロパガンダである。創造性を問われる立場の芸術家なら余りにベタだと使用を躊躇するエンヤの音楽を用いたのも、目的にかなっていたからである。そして成功したのである。もし誰かが母親に、芸術的にはエンヤはやめたほうがいいとアドバイスしたら、彼女は「私は芸術には興味がない」と答えただろう。
芸術の自律性という信仰を裏から支えたのはカントの無関心性の美学である。カントは『判断力批判』において無関心性を美的判断の条件とした。無関心とは対象の実在を意識しないことである。たとえば空襲の経験談に、丘の上から炎上する町を見て美しいと思ったという話がある。火の下には自分の家が、そして自分の町があるのだが、一瞬それを忘れたのだ。美は、対象が実在することを忘れ、実際に自分や人々と関係があることを忘れた無関心性の中ではじめて現れるというのがカントの考えである。逆に関心による判断とは、カントの挙げた例を引けば、宮殿に対して「王侯の虚栄心のために人民の膏血でこんなものを作るのはけしからん」とか「自分は無人島に住んでいて誰にも会わないからこんなものは要らない」などと言う場合である。これらは善悪とか有用性とかが判断の規準になっている。宮殿を美しいと見るためには、倫理とか実益など通常の価値判断を忘れねばならない。言い換えれば、それが現実世界の中で自分ないし人々とさまざまな関係を持つことを忘れなければならない。美的判断とは、無関心性を保持しつつ、ただその形の特性のみを見て美しいとか美しくないとか言うことであるとされる。同様に、小説・映画・演劇などは虚構であり、読者・観客はそれが現実の自分と無関係であることを知っており、従って現実的関心をもつことなく物語を眺める。だからこそ純粋な感動が得られるというわけだ。不幸なヒロインを見ながら、この役者のギャラはいくらだろうなどと想像していてはとうてい深い感動は得られない。
だが法廷での母親のビデオを見る陪審員は正反対である。ビデオは証言の一部であり、自分はそれに基づいて被告への対処を判断しなければならない。現実に人命を左右する権限を与えられたとき、人は無関心ではいられない。まさに関心のただなかで、加害者の行為の意味を確認するためにこのビデオは提示されたのである。幼い頃のスチール写真に始まり(まだ家庭用ビデオは普及していなかった)、やがてビデオが成長する少女を記録しつづけ、突然小さな墓の映像で終る。その墓石に刻まれた生年と没年を見るとき、あまりにも短いと思わずにはいられない。少女は映画スターのように美しくはないし、編集にはプロのようなモンタージュの妙もクライマックスもない。けれども陪審員にとって、被害者が抽象的な人名から具体的な実在になるのには十分だった(つまり「関心」の対象となった)。家族とまでは言わなくとも、知人ていどには被害者は実在する人間となった。そして彼女が19歳で人生を終らねばならないことの不条理と、とつぜん娘を奪われた母親の悲哀とが陪審員に実感されたのである。現代人の多くは、これは芸術的感動とは違うと言うかもしれない。しかし古来詩の存在理由として道徳的判断の涵養が主張されてきた。もし人の心を動かして善悪の正しい判断に至らしめることが芸術の存在理由の古典的理論であるとするなら、このビデオはまさにその条件を満たしてはいないだろうか。
カントの美学はもっぱら芸術作品の形式を見て内容を無視するものだとして形式主義美学とも呼ばれた。たしかに彼の理論が一番あてはまるのは抽象美術と自然だろう。形式主義の美術批評家は、内容など美術にとって狭雑物であるから排除すべきとし、抽象美術を本来の美術だとして20世紀後半に影響力を持った。しかし実際の芸術にはたいがい内容がある。とくに文学・映画・演劇などは。形式主義的芸術運動が1970年代のミニマリズムで行き詰まり、80年代のポストモダンの時代を経たあと、芸術の世界は政治的内容を籠めるものが多くなる。そしてその傾向は今なお続いている。これは形式主義への反動としてということもあろうが、ポストモダニズムによってそれまでの価値規範が効力を失い、「芸術のための芸術」への信仰が揺らいで新たな芸術の価値づけが必要となったとき、芸術そのものをいくら掘り下げても自律的な存在の根拠を見つけがたいという事情があるだろう。だから社会や根源的衝動などについての知見ないし思想を「内容」とすることが芸術の方法として普通になっている。ただ内容とするだけでは論文や記事と区別がつかない。だから芸術は感性への作用(典型的には「感動」)を利用してその内容を訴えようとする。ということは、実質的に証言ビデオと変わりはないということである。
ダントー、ディッキーに始まった芸術制度論は、今や芸術研究者の間では共通の前提となっている。芸術は文化的制度の一つであり、何が芸術であり何が芸術でないかの境界線は時の制度によって偶然に引かれているだけで、必然性などありはしない。証言ビデオが「芸術」ではないのは、ただ現行の制度ではそうだというだけであって、もし制度が変われば「芸術」の分類に入っても不思議はない。じっさい「芸術」の範囲は拡大してきた。明治時代には書が芸術であるか否かの論争があったが、現在書道家を芸術家といっても誰も反対しないだろう。かつて「大衆芸能」と呼ばれて真正な芸術とはみなされなかったものが「大衆芸術」となり、芸術祭の演目となり、芸術関係の賞の対象となり、いまや「芸術」の一部として扱われることに誰も違和感を覚えなくなってしまった。「商業美術」と呼ばれて純粋な芸術とは一線を画されてきた広告宣伝の作家たちは今では「クリエーター」と呼ばれて創造力を評価されている。子ども向けと軽んじられてきたマンガやアニメも国際映画祭で受賞するなど芸術的価値を認知されている。レストランのシェフやパティシエに対する世間の態度は今や芸術家に対するのと変わりがない。20世紀末のいわゆる「芸術の終焉」現象は、既存の制度管理者としてのアート・ワールド(芸術専門家・関係者集団)の役割を弱め、代わって一般人の関心を代表するマスメディアが何を「芸術」とみなすかを決めるようになり、「芸術」「作家」「アーチスト」「クリエーター」のインフレが起こったのである。
芸術のインフレ現象は別の面でも起こった。プロとアマの境界が薄れたことである。もともと日本では詩歌を代表として芸能は貴族らが自分で行うものであり、専門家の作品を鑑賞するだけのものではなかった。平安時代の日記や小説を見れば貴族たちが関心を持っているのは貴族自身による和歌、演奏、舞であって、プロのものではない。彼らにとって身分の低いプロなど出入りの職人か、精々が教師にすぎない。じっさい勅撰和歌集や百人一首に収められた作品のほとんどはアマチュアのものである。中国でも、代表的芸術である詩・書・画は作者の人格や気韻の反映とされ、画工(職人)の仕事よりも士太夫(アマ)の作品の方が高く評価された。技術はたしかにプロの方がうまいかもしれないが、大事なのは作者の内面だということである。作品評価の規準が技術よりも内容だということになれば、アマとプロの壁は低くなる。短歌や俳句において、素人がたまたま秀作を作り出すことは珍しくない。美術や演劇、舞踊においても同様である。じっさい、1990年代以降の演劇や舞踊における学生を中心とした小劇場とコンテンポラリー・ダンスの登場は、芸術への参入の敷居が低くなったことが理由の一つと考えられる。技術的には未熟でも、観客にとって面白いものはいくつもあり、やがてそれらは新しい潮流を形成したのである。マンガにおける同人誌の活動は周知のとおりコミケという場を得て拡大し、そこから生まれたコスプレなどは国際的文化現象として定着するまでになった。インターネットの発達はYouTubeやニコニコ動画といった巨大CGM(Consumer Generated Media 消費者発信メディア)を生み出し、アマチュアによる活発なUGC(User Generated Content ユーザー作成コンテンツ)制作活動が行われている。これらは既存の芸術制度の外側で行われているオルタナティブな文化創造制度となりつつある。
ここまで来ると、次の段階は容易に想像できるだろう。個人の生活の中にあるものの「芸術」化である。それらは実在し、自分の生活と関わっていることが美的判断の前提となっているという意味で、カントの考えた無関心な対象とは逆の存在である。これらを「生活世界の芸術」と呼んでもいい。既に生け花などは「生活芸術」と呼ばれることもあった。かつてインテリアであった絵画や、「お道具」と呼ばれていた茶器などが既に「芸術」の仲間入りをしている以上、他のインテリア(建築が芸術なら家具・照明器具などの工業デザインもそうなるだろう)、ガーデニング(庭園が芸術ならアマチュアの造園もそうだ)、料理(プロのシェフの料理が芸術なら家庭料理だって)なども一種の芸術として扱われるようになるだろう。もちろん、一般人が撮影した写真やビデオも例外ではない。
問題は、それらの評価規準である。技術水準だけを規準にするなら、プロとアマの差は歴然である。しかし内容を問題にするとき、事情は違ってくる。そして芸術的価値は普遍的なものだなどという前提を取り外し、観客・読者などの作品体験(感動の度合い)を規準とするとき、誰がどのような状況で体験するのかという条件の違いが芸術的価値に影響する。つまり「関心」の在り方が体験を左右するのである。生活世界の中の芸術の場合、一般的に関心が強い方が対象への没入や共感や感動が起こりやすい。前述の証言ビデオの場合、たぶん一番力を持つのは被害者の親類縁者などの関係者であろうが、陪審員もまた一般の視聴者よりも感動したに違いない。というのも、陪審員たちはこの事件について票決を下さねばならず、そのために被害者に対して「理解したい」という強い意欲を抱いていたからである。それはまさに被害者への「関心」であり、しかもその関心の強さは、通常の映画の観客が主人公に対して抱くものよりも強いであろう。芸術作品には普遍的な価値があるわけではなく、その都度の受容者の体験の深さ(感動の深さ)がその時々の価値として体験されるのだと考えれば、このビデオは、少なくともこの法廷の陪審員には優れた芸術であった。
だがこのように考えるとき、私たちの抽斗の中のアルバムの写真、昔の恋人からのラブレターなどが「芸術」の範疇に入ってくる。いやそればかりか、昔の旅行地で買った記念品、友人からのプレゼントなどが、人生の記憶と結びついて価値ある芸術になってしまう。それらはまったく個人的なものであって、他人には同じ価値体験を期待できない。そもそもそこで得られる感動は、自分自身の記憶から来るものであって、物品はその記憶を解発する引き金にすぎない。いわば古い日記の中の1行のようなものだ。ここまで「芸術」の範囲を拡張していいのだろうか。たぶん私たちはその用意をしなければならない時期に来ている。
東販と日販ともに、2007年度文芸書ベストセラーの1~3位をケータイ小説が占めたことは記憶に新しい。しかもこれらは宣伝の力というより口コミで売れたのである。理由は、既にケータイ上でこれに感動した読者が多かったからだ。インターネットで読者のコメントを見ると「感動の二文字では言い尽くせない」といった賛辞に溢れている。じつは専門家の見地から内容は陳腐、文章は稚拙であるというのが定評になっている。けれども、ケータイ小説の読者たちにとって評論家の「芸術的判断」などは眼中になく、確かに強く心を動かされる体験が起こったという事実だけが大事だったのである。他人にとってはともかく、自分にとってそれは芸術であったのだ。
ケータイ小説にあって従来の小説にはない特徴的類型が二つある。一つは書き手自身に小説であるという自覚のないままに私的な記録を綴るケースである。「私自身、小説だとは思っていなかったので、初めて〝ケータイ小説〟と呼ばれることを知ったとき、〝えっ、これって小説っていうんだ〟って驚きました」(美嘉)、「小説って意識がないってのはあるかもしれない。・・・文章を書いていると言うより気持ちを書き綴ったって思いのほうが強いね」(SINKA)などというケースがこれだ(『このケータイ小説がすごい』ゴマブックス)。そして公刊された書籍を読むのとは異なり、これをケータイの小さな画面でキーを押しつつ読み進める体験は、極めて私的な世界に没頭する行為であり、他人の内面を直接覗き見ているような感覚がある。つまり強い関心がそこには働いており、それだけ没入と共感の作用が強いのである。
もう一つは作者が読者の反応を見ながら次を書き進めていくケースである。それによってストーリーが変わることも珍しくない。ケータイ小説にはたいてい掲示板が付随しており、読者は即時にコメントを書き込むことができる。それは作者だけでなく読者も読むことができる。もし掲示板をケータイ小説という制度の一部とみなすなら、これは読者参加型のイベントということができる。つまりケータイ小説を読む経験は、完成された小説作品を読む経験とは内実が違う。作品が日々更新されていくのを追いかけるように読み、時には掲示板で自身の反応を書き込むうち、インタラクティブなイベントに参加する者に特有の共犯者的連帯感を感じるようになる。それはライブ公演の経験に近いだろう。これは従来の制度の中の「小説」ではなく、CGMにおけるUGCの一つなのである。従来の小説形式を規準にするなら、ケータイ小説は「芸術」ではない。しかし読者が実際に感動したこと、またはコンテンツ形成に参加してその生成プロセスを楽しんだという意味で、これらは新しい芸術形式の規準を満たしているとも言えるのである。
最初の問題に戻ろう。現在の文化政策で支援すべき対象とされているのはもはや古典的な「芸術」だけではない。私たちの生活の質を豊かにしうるために、私たちに感動や美的体験を与えるもの全てである。このとき芸術の範囲は生活世界の中の対象にまで広がり、人々は強い関心に支えられてそれを味わうのである。またそれは作品が一般人に対して与えるものだけでなく、一般人がその生成プロセスを自ら楽しむことを含む。つまり人々は単なる鑑賞者からアマチュア芸術家となり、みずから創造(二次創作やパターン化したものが多いとしても)やパフォーマンス(演奏・演技・演舞)を楽しむのである。
「芸術」のインフレは既に既成事実であり、法律もこれを認めている。私たちの芸術についての研究、思索、提言は、これを踏まえた上でなされなければならない。このとき私たちは、無関心性の美学ではなく、むしろ関心ゆえに深く心を動かす芸術の存在を認めなければならないし、また一般人の芸術への関わり方が受動的鑑賞から能動的参加へと変容したこと、日本の古い言葉を使えば「遊芸」として芸術に関わるようになったことを認めなければならない。それは現代の「芸術」の制度が「芸術のための芸術」(l'art pour l'art) から「人生のための芸術」( l'art pour la vie)へと変化しつつあることということであり、生活世界の外部にあって無関心に接しうるものから生活世界の内部にあって関心を向けられるものへと存在の様相を変えつつあるということである。私たちはそのような時代変化を前提に、新たな芸術理論を構築しなければならないのである。
Flying Cabinet