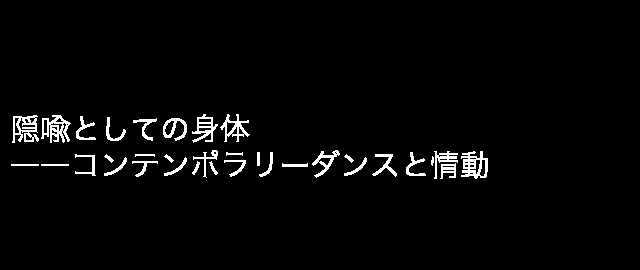序 ダンス概念の革新――舞踏とピナ・バウシュ
20世紀の前半、モダンダンスは西洋のダンスを革新しただけでなく、ダンスについての新しい概念を創造して世界に影響を与えた。その代表者はマーサ・グラハムであり、彼女がダンス界に提出した新しい概念は「表現」である。20世紀後半にもまたポスト・モダンダンスをはじめさまざまなダンスが「創造」され、新しい概念が提示された。それらは一括りにできないほど多用であるけれども、二つに大別できるように思われる。一つはダンス史という文脈(バレエなどの前近代からモダンダンスなどの近代へ)を踏まえ、それ以前のダンスを否定する形で構想されたもの。言い換えれば20世紀芸術の各分野で行われた芸術ジャンルの自己批評(反省)としての様式革新(前衛芸術)をダンス分野で行ったものである。もう一つは舞踊家が自分のやりたいことが従来のダンス形式ではできないため、結果的に新しいやり方を発明してしまったもの。言い換えれば作家の内的必然性から生れた創造である。
両者の作家はともに過去の様式を無視しているわけではない。前者は否定するために過去の様式を参照するし、後者は過去の資産が自分の目的に利用できるかどうか一通り調べてみるからだ。しかし両者の観客は大きく違う。前者の観客はダンスの(あるいは美術でも音楽でも)歴史を知らなければ、新しい作品のどこが面白いのかわからない。芸術ジャンルの自己批評としての新様式はその芸術ジャンルの歴史(あるいは系譜)を文脈として成立しているからである。一方、後者の観客にそのような知識は求められない。むしろ「芸術とはこういうものだ」という先入観を持たず、白紙で対面するほうがよい。前者が観客に与えるものが「新しい芸術」の面白さであるとすれば、後者が与えるのは人生についての特異な経験である。ヴッパタール舞踊団員であるジュリー・アン・スタンザックの言葉を借りれば「人間の経験を深めること」(deepening human experience)である(注1)。
後者の代表的作家として、「暗黒舞踏」を創造した土方巽と「タンツテアター」を再創造したピナ・バウシュとをあげることができる。この二人が20世紀後半においてとりわけ独創的な舞踊家であったことは多くの人が認めるだろう。それも新しさを追いかけていたらたまたま風変わりなものができたということではなく、二人とも自分が「やりたいこと」を明確に把握しており、意識的にそれを達成しようと努力し、そのために新しい身体利用の方法を発明し、その方法を反復して使用した結果、それらはクラシック・バレエやモダンダンスに並ぶダンスの新しい様式(スタイル)として世界から認められたのである。
暗黒舞踏とピナ・バウシュの作品は、外見上の大きな違いにもかかわらず、観客にとっていくつかの共通点がある。第一に、従来の演劇や舞踊を見馴れた者にとって、いずれも理解が困難だということである。いったい何をやっているのか、何を表現しているのか、何を伝えたいのか、既知の舞台芸術の見方ではわからず、途方にくれてしまうのだ。第二に、にもかかわらず、それらの舞台はしばしば観客の心に深く突き刺さり、ときには感動と言ってよいような経験を与えることである。それも「これは芸術でしか得られない」と思わせるような経験を。これはいったいどういうことだろうか。
芸術作品に対して、とりわけ20世紀の芸術に対して、「わからない」という言葉が発せられることは珍しくない。ではこの「わからない」とは何を意味しているのだろうか。たとえば暗号が「わからない」と言う場合、二つの意味がある。ひとつは暗号の意味するところが「わからない」という場合であり、これは発信者が伝えようとしている内容が理解できないということである。もうひとつは暗号解読の方法が「わからない」と言う場合であり、これは理解に至る方法を持っていないということである。多くの場合観客は内容が理解できない、ひらたく言えば「言いたいこと」がわからないという意味で「わからない」というのだが、じつはそれ以前に理解のための方法を持っていないのである。硬く言えば新しい芸術様式に適用可能な認識枠組を習得していないのであり、ひらたく言えば「見方」がわからないのである。
ではダンスの場合「わかる」とはどういうことだろうか。それは既知のダンスから学んだ認識の枠組(見方)を新しい舞台にあてはめて、そこにさまざまな意味や価値を見出すことである。それではダンスを見るさいの認識の枠組とはどのようなものだろうか。
まずダンスのジャンルの判別がある。これはバレエであるとか、盆踊りであるとか。次にジャンルに応じた認識の枠組がある。たとえばバレエであれば物語を踏まえた役柄とか筋書きとか。盆踊りであれば踊っているのが知り合いかそうでないかとか。さらにダンスそのもの、つまり動き(ムーブメント)にもジャンルごとに認識の枠組(注目すべき要素)が違う。バレエであれば回転とかジャンプとかの大技が抜きんでているか、バランスや安定性はどうかといった技術面があり、しぐさやポーズが優雅かかわいいかといった相貌的印象がある。この相貌には生得的な身体特徴(容姿)も影響する。ヒップホップであればアクロバット的な身体操作や動きの切れのよさが注目されるだろうし、タップダンスなら観客を引き込むようなリズム感が期待されるかもしれない。さらにバレエや日本舞踊のように特定の役名が与えられている場合には、どのような人格を演じているか、またそれにふさわしい雰囲気をかもしだしているかといったことも見られるだろう。私たちはこのような何重もの認識の枠組をあてはめてダンスを見、そして理解し、評価するのである。
暗黒舞踏もピナ・バウシュの作品も(とりわけ前期のものは)これらの認識の枠組がうまく適用できない。まず人々の見馴れたダンスらしい動きがないか、あるいは少ない。しかもアクロバット的な回転とかジャンプといったわかりやすい技巧もない。舞踏家もヴッパタール舞踊団のメンバーも日々身体的訓練を重ねており、決してアマチュアの素朴な身体ではないのだが、従来の見方ではうまく認識・評価できないのである。けれどもそこには身体の相貌と演技はある。暗黒舞踏の場合は異形と言ってもいい身体の相貌があり、ピナ・バウシュのダンサーには逆に見馴れた現代人の相貌がある。さらにピナ・バウシュの場合は演技さえある。コントのような短い演技ピースが次々と展開されていくのだ。ただし、それがどんな物語なのかはわからない。あるいはそれが何を再現しているシーンなのかさえわからない。むしろ夢の中の光景のように、現実にはありえないほど奇妙な、それでいてなつかしいような振舞いがコラージュされていくだけだ。これはいったいダンスなのか演技なのか。だがそもそも舞台上のある振舞いを「演技」と呼ぶための条件は何なのか。「ダンス」と「演技」とは両立不可能なものなのか。それとも両者は根底において一致するのか。ひょっとしたら暗黒舞踏とピナ・バウシュ作品の身体パフォーマンスは、新しいダンスであると同時に新しい演技なのかもしれない。とすれば、これらを「ダンス」という認識枠組だけで語ろうとしてきたこれまでの研究には見落としがあるかもしれない。私たちは新しい「ダンス」について語るためにも、「演技」というものについてもう一度考察をしなければならないと思われる。
コンテンポラリー・ダンスを分析するための視点はいくつもあるだろう。しかしここでは「演技」を再考するところから暗黒舞踏とピナ・バウシュにアプローチしてみよう。
1 演技術とレトリック
まず演劇において演技とは一般的にどういうものかという基本の反省から始めよう。演技というのは、役者Aが戯曲の登場人物Bと見えるように振る舞うことである。ただしそれは常に、設定された状況に対してあるキャラクターがいかに反応しているのかという形で行われる。演ずべきことがらは多岐にわたるが、観客に伝えるべき演技内容は主に三つある。第一にBが何者であるのか。つまりそのキャラクターは男なのか女なのか、老人か若者か、王子か農民かといった人物設定である(このキャラクターは古典劇においては類型であり、近代劇においては個性をもつ個人となるが、ここでは立ち入らない)。これは台詞や衣装などでも示される。
第二にBが何をしているのか。これは設定された状況に対してどう反応しているのかであり、行為の意味と言ってもよい。たとえば、ただ落ち着きなくうろうろしているとしても、戦場で戦闘準備をしているのか、裏庭で恋人を待っているのかでは様子が違うだろう。これも筋書きを説明する台詞やセットなどが支援する。第三にBの内面である。心理や性格と言ってもよい。役者は状況に対してどのように反応しているかによって心理や感情を示し、さらにその反応の傾向によって人物の性格を表現する。これは台詞で示される部分もあるが、演技に頼る部分がもっとも大きい。
役者Aが自分とはまったく異なる人生を歩む人物Bの人格、状況、心理などを演じるにあたっては、いくつかの方法がある。
第一に定型的演技。これは記号的演技と言ってもよい。老人ならば腰を曲げてよたよたと歩き、驚いたときには身をのけぞらせて大口を開けるといった、定型の動作によって観客に誰が何をしているかを説明するものである。このためにあらかじめ身体による特徴的表現のリストを用意し、単語を並べて文章を綴るように、舞台でこれらの身体語彙を次々と並べていく。吉本新喜劇などが採用しているもので、一般に素人の「学芸会」と言われる演技もこのパターンが多い。これは「型」による演技のもっとも初歩的なものである。ただ、役者にとっては演じやすく、観客にとってもわかりやすい。
第二に「リアリズム」と呼ばれる再現的演技。これは舞台上の出来事や登場人物が虚構ではなく現実であるかのように見えることをめざすものである。初心者の段階では演ずべき登場人物に近い実際の人物、つまり年齢、職業、性格、状況などが近い人を観察してその特徴を記憶し、またさまざまな状況での人々の喜怒哀楽の表情や動作を観察し、それらのしぐさや表情を模倣再現するというやり方が採られる。しかしこのような観察結果の組合せだけでは、まだ演技は他人の身体のさまざまな外見的特徴を抽出提示しただけの記号的再現であって、一人の統合された人格の表現ではないため、なかなか登場人物がほんとうに眼前に居るというリアリティが得られない。そこでスタニスラフスキー・システムをはじめ、リアリズムの演技術では、最終的に役者Aが登場人物Bに成りきることを求める。AはBの人生を想像し、置かれた状況を想像し、Bに成りきって舞台の上に立てと言うのである。日本ではいわゆる「新劇」の演技術がこれである。また映画やテレビドラマで採用されているのも、基本的にこれである。しかしこのようなリアリズムの演技とは異なる第三の演技術の伝統が日本に存在する。
六代目菊五郎は闇の中で蛍を追う演技に苦労していたとき、ある人から「指先を目玉にしたら」とアドバイスを受け、その通りにしてうまくいったという。また十七代目勘三郎が『忠臣蔵』の判官切腹のシーンで力弥を演じたとき、主君が最後の対面を望む由良助がなかなか到着せず、花道のつけ際に座って気を揉みながら父由良助を待つ演技がうまくいかなかった。すると六代目菊五郎から「揚げ幕に仮に丸い穴をこしらえて、そこから向うを見てみな」と教えられた。そこで揚げ幕に丸い穴を想像し、そこから遠くをじっと透かして見るようにしてみたところ「形と心がいっぺんにわかりました」という(注2)。
これらはAがBになりきるというリアリズム演技ではない。指先を目玉にする身体を実現したら、観客にはそれが蛍を追う身体に見えたということである。また、想像の揚げ幕の穴から向うを透かし見たら、それが父を待つ力弥の身体に見えたということである。
このような演技する身体(表現する身体)と観客の目に映る身体(表現された身体)との関係は、言語におけるメタファーの関係に相当する。メタファー(隠喩)とは、ある語が文字通りの意味ではなく、別の意味を、類似を根拠に表すというレトリックである。
メタファーの仕組みは、新たなカテゴリーの提案である。もう少し詳しく言おう。私たちの認識の単位は命題、すなわち「xはpである」という形をとる。これはxの別名がpであるという同一性を語っているか、さもなければxという存在(個物、特殊)がpというカテゴリー(類概念、普遍)含まれるということである。たとえば「今年のゴルフコンペ優勝者は田中さんだ」と言うのは「田中さん」と「コンペ優勝者」が同一だということであり、「田中さんは日本人だ」と言うのは、「田中さん」は「日本人」のカテゴリーに含まれるという意味である。ところが「田中さんはドン・キホーテだ」という命題では、両者は別人であり、しかもともに個物であって一方が他方に含まれるという関係にはないから、この文章を文字通りに解釈すると虚偽ということになる。こういう場合ふつう「ドン・キホーテ」という単語は「ドン・キホーテ」その人を指すのではなく、「ドン・キホーテのような人」という意味である。つまりこの文章は「ドン・キホーテのような人々」という新しいカテゴリーを提案し、田中さんはそのカテゴリーに属すると言っているのだ。このカテゴリーを定義しようとして「無謀で、理想主義的で、夢想家で、云々」といくら言葉を重ねても正確に定義することは難しい。ただその典型的な事例として「ドン・キホーテ」をあげることができるだけなのである。こうして隠喩とは、主題(主語)が属する新しいカテゴリーを提案し、その説明に概念的定義ではなく典型的な一事例(プロトタイプ)を用いる手法なのだと言える。ここで「典型的」とは、誰にでもわかる、ないし一番わかりやすいということである(注3)。
これを言語ではなく身体に適用すると、「指先が目玉の身体」は「蛍を追う身体」と同じカテゴリーに属するものであり、ただ演者にとっては前者のほうが身近で実現しやすい身体だということになる。つまりここでは、唯一無二のキャラクターとか特殊な心理とかではなく、同じカテゴリーに属する別の身体のあり方を実現するという、隠喩的手法をとっているわけである。これはリアリズムの演技理論とは異なる考え方だ。日本芸道における「型」の演技術は、ここから来ていると考えられる。
このような「型」の演技術は、第一の記号的提示としての型とどこが違うのだろうか。「老人」を表すのに「曲がった腰」を提示するのは、身体の外形的記号である。観客は演者の「曲がった腰」を見て、彼が「老人」だと解釈する。しかし「指先が目玉」というのは、演ずる側の内面の意識である。観客にはわからない。観客に見えるのはただ「蛍を追う身体」なのだ。演者の側からすれば、第一の演技術は、修辞学用語を使えば、「リテラル(文字通り)」な表現であり、第三の演技術は「メタフォリカル(隠喩的)」な表現である。観客の側からすれば、第一の表現は記号的であり、常識的なコード(記号解読規則)によってただちにその指示内容を解釈できる。一方第三の演技術にはあらかじめ決まったコードはない。だから観客の作業は頭で解釈することではなく、その場で即興的に行われる身体的同調によって「何が起きているのか」を理解することである。たとえば正座しつつも背伸びするようにして遠くを見る力弥の身体に共感することによって、観客はその切羽詰まった心情を理解するのである。ではこの演技術があてにしている身体的同調とか共感といった観客側のプロセスはどういうものだろうか。
2 共感と感情移入
人は誰でも他人の表情からその気持ちを推量できる。この能力はどのようにして身についたものだろうか。相手の顔の目や口の形状や配置パターン、たとえば眉や目尻が垂れており口角が上がっていれば、ふつう私たちはこの人は喜んでいると解釈する。マンガ家が簡単な線描で登場人物の心理を表現するとき、このようなパターンを利用する。眉を八の字に描けば困った顔になり、それを上下逆にすれば怒った顔になる。このような記号化された表現が可能なのは、私たちがそのようなパターンを解読できてしまうからである。けれどもそれは、認識されたパターンを過去の同種の表情データと突き合わせて行われる解釈なのだろうか。いや、これはおそらく生得的なものである。
認知心理学で「心の理論」と呼ばれるものがある。さまざまな実験から幼児や猿にも他人の認識内容や行動の意図を解釈する能力があることがわかっている。人は世界を認識し状況を解釈するにあたって、目に見えるものだけを材料にするのではなく、他人の内部に心があることを前提に、思考し、判断を行う傾向があるのだ。つまり人間は子供のころから自分の環境を解釈するにあたって「他者の心」という目に見えない仕組みがあることを想定し、そのブラックボックスの内容を推測するという作業を行っている。この対象を人間のみならず、犬であれ無生物であれ、なんなら天とか海とかまで拡大すれば、それは擬人化という現象になる。これは世界の状況を解釈する一つの方法であって、幼児や古代人にはよくみられる。たとえば幼児が降る雨を見て「空が泣いている」と言う。あるいは古代人が目に見える空の背後に目に見えない空の神という人格を設定し、その悲しみの現れとして雨を理解するなら、いわゆるアニミズムとなる。日本の八百万の神々も擬人化の産物と言い得る。
私たちには他者の心を理解しようとする傾向があるとして、次になぜある種の表情が特定の心理を表しているものとして解読されるのかが問題となる。これについては近年のミラーニューロンの発見が、新しい説明を生み出している(注4)。ミラーニューロンとは脳内にある細胞の一種で、他人の身体の動きを見たとき、自分自身の身体が動いた場合と同じパターンで発火する(電位上昇)という特徴を持つ。他人の筋肉活動や情動の変化に対応するその他人の脳内ニューロンの発火パターンが、まるで鏡のように自分の脳内ニューロンにも生じるという意味で、ミラーニューロンと名付けられた。これは他人から自分への脳内反応の伝染であるだけでなく、しばしば筋肉反応の伝染をもたらし、その結果身体的模倣を生む。たとえば生後2カ月の幼児は、まだ他人の表情の解釈ができるかどうか疑わしい。しかし彼は眼前の他人の表情を模倣するのである。たとえば相手が舌を出せば、幼児も舌を出す。幼児には相手の顔面の筋肉がこう動いているから、自分のどの筋肉をどう動かせば同じ顔になるだろうかといった計算があるはずもない。だからこれは意識的な反応ではない。無意識の反応である。少なくとも、筋肉や表情や心理についての知識も、模倣しようという意図もなく行われる自動反応である。従来の知覚-判断-行為という図式ではこれを説明できないが、ミラーニューロンの存在はこれを説明できる。
もちろん私たち大人はこのような自動的物まねをいつもやっているわけではない。しかし相手の動作や表情にたいし、その筋肉の動きに対応する反応が脳内のミラーニューロンに起こっている。それは、実際に自分の筋肉を動かしても動かさなくても生じるのである。これにより、たとえ動かさずとも、私たちは自分の筋肉が動いているかのような気になることはできるし、そして何より、そのような筋肉の動きに伴う情動を知覚することができるのである。その知覚をもとに「彼は怒っている」とか、「悲しんでいる」とか判断するのだ。
この反応は無意識のものであって、感覚器官で知覚し、脳で反省するというプロセスを経ない。そのような反省と筋肉への指令などなくとも、私たちは相手の動きを正確に捉え、反応することができる。このことはボクシングの研究から証明されている。相手のパンチを見てからそれを避けようとすれば、知覚と反応のプロセス、つまり視覚から脳への情報伝達と脳から筋肉への運動指令にかかる時間が、少なくとも180ミリ秒必要とされている。ダニエル・スターンはムハマド・アリとミルデンベルガーの試合のフィルムを調べ、アリのパンチの半数がこれより速いことを発見した。これは知覚と反応に頼ってはアリのパンチは防げないということである。しかし実際にはその試合で彼のパンチはほとんどブロックされるか、避けられていた。スターンはこの事実を次のように解釈した。ミルデンベルガーはアリのパンチ行動を見てから反応したのではなく、「アリのプログラム化された一連の行動を時間的空間的に予測し」たのだと。しかしいったいそんな短い時間にどうやって相手の行動を予測し、それへの対応を実行に移すことができるのか。スターンによれば、二人は「同じプログラムに共に従って」いたという。ちょうど社交ダンスのワルツを踊る二人が、同じプログラムにもとづいて動くとき、ステップは即興的に決められていくにもかかわらず、あたかも事前に決められた動きをしているかのように動きのタイミングも方向も正確に一致する。まるでふたつの身体が一体化しているように(注5)。つまり、ミルデンベルガーはアリの動きのパターンに自分の動きのパターンを合わせていた、ウィリアム・コンドンの言い方を借りれば「引き込みentrainment」を行っていたのであり、より一般的な認知科学の言い方を使えば「同期(シンクロ)」させていたのである。
しかし動きを相手にシンクロさせるプロセスの場合も知覚反応プロセスと同じ時間が必要ではないかと疑うこともできる。ところがシンクロはきわめて素早く行われる。アリに閃光を見てからパンチを放つように求めた実験では、閃光の感知に190ミリ秒、そしてパンチを繰り出すのに40ミリ秒、計230ミリ秒を要した。しかし「ある研究によれば、大学生たちが無意識に動作をシンクロさせるのにはたった21ミリ秒しかかからなかった」という(注6)。動作のシンクロには意識的判断という経路が省略される(扁桃体を経由するショートカットがあるらしい)ため、極めて高速なのだ。
ここから、私たちは他人の表情を見たとき、無意識のうちに高速でその顔の内側の筋肉の動きに自分の筋肉をシンクロさせていると想定することができる。むろんそれは外見からわかるほどの表情模倣ではないとしても、それに準ずる活動がミラーニューロンの活性化という形で実現しているはずである。そしておそらく、その活動がある種の情動を生起させる。つまり筋肉のシンクロだけでなく、情動のシンクロが起こる。これが共感である。
筋肉の活動パターンが特定の情動を呼び起こすということが、ほんとうにあるのだろうか。どうやらあるらしい。というのも、モダンダンスの母ともいうべきマーサ・グラハムはそのような指導を行っていたからである。グラハムは身体が内面を表現できるという信念に従い、新しいダンス技法を開発し、今日なお世界のダンス・レッスンの基本の一つとなっている。そして驚くべきことに、彼女のもとへレッスンに来たのはダンサーだけではなく、映画・演劇界の俳優たちも少なくなかった。彼らが学ぼうとしたのは、他者になりきるという第二の演技術に必要な技法、つまり自分の身体の内部に登場人物の感情をいかにして実際に生起させるかというテクニックだった。感情を想像するだけでは、自分の内部にその感情をほんとうに生起させることは難しいからである。しかしグラハムはこう教えた。まず身体を動かせば、情動はそれについてくる、と。グラハム・テクニックで最も有名なのはコントラクションという骨盤のあたりを激しく突くような動きである。映画女優アン・ジャクソンは泣き崩れる演技が必要だったときコントラクションを用いると、それが感情に影響を及ぼし、リアルな演技ができたと証言している(注7)。
ここで、先に引用した勘三郎の言葉を思い起こそう。
「心の中で揚げ幕に丸い穴をこさえて、そこから遠くをじっと透かして見るようにしてみな、って言われて、形と心が一ぺんにわかりました」(注8)
菊五郎が教えたのは形だが、勘三郎はその形を演ずることで、心もわかったというのである。これはまさに、身体的隠喩が演ずる役者自身の内面にある種の心理状態を呼び起こしたということを意味している。第三の演技術は観客に共感をよび起こすだけでなく、同時に役者自身にも同じ共感を生じさせるのである。身体に感情を呼び起こすには、意識的想像だけでなく、肉体的運動もまた有効なのである。
ここで人間の有り様を深く揺り動かし行動へとかりたてる「情動」と、意識に自覚され、喜怒哀楽といった形で意味づけされる「感情」とを区別しておく必要があるだろう。シャクターとシンガーは交感神経の興奮を引き起こすアドレナリン(エピネフリン)を被験者に投与し、自分の感情を説明させる実験を行い、次のような結論を得た。
人は自分の生理的興奮状態に対して直ちに説明ができないとき、もち合わせの認知情報によってこの状態に〈ラベル〉を貼り、自分の感情が何であるかを言葉に表すものだ。(注9)
つまり自覚されている感情とは自分の身体に生起している情動を後付けで説明したものだというわけである。これに似た事例はその後いくつも報告されている(注10)。たぶん肉体の動きは何かの情動を起こすだけであり、それを悲哀という感情として自覚するには想像という意識による水路づけの作業が必要なのだ。言い換えれば、私たちは無意識の情動を意識によって解釈し、意味づけているのである(いわゆる「吊り橋効果」)(注11)。そしてそのような感情が今度は涙を流すといった次の肉体的反応を呼び起こすのである。コントラクションなどによって情動を生起させつつ、登場人物の心境を想像し、眉を寄せるとか唇をかみしめるといった悲しみに特有の表情を模倣するとき、強い情動は悲しみの感情へと水路づけられ、俳優は涙を流すことができる。そしてそれを見た観客は共感して悲哀を感じるのである。
3 感情移入と型
前章末のような観客の反応に関しては、古典的な感情移入論があてはまる。テオドール・リップスの説く「感情移入Einfuelung」(共感empathy)とは、自分の感情を対象側に移し入れる作用のことである。単純化して言い換えれば、自分の内部に起こった感情を他者の内部にある感情だと思い込むことである。当然ながら、一方的錯覚に終わることも珍しくない。演劇はこれを利用する。役者の演技する身体の外見を見るだけで観客の内側には身体的模倣が生じ、これが情動を生む。さらに芝居の筋や台詞や表情から、その情動を特定の感情、たとえば悲哀などに水路づけする。これによって観客の内部に悲哀と自覚される感情が起こる。すると観客は、自分の内部に生じた感情を、舞台上の人物の感情として解釈してしまう。これが共感と呼ばれる現象のいきさつである。直接にふたつの心が共鳴しているわけではなく、身体的模倣を介して生起した感情をあたかも直接感じ取ったかのように思い込んでいるだけである。
しかし、そうであるとすれば、俳優は必ずしも自分の内部に実際の感情を生じさせる必要はない。それどころか、情動を生じさせる必要さえない。観客が模倣できる身体を形成するだけで、あとは観客が勝手に錯覚してくれるだろう。ここに身体的レトリックを用いた演技術が可能となる。先に述べた第三の演技術である。
絵画のような二次元の物体は身体をもたない。しかしよくできた人物絵画は見る者の内部に模倣反応を生じさせ、感情さえ生じさせるだろう。そして感情移入によって、人はこの絵画はかくかくの感情を表現していると言うだろう。これは描かれた人物像があまりにリアルであって、実物とまがうほどの場合のみ起こる錯覚ではない。抽象化されたマンガのような図像ですら起こりうる。それどころか、私たちはペットの表情や動作さえ、そこに感情を感じる場合がある。つまり非人間的存在に対してさえ、私たちは擬人化によって、それに対応するミラーニューロンを活性化させていると考えられる。おそらくミラーニューロンは認知対象の筋肉と一対一に対応しているのではなく、ある種のパターンに対して対応しているのである。とすれば、演技者は観客の感情を誘発するのに、自分でその感情を生起させる必要がないばかりか、身体レベルでも正確にその感情を表す活動をする必要はない。同じ反応を引き起こすに足るパターンさえ実現すればよいことになる。ここに隠喩としての演技が可能となる。
日本の伝統芸能における「型」とは、ある種の身体反応を引き起こすための単純化された、それゆえ明確な、共感を喚起しやすい身体演技である。この意味で、記号と化したおおげさな表現も一種の型と言うことができる。それはリアルな身体パターンの極端な、見方によってはカリカチュア化された再現である。カリカチュアとは、不要な情報を全て捨て去りながら見る者の感情を特定の方向に誘導するための条件だけは拡大して見せるような、特徴的パターンの選択的表現のことであるから。
第三の演技術として取り上げた隠喩として使用される「型」は、現実世界ではけっして採用されない動きや姿勢であるにもかかわらず、観客にとってはその身体的模倣から思いもかけない感情を、強い情動を伴って呼び起こすような刺激である。そして観客は感情移入によって俳優の身体に強い感情を読み取り、それに自分も共感したと思う。
こうして花道の端に座って揚げ幕の仮想の穴を見る力弥の身体は、観客にとって父由良助の到着を待ちわびる悲痛な力弥の心情を観客に呼び起こし、共感の魔術を生じるのである。
われわれは演技術に三つの種類があることを見てきた。第一にリテラルな記号としての型。第二にリアリズムの再現的演技。第三に隠喩としての型。これらの演技はどのようなメカニズムによって観客に共感や称賛をもたらすのだろうか。
この三つの演技術はいずれも観客に対してミラーニューロンの発火を促すものである。つまり観客はその演技する身体に対して鏡像のような運動感覚をおぼえ、それに対応する情動を生起させる。さらにコンテクスト情報によって特定の感情へと水路づけされ、観客は自分がある感情を抱いたことを自覚する。しかもその感情を対象へ投射(移入)し、登場人物の感情を理解したと思いこむ。共感と呼ばれる現象である。観客は「わかる、わかる」とうなずいたりするだろう。そしてさらに感動に及ぶことがあり、涙を流すといった身体反応さえ生ずる。このとき観客は、自分の「泣く」という反応の理由を、「登場人物の状況や行動に対して感動したからだ」と解釈する。その結果、登場人物の状況や行動に対してある種の価値付与を行う。「かわいそう」とか「なんて崇高な行為だ」とか。劇場を出た観客は、人に感想を聞かれるとこう答えるだろう。「主人公の哀しい運命に泣きました」とか「崇高な行動に感動しました」とか。このとき役者は演技に成功したと言えるのである。
4 ピナ・バウシュの情動表現
観客の情動に影響するのはもちろん役者・ダンサーの身体だけではない。筋書きや音楽、舞台美術や衣装、そして何より演出が影響する。たとえばピナ・バウシュの初期の傑作である『春の祭典』ではストラビンスキーの音楽や舞台一面を覆う本物の土が、観客の身体に作用している。しかし本稿ではダンサーと観客の身体間の関係のみに焦点を絞っている。
ここで問題にしたいのは、暗黒舞踏やピナ・バウシュの作品を見た観客が衝撃を受けたり感動したりするのは事実であるとしても、それらは前章のような感情移入論ですべて説明できるであろうか、ということである。感情移入は、観客の内側に生じた情動を、意識が感情の一種として解釈し、過去に体験した情動の記憶と、喜怒哀楽についての既存の概念を利用して「これはしかじかに対する〈怒り〉」「これはしかじかによる〈悲しみ〉」などのラベリング(名札貼り)を行うことである。とすれば観客が報告する感動とは、このラベリングに基づいて自分の内部の情動を「悲哀への同情」とか「崇高なものへの感動」とか説明しているわけである。
多くの演劇や舞踊ではこの説明があてはまるかもしれないが、暗黒舞踏とピナ・バウシュ作品の場合にはいささか疑問がある。というのも、これらの舞台に際しては、観客は自分の感情に適切なラベリングが行えないからである。あまりにも複雑であるためか、未体験の情動であるためか、それともラベリングの手がかりになるような情報(筋書きとか音楽とか)が乏しいためか、あるいは多すぎるためか。たぶんその全部である。
たとえば暗黒舞踏において未知の身体が目の前に立ち現れるとき、観客は一種の戦慄を覚えるのだが、それは既知の感情に分類することはできない。そもそも自身の内部の戦慄を感情とみなしてよいのかどうかさえよくわからない。たしかなことは、自分が新しい身体の可能性をかいま見たということだけであり、それがダンサーの身体だけでなく自分の身体の可能性でもあるという自覚であり、たぶんそのこと(自分が自分の知らない身体を内部に宿していたこと)に戦慄するのである。
ピナ・バウシュの場合にはさらに複雑になる。舞台上のダンサーたちは観客を刺激して強い情動を生じさせる。しかし観客は多くの場合その情動を意識によってラベリングできない。というのも、眼前の情報が互いに矛盾するため、意識はうまく既知の感情へと水路づけすることができないのだ。たとえば純白のウェディングドレスを着た女性がその長いトレーン(引き裾)を男二人に持たせて歩んでいる。私たちの既知の情報では、これは多くの物語のラストシーンであり、人生のハイライトを迎える花嫁は喜びに輝き、裾を持つ従者は厳粛な表情で儀式の荘厳さを示すものである。ところが女性は悲しげであり、男たちは下品に笑いながら煙草を吸っている。観客はうまく状況を理解できない。そこでもっと手がかりを求めるのだが、何も与えられない。ピナ・バウシュはこのシーンを唐突に提示し、そしてすぐに次のシーンに移る。前後には何の脈絡もない。観客は自分の情動を持て余してしまう。つまり明確な感情として意識化されないまま、内部に蓄積していくのである。ピナ・バウシュは一見無関係なシーンをコラージュしてゆくのだが、その一つ一つは観客にさまざまな情動を与えて過ぎて行く。はっきりと「滑稽」なシーンでは観客は緊張から解放されて大笑いするし、優雅なユニゾンの群舞では期待通りのダンスの快感を得る。けれども、そういう息抜きを挟みながら、ほとんどのシーンでは不可解な情動に翻弄されることになる。それは目隠しして川下りするとき予想もつかぬ運動に内蔵が飛び跳ねるような、一種の身体的経験である。意識の整理は追いつかない。けれども、そのうちに不意に何かが思い当たることがある。記憶のデータの中に、これに似た情動があったような気がするのだ。舞台を見ながら積み重ねてきた情動の破片が集まって一つの形を得るのだ。そこから先は人さまざまである。泣く人は多い。解放されたという人もいる。たとえば映画監督ヴィム・ヴェンダースはこんな風に報告している。
いやいや、嵐が舞台を横切ったわけではありません。ただ・・・人間たちがそこで何かを演じていただけでした。その動きはいままで見たこともないものでした。それが次に、いままで経験したことのないやり方で私を動かしたのです。
わずか数秒で私の喉に何かが詰まり、当惑の数分を経て、私はただ感情に身をまかせました。すると一切の抑圧から解放され、私は泣き始めたのです。こんなことは生れて初めてでした。(注12)
これはピナ・バウシュの舞台を見るという経験の典型である。なんだかわからないうちにある情動に捉えられてしまう。何が起こったのかを解釈しようとしても、たいていの場合、その情動を名付けること(ラベリング)はできない。ただ、何かがわかった、という気がするだけなのだ。そしていつの間にか自分が解放されているのを知り、涙を流すのである。
人間は強すぎるトラウマを忘れてしまうことが知られている。戦争や強姦などの被害者はその記憶をまったく失っていることがあるという。フロイト風に言えば、受け入れがたい記憶は防衛規制によって抑圧され、意識に上らないようにされてしまうのである。だが意識的な情報としては消されていても、無意識の情動の形だけは記憶しているのかもしれない。私たちは「これはいつどんな風に起こったものかわからないが、この経験は知っている」という情動の形を意識下に持っているのだろう。ピナ・バウシュはそれを再現してしまうのである。だから、ピナ・バウシュを見るときの衝撃的な経験は、未知の経験であるにもかかわらず、「これは知っている」というなつかしさを覚えるのだろう。それは言わば、「無いことにしてきた自分」の再発見である。ちょうど土方巽が無いことにしてきた自分の身体(「はぐれてしまった」身体)の再発見を目指したように、ピナ・バウシュは無いことにしてきた自分の心を観客に再発見させようとしたのかもしれない。
演劇や舞踊は身体を隠喩表現の媒体として使用することがある。尤もその隠喩は解読できるとは限らない。少なくとも、自覚的にその隠喩の表す情動を対象化し、言語化できるとは限らない。しかしその場合でも観客の身体はその隠喩を把握し、自らの情動として再現できることがある。いわば、身体的隠喩を身体的に解読し、再現するのである。このとき観客はまさに「わけがわからない」まま、ただ感動し、涙を流している自分の身体に驚くかもしれない。ピナ・バウシュがなしとげたのは、そのような身体芸術の新しい方式の完成である。そしてもし人々が芸術に期待しているものが「感動」であるなら、身体を媒体とするダンスこそがそのためにもっとも強力で直接的な手段であることを実証したのである。なぜなら「感動」とは情動の激流によって理性が押し流され、ただ身体が打ち震え続ける経験であるから。
注
1.コンテンポラリー・ダンス研究会主催シンポジウム「『ダンサーに聞く』におけるスタンザックの発言。2013年3月20日。
2.生田久美子『「わざ」から知る』東京大学出版会1987、94~95頁
3.詳しくは尼ヶ崎彬『ことばと身体』(勁草書房1990)の1・2章を参照されたい。
4.ジャコモ・リゾラッティ&コラド・ジニガリア『ミラーニューロン』柴田裕之訳、紀伊国屋書店、2009。マルコ・イアコボーニ『ミラーニューロンの発見』塩原通緒訳、ハヤカワ新書、2009
5.ジェレミー・キャンベル『チャーチルの昼寝』中島健訳、青土社、1988、307頁
6.マイケル・S・ガザニカ『人間らしさとはなにか?』柴田裕之訳、インターシフト、2010、236頁。言及された「ある研究」とはHatfield, E., Cacioppo, J.T., and Rapson, R.L., “Emotional contagion,” Current Directions in Psychological Science 2, 1993, pp.96-99
7.キャサリン・タッジのドキュメンタリー・ビデオ『マーサ・グラハムの生涯』(Martha Graham: The Dancer Revealed)1994
8.関容子『中村勘三郎楽屋ばなし』文芸春秋社、1985、46頁(注2より再引用)
9. Schachter, S. and Singer, J., “Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State,” Psychological Review, Vol. 69, 1962. p.398
10. たとえば、アントニオ・R・ダマシオ『感じる脳』田中三彦訳、ダイヤモンド社、2005.99-102頁、109頁。
11. 無意識の情動が意識化されるメカニズムについては次の本が詳しい。ジョセフ・ルドゥー『エモーショナル・ブレイン――情動の脳科学』松本元・川村光毅訳、東京大学出版会、2003
12. 「Wim Wenders on Pina Bausch」(英訳Roger W. Benner)。ヴィム・ヴェンダースの映画『Pina』の英語版BDディスク付属パンフレット28頁。元は2008年ピナ・バウシュがゲーテ賞を受賞した時のヴェンダースのスピーチ。