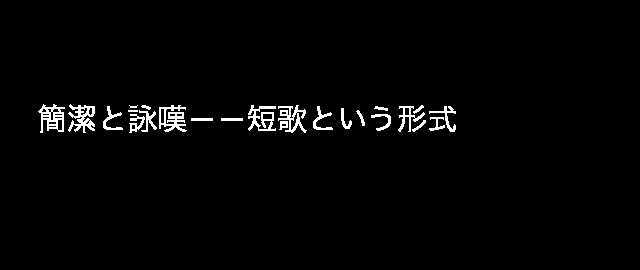序
短歌はなぜ短いのだろう。
こう問えば、それは当たり前だ、短いから短歌と呼ぶのだという答が返ってくるだろう。しかし五句三十一字の詩型を一般に「短歌」と呼ぶようになったのは明治以降のことであって、それ以前は単に「歌」あるいは「和歌」と呼んでいたという事情を考えると、これは当たり前の話ではなくなる。先の問いは実は「和歌はなぜ短いのか」というのと同じことになるからだ。言い換えれば、歌にはさまざまな形式が可能であるのに、そして実際さまざまな形式があったのに、なぜ日本人はかくも簡潔なものを自国の文芸の代表として選んだのかという問題である。
「短歌(みじかうた)」という用語は古代からみられる。そこでは「短歌」は「長歌(ながうた)」に対する呼称である。歌には長い形式と短い形式とがあり、前者を「長歌」、後者を「短歌」と呼んだわけだ。だから「短いから短歌と呼ぶ」というのは、歴史的には正しい。もっとも長歌はすぐに衰退し、歌といえば短歌形式で詠むのが普通になると、もはや歌を長短で区別することは無意味になる。そこで短歌をただ「歌」とか「和歌」(これは漢詩に対する場合だけれど)と呼ぶようになった。だがいったいなぜ日本人は短歌を偏愛して長歌を捨ててしまったのだろうか。
一つの理由として考えられるのは、短歌なら誰でも詠めるということである。つまり日本人にとって歌は特別な才能を持つ作家の作品を凡人が鑑賞するというものではなく、誰もが作り鑑賞し合うという相互性を持つべきものだったということである。とすれば歌は西欧的な「芸術」という観念にぴったりと適合するものではない。生活の(ただし風雅な生活の)一部としてやりとりされ、もてあそばれ、楽しまれる文芸が、ヨーロッパの近代に生じた「芸術」という制度に当てはまらなくとも不思議はない。西欧的芸術観からすれば、和歌のあり方は「遊び」にすぎないと言うかもしれない。しかし今日の「音楽会」にあたるものを「遊び」と呼んでいた平安時代の人々は、そう言われても少しも困ったことと思わないだろう。むしろ「遊び」が人生にとっていかに大切かを説くかもしれない。そして遊びがうまくできるためには知識の学習も技術の訓練も、そしてなにより感性の洗練が必要なのだと言うだろう。芸術という制度においては、少数の作家以外はみな鑑賞者という受動的地位に甘んじるほかはない。けれども遊びとは自ら参加し、相互に主となり客となるものである。いずれが人生を豊かにするか。ひるがえって現代の前衛芸術が一般の人々の生活にほとんど関与しないのを見るとき、むしろ芸術の存在理由を疑わずにはいられないだろう。そもそも「芸術」という制度のなかった日本において、人々が長歌よりも短歌を好んだのは、誰でも参加できる創作行為であったからではなかったか。
しかしまだ疑問は残る。これで日本人が短歌を愛した理由は説明できるけれども、長歌という形式が廃れた理由がわからないからだ。日本人は自分では容易に作れない漢詩を価値あるものとして認め、漢詩人を尊敬していた。漢詩に相当する堂々たる構成をもつ作品を日本語で作ろうと思えば長歌の方が適している。ひとびとが、自分では作れないにせよ、文学作品として長歌の価値を認め、長歌の作家に敬意を払えば、もっと長歌形式は後世にまで生き延びただろう。しかし技術的には十分長歌を作りえたと思われる専門歌人たちも、長歌を作って人々に評価されたいとは考えなかったようだ。日本人は、専門家が高度な技巧を駆使して創作し、非専門家の読者はただ受動的に作品を享受するという場合でさえも、長歌よりも短歌を選んだということである。
そしてもう一つの問題は明治にある。西欧の文学を知り、その詩型を知った明治の文学者たちが、日本の詩歌の近代化を試みて、つまり日本語で「芸術」としての詩歌を作ろうとして、さまざまの定型を試行錯誤しながら、結局選んだのは昔ながらの短歌形式であった。しかも今度は「歌」でも「和歌」でもなく意識的に「短歌」という呼称を復活させたのである。たとえば与謝野晶子は多くの詩を作っているが、中でも代表作とされる「君死にたまふことなかれ」は七五調であり、一種の長歌といってもよい。しかも名作といってよい。けれども彼女が結局自分の基本形式としたのは短歌だった。そしてひとびともまた彼女を短歌の作家とみなしている。同時代の青年子女に影響を与えたのも、今日代表作として人口に膾炙しているのも、みな短歌の方である。明治以降三十一字より長い詩歌はたくさん試みられたけれども、歌謡曲の歌詞と音数律のない自由詩を別にすれば、結果的に生き残った形式は、短歌と俳句であったといってよい。もし三十一字が短いと思えば、歌人は短歌の連作というやり方で対処した。長い歌によってしか実現できないものがあることを知りながら、やはり短歌こそが自分の求めている形式だと再確認したのだとしか思えない。どうやら「短歌」であることは、単に古来の名前であるという以上に、和歌という文学形式の本質に関わるものだったのだ。つまりこういうことだ。短歌の特徴はまさに短いということにある。そして短いが故に実現する文学的特質こそが、短歌の本質であるだろう。ここで考えようとするのは、短歌形式がもつその特質である。
1 物語と歌--世界への没入と図式の受肉
私たちにとって長歌と短歌の違いは、文学としてそれらを享受するさいに現れる。だがここではいきなり長歌と短歌の享受の違いを述べるのではなく、そもそも文学の享受とはいかなるものか、と話を基本的なところから始めたい。文学を言葉による作品と広くとれば、さまざまな形がある。長大な小説や風雅な詩歌だけではない。語り物である浄瑠璃や浪曲が入るなら戯曲も入るだろうし、和歌俳句の形式を借りた狂歌や川柳が入るなら、ことわざや標語を排除することはできないだろう(たとえば交通標語のパロディ「赤信号みんなで渡れば怖くない」は標語でも川柳でもあるし、新しいことわざといってもよい)。むろんその享受の仕方は違ってくるわけだが、内容の享受に関しては小説や語り物と標語やことわざとでは対極にある。前者からは私たちはまず物語を受け取ろうとするのに、後者からは物語に至らない内容を理解しようとするからだ。そこでここでは文学を分けるのに、物語であるか否かを基準とすることにしよう。
物語とは、基本的に固有名詞をもつ主人公が事件に出会い、行動をおこし、状況の変化を経験するという内容をもつ。小説、叙事詩、悲劇(かつて西欧では韻文)などは物語であり、短歌などの短詩型はふつうそうではない。白居易の「長恨歌」は物語だが柿本人麻呂の長歌はそうではない。
物語を語るとは、虚構の世界と事件と人物を語りによって作りだすことである。物語の享受に際しては、読者(聞き手)は語られた世界に没入し、登場人物に同一化する(少なくともしようとする)ものである。没入と同一化が容易であるためには細部が具体的であることが望ましい。そこで時代や場所が特定され、人物には固有名詞が与えられ、出自が語られ、容姿や情景は細かく描写される傾向があるだろう。物語の「語り」は印刷された文字だけで行われるとは限らない。かつては琵琶法師から浪曲にいたる語り芸の伝統が日本にはあり、映画やテレビがより精巧な虚構世界の提示を行うようになるまでは、ラジオやレコードをも利用しつつ隆盛していた。その語りは、場面に応じて声の調子を変え、台詞に応じて声音を変えて、状況や性格や心理を髣髴とさせるべく語り分けていた。物語は虚構に現実感を与えようとして、できるだけ具体的な再現を目指すのである(だからさらに完全を期せば視覚的情報を加え、演劇や映画へと向かうことになる)。その目的は物語の享受者に虚構世界への没入と虚構人物への同一化を促すためである。
物語を享受するとは、ただ言葉の内容を理解するだけではないのだ。今この場の現実世界から離脱し、言葉によって構築された世界の中を身をもって反応しつつ生きるという、一種の身体的体験をするのである。もし小説が読者の身体に興奮も緊張も与えなければ、それはたいがい失敗作である。「はらはらどきどき」とか「血沸き肉躍る」と形容されるように、実際に血圧は高まり脈拍は速くなる。笑うことも泣くことも珍しくはない。
長い小説を読むのは面倒だが筋だけは知りたいという人のために、文学事典などでは要旨が書かれている。だがこの要旨を読んで興奮や緊張を覚える読者はまずいない。理由は二つあるだろう。ひとつは世界を構築するには言葉が足りないということである。だがもっと大きい理由は、そもそも筋を知りたいという読みの態度が、虚構世界を身をもって生きようとする態度とはもともと異なるということである。だからこういうものは、筋だけ知ればよいという人しか利用しない。これが抽象命題で語られる主題となるともっと違いははっきりとする。文庫本の巻末にはたいてい解説があって、その物語の主題が「義理と人情の板挟み云々」であるとか「被抑圧階級の悲劇云々」であると解明してくれているけれども、そしてそれは多分正しいのだろうが、そういった抽象命題を読んで感動する読者はいない。しばしば主題は物語の本質であるかのように言われるけれども、どれほど忙しい人でも小説の本文の代わりに主題を読んで済ませようとは思わない。人が小説を読むのは(そして語りものを聞き、演劇や映画を見るのは)主題を理解するためではなく、虚構世界を実地に生きてみるという体験をしたいからである。
主題は古来口実に使われてきた。たとえば「勧善懲悪」とか「忠孝の教え」といった口実で歌舞伎は幕府に対して殺伐卑俗な脚本を正当化してきた。たとえば悪人を主人公に胸のすくような悪事を四幕まで見せても、終幕で彼が裁かれればそれは「勧善懲悪」の芝居ということになるわけである。もちろん観客は終幕なんかどうでもよく(浄瑠璃では「見いでもいい、せいでもいい」とさえ言われた)、主人公がいかに悪事を行うかを痛快に見ているのだ。このことは、確かに主題が物語に内在するものではあるとしても、じつは物語の本質ではないということを示しているだろう。個々の物語の本質を成すものはむしろ主題とあらすじの中間にある。それはあらすじから抽象される骨格のようなものである。ここではそれを「図式」と呼ぶことにしよう。たとえばフロイトが注目した悲劇『オイディプス王』の図式は、「息子が父を殺し母と結ばれる」ということにある。読者や観客にとっては、この抽象的な図式を具体的に生き直してみることが文学的体験となるのである。
抽象的な図式に具体的な人名や場所や状況などを加えて具体化すると物語になる。たとえば「働く者は富み、遊ぶ者は零落する」という抽象的な図式から「アリとキリギリス」という寓話を作ることができる。この寓話は図式を具現している事例のひとつである。逆に図式は個々の事件や人生の事例から具体的な要素を剥ぎ落として抽象化したものである。その代わり図式は普遍性をもち、多くの事例に適用できる。もっとも「アリとキリギリス」のように教訓的な図式はほとんど主題と区別がつかない。そしてこの種の簡潔な図式は具体化せずとも、そのまま抽象命題として流通することができる。即ち「働かざる者食うべからず」。同じことが「情けはひとのためならず」「失敗は成功のもと」「時は金なり」などについても言える。ことわざや標語は、過去にもあり未来でも繰り返されるであろう事例のための普遍的図式なのである。しかも物語や寓話といった虚構の事例ではなく、現実の事例に適用するための図式である。個別的事例を詳細に語る物語と普遍的図式を簡潔に語ることわざとはこの意味で対極にある。
しかし興味深いことに、ことわざですら、抽象的な図式をむき出しにしたものよりも、卑近なあるいは典型的な事例に具体化したものが多い。「雨降って地固まる」「花より団子」「羹に懲りて膾を吹く」「井の中の蛙」など。にもかかわらず、人がことわざを口にするときには、言葉の上の具体的事例にはこだわらず、ただそこから抽象される図式だけを言おうとしている。ある男を「井の中の蛙」というとき、彼が世間知らずであることだけが問題であってその顔が蛙に似ているかどうかは誰も気にしない。「雨降って地固まる」が実際の地面について言われることもまずない。ことわざの語る虚構事例(井戸の中しか知らない蛙)は、発話時に適用される現実事例(世間を知らない男)に対して隠喩の関係にある。つまりことわざや寓話は、隠喩ないし寓意の形式をとり、抽象的図式を語るのにわざわざ具体的事例をもってするのである。
そもそもことわざの価値は世間のさまざまな場面に適用できるという普遍性にある。物語のように具体的な虚構世界を体験するためのものではない。だから抽象図式のままでよいのであって、なにも具体的事例に翻訳する必要はない。にもかかわらず、なぜ隠喩というまわりくどい形をとってまで具体的事例を通じて図式を示すのだろう。おそらく具体的な事例だけがもつ力があるからだ。そればいかなるものか。たとえば「失敗に懲りて慎重になる」という言い方と「羹に懲りて膾を吹く」を比べてみよう。図式としては同じといってよい。しかし後者から具体的なイメージを思い浮かべるとき、私たちは懸命に膾を吹く者の気持ちもわかるし、同時にその光景の滑稽さも実感できるだろう。この実感は抽象的命題では得られないものである。そしてこの実感こそ、実はことわざの図式がもつ本当の意味なのである。「羹に懲りて膾を吹く」とは単に失敗に懲りて慎重になるという事態を指しているだけではなく、その事態がしばしば人にもたらす哀れなほどの滑稽さを意味している。しかしこの意味は具体的事例の印象として実感されるほかはないのである。たしかに失敗に懲りて慎重になることはよくあることだ。しそれだけならことわざは生まれない。その事態がしばしば一種の悲喜劇の色彩を帯びるからこそ人々はこの事態に注目し、ことわざとして定着したのである。「羹に懲りて膾を吹く」とは、その色彩を典型的に実感させる事例なのである。
ではこのようなことわざは具体的であり実感を与えるという理由で物語と同一視してよいだろうか。具体的事例を語る言葉を精密にしてゆけば、いずれ物語になる。その境界線を引くのはむつかしい。だが中世と近代の転換点となる日付を正確に指定できないからといって二つの時代区分が無意味ではないように、境界が曖昧であるとしてもやはりことわざと物語との区別はしておいたほうがよい。物語は虚構の世界を作り、読者は自分の住む世界を忘れてこの作り物の世界に没入し、作り物の登場人物に同一化する。実感はこの虚構の世界の中での経験に付随するものである。しかしことわざの場合、私はこの世界から抜け出すことはない。というのも、ふつうことわざは現実のなにがしかの事態について言われるものだからである。たとえば共通の知人の最近の行為について「あいつは羹に懲りて膾を吹いてるね」といったふうに。このとき私はことわざの図式を通して彼の行為を見るようになる。すると彼の行為が急になにやら哀れな、あるいは滑稽な印象を帯び始める。あいまいな現実が明確な意味に収斂し始めるといってもいい。だが同時にことわざの方も、手応えのある現実に裏打ちされることで、その実感を強固にするのである。もっとわかりやすい例をあげよう。「馬子にも衣装」ということわざは、もともと皮肉な感じをもつ。しかしこれだけを聞いて笑いだす人はいない。ところが実際に知人が突然ブランド物を着て現れ、それに対して誰かが「馬子にも衣装だね」と言ったとすれば、つい笑ってしまうだろう。そもそもいまどき「馬子」という言葉からその風体を想像できる人は少ない。だが実在のむさくるしい誰かをこの言葉にあてはめる(つまり「馬子」に見立てる)ことで、この古めかしいことわざは生き生きとし始めるのである。ことわざは確かに具体的事例であっても(そうでない抽象的命題の場合はもちろん)それだけでは強い意味を実感させるものではない。それを特定の現実事態にレッテルとして貼り付けるとき、事態の方はレッテルの作用で特定の解釈だけを受け入れることになり、同時にレッテルの言葉の方もその裏打ちである現実の力で強力な実感を帯びるのである。
物語においては語られた言葉の力だけで体験可能な虚構世界を構築する。しかしことわざは言葉の外部で体験している(あるいはかつて体験された)現実に裏打ちされることで力を持つ。このように言葉の示す図式に対して私たち自身が適合する現実をあてがい、それによって言葉の実感を強化することを「受肉」と呼ぶことにしよう。すると物語を構築できない短い言葉でも、受肉によって物語に負けない実感をもつことができることがわかる。この現象が起こるのは何も旧来のことわざに限らない。たとえば「人は集団になると大胆に行動する」といった言葉は、集団心理のひとつの図式ではあるけれども、たいていの人にはすぐにその具体的事例に思い当たらず、したがって受肉も起こらず、何の感慨ももたらさないだろう。しかしビート・たけしの交通標語「赤信号みんなで渡れば怖くない」には日本人なら誰しも苦笑するだろう。じっさいに自分たちがそうしている現実に思い当たるからである。しかも日頃当たり前のようにしている行為が、実は「一人では臆病なくせに集団になると大胆にも法規さえ無視してはた迷惑な行為に及ぶ」という情けないものであることが、この標語の図式によって明るみに出るからだ。しかもこの標語の図式のおかしみが自身の経験の裏打ちによって実感されるとき、同時にその図式がじつは交差点ばかりではなく私たちの生活のさまざまの場面にあてはまることが予想される。実際私たちはこの標語をことわざのようにさまざまの場面で口にするのだけれども、たいていは文字通りの交差点での行動ではなく、旅行先での日本人団体の振る舞いなど、同じ図式があてはまる別の事例に対して言い、同じおかしみの実感を確かめるのである。
要するにことわざは図式を提示するためのものであるけれども、具体的事例をひとつ示し、それを受肉させることで、その図式が持つ意味を実感させることができる。私たちはその実感に基づいて図式の意義を理解し、その図式を日常生活のさまざまな場面に当てはめはじめる。すると現実の事態がこの図式にしたがって眺められ、見逃されてきた意味が(哀れであったり滑稽であったり)実感されはじめるのである。
こう考えてくると、短歌はことわざに近いということがわかる。短歌は物語を形成するに至らない具体的事例の記述であり、私たちが没入や同一化できるほどの具体的細部をもたないけれども、私たち自身の経験を受肉させることによって強い実感をもたらすことができる。それは言葉の意味を概念や表象として把握し理解することではなく、事態の意味を生きることであり、ある意味で身体的に体験することである。「思い当たる」とは意味を帯びた事態、意味を生きた経験に思い当たることであり、「受肉」とは言葉が身体的に経験可能なものになるということである。
短歌はそのために物語とは正反対の戦略さえとる。たとえば物語では人名は固有名詞が与えられるか、たとえ名前が分からなくとも誰であるかが特定される。しかし短歌では人名は「われ」とか「きみ」といった代名詞がつねであって、固有名詞が語られることはない。なるほど地名では固有名詞が用いられる。けれども、奇妙なことに歌道の伝統はその地名を「歌枕」と呼び、一種の伝説の場所とみなして現実の世界からは切り離してしまった。中世の歌論書は「吉野」は桜の名所であると知っていればよいのであって、実際にどこにあるか知らなくてもよいと教えている。つまり歌の中に「吉野」という地名が出てきても、読者は奈良県の吉野という現実の場所を想定する必要はなく、ただ「桜の美しい場所」を意味する普通名詞だと思えばよいのである。また内容の素材についても歌と物語とは志向が違う。物語が凡人の日常を語るようになるのは近代小説以降のことであって、それまでは神話伝説でなければ珍談奇譚、つまり超人的存在や異常な事件や異界のありさまを好んだ。オデュッセウスやかぐや姫、神々の戦争や宗教的奇跡、天界や冥府や桃源郷などなど。しかし短歌は凡庸な生活を送る凡人でも思い当たることのできる(たとえ未経験でも容易に自身のこととして想像できる)恋や老いや別れを、あるいは身近な四季の推移を詠んだ。短歌の提示する型は、同じ文化圏でふつうの生活をしていれば、誰でもその型に自分の記憶や想像を鋳込んで受肉させることができる。享受されるものの型は与えられたものだが、その肉は自分自身である。
私たちの内部の何かに思い当たることによって言葉が受肉し、深い実感を(そして感動を)与えるという好例は流行歌の歌詞にみられる。『神田川』が六〇年代、七〇年代に青春を送った人々にとって不朽の名作あり続けるのは、聞き手の記憶の中に思い当たるものがあり、それが言葉を受肉させるからだ。むろん歌詞に語られたような境遇を聞き手たちのすべてが経験したわけではない。ただ歌詞の内容を典型とするような生活、そして生活感のパターンを当時の学生たちは共有していたのだ。九〇年代に中学生・高校生であった人々にとっては、尾崎豊の『卒業』が永遠の古典になるかもしれない。だからこう言ってもいい。ある時代の生活経験に共通する図式の具体的事例、それも典型事例を示すことが歌詞として成功するための条件であると。
逆にいうと生活実態にあわない言葉は、ただ言葉の上の理解にとどまって受肉することができない。たとえばさきの「赤信号みんなで渡ればこわくない」という標語は、赤信号を見ると必ず立ち止まるという国では、また赤信号などまったく気にしないという国では少しも面白くないだろう。言葉が現実によって受肉されないからである。江戸時代の川柳が現代の私たちにとって必ずしも面白くないのは、風俗の変化のためにもはや語られている事態に思い当たることができず、そのため言葉が受肉しないからである。かつてあれほど隆盛した演歌が今日凋落しているのは、その歌詞が具体化している図式、たとえばひたすら不幸に耐え、別れた男を想いつづけることに自分の存在理由を見出している女というものが、現代の生活のなかで経験しにくくなっているからだ。あるいは少なくとも、そういう生き方に共感よりも拒否感を覚えるようになっているからだ。
広告コピーもまた時代の生活実態が人々にもたらしている実感をあてにしている。同時代の人々がその言葉に思い当たり、受肉しなければ、コピーは力を持たない。高度成長期、自分の活力と未来の成功を信じていた時代には「オー、モーレツ」という能天気なほどに単純なコピーが共感を得たが、不透明な未来のために現在を犠牲にすることを疑問に感じはじめた時期には「おいしい生活」というコピーが、ちょっとしたこと(たとえばちょっと高いパンを買うなど)で今の生活を楽しむことができることを発見した人々の共感を得た。ただコピーはあまりにも時代と密着しているため、消耗の速度が速い。十年もたつと時代の気分とずれが生じる。だが同じコピーを十年も使用することはないから、それで差し支えないわけである。俵万智の『サラダ記念日』が登場したときコピーのようだと言われたが、それはあまりにも正確に時代の生活感を具体化していることへの驚きと同時に、時代を超えて享受されることができないのではないかという危惧の表明であったろう。逆に言えば、歌はコピーとは違って消耗品ではないこと、古典となって末永く共感を得ることが期待されているのである。(私見を言えば『サラダ記念日』は『神田川』同様古典になりつつあると思うけれども。)
これに対し物語は時代を超えて生き残る。現在の私たちの生活実態とかけ離れていても、そんなことは問題ではない。たとえば主人への忠義のためにわが子の命を犠牲にするといった話は、いまどき誰も思い当たることはない。だから歌にならない。演歌でさえこんなテーマは扱わない。しかし歌舞伎座では今でもこの種の話が観客の涙を誘っている。それどころか古典として頻繁に上演され、観客もそれを期待している。たいがいの新作より封建的な物語のほうが客の受けはいい。なぜか。客に聞けば「だって泣けるもの」という答が返ってくるだろう。いうまでもなく「泣ける」ためには、観客はかなり深く「お芝居」の世界に没入し、登場人物に同一化している必要がある。
物語が時代を超えやすい理由は明らかだろう。虚構世界がしっかりと構築され、観客や読者がその中に没入し、私たちとは異なるモラルをもつ登場人物に同一化して生きはじめるなら、実生活ではとっくに失われたはずの生活経験を私たちは実感できるのである。過去の生活だけではない。異国の王族であれ、未来の宇宙生活であれ、誰も見たことのない天国や地獄であれ、虚構世界がリアリティをもって語られさえすれば、私たちは未知の経験をし、興奮したり笑ったり泣いたりできる。内容の図式の古さは物語が時代を超えるための障害にはならないのである。むしろ物語は私たちに未知の経験を教えることに意義があるともいえる。小説に私たちは何を期待しているだろうか。自分では想像もできない人生を仮想のうちに生きることではないだろうか。ダンテやカフカやSF作家は異様な世界を仮構した。古代の神話の語り手から現代の推理作家まで異様な事件を創作した。そしてドン・キホーテをはじめ無数の異様なキャラクターが誕生した。それはひとびとが物語による未知の経験を望んだからだ。没入と同一化によって、実生活では味わえないほどの興奮や緊張をしたいと思ったからだ。
むろん詩歌は物語であることができる。叙事詩もそうだし、韻文で書かれた西欧の悲劇もそうだ。日本では長歌がその可能性をもっていた。しかし長歌はついに物語へは向かわなかった。やがて長歌はその存在理由を失ったかのように消えてしまう。平安期の歌物語(伊勢物語など)は、歌にさまざまの事情説明を散文で加えて物語化しようとしたものである。要所要所に歌を配した源氏物語もある意味では歌物語であり、ただ事情説明部分が肥大しただけとみることもできる。しかしついにこの様式は日本文学の主流とはならなかった。歌は歌、物語は物語として発展したのである。日本人は歌と物語の役割をはっきり区別したのであり、しかも歌の役割は三十一字の短歌形式で十分に果たしうるものであった。
2 説得と詠嘆--長歌と短歌
長歌(ないし長詩型の歌)と物語とはどこが違うのか。また長歌と短歌はどこが違うのか。いくつか長歌の実例を見てみよう。
まず、柿本人麻呂の代表作といわれる「近江の荒れたる都を過ぐる時」の歌。
玉襷[たまたすき] 畝火[うねび]の山の
橿原[かしはら]の 日知[ひじ]りの御代[みよ]ゆ
生[あ]れましし 神のことごと
樛[つが]の木の いやつぎつぎに
天[あめ]の下 知らしめししを
天[そら]にみつ 大和を置きて
あをによし 奈良山を越え
いかさまに 思ほしめせか
天離[あまざか]る 夷[ひな]にはあれど
石走[いはばし]る 淡海[あふみ]の国の
ささなみの 大津の宮に
天の下 知らしめしけむ
天皇[すめろき]の 神の尊[みこと]の
大宮は 此処と聞けども
大殿は 此処と言へども
春草の 繁く生ひたる
霞立ち 春日の霧[き]れる
ももしきの 大宮処
見れば悲しも
反歌
ささなみの志賀の辛崎[からさき]幸[さき]くあれど大宮人の船待ちかねつ
長歌の大意は、神武天皇以来代々大和に都を置いてきたのに、何を思ったのか大津に遷都したが、その都もいまは失われ、廃墟は春草と霞に覆われて面影さえも見えないというものである。反歌は、琵琶湖畔の辛崎は昔に変らないが、もう大宮人の船は待っても現れないというもので、長歌の後半と同じ感傷を別の角度から反復したものである。長歌と反歌のちがいはといえば、長歌の方には「神武以来の都をわざわざ捨ててまでやってきたのに」という前半のくだりが後半の感傷を強化するための助走として、あたかも序詞のように付随していることである。だが結局長歌も短歌形式の反歌も、読者に求めている実感は同じものであり、ただ長歌はその長さを助走に利用したというだけのものである。これでは長歌形式であるための必然性に乏しく、長い短歌にすぎないと言われてもしかたがない。というより、人麻呂は短歌を作るように長歌を作ったのである。もともと彼にとって長歌と短歌は長さの違い以上の意味はなかったのだろう。
これに対し額田王の「春山の万花の艶と秋山の千葉の彩り」との優劣を判定する歌は、長歌ならではの内容をもつ。
冬ごもり 春さり来れば
鳴かざりし 鳥も来[き]鳴きぬ
咲かざりし 花も咲けれど
山を茂み 入りても取らず
草深み 取りても見ず
秋山の 木の葉を見ては
黄葉[もみつ]をば 取りてぞしのふ
青きをば 置きてぞ歎く
そこし恨めし 秋山われは
この歌には内容の展開がある。まず春について、鳥が鳴き花が咲くことを評価しながら、しかし手にとることはできないと不満を述べる。これに対し秋の木の葉は手にとって賞美できることを次に述べる。そして最後に、だから私は秋山を選ぶ、と宣言するのである。ここでは後の文の内容が先の文の内容を前提し、対照し、最後に全体を結論するといった内容の論理的展開が構成の骨格を成す。これは短歌ではできない。
また山上憶良の長歌も短歌で代えることはできない。たとえば「貧窮問答歌」
風まじへ 雨降る夜の
雨まじへ 雪降る夜は
術[すべ]もなく 寒くしあれば
堅塩[かたしほ]を 取りつづしろひ
糟湯酒[かすゆざけ] うち啜[すす]ろひて
咳[しはぶ]かひ 鼻びしびしに
しかとあらぬ 鬚[ひげ]かき撫でて
我をおきて 人は在らじと
誇ろへど 寒くしあれば
麻衾[あさぶすま] 引き被[かがふ]り
(中略)
直土[ひたつち]に 藁解き敷きて
父母は 枕の方に
妻子[めこ]どもは 足の方に
囲み居て 憂へ吟[さまよ]ひ
竈[かまど]には 火気ふき立てず
甑[こしき]には 蜘蛛の巣懸[か]きて
(中略)
しもと取る 里長[さとおさ]が声は
寝屋戸[ねやど]まで 来[き]立ち呼ばひぬ
かくばかり 術[すべ]なきものか
世のなかの道
反歌
世のなかを憂[う]しとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥にしあらねば
長いのでかなり略したが、それでも長歌の方は反歌とはまるで言葉の働きが違う。貧窮生活は単純に貧しさだけが強調されるのではない。貧窮という状況を生きることのいかなるものかを象徴する具体的事例をさまざまに積み重ねて、次第に複雑な生活が複雑なままに実感されてくるよう仕組まれている。厳しい気候に始まり、不甲斐ない生活と不釣り合いな自尊心とが滑稽に語られ、やがて家族を含めた一家の貧しさの実態が描写されてゆく。その内容の展開がこの歌の効果に必須であり、短歌という一息で思いを語る形式ではとうてい同じことはできない。実際、反歌は同じ主題で一つの図式を提示しているのだが、あまりに抽象的で本当に貧窮生活を送っている者にしか深い受肉はできないだろう。ふつうの人が読めば生活の不如意に愚痴を述べただけのように見える。これに対し長歌の方は、安楽な貴族にさえ世の中の不条理を実感させるだけの説得力を持っている。
与謝野晶子が日露戦争時に作った七五調の詩「君死にたまふこと勿れ(旅順口包囲軍の中に在る弟を歎きて)」も、古典的長歌形式ではないが一種の長歌であり、憶良の長歌と同じことが言える。
あゝをとうとよ君を泣く
君死にたまふことなかれ
末に生れし君なれば
親のなさけはまさりしも
親は刃[やいば]をにぎらせて
人を殺せとをしへしや
(中略)
旅順の城はほろぶとも
ほろびずとても何事か
君知るべきやあきびとの
家のおきてに無かりけり
君死にたまふことなかれ
すめらみことは戦ひに
おほみづからは出まさね
(中略)
すぎにし秋を父ぎみに
おくれたまへる母ぎみは
なげきの中にいたましく
わが子を召され家を守[も]り
安[やす]しと聞ける大御代[おほみよ]も
母の白髪はまさりけり
暖簾[のれん]のかげに伏して泣く
あえかに若き新妻[にひづま]を
君わするるや思へるや
十月[とつき]も添はでわかれたる
少女[をとめ]ごころを思ひみよ
この世ひとりの君ならで
あゝまた誰をたのむべき
君死にたまふことなかれ
この歌が発表された当時、帝国は大いに戦意高揚していた。熱狂していたといってもよい。そこへこのような歌を送り出すことは、襲撃されないまでも国民の憤激をかう危険がある(実際「乱臣賊子」との批判もあった)。それゆえ虎口に向かって放たれたこの歌は確実に読者の共感を得なければならない。ということは、好戦的な読者の意識さえ一八〇度逆転させるだけの説得力を持たねばならないということである。おそらく与謝野晶子はこの歌にその力があると確信していたであろう。だがそのためには短歌ではなく長歌が必要であった。さまざまの角度から弟に戦死すべきでないことを説き、「君死にたまふことなかれ」と繰り返して一歩一歩説得力を高め、最後には母や若妻の哀れな様子を述べてとどめを刺す。その見事な効果は、ただ一つ「戦争なんかで死んではいけない」という大きな実感に導くために、共感を得やすい小さな事項を適切な順序でひとつ又ひとつと積み重ねてゆく構成に由来する。
だが、ほかの長歌もそうだけれども、その言葉の積み重ねは物語のような世界の構築には向かわない。むしろひとびとが思い当たることのできる内容を、いくつか選択して並べるだけである。ただしその選択と配列には配慮があり、前の句を前提として後の句が効果をもつようになっている。つまり流れや展開という構成がある。その構成は読者に何事かを説得しようとするときに有効である。たとえば額田王のように、秋が好きだという自分の判断に論拠を与えようとする場合。あるいは憶良や晶子のように社会的な主題をもつ内容を読者に納得させるために、情景や心情を次々と提示して予定の場所にまで読者を誘導する場合。逆にいえば、それらは誘導されるべき終点、収斂されるべき結論に向かって流れる一本の川である。たとえば「やっぱり秋がしみじみとしていい」「なんてこの世は不条理なんだ」「戦争なんかで死んではいけない」という、必ずしもすべての人が共有しているわけではない物の見方を人々に納得させるべく設計されている。。しかしこれらの長歌には構造の構築、つまり全体で一つの新しい世界を作るという目標はない。これに対し物語は何よりもまず世界を構築し、その中に多様な人物や困難な状況を設定し、さらに伏線をいくつも張って事件を展開させてゆく。その建築にも似た構造に比べれば、長歌の構成はほとんど流れてゆくだけけのように見える。要するにそのやり方は短歌の連作に近いのである。
内容からみれば、物語は世界を構築したうえで事件を語り、ことわざは処世に際して起こりがちなパターンを図式化する。では歌は何をしてきたのか。長歌は人々にただちには共感されない見解を、誘導によって説得しようとする。短歌の場合、ひとことで言えば、詠嘆である。詠嘆とは情報の伝達でもなければ見解の主張でもない。眼前の事態に対し、あるいは自分が陥っている事態に対し、「ああ」とか「やれやれ」とか「ほほう」とか言うことである(昔ならば「あはれ」と言うだろう)。それは客観的な事態の冷静な認識ではない。自分の身体が既に事態に巻き込まれてしまっているがゆえの悲鳴とか呻きとかに近い。詠嘆の言葉が意味を表現しているとしても、その意味は概念として理解されたり表象として把握されたりするようなものではない。人はそのとき当の意味を自分の身体で生きているのであって、対象化しているわけではない。比喩的に言えば、人は意味に掴まれているのであって、意味を掴んでいるのではない。自分が対象化して掴んでいる意味は言語化できるけれども、自分を掴んでいる意味は言葉にならない。無理に言葉に出せば「ああ」とか「すごい」とかいった嘆声にしかならない。詠嘆とは、自分を巻き込んでいる事態、巻き込まれている身体、身体の事態への身構え、心の動揺や苦悩、それらのすべてを含んだ身体的意味の自覚の声である。短歌はそのような意味の型を凝固する。人麻呂の長歌はその意味の型が明確なひとつの型に凝固するまでの助走期間をもっているが、短歌はいわばクライマックスの一瞬だけを捉える。それは流れゆく生きる身体の一瞬の停止といってもいい。ちょうど歌舞伎の見得の型のように。
何事かを説得しようと思えば、歌は一歩一歩予定の場所へ読者を導いて行くための長さがあった方がよい。額田王のように理屈を語るためには長歌でなければならないし、与謝野晶子のように世論に反する思いの共感を得るためにはやはりそれだけの手続きが必要である。しかし詠嘆とはもともと「ああ」のひとことで足りる一瞬の事態であるとすれば、その詠嘆の型を明確に凝固するには、歌は短い方がよい。説得のためには読者を出発点では見えていなかった場所へ連れて行くために観念の展開が必要だが、詠嘆のためにはむしろ読者がすべての観念を一望に見渡せる程度の量であることが望ましいのだ。ただし短歌の内容は読者にとって思いがけないものではない。読者は歌の言葉に思い当たり、明確な型としては捉えていなかった経験を凝固して、一つの図式として確認するのである。これは読者を思いがけない場所へ連れていこうとする説得という目的には向かない。これに対し長歌は、その一句一句が既知の図式に思い当たるだけであるとしても、その積み重ねによって読者を新しい確信へと導くことができる。だから政治的社会的な訴えのためには長歌の方がふさわしい。山上憶良の「貧窮問答歌」が反歌のみであれば貧者の愚痴としか受けとめられなかったろうし、与謝野晶子の先の歌がもし短歌であれば婦女子の泣き言としか聞こえなかったろう。だが日本人は結局長歌よりも短歌を愛した。これは歌に対して、眼から鱗が落ちるような認識や深い共感にもとづく感動よりも、一瞬の詠嘆を求めたということである。もし文学の目的を社会的認識や芸術的感動を得ることにあると考えるなら、これは奇妙なことである。日本人は何か別のことを短歌に期待したのだと考えるほかはない。
現在、一般に文学というものがどのように考えられているだろうか。作者が言葉を媒体として作品を作り、読者(または聞き手)がその作品を読んで(聞いて)認識なり感動なりをする、というものだろう。この近代的芸術観の公式は最近問題視されているけれども、とりあえずここまではよいとしよう。問題はその先である。多くの文学論はその先を無視する。さもなければ、何らかの行動という形で読者に影響が現れると考える。たとえば道徳心を身につけて善行をするとか、社会的正義感に駆られて政治的行動に及ぶ、といったぐあいに。いずれも西洋や中国に古くからみられる詩の効用説である。しかしここでことわざの機能を思い出そう。「馬子にも衣装」ということわざは必ずしも人のファッションを変えるものではない。「赤信号みんなで渡ればこわくない」という標語は人々に交通規則を遵守させるわけではない。それらの言葉が発せられるとき、それは言葉の意味そのものを味わうというより、現実の私たちの状況をある図式にしたがって解釈することを促している。つまり、現実の認識、解釈、経験のしかたを指示しているのである。基本的にことわざは、現実の認識のための道具である。
ことわざを道具として現実を認識するやり方には、つまり私たちがことわざに「思い当たる」には二つのケースがある。ひとつは、あることわざを聞いてその図式を具現している実例に思い当たる場合。もうひとつは、ある現実の状況を前にしてその図式を言い当てたことわざに思い当たる場合。同じことは他のいくつかの文学形式にも言えるだろう。川柳や交通標語、寓話、そして短歌である。
白い航跡を残して湖上を行く舟を見て人は何を思うだろうか。人によってさまざまであろうし、何も思わないこともあるだろう。しかしたとえば「世の中をなににたとへむ朝ぼらけ漕ぎゆく舟のあとの白浪」という歌を思いだすとき、眼前の光景は無常の象徴に見えはじめるだろう。またたとえば風に散る桜を見ながら「久方の光のどけき春の日にしづこころなく花の散るらむ」という歌に思い当たれば、空中を絶え間なく舞う花びらに胸騒ぎが治まらなくなるかもしれない。私たちは過去の短歌に思い当たることによって、現在の状況を詠嘆することができるのである。
短歌は自分の生きている状況をひとつの型に凝固させるための呪文である。長歌にはこの機能がない。人麻呂の挽歌がどれほど優れていても、自分の愛する人の死にさいして誰もその長歌を諳じたりはしない。ことわざが短いものでなければならないように、現実から思い当たるための歌は短くなければならない。
平安時代の日本人は、現在の状況にぴったりの詩句に思い当たると、それを朗詠する習慣があったらしい。そのための虎の巻として編纂されたのが和漢朗詠集である。これは人の出会う状況を歳時記のように季節の題材(春夜や落花など)や人事の主題(慶賀や無常など)によって分類し、時宜に適した漢詩と和歌とを並べたものである。たとえば「春夜」の項を引こう。
燭[ともしび]を背[そむ]けては共に憐れむ深夜の月 花を踏んでは同じく惜しむ少年の春 白
春の夜のやみはあやなし梅の花いろこそみえね香やはかくるる 躬恒[みつね]
「白」は白居易のこと。出典は白氏文集中の作品だが、興味深いのは原作が八句から成る律詩であるのに、ここに引かれているのはその中の第三、四句だけだということである。この例は特殊ではない。実は和漢朗詠集に引かれている漢詩は、たいがい長い原典から二句だけを切り取ったものである。その情報量は短歌とほぼ同じになる。だいたい自立語で八~十語。現実の複雑な事情の全体ではなく、その一瞬の切断面を捉えるためには、漢詩の最短詩型である絶句の四句さえ長過ぎるのである。人が一掴みにできる観念の量は、おそらく八から十くらいなのであろう。短歌はこのような目的にはちょうどよい量なのである。
現在の文学論は文学のモデルを小説に置くことが多い。しぜん文学の機能を認識とか感動とかと考えやすい。しかし小説の対極であることわざをモデルにすれば、私たちは異なる文学の機能を設定することができる。それは人々が自分の身体で生きている意味を図式として共有し、そのときどきの自分の生きている現在の意味を確認するための文学である。処世についての図式はことわざや寓話や川柳で与えられる。しかし季節を生きて行く喜びや他者への思い(恋や哀悼)や自分の人生への呻きなどは短歌によって詠嘆の型として与えられたのである。
問題は、時代が変わると生活様式が変わり、同じ図式に思い当たる度合いが違ってくることである。古代の和歌は、じつはすでに今の日本人にとって異文化の所産である。語彙や文法の問題だけでなく、生活感覚や価値意識がかなり違ってしまったからだ。むろん短歌の選ぶ主題は比較的日常的なものである、四季の変化も、恋も老いも別れも、今なお私たちの生活の中で大きな意味を持っている。ただ昔の人と同じようにそれらを感じているとはかぎらない。むしろ私たちは古典を読み、その文化を学習することで、ようやくその美意識や恋のあり方を理解しているのかもしれない。しかし時代に応じて短歌は新しい型を言葉に表すことに成功してきた。古今集の恋歌に思い当たることがむつかしい若者も、俵万智の歌には思い当たってしまう。日本人が自分の生きている姿を型として捉え、その意味を繰り返し実感したいと思う限り、短歌は滅びない。第二、第三の俵万智は現れるだろう。