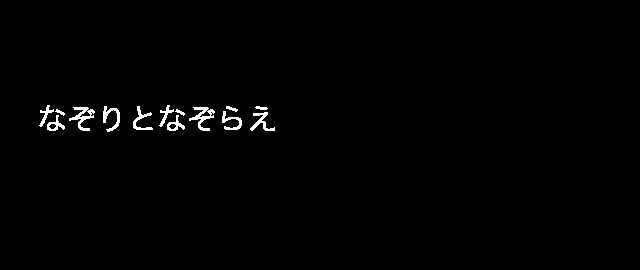序
パソコンを動かす基本システムには、よく知られているようにアップル社のマックとマイクロソフト社のウィンドウズの2種類がある。昔マックの愛好者はウィンドウズとの違いについてよくこう言ったものだ。「マックはマニュアルを見なくても使える」。それは嘘ではなかった。私の最初のパソコンはマックだったが、新しいソフトを使うのにマニュアルを見ることはほとんどなかった。多分こうするんじゃないか、という直感に頼って動かして、たいがいうまくいったからだ。私の勘がとくによかったわけではない。マックの操作法が「デスクトップ・メタファー」(机上の比喩)という原理で設計されていたからであった。使用者は、ふだん机の上でやり馴れた作業を、つまり引出しから書類を取り出し、書いたり消したり切り貼りしたり、ごみ箱に捨てたりといった作業をコンピュータの画面上ですればよい。じっさい画面は「デスクトップ(机の上)」と呼ばれ、隅にはごみ箱の絵がある。これに対しマイクロソフト社のシステムは(とりわけウィンドウズ開発以前は)、いろいろと定義や規則を覚えてしまえば自由に操作できるらしいのだが、素人には外国語の世界だった。やがてウィンドウズもマックの操作法をまねて、いまでは大差ないものになってしまったが、これは論理的体系的な使用システムよりもデスクトップ・メタファーの方が一般のユーザーには結局のところ使いやすかったためだ。ここには、私たちにとって新しいシステムを理解するとはどういうことか、という問題がよく現れているように思われる。たとえば、「コンピュータの中に登録された情報は適切な命令法を覚えれば、一時的に利用できない状態にしたり、再び利用できる状態にしたり、完全に消去することもできます」と言うのと、「いらない物はごみ箱に捨ててください。ごみ箱を空ければ永遠に廃棄されますが、ごみ箱にあるうちはもう一度拾い出すこともできます」と言うのと、どちらがわかりやすいだろうか。ふつうの人なら後者である。しかもその操作はコンピュータに「ごみ箱に捨てよ」などという命令をするのではなく、画面上でいらない文書の絵(アイコン)をつまみ、ごみ箱まで移動させるだけだ。これは二つの点でふだんの机上作業の比喩である。ひとつは不要の文書を掴んでごみ箱に入れるという身体動作。もう一つはその動作がもたらす「廃棄」という意味。私たちは、マウスで画面上の文書を掴んで動かしながら、この動作が意味していることをいわば身体で理解している。「マックはマニュアルなしでも使える」とは、私たちの体にしみこんだ日常の振舞いからこういう動作が何を意味するかを直観的に理解できるということであり、そのおかげで私たちはパソコンの構造について全く無知であっても、机上での振舞いになぞらえてパソコンを操作できるのである。
未知の世界を理解するのに既によく知っている世界になぞらえるという方法はいろいろな場面で使われている。たとえば「電気」という目に見えないものを理解するのに、私たちは「水」という、目に見える、しかもよく知っているものになぞらえる。電気に関する定義や法則を覚えただけでは今ひとつわかった気がしないのに、水をイメージすることで電気というものがわかった気になる。電流は水の流れに、電圧は水圧に、電力はほとばしる水の力になぞらえて、ようやく電気の定義や法則が何を意味しているかが理解できるのである。
デスクトップ・メタファーはもうひとつ重要なことを含んでいる。たとえば画面上の文書のアイコンをごみ箱のアイコンまで移動させるとき、それはヴァーチァルではあるが、紙の文書を掴んで机の横のごみ箱に投げ入れるという行動の模倣ないし再現である。これを言い換えればユーザーは画面を見ながら自分の手を使って、現実の身体操作を「なぞっている」のである。こうして理解のために「ある物」を「別の物」になぞらえること(なぞらえ)と、自分が「何か」を遂行するためにとりあえず「別の何か」を真似ること(なぞり)とが密接な関係にあることがわかる。以下この「なぞらえ」と「なぞり」について詳しく見てみることにしよう。
1.なぞらえ--理解の戦略
「なぞらえ」というのは世界を理解するための基本的戦略であり、子供の頃から身についた(おそらく生まれながらの)やり方である。たとえばポチという名の犬を飼っている家の幼児を考えてみよう。彼の最初の犬体験はこのポチである。母親が毛のふさふさした生き物を連れてきて「ほら、ワンワンよ」などと言いながら触らせたりすると、子供にもどうやらこの生き物は「ワンワン」と呼ばれ、頭を撫でると喜ぶらしいということがわかる。外へ出ると似たような生き物が近所にいる。子供は指さして「ワンワン!」と言い、ついでに頭を撫でようと手を伸ばしたりするかもしれない。これは子供が我が家のポチとよその犬を混同したということではない。子供はいつものワンワンによく似たものを見て、違う個体であることを知りながら同じ名前で呼んでみたのである。なぜそんなことをするのか。実は私たちが何かを学習する目的は、同じことを繰り返すためである。昨日食べたものと似た物が出てくれば、それも食べて構わない。以前自分に襲いかかった生き物に似たものが現れれば逃げ出したほうがいい。私たちの環境は時々刻々と変化しているけれども、それをいちいち新しい状況と見なしていたのでは生きていけない。似たようなものに対しては同じ対応をとる方が間違いが少ない。未知の物を前にしたとき、既に知っているもののリストの中から似たものを探し、学習ずみの対応をとることは、私たちが生まれながらに知っている戦略なのである。だから子供が初めて見る犬を「ワンワン」と呼ぶのは、単に形が似ているということの確認だけでなく、よく知っている我が家のワンワンと性格や振る舞い方がよく似たものであろうし、したがって同じ対応をとってもかまわないだろうという判断を伴っているのである。そこには既知のものになぞらえて未知のものを理解するという戦略が働いている。
子供は町を歩くうち、うちの「ワンワン」のようなものがあちこちにいることに気づくかもしれない。そいつらに出会うたびに「ワンワン」と呼んでみると、大人は「そうだよ、ワンワンだよ」と言って、子供の理解の正しさを確認してくれるだろう。このとき子供は、一群の個体がいずれも「ワンワン」という同じ一つの名前を共有することを学ぶ。そして同じ名前を持つものは同じような特質をもつはずだから、同じように対応していいと判断する。これを「カテゴリー」の学習という。彼は犬のカテゴリーの名称(「ワンワン」という記号)と、その概念(特徴やイメージ)と、その事例の群(外延)とを知ったのである。このカテゴリー学習こそ、人間が世界を構造的に理解する基本である。
しかしこのとき子供の得た犬の概念は、けっして動物学者が抱くようなものではない。彼の〈ワンワン〉の概念は、じつは最も身近な我が家のポチを事例として得たものである。あとの犬は、この「ポチのようなもの 」として理解される。もしポチが凶暴なら、犬とは一般に危険で近づかないほうがいいものとして学習されるだろう。大人から見れば「偏見」である。だがこれはカテゴリー学習として異常なことではない。また子供だけに特徴的なことでもない。大人だって、たまたまフランス人を一人知っている者が「いやあ、フランス人てのはねえ」などと、たった一人の事例から得た印象を一般化して語るのはよくあることだ。もともとカテゴリーを作るとは、似たようなものは面倒だから同じものとして扱おうという生活上の経済から出たものである。このとき既知の事例の特徴を一般化して、そのカテゴリー全体の特徴とみなすという乱暴なことが起る。これは確かに偏見のもとではあるが、私たちがふだん採用している一般的戦略なのである。現実にはフランス人といってもいろいろだろう。しかし実践的には、とりあえず自分の知る例をフランス人の典型事例とみなし、あとは「彼のようなもの」として対応の戦略を練るのが一番容易なのである。
既知の事例になぞらえて未知の事例を理解しようとするとき頼るべきデータベースは、個人的経験だけではない。歴史もまた現在の理解のために参照される。歴史書や文学の中に記された事例は「先例」として、繰り返される類型の原型とみなされる。たとえば源氏物語の第一帖には、後宮で帝の寵愛を一身に得ている桐壺の更衣を人々が楊貴妃になぞらえる話が出てくる。これは「帝と桐壺」の関係を「玄宗皇帝と楊貴妃」のようなものとして理解しようとする行為である。このなぞらえは、単に「帝の愛情の独占」といった解釈にとどまるものではない。歴史上の先例から「身分が低い者の分不相応な寵愛」「恋のために理性を失った君主」「失政による国の乱れ」「最期はろくな死に方をしない女」といった一連の意味がついでに含意されている。心あるものは桐壺の更衣を帝から遠ざけるよう努力すべきだという意味さえ暗示されている。つまり「楊貴妃」という先例は「傾国の美女」というカテゴリーの典型事例であり、桐壺を楊貴妃になぞらえるとは、桐壺もまた傾国の美女の一人だという解釈をすることであり、それは国の行く末を憂うことでもあるのだ。つまり現在の状況を先例になぞらえるというのは、一種の解釈行為であり、先例のイメージや構造を当てはめることで新しい状況の意味や構造が直観的に理解されるのである。
てっとりばやく理解してもらうために既知の典型例を差し出すことは、「メタファー」(隠喩)と呼ばれるレトリックにも利用されている。たとえば「Aさんてどんな人?」と聞かれて「客観的状況とか自分の実力とかをろくに考えずに無謀なことをやってしまう人だね」と答えてもいいけれども、そういうキャラクターの好例を共通の知識の中から見つけ出すというやり方もある。
「ドン・キホーテだね」
というぐあいに。ここで行われている操作は、子供が初めて見る隣の犬を理解するのに、既知のもののなかから似たものを探し、我が家にいる動物のようなものらしいと見て「ワンワン」と呼んだ、あのやり方と同じである。また「ふーん、Aさんてドン・キホーテなのか」とわかった気になる聞き手は、未知の「Aさん」を既知の「ドン・キホーテ」になぞらえて理解しているのである。
理解のよりどころとなるものは、人間でなくともかまわない。共有された動物のイメージはよく利用される。「男はみんな狼よ」「あの爺さんとんだ狸だ」「豚みたいに喰うね」等々。逆に人間以外のものを人間になぞらえて理解することも珍しくない。とりわけ理解のための既知のよりどころに乏しい子供には多い。たとえば雨の降るのを見て「お空が泣いている」と言ったりする。詩人もこれを利用してレトリックをあやつる。たとえば
春雨の降るは涙か桜花散るを惜しまぬ人しなければ(大伴黒主)
もっともこれは近代以前にはどこにでも見られた世界の解釈法で、海が荒れると「海神さまの怒り」のせいにしたりしたものだ。近代以後は自然現象を科学の言葉で説明することが普通になってしまったけれども、誰かの意志として説明するのはなかなか分かりやすいものである。なんといっても人の心や振る舞いは私たちにとってもっとも身近なものであるから。人になぞらえるレトリックを擬人法というけれども、これは文学者の専門ではなく、むしろ私たちの理解の戦略としてはもっとも基本的なものの一つなのである。むろん人間の身体へのなぞらえもある。椅子の「脚」と言い、釘の「頭」と言い、システムの中枢を「心臓部」と言う。マックのデスクトップ・メタファーも、私たちの身体の振る舞いになぞらえているという意味で、擬人法の一種だともいえるくらいである。
かっこよくて異性に人気のある少年少女を指して「A組のキムタク」とか「B女子高の紀香」などと言うのは、もちろんなぞらえのメタファーである。だがこのようななぞらえは、自分のアイデンティティにも利用される。サッカー少年はベッカムを、パソコン少年はビル・ゲイツを理想像としてそれに近づきたいと思うだろう。かっこよさで異性にもてたいと思う少年は木村拓也を理想像として、将来の自分に重ね合わせるだろう。彼らはベッカムやキムタク「のようになりたい」と思い、美容院で髪形だけでもそっくりにして貰ったりする。鏡をのぞきながら、なにやら自分が「ベッカムのようなもの」(つまり「かっこいい男」というカテゴリーのメンバー)になった気がし、他人からもそう見て貰えるのではないかと期待し始める。そしてベッカムの表情やしぐさを学んで、その真似をはじめるとき、「なぞり」という行為がはじまる。
2.なぞり
「真似る」の文語形の「まねぶ」が「学ぶ」と同じ語源であることからわかるように、真似は学習の基本である。しかし真似には二つの面がある。たとえば名人の踊りを見てこれを真似ようとする場合、ビデオを繰り返し観察して全身の形が同じになるように操作しても、見るものはどこか違うというだろう。そういう場合、たいがい本人にもどこか違うという気がしている。鏡を見ても形の上ではどこが違うかわからないのに、感覚として「そうだこれでいいのだ」という納得がないのである。ではなにが違うのか、なにが足りないのか、そしてなぜ違うことが感覚的にわかるのか。どうやら模倣には、外から見た形を真似ることと、そのとき身体内部で起こっていることを真似ることの二面があり、その両方に成功しなければ模倣はうまくいかないのである。
たとえば扇を差し出すという型がいくらやってもうまくいかないとき、師匠から「降る雪を受けるように」というアドバイスを受けて、とたんにうまくいくというようなことがある。師匠が「それでいい」と言い、自分にも「あ、できた」という納得がある。断るまでもないだろうが、これはもともと雪のシーンではないのだから、雪とわかるような演技をやれということではない。師匠はある種の身体の動きを、雪を受ける振舞いに「なぞらえ」たのである。弟子はその振舞いを心の中で想像し、「なぞって」みたのである。このとき弟子は、筋肉の力の入れ具合や動きの緩急など一連の身体的内部感覚をいわば音楽のメロディーのように一つの型(心理学でいう「ゲシュタルト」)として把握する。これを、「腕の角度はこうで、力はこのくらい、次の瞬間の動きの速度はこのくらい」といったぐあいに捉えようとしたり、師匠が「いやもっと腕を上に、速度は遅く」などと言っているうちは、覚えにくい上に何を表現しているのか自分でもわからない。仮に一度うまくいっても、もう一度実現することはむつかしい。そのやり方はまるで歌を歌うのに歌詞を発音記号の連鎖、曲を音の高さと順番として覚えようとするようなものだ。歌詞は意味のある言葉として、曲はまとまったメロディーとして覚えたほうが楽だし、実際ふつうはそうしている。踊りの弟子が「あ、できた」と思ったのは、身体を動かすさいの緩急や強弱の内部感覚を意味あるメロディー(ゲシュタルト)として捉えることに成功したということである。そして身体のメロディーとして覚えることに成功した動きの型は、その後何回でも繰り返し再現することができる。この身体メロディーは「もっと速く」「もう少し弱く」といった言葉の積み重ねで伝えることは、不可能ではないにせよむつかしい。そこで似たメロディーを持つ別の所作になぞらえるのである。弟子はその所作の身体メロディーをなぞることで、自分が実現すべきメロディーを掴むのである。
身体の型の「なぞり」や「なぞらえ」は、身体感覚だけでなく、その時の気持ちまで呼び起こすことがある。中村勘三郎の回想にその好例がある。忠臣蔵四段目で判官(浅野内匠頭がモデル)が切腹するとき、由良助(大石内蔵助がモデル)がなかなか到着しない。判官は由良助の息子力弥に「由良助はまだか」と訊く。力弥は花道が本舞台に接する端に座り、遠く花道の奥を見て「いまだ参上つかまつりませぬ」と悲痛な声で答える。この力弥の演技について六代目菊五郎は「揚げ幕(花道の奥にある役者の登場口)に仮に丸い穴をこしらえて、そこから向こうを見てみな」と教えた。勘三郎は心の中で揚げ幕の穴を想像し、そこから遠くをじっと透かして見るようにしてみた。すると「形と心がいっぺんに」わかったという(注1)。揚げ幕の架空の穴を見る役者の身体は、由良助の到着を待ち望む力弥の身体のなぞらえである。前者の身体を実現した勘三郎は、演ずべき力弥の身体の形だけでなくその心情まで同時に理解したというのだ。身体の外形を模倣することは、内面の型、則ち身体感覚や心情のある型を再現する。これが芸道における型の学習の意義である。直接に模範例をなぞることがうまくいかないとき、似たような型をもつ別の例(比喩)になぞらえてまで、なんとか当の型を再現しようとするのである。
勘三郎が「心と形がいっぺんにわかりました」というとき、その力弥の心とは何か。それはその場の状況の中の心である。理不尽な切腹を命ぜられ、恥辱と憤怒のなかでどうしても自分の思いを由良助に言い残そうと願っている主君。迫っている死の刻限。現れない由良助。しかもそれが自分の父であるという申し訳なさ。あれやこれやの複雑な心情があの「いまだ参上・・・仕りませぬ!」という悲鳴のような言葉になる。つまり力弥が自分の置かれた状況をどう理解し、それに対しどう思っているかということが、ここで体得すべき力弥の「心」なのである。「形」はこの「心」の反映である。「武家の作法」という厳格な文化的制約に身体を鋳込みながら、間に合わぬかもしれぬ父の到着を待って遠く一点を見つめる力弥の身体は、芝居の設定したその場の状況を一身で集約して表現する。つまり身体の型をなぞるとは、じつは単に身体という個物の問題ではなく、ある状況の全体とその中に置かれた身体という関係を理解し、実感するということである。
これは芸道だけでなく、なぞり一般の本質にかかわる。たとえば子供が親の言葉や振舞いをまねて覚えていくとき、それは音声の型や所作の型を覚えているだけではない。「おはよう」という言葉を覚えるとは、じつは朝という時間帯、他人と出会うという状況、その他人と自分とが友好的であるということを確認した方がいいという判断、そしてその他人を狙って何か合図を送ろうとしていることを示す明確な所作(見つめるとか微笑むとか手を挙げるとか頭を下げるとか)、そういった一連の状況や行動のなかで「おはよう」という発声を行うことを覚えるということである。それはある特定の状況下での自分の身体の振舞い方を覚えることであり、別の言い方をすれば世界の中でのこの身体の処し方を覚えることである。
「おはよう」と口にすることは社交的行為の一部としての音声による合図にすぎず、何か意味のあることを語るという通常の言語活動とは違うというかもしれない。しかし幼児が言葉を覚えるはじめの段階では、言葉の意味が身体的行動や状況に密接に結びついていることはよく知られている。たとえばウェルナーたちはある女の子が「ピン」という言葉で針やパン屑や蠅や毛虫まで指していたという例を挙げている(注2)。一件支離滅裂のようだが、じつはこの子供は床から慎重に指でつまみあげるものを何でも「ピン」と呼んでいたのである。おそらく大人が床から小さい針をつまみあげてみせ、この子に向かって「ピン」と言ったのであろう。それは危険に注意を喚起する行為だったかもしれない。その後この子はこの大人の行動をなぞろうとする。床の上に何か小さなものを見つけると、これを指でつまんで「ピン」と呼ぶのである。このとき「ピン」という言葉は、「小さく、細く、先の尖ったもの」というように特定の特徴をもつ事物を意味するのではなく、「床の上を歩く、小さなものを見つける、指でつまみ上げる、そのつまみ上げられたもの」というように事物を取り巻く状況や事物に対する活動を含めてその事物を意味している。大人の言語活動を子供がなぞりによって学習するとは、その言葉が使われる状況やその状況への身体の対応などを一緒になぞって体得してゆくということなのである。泳ぎかたを学ぶのに、机に座って泳法の図解を読むだけですまそうとする人はいない。プールなどの安全な場所で見よう見まねでもまず身体を動かしてみるだろう。言葉の学習もまた身体的学習であり、状況に対する対応法の学習であり、要するに世界の中での生き方の学習なのである。
ここで「なぞり」という身体的学習は内面の学習でもあるということを思い出してほしい。それは言葉や所作の「形」だけでなく、「心」をも学ぶのである。こどもは大人のあらゆる行為を真似ることによって、言葉やしぐさや物の扱い方などを学んでいくが、それは同時に伴う心をも学ぶのである。たとえば親の態度を真似ながら排泄物など不潔なものについて学ぶとき、それは何が「汚いもの」なのかという分類基準だけでなく、「バッチイ」と言う時の眉をひそめる表情や、なるべく手で触れないという態度、そして嫌悪感という感情まで学習し、身につけていくのである。身体的なぞりは、実は同一化対象としてのモデル(母親など)と世界を共有しようとする行為であって、外から見える所作だけでなく、世界をどう見るかという世界観、そこで見えてくる世界の状況、そして状況がもたらす心情まで同一化する。しかも知識や技術なら何を学習したかは本人にも自覚されるが、世界観や身体性の共有は当人にも意識されないことが多い。いつのまにか特定の物の見方や感じ方、あるいは身体のリズムなどが身につくのである。
ここに芸道の伝承で、「家」や内弟子という制度の果たす役割がある。成人してから歌舞伎の道に進んだ研修生が「やっぱり歌舞伎の家に生れた人にはかないません」というとき、それは訓練量の多さによる技術水準のことを指しているのではなく、幼児から役者の家に育つことでにいつのまにかからだに染み込んだ「歌舞伎的」な感性や身体性(間のとり方など)を指している。また内弟子は稽古時間としては通いの弟子より多いわけではないのに後継者となりやすいのは、師匠と日常の起居を共にすることで、その世界観や身体性が共有されてゆくからである。いわばクローンとして他の弟子より完成度が高いからである。技術は稽古だけで教えられるが、大事なことは技術の背後にある身体の生き方なのだ。それには絶えず師匠の身体を見て、それをなぞることが役に立つのである。
伝統芸能の稽古が目指しているのは、最終的に師と同じ身体を実現すること、つまり一種のクローンである。芸道で襲名という形で伝承がなされていくのは、この意味で自然だといえる。名前が同じということは、身体も同じということだ。代々同じ身体が継承されていけば、たとえば十一代目団十郎は初代団十郎と同じ身体を持っているはずである。少なくとも観客は彼に代々受け継がれてきた「家の芸」を期待する。それは何代目であろうと、「団十郎」の名前を襲名した者ならできるはずの身体の型である。それは二代目が初代の身体をなぞり、三代目が二代目を、四代目が三代目をという形で今に至るまで、そしてこれからも再現され続けるものである。
3.たとえ
菊五郎が「揚げ幕の穴」を見よと指示し、勘三郎がそれを実践することで力弥の「形と心」がわかったという話に戻ろう。この逸話は、相手の心とからだに何かを理解させようとするとき、ただ見るべきものを指示すればよいということを示している。こういうやり方は、じつはさまざまな場面で応用されている。この手法を宮崎清孝氏は「見え先行方略」と名付けた。たとえば文学作品の登場人物の心情を理解するのは小学校二年生の子供には容易ではない。そういう時教師はどうするか。宮崎氏はきつねの母子の物語を教材にした実際の授業を報告する。教師は子供たちにこんなふうに問いかけた。
雪野原を子ぎつねひとり、よちよちした足どりで町へ向かううしろ姿を見送っているかあさんぎつねは、どんなことを心の中でつぶやいたと思いますか。子ぎつねの姿はだんだん小さくなって、ごまつぶより小さくなって、あっ、もう見えなくなりましたよ。(注3)
物語を読み聞かせただけでは小学校二年のこどもは母ぎつねに共感してくれない。しかし母ぎつねの視点からどんなふうに子ぎつねが見えたかを語り、そのイメージをこどもたちに想像させることで「教師はこどもたちをかあさんぎつねの立場に『たたせて』しまい、それによってかあさんぎつねの心情を実感的につかませようと」しているのだと宮崎氏は解説する。大事なことは、ここで教師は母ぎつねから見た光景を語っているだけで、母ぎつねの心情については一切語っていないということである。かりにその心情を「不安」とか「淋しい」とか「心配」とか「気遣い」とかいろいろ言葉を並べて説明しても、七、八歳の子供に正しく理解できるかどうかは覚束ない。しかも文学作品の場合、そもそも心情を言葉で説明しても意味がない。というのも、文学が要求しているのはその心情を実感することであって、それを適当な言葉で整理することではないからだ。(だから和歌では「淋しい」などと心情を直接表現すると拙いと批判されたりする。)
こどもたちが行なったことは、ただ母ぎつねの視線をなぞることである。 そしてそれによってこどもの身体の中に何かが生じ、心情が意図せずして実感されたのである。じつはこの仕掛けこそ、古来「たとえ」とかレトリックと呼ばれてきた文学的手法の中核である。江戸時代の歌学者富士谷御杖は和歌の伝統的レトリックを読者が心情を自発的に生起するための戦術として説明し、その方法を「比喩」と「外へそらす」の二つに分けた。
比喩とはある物を別の物になぞらえることである。たとえば「あいつは狼だ」という時、それは「あいつ」という人間を「狼」として見るということである。「として見る」とはどういうことか。それはあいつが「狼」に見えるような特別な視線を想像し、そのような見方をなぞってみることである。そのとき狼を見るときの身体が仮想的に生じ、その凶暴への恐怖、貪欲への嫌悪などの心情が実感されるだろう。この実感が生起するとき、比喩という方略は成功する。「あいつは狼だ」と言うのは「あいつは凶暴だ」と言うのと同じではないし、その言い換えでもない。「凶暴」という言葉を直接に使用しても、身体的「なぞり」がなければ心情は生起しにくいからである。
「外へそらす」とは、御杖の説明を借りれば、人から貰った贈り物を感謝するのに、その物が珍しい物であることを述べるなどである。礼状で心情を直接に伝えようとして「ありがとうございます」とか「喜んでいます」などと書いても、本当にそう思っているのか疑わしい。しかしその珍しさについて書いてあるとき、読み手は書き手の視線を知ることができる。ある物を「珍しい物として見る」視線をなぞるとき、珍しい物を手に入れればうれしいのが人情であるから、書き手の喜びを実感できるだろう。
こうしてレトリックとしての「見え先行方略」は、単なる言葉の言い換えとか、巧みな表現といったものではなく、読者に視線をなぞるという身体作業を要請し、自発的な心情の生起を促し、書き手への共感を得るという、一種の身体的方略なのである。ひらたく言えば、頭でわかるためではなく、身体でわかる(「腹に入れる」とか「腑に落ちる」)ための方法である。もともと人は「なぞらえ」によって世界を理解し、「なぞり」によって世界の中での身の処し方を学習してきた。詩歌が新しい世界の見方や、その美しさへの驚きなどを語ろうとすれば、「なぞり」や「なぞらえ」そして「たとえ」を利用するのは自然な戦略であるといえる。
結
「なぞらえ」とは未知の物や事態を既知の物や事態「のようなものとして見る」ことである。それは私たちが世界を生きてゆくさいの、基本的な理解の方略であった。「なぞり」とは自分が「先例(手本)のようなもの」となるために、その身体を内部から模倣する(まねる=まなぶ)ことであり、それは他者を理解する方略であるだけでなく、自分のアイデンティティを実現するための方法でもあった。本稿では基本的図式だけを提示したが、この仕掛けはさまざまな場面で大きな役割を果たしているように思われる。この問題の広さを示唆するため、二つの例をあげることでこの稿を終えよう。
「ジェンダー・アイデンティティ」はどのようにして身につくのだろう。つまり「自分が男だから、男らしくしよう」とか「自分は女だから、女らしくしようは」といった意識はどのようにして教育されるのだろうか。親や社会が外部から強制したり、教育したりした結果だろうか。それもあるだろう。しかしむしろそれらは自発的に学ばれるのだと思われる。自分の手本として選んだモデル(女の子なら母親とか)を身体でなぞるうち、所作の型だけでなく、その見方や感じ方、そして価値観や感情の動き方までも身についてくるのである。なぞりは「形と心がいっぺんに」わかるだけでなく、それを無意識のうちに自分のものにしてしまう。言い換えれば、先例のジェンダーの型に嵌まってくるのである。むろんモデルは年代によって変わってくるから、また場所によっても使い分けたりするから(先生の前と友だちの前では「女の子」の手本は違う)、「女らしさ」の実体は単純ではない。けれどもジェンダーの制度の大枠から外れる身体を目にすると、それが排除すべき(あるいは珍物として鑑賞すべき)異物と見えてしまうほど、その制度は身体に染み込んでいるのである。
もう一つのケースとして、人と人とのコミュニケーションの場面をあげよう。うまくコミュニケーションがとれている関係をよく「波長が合う」とか「息がぴったり」などと言う。これは実は比喩ではなかった。岡山県立大学の渡辺富夫氏は、対話している二人の心臓の鼓動や呼吸のリズムが同調してくることを実験から確かめた。これを「引き込み」という。対話の場面では相互に相手のリズムに引き込まれる、あるいは引き込むという現象が起こっているのである。これはコミュニケーションがうまくいくために、無意識のうちに互いに相手の身になろうとして相手の身体リズムをなぞろうとしていることを意味している。また渡辺氏は、相手の言葉に対する反応であるはずの「頷き」という動作が、実は相手の言葉が終わらないうちから開始されていることを発見した。これは身体リズムの同調があるからこそ、相手の話が一段落しそうになるとき自分の身体も一段落の準備を始めるのだということを示している。またこのような身体リズムの同調の有無は話し手にも影響する。渡辺氏は「SAKURA」という疑似聴衆ロボットを作り、このサクラが的確なタイミングで頷きなどの反応を行うと話し手にとっても話がしやすい(ノリがよくなる)こと、逆にこの反応をずらすと(つまりシラけた、あるいはだらけた聴衆を演じさせると)話がしににくくなることを確かめた。これは話し手の方も聴衆の身体リズムに同調しようとしており、そのリズムが明確でないか、あるいは自分の話のリズムと合わないとき、自分のリズムをうまく維持できなくなる(ノリが悪くなる)ということを示している。渡辺氏の研究は「引き込み」という身体リズムの同調がコミュニケーションの成否に決定的な影響を与えることを証明したものである。だがこの事実は、他者の身体の「なぞり」という行為が、私たちの日常生活の中で不断に行われているということを意味している。身体的なぞりはなにも学習のためだけでなく、私たちが相手を理解するために相手の身になろうとするとき、いつも行われているのである。リズムの同調はいわば「形」を相手に合わせることだが、それによって「形と心がいっぺんに」わかるだろう。それは相手の言い分の論理を理解するというより、端的に相手自身をその内面から理解しようとすることであり、その理解は「頭でわかる」というより「身体でわかる」というべきものなのである。 コミュニケーションとは「情報の伝達」ではなく、「世界への視線」や「世界に対する心情」を共有することであると考えてみよう。するとコミュニケーションとは実は「世界の中の身体」のありかたを共有することであり、「引き込み」という身体的同調はその基礎なのだとわかる。そして「たとえ」や「なぞらえ」というコミュニケーションの方略は、まさに同じ視線を共有するための仕掛けであり、身体の「なぞり」を喚起するための手段である。それはコミュニケーションの困難な他者と相互理解を成功させるために、古今東西を問わず人々が自然に利用してきた方法なのである。
注
1 生田久美子『「わざ」から知る』東京大学出版会、九五頁
2 H・ウェルナー+B・カプラン『シンボルの形成』柿崎祐一監訳、ミネルヴァ書房
3 宮崎清孝+上野直樹『視点』東京大学出版会、一三九頁