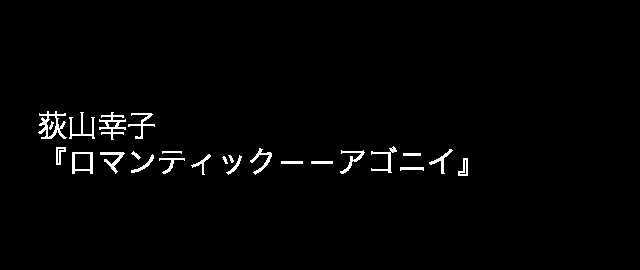荒野のウェディングドレス
作家たちが些細な新しさを争う現代に、今どき前世紀の西欧の美意識で作品を作る者がいれば、時代錯誤を笑われる。しかもそれが大仰な浪漫主義や濃厚な世紀末風であったりすれば、見ている方が気恥ずかしくなる。だがそんなことは百も承知の上で、荻山幸子は西欧の伝統の中にある「美の究極としてのエロチシズム」を再生しようとしてきた。彼女は確信犯であって、勘違いしていたのでないことは確かだが、それにしても現代の舞踊界の中で彼女の行為は、ウェディングドレスで運動会に出ていくように見えたものだ。毎年の試行錯誤を見るうちに私は彼女の反時代的実験を貴重なものと思うようになったけれども、現代の作品として成功するためには何かが欠けているような気がしていた。そして今年、彼女はついにその何かを手に入れたようだ。幕が降りた時、私には、自身の様式と自身の世界とを確立した一人の作家の誕生に立ち会ったという感慨があった。同時にそれ以上に私を考えこませたのは、この舞台の成功が示唆していることだった。つまり、彼女は間違っていなかったのだ。ポスト・モダニズムさえ古びてしまった現在の舞踊界は確かに荒野であり、人はつい自由な運動着で走り出してしまうけれども、この荒野を劇的な空間にするためには、むしろウェディングドレスこそふさわしいのではないか。
出演は荻山の他には喪服のような黒いドレスと黒いヴェールを着けた四人のコロスだけである。コロスは黒子であり、死神にも見える。一時間半のソロを持ちこたえさせるための凝った仕掛けは何もない。舞台装置はないに等しく、ただ衣装と小道具だけは上等の本物を用いる。始まりはこんな風である。全ての明かりが落ち、『トゥーランドット』のアリア「誰も寝てはならぬ」が闇の中に響く。照らされた客席の通路に黒子が現れ、観客の頭上に本物の香水と本物の薔薇とを撒き散らして消える。曲は『ローエングリン』に変わり、華麗な白鳥の仮面をつけた荻山が白いドレスで通路に現れる。と、こう書くといかにもクサイように思えるかもしれない。実際これで荻山が思い入れたっぷりに踊りだせばげんなりしただろう。しかし予想に反して彼女はほとんど何もしないのだ。実はこのシーンは音楽が主役であり、プッチーニとワグナーは嗅覚と視覚の助けを得て、いつも以上の官能性をもって観客を捉えるのである。今回の公演の成功は、おそらく「舞踊公演である以上、踊ることが中心になるべきだ」という観念から自由になったことが大きいだろう。荻山は音楽・照明・衣装・小道具などを踊りと同じ比重で扱い、荻山自身も踊るだけでなく演技し、喋り、唄まで歌った。要するに踊りを見せるよりも世界を構築しようとしていた。例えばフラメンコのシーンでも、普通のダンサーのようにここが芸の見せ場と踏ん張ることをせず、ある情感と雰囲気とを紡ぐだけだったが、それは前後のシーンとの対比の中で意味をもつように計算されていた。最後にマーラーの交響曲五番からあの有名なアダージェットが使われたが、ここでも荻山はわずかな所作と歩くことの他は何もしなかった。しかしこれまでの時間が既に濃厚な世界を作り出していたため、それで十分だった。私にはアダージェットがこれほど官能的に聞こえたことはなかった。それは聞くというより、蜜のようなものが身体に染み込んでくるような体験だった。「マーラーってこんなに凄かったのか」と思うと同時に、ベジャールの『アダージェット』にはこれほどの官能性を感じなかったことを思いだした。荻山はアダージェットにふさわしい振付を考えたわけではない。ただアダージェットを正しく聞くための準備を私たちの内部に作ったのだ。一つの音楽の深みを観客に教えるためには、なにも踊って見せる必要はない。その音楽をどのように受けとめるべきかを示唆する身体、ある表情をもった身体がそこに立っているだけでもよいのだ。
今世紀の舞踊は常に古いものを乗り越えてきたと言われるが、それは蓄積された文化の資産をひとつずつ捨ててきただけだとも言える。厳格な型の技術を捨て、役柄を表す衣装や意味を表す所作を捨て、身体による表現を捨て、というふうに。最後に残ったのはダンサーの生身だけだ。全ての文化遺産を破壊すれば荒野になるほかはない。確かに自由は たっぷりあるけれども、そこで何ができるだろう。剥き出しの性か剥き出しの暴力。あるいは単なる運動会。といって独力で建設できるものは、せいぜいがみすぼらしい小屋だろう。かつての文化が人材を尽くし歳月をかけて達成した宮殿の豪奢やエロチシズムの深淵には及びもつくまい。
社会が文化を育てあげていくとき、それはどこへ向かうのか。一つは多分宗教的なものだろう。だが一つがエロチシズムであることも確かだろう。爛熟した文化は必ずその結晶としてエロチシズムの様式を作り出すのだ(たとえば江戸文化の粋としての歌舞伎)。逆に言えば、エロチシズムを実現するためには、どこかの文化資産を利用するほかはない。それは時代錯誤的な試みにならざるをえない。しかし一度エロチシズムの深さに戦慄してしまった者には、剥き出しの性など原始的にしか見えないだろう。荻山にできることは荒野にウェディングドレスで出で立ち、闇と光と音楽と香水とでそこを儀式の場に変容させることしかない。