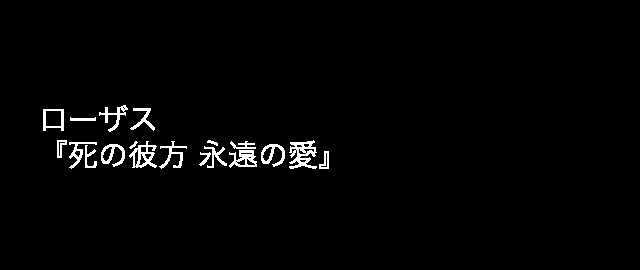ハイヒールのピュタゴラス
「死の彼方」へ行くために人は何をすればよいのだろうか。かつて霊魂の不滅と輪廻転生を説いたピュタゴラスは、万物の原理は数にあるとし、音楽を薦めた。音楽は宇宙の数学的秩序を反映しているため霊魂を浄化すると考えたのである。彼の教団では数学と音楽が学ばれた。その後永く西洋では、音楽は数学の一種として、文法や論理学とならぶ貴族の教養の一つとなった。けれども、もしピュタゴラスが女性だったら、音楽ではなく舞踊を薦めたのではないだろうか。彼はディオニュソスの徒でもあったのだから。
ローザスの新作『死の彼方 永遠の愛』を私は春にパリとバルセロナで見る機会があり、それについては昨年の6月号で報告したが、12月の横浜公演はいちだんと洗練が加えられていた。多様な要素を複雑に縫い合わせたこの作品は、緊張の糸を失えば雑然とした舞台になってしまう。だが今回はその糸が切れることなく、見終わったあとには何か透明なものを見たような印象さえ残った。とりわけダンサー達の動きの間合いや絡みがいっそう緊密になったように思われる。春には要素の多様さが目立ったのに、今回はそれらを一つの式に括りあげる数学的構造の完成度が目に鮮やかだった。
プログラムを見てまず気がつくのは、「構想・演出 アンヌ=テレサ・ドゥ・ケースマイケル/ティエリー・ドゥ・メイ」とあり、そのあとに振付がケースマイケル、音楽がドゥ・メイと記されていることである。これは二人の合作なのだ。しかもその共同作業は完全に対等であった。あるときはドゥ・メイの音楽を分析して得られた構造をもとにケースマイケルが動きを作り、ある時は先に作られたダンスのフレーズを解析してリズムを取り出し、それにドゥ・メイが音楽をつけた。この共同作業が成功したのは、二人が同じような制作手法をとっていたからである。第一に、二人とも古典的な振付家でも作曲家でもなく、新しい作品のあり方を模索していた。第二に、創造性は作品の主題や表現内容よりも形式や構造に求めるべきだと考えていた。つまり、新しい語彙群の発明とそれを操作する文法の開発に関心があった。第三に、その文法は数学的な構造として考えられた。つまり二人は数学者のように作曲し、振付を行ったのである。
公演の翌日、二人は共同のレクチャー・デモンストレーションを催し、その一端を披露した。ケースマイケルは、簡単な動きの基礎的単位をとりあげ、これにさまざまな変形規則を与えて展開してみせた。たとえば、おなじフレーズを、次第に速くしたり遅くしたりする。さらに上半身は速く、下半身は遅くしてみる。あるいは二人のダンサーの一人が速く、もう一人が遅くしてみる。三人目のダンサーが一人の右半身ともう一人の左半身を組み合わせてみる等々。基礎となる動きのボキャブラリーは主にダンサーたちの即興的動きから拾い出され、ケースマイケルはむしろその分解・変形・組合せを自分の仕事とみなしていた。その構成原理は数学的秩序である。つまり音楽の秩序と同じである(ケースマイケルは振付家は楽譜が読めなければだめだと言った。使用する楽曲の構造が把握できなければ、振付などできるわけがないという意味である)。だが動きの解析と数学的再構成なら、カニングハムもフォーサイスもやっていることだし、多くのヌーヴェル・ダンスの振付家が試みていることでもある。彼女の独自の感性は、数学的構造という骨にどのような肉と皮を着せるかに現れる。
最後の質問者が「踊りにくいのに、なぜハイヒールを履かせるのか」ときいたとき、ケースマイケルは一言「だってセクシーでしょ」と答えた。フェミニズムの時代にこの不用意といってもよいほど無造作な答えは、彼女の感性をよく示しているだろう。これまで男性振付家たちが潔癖に性を排して抽象的運動のみを提示した結果はどうだったか。純粋ではあるけれども、かえって豊かな音楽のもつあの魔術的な力を失っていたのではないか。もし純粋であることだけでは満足できないなら、低俗な性も永遠の愛も、ダンスの力の回復のために採用をためらうことはない。ただしそれは観客の欲望に応えるためではなく、ただ数式の一変数として利用されるだろう。かくして『死の彼方 永遠の愛』では、激しいダンスと共に愛の詩が語られ、ズボンやスカートのない男女が軍隊のように整然と動き、ハイヒールが凶器のように風を切る。そこにはミ ュージカルのように観客に媚びるセクシーさはないけれども、たしかに目を引きつけてやまぬ力がある。女性となって現代に転生したピュタゴラスは、音楽によって人々の霊魂を浄化するより、ハイヒールで踊ってみせることによって魂を揺り動かすことを選んだようである。