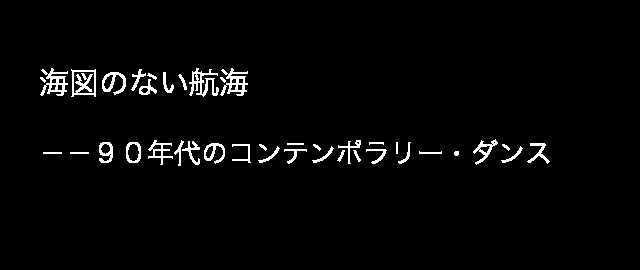一九九〇年代は、日本の近代史の上で特異な時代だった。人々は経済の沈滞ぶりから「失われた十年」と呼ぶ。しかしこの時期に生まれたダンスを見ていると、実は文化的にはとても意義のある時代だったのではないかと思えてくる。
わずか十年の間に日本人の意識はまったく変わってしまった。「土地神話」の崩壊以後ひとびとは「安全な資産」などどこにもないと覚悟した。ソ連の空中分解以後「正しい思想」というものがみな空論に見えはじめた。さらには不滅の日本文化と思われていた終身雇用制さえあっけなく見捨てられ、いい大学を出て大企業に入ればとりあえず一生安泰というお約束は反故になった。若い世代は「安定した身分」どころか年金さえ当てにできないと腹を括っている。要するに旧世代が確かなものとして信頼してきた世渡りのシステムがいきなり蜃気楼のように不確かになってしまったのである。人生は坂道のようなものだという年寄りの教訓は、楽な人生はないけれども地道に努力を続ければいずれ目的地に着くという比喩だが、これは道も目的地もはっきりしていて、おまけに地盤が崩れないという前提があるからこそ言えることだ。今や社会へ出て行こうとする若者にとって、確実な地盤などありはしない。気まぐれな天気のもと大海に小舟を漕ぎだすような気分だ。これは見通しのきく人生を送ろうとする者には困ったことだが、何一つ確かなものはないという状況は、しかし芸術にとって悪いものではない。経済的には苦しいとしても、掛け値なしの自由がそこにはある。そして、その果実のひとつが日本の新しいダンスである。
ダンスに限らず、芸術というとき、二つのタイプがある。一つは登山型、もう一つは大航海型である。登山型とは、目の前にある山にできるだけ高く登ろうとするものをいう。高みに達した芸術家は達人とか名人とか呼ばれる。芸道がよい例だ。道は既に先人がつけている。どこまで行けるかが問題なのだ。必要なものは、善い師とたゆまぬ修行である。一方大航海型は、新しい航路を開き、未知の大陸を発見して人々に知らせるものである。芸術家に期待されるのは、創造力によって新しい美の領土を切り開き、人々を招き入れることである。必要なものは、かすかな風に新しい島の匂いを嗅ぎつける直感と試行錯誤に耐える忍耐力である。登山型は完成度の高さに価値を見出し、大航海型は新しさに価値を見出す。クラシック・バレエや日本舞踊などは登山型だが、近代芸術は一般に大航海型だった。なにせ「モダン」(近代・現代)とはもともと「昔」に対して「今」を指す言葉だから、芸術家が自分の仕事を「モダン」と形容するときには、暗に芸術は時代によって変わるものだと言っているわけである。背後には、新芸術は旧芸術より進歩しているという歴史観がある。モダンダンスもモダンアートも「新しい」からこそ価値があるのだとすれば、芸術家は常により新しいものを求めて航海しなければならない。というわけで、二十世紀の芸術家たちは「新しさ」のトップランナーになろうとして独創を競ったのだが、中でも新しさで際立つものを「前衛」と呼ぶ。二十世紀の芸術史の本を開くと、その中心はたいがい前衛芸術の歴史であって、まるで新発明や新発見の歴史を書いた科学史の本のようだ。けれども「新しくなければならない」「常に過去を否定して前進しなければならない」という条件で芸術をやるのはきついものがある。一九八〇年頃には前衛芸術も「芸術の進歩」という考えも行き詰まった。もうやれることはやり尽くし、歴史は前進を止めたように見えた。「芸術は終わったのか」とさえ問われたほどだ。それは「モダン」信仰の終りでもあった。このとき、忽然として世界に新しい風が吹いた。「ポストモダン」つまり「モダンの後」である。これは要するに「なんでもあり」ということだった。古い手を使ってはならないという制約に縛られていた芸術家たちは、解放されたようにあの手この手を使い始めた。古い素材が重苦しい約束事から切り離されて、新しい調理法で軽やかに、たいがいはむやみに明るい作品へと料理された。それはとりわけ日本では、あのバブルの時代にふさわしいものだったといえる。けれども「ポストモダン」という思想ははじめから奇妙なところがあった。それは過去を否定する近代主義から解放されたと言いながら、じつは「モダンの後」という名称からわかるように、歴史を意識した思想だった。それは「偉大な規範があったモダンの時代」を前提とした「モダンの後の何も規範がない時代」なのだ。そしてポストモダンがモダンより優位なのは、モダンよりも「新しい」からなのだった。結局ポストモダンは、「新しいもの」を礼賛するモダンの時代の最後のファッションだったと言える。「新しいもの」を作るこつは「古いもの」をよく見ることである。「古いもの」に何が欠けているかさえ見つかれば、それを使えばよいわけだ。こうしてモダンであれポストモダンであれ、過去を見ながら新しいものをひねり出すという点では同じやり方をしていた。けれどもこのことが意味しているのは、芸術家の独創がどこにあるのかを知るためには観客の方も古いものの知識が要るということである。前衛を好む芸術愛好家は芸術の歴史を知っているからこそ、新しい芸術に驚き、感動することができたのだ。
ポストモダンの芸術家たちにとってまだ芸術という制度は確固たるものに見えた。しかし九〇年代に芸術に参入した者にとって、ポストモダンという様式も、芸術という制度ももはや確固としたものではなかった。しかも社会の過去のシステム全般が既に崩壊しつつある時代に、「古いもの」を否定してみましたなどという芸術には意味がない。九〇年代の後半に日本のダンス界に現れた若者たちの仕事がそれ以前と違うのは、彼らがもはや過去を見ていないということだった。かわりに見ていたのは、現在の自分の周囲である。つまり、まさに同時代の状況から彼らのダンスは生まれていたのだ。まただからこそ彼らのダンスは、綿々と続くダンスの歴史をふまえて見る必要はなく、私たちが呼吸している現代の空気と同じように、自然に私たちの感覚に呼応する。そして彼らの観客もまた、ダンス一般のファンというより、現代文化の先端に面白いものを探している同世代の若者たちだ。この意味で、彼らのダンスは「モダンダンス」というより「コンテンポラリー・ダンス」(時代を共有する舞踊)と呼ぶのがふさわしい。逆に言えば、それらは現在の都会の文化状況を反映している。しかもその文化は21世紀となった現在、ひろくアジアの大都市に共通するものでもある。
ひと口にコンテンポラリー・ダンスといっても、実際はいろいろである。珍しいキノコ舞踊団は「かわいい」皮膚感覚を維持しつつ親密な日常がそのまま非日常に反転するような場所を作り出す。レニ・バッソは自分と他人の身体の間に古武術の試合のようなスリリングな空間を作りだす。発条トは時間を寸断し再編集して時間の迷宮を作り出す。それらが共通に持っているものを探そうとすると難しい。けれども私のような旧世代の人間が見ると、共通に持っていないものがあることに気がつく。それは西洋の眼である。そもそも「芸術」も「前衛」も「モダンアート」も「ポストモダン」もみんな西洋生まれの言葉である。だから私たちが日本の芸術を見る時も、どうしても西洋的な「芸術」の基準で物を見る癖がついている。それはいわば西洋の眼で見ることである。日本の新しい芸術を評価するときも、参照されたのはいつも西洋の新しい芸術であり、それと比較することで国内の作品のレベルを語っていた。いや登山型芸術でさえそうだ。日本も文化国家であるためには普遍的芸術であるオペラやバレエの水準を上げるべきだという植民地主義的な主張から、西洋人が感心するのは西洋の猿まねではなく日本の伝統芸術なのだというナショナリズムまで、西洋の眼は明治以来いつもつきまとっていた。しかしコンテンポラリー・ダンスの若手たちには、どうやら西洋はモデルでもライバルでもない。現代文化の中で生まれ育った彼らにとって、現代西洋は他者ではなく、携帯やメールで連絡をとりあっている友達のようなものだ。憧憬もなければ敵意もない。同化しようとも思わなければ、違いを強調しようとも思わない。西洋の眼で自分の姿を見直すことなど、もう何の意味もないのだ。このことはあまりにも当たり前なので彼ら自身意識していないことかもしれないが、旧世代からみるとたいへんな解放である。ただ自分の感覚さえ信じればよいのだから。
もっとも、自分の感覚のほか頼るべきものがないという状況は、多くの人にはむしろ不安なものである。だからこそ人々はメディアにトレンドの教えを乞う。トレンドとは来年には変わってしまうものであることを知りながら。この全てが流動する中で、一部の芸術家だけは水を得た魚のように自由だ。彼らは海図のない海をためらうことなく航海してゆく。そして私たちにとっても、芸術を含めてあらゆる地盤が崩壊してゆく時代に、少なくとも自分の感覚を信じて独自の世界を構築することに成功した若いアーチストたちの出現は、なんと心強いことだろう。
日本の都会では見回せばあらゆる情報と刺激とがある。洗練を極めたデザインも、技術の粋も、古今東西の珍品も簡単に手に入る。シックもハイテクも正義も悲劇もみな凡庸にしか見えないこの環境で、なお芸術が可能であることを彼らのダンスは証明している。現代都市の軽やかな混沌の中から生まれたコンテンポラリー・ダンスは、どのような時代にあっても芸術はそれにふさわしい形式を発明してくれるということを示しているだろう。
Flying Cabinet