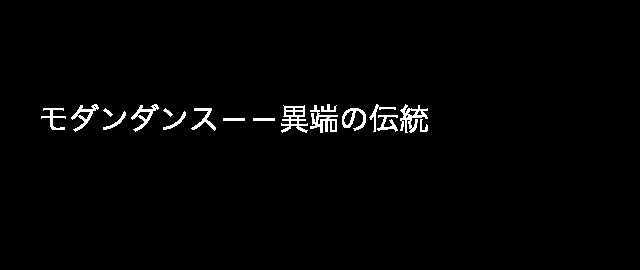「モダンダンス」という英語を文字通りにとれば近代の舞踊である。しかし実際には、近代に始まった舞踊の全てを指すわけではなく、事実上、「バレエ」や「暗黒舞踏」と同じく舞踊の中の一ジャンルを指す言葉となっている。では「モダンダンス」というジャンルはいかなるものか。これを様式から定義するのはむつかしい。イサドラ・ダンカンと マーサ・グラハムとマース・カニングハムを比べても、非バレエ的という以上の共通点は見当たらない。外見だけを見るなら、むしろバランシンの抽象バレエやミニマルなポストモダンダンスの方がカニングハムに似ているだろう。モダンダンスを成立させていたものは様式ではなく、その芸術観である。たとえば、カニングハム以後のダンスがなぜ「ポストモダンダンス」と呼ばれたのだろうか。モダンダンスは終わったという認識があるからだ。ではなぜ終わってしまったのか。その答は多分こうである。モダンダンスはモダニズムという芸術運動の舞踊版であり、モダニズムの終焉とともに終わったのだ、と。もちろんモダンダンスは今なお生き延びている。歌舞伎が今なお公演を続けているように。そして新派がついに歌舞伎を超えられぬまま消えてゆくように、ポストモダンダンスもモダンダンスを超えられぬまま消えてしまったと言ってもいい。さらに小劇場が歌舞伎から遺産を引き継いだように、ピナ・バウシュやヌーヴェル・ダンスもまたモダンダンスの遺産から多くを得ているのは間違いない。だが歌舞伎が現代演劇とは言えないように、モダンダンスも現代の舞踊とは言いにくいものがある。それは多分、モダンダンスを成立させていたモダニズムが欧米において終わってしまったからである(日本のモダンダンスの場合には、そもそもモダニズムがあったかどうかから問われねばならないけれども)。
「モダニズム」という言葉は日本語に移しにくい。思想体系ではないから「近代主義」というのもおかしい。せいぜい「近代的流儀」とか「近代風」だろうか。だがこれでは、この言葉にこめられた思い入れが伝わらない。「モダニズム」とは、何よりも体制の否定、伝統の拒否という態度であり、意志であった。しかも、敵が十分に強力であり、巨大であるという覚悟であった。高度な文明を達成し豊かな社会を築いたと信じている人々は、この快適な体制を守ることが必要であり、そのためには伝統を維持しなければならないと考えがちである。これに対し、新しい時代・新しい社会には新しい文化・新しい体制が必要であるとする考えからモダニズムが出てくる。それは権威ある父親への反逆であり、優美な母親のドレスを剥ぎ取ることである。むろんそれは破壊のための破壊ではない。規範の無視は自由の獲得のためであり、虚飾の排除は真実の発見のためであった。少なくとも、そう信じられていた。二十世紀のモダニズム芸術、たとえば抽象絵画以降の美術、十二音音階以降の音楽はこの精神から生まれた。いや印象派の絵画や音楽に、既にその先駆を見出すこともできよう。二十世紀初頭、ヨーロッパでは社会の現状に対する不満が強まり、抑圧されていた者が支配者を打ち倒すという革命の幻想が広がっていた。一九一七年、幻想はロシアで現実となる。知識人たちは革命が西へ波及することを信じた。芸術家たちは芸術における革命を自らの使命とした。伝統の否定。ブルジョア的芸術の拒否。新しい時代のための新しい芸術。彼らは必ずしも共産主義者であったわけではない。ただ共産主義が社会体制に見出したのと同じ問題を芸術にも見ていたのだ。既存の芸術における、支配、堕落、不合理、抑圧等々を。そしてそれゆえにしばしば共産主義に共感したのだ。モダニズムの芸術家にとって、たとえ自身の内的必然から新しい様式を必要としただけであったとしても、自分が革新者のグループに属しているということ、そしてそれが既存の体制の側からの大きな抵抗を受けているということは、確かな実感であった。事情は舞踊においても変わらない。
イサドラ・ダンカンの感動的な自伝『わが生涯』(小倉重夫・阿部千律子訳、冨山房)は著者による脚色があって、事実の細部は正確ではないといわれる。だが逆に言えば、その脚色はダンカンが自身の姿をどのように思い描いていたか、自分の役割をどのように位置づけていたかを示しているだろう。これは、誇り高い異端者が自らの志を実現しようとして既存の体制に宣戦布告し、勝利と敗北を繰り返しながら執拗に戦いつづけてゆく物語である。彼女が追い求めたものは自由と芸術であった。敵は、小さいものから順に、バレエであり、当時の芸術観であり、社会体制そのものであった。当時芸術とは男のものであり、舞踊は女性の芸能とみなされていた。ということは、一種の目の保養であって芸術ではなかったということである(さらに意地の悪い言い方をするならバレリーナが優美を競うのは金持ちのパトロンを見つけるためであった)。舞踊家としての名声は、多くのファンから愛されているという意味であって、芸術家として評価されているという意味ではなかった。だからミュンヘンのキュンストラー・ハウス(芸術家の家)でダンカンの公演計画が持ち上がったとき、シュトゥックは芸術の聖堂に舞踊はふさわしくないと反対したのである。自伝によればダンカンは彼の家を探し出し、「彼のスタジオで着物を脱ぎテュ ニックに着がえて踊り、さらに四時間ぶっつづけに私の使命の神聖性、舞踊の芸術としての可能性を述べたててやった」という。シュトゥックは降参した。ダンカンの生涯はこのときの行為に集約されているだろう。舞踊を芸術として認知させること。そのために新しい舞踊を創り出し、踊ってみせ、説得すること。ではその舞踊はいかなるものであるべきか。ダンカンはその理想を芸術の黄金時代(と信じた)ギリシアに求めた。ダンカンの考えでは、昔の人々は自然の呼び声に応え自由に踊っていたはずであった。しかるにバレエは不自然な姿勢を強要し、自由を束縛する。中国の女性の纏足のように、バレエの訓練は異常な肉体を作るための拷問である。ペテルブルクの帝室バレエ学校を見学したダンカンは、この学校を「人間性と芸術の敵」と感じたとまで書いている。彼女にとって、舞踊は練習でさえ踊る喜びに満ちていなければならなかったからだ。この喜びを妨げるのは、人工的な規範の押しつけである。規範は自然からくるべきであり、表現は自由であるべきだというのがダンカンの考えだった(今でも他のダンスの訓練を経た者がダンカン・ダンスのレッスンを受けると、身体的解放を感じるという)。彼女の自由の希求は徹底していた。女性の抑圧が現在とは比べ物にならないほど大きかった当時、女は自由に恋愛し自由に子供を生む権利があると主張し、実行していた。彼女は芸術だけではなく、道徳においてもブルジョア社会の常識と戦っていたのだ。いずれもそれは解放のための戦いであった。しかし皮肉なことに、この戦いを継続するためには、その財政的基盤を貴族や富豪の気まぐれな援助に頼るほかなかった。とりわけ舞踊学校維持の負担は大きく、しばしば身を屈して寄付を乞わねばならなかった。ほとんど力尽きたとき革命成ったロシアから一通の電報を受け取る。「ソビエト政府のみ貴嬢の芸術を理解す。来れ。貴嬢の学校を設立しよう」。ダンカンは船に乗った。プラトンの理想国をレーニンの理想国に重ね合わせながら。自伝はこう結ばれている。「さようなら永久に、古い世界よ、私は新世界を歓迎する」。やがてソビエト政府は芸術の革命家を弾圧し、クラシック・バレエの大パトロンとなるのだが。
マーサ・グラハムもまた異端者であることを自覚していた。自伝『血の記憶』(筒井宏一訳、新書館)で言う。「多くの人から見て、私は異端者だった。異端の女性のすることはすべてが不当に扱われる」と。彼女も世の主流と戦わねばならなかった。しかしロマン主義という十九世紀の芸術思想を引きずっていたダンカンに比べ、グラハムはより純粋なモダニズムの徒であった。新しい時代の芸術がいかなるものかについて、ずっとはっきりしたビジョンを持っていたし、その「近代性」が複数の芸術ジャンルに共通したものであることも意識していた。シカゴ美術館で初めて抽象絵画を見たときの驚きをこう書いている。
「私は気を失いそうになった。そのとき私が狂っていないこと、私と同じように世界を、芸術を見ている人がほかにもいるのだと気づいたからだ。それはワシリー・カンディンスキーの作品で、一筋の赤い線が絵の端から端まで走っていた。私は誓った。『いつか私もあんなダンスをつくるのだ』と」
「近代絵画」と「モダンダンス」とが同じ世界観、同じ芸術観から生まれたことをグラハムは確信していたのだ。それは、ブルジョアの好む俗悪な趣味を排除して、もっと本質的なもの、もっと力強いものを実現しなければならない、という意識である。カンディンスキーの絵画はもはや美女でも田園でもなく、力強い色と力強い線の運動にまで還元された。近代建築もまた前世紀までのごてごてした様式を捨てて、簡素な幾何学の必然に従おうとしていた。そしてダンスも、とグラハムは考える。「装飾的な要素や派手で浅薄な飾りを排したという点で、ダンスは近代絵画と建築に続いた。ダンスはもはや『かわいらしく』あるべきでなく、もっと真なものになろうとしていた」と。では「真なもの」とは何か。表現形式としては、優美な姿勢ではなく力強い動きである。表現内容としては、子供だましの童話ではなく「無意識の世界」「人類としての記憶」である。もちろん「無意識の世界」などというのは、ダンカンの「自然」と同じく、戦略的用語かもしれない。舞踊が芸術であることを主張するためには、何かしら普遍的な観念と結びつけなければ説得力に乏しいからだ。グラハムの場合も、その仕事は人類としての記憶より個人的記憶や経験に根ざしていたように思える。ともあれ彼女は、優美なポーズやアティテュードでもなく回転や跳躍の曲芸でもなく、醜い姿態や劇的な動作によって人間の情念を表現するダンスを創り出したのである。それは舞踊を趣味のいいきれいごとにとどめようとするブルジョア的芸術観に対立するという意味で、確かにモダンであった。もっともダンカンに比べるとグラハムの戦いは楽に見えるだろう。舞踊が芸術であるという説はもうたいして抵抗を受けなかったし、アメリカはモダンダンスを国産の芸術として大事にした。晩年の彼女は勲章をはじめ、およそ芸術家として考えうる限りの栄誉を得た。グラハムを異端だなどと言えば大抵の人は驚くだろう。実生活もダンカンのように奔放ではなかったから、保守的な人にも評判がよかったらしい。だが九十歳を越えた彼女がマドンナについて語るのを聞いてみよう。「彼女は女性が普通隠すものを、舞台の上で出しているだけである。たしかに、それは世間体のよいことではない」。そしてこう続ける。「一九八〇年のこと、善意の寄付者が私のところに来て言った。『グレアムさん。お金をもらおうとなさるときに一番強みになるのは、あなたの世間体がよいことです』。私は唾をかけてやりたかった。世間体! 世間体を望むアーチストなど、いたらお目にかかりたいものだ」。少なくとも彼女の精神は、最後まで異端者でありつづけたのだ。
抽象絵画に共感したグラハムも抽象的な舞踊を作ったわけではなかった。今日の分類では、彼女の舞踊は「表現」である。抽象に達したのは、弟子のマース・カニングハムだった。彼はモダンダンスから表現内容を削ぎ落としてしまった。この意味で彼はグラハムより過激なモダニストである。だが異端者としての彼の地位は曖昧である。というのも、彼が登場したころには、既にモダニズムこそ二〇世紀の真の芸術であるという考えが常識となっていたからだ。社会は彼を初めから芸術家だと思った。批評家たちはこれこそ新しいダンスだと言った。カニングハムの敵はもはやバレエでさえなく、モダンダンスの権威、要するにグラハムだけであった。彼はグラハムを否定した。だが誰もけしからんとは言わなかった。なぜなら、前の世代の様式を否定することこそがモダニズムの伝統であったからだ。むしろグラハムを模倣すればカニングハムは軽蔑されただろう。異端者であることが正統の証となるとき、異端とアカデズムとは区別がつかない。批評家は彼をモダンダンスの頂点と書き、政府や財団が支援し、バレエ団までが彼の作品をレパートリーに加える。この快適な環境をカニングハムが拒否しなかったとて誰が非難できよう。彼は自分がモダンダンスの求道者であるとは自覚していただろうが、多分異端であるとは思っていなかっただろう。つまり、モダンダンスはカニングハムに至って権威ある体制、すなわちアン シャン・レジーム(旧制度)となったのだ。舞踊におけるモダニズムはカニングハムで終わったのである。もちろんこれはカニングハムの業績を貶めることではない。ただ、彼以後の舞踊家が新しいものを求めるとき、モダニズムとはまったく違ったスタンスをとらねばならなかったということである。
一九六〇年代後半、欧米と日本の芸術界に激動が起こった。それは政治や文化を含めて一切を御破算にしようという過激な運動であり、六八年頃に頂点に達する。このとき既に権威ある体制となっていたモダンダンスは、バレエとともに否定の対象となった。そして一切の制度から自由に、新たな芸術の可能性が実験された。彼らの困難はむしろ、「何をやってもよい」とすれば何をやったらよいのかわからない、ということにあっただろう。この時試みられた形式は「ポストモダンダンス」と呼ばれた。今日この語は死語となりつつあり、その上演の記憶さえ忘れ去られようとしている。
しかしモダンダンスは生き永らえている。バレエのように古典として。
Flying Cabinet