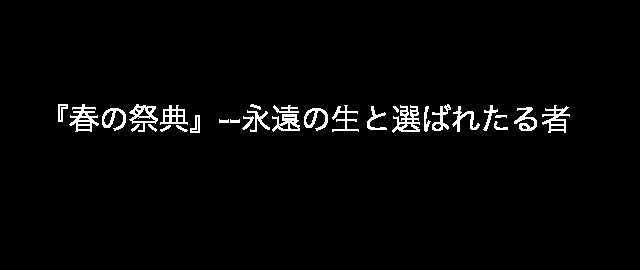1 誕生と死
一九一三年五月二九日。この夜パリのシャンゼリゼ劇場で起こった事件を当時の新聞は「春の虐殺」と呼んだ。熱に浮かされたような目撃者の証言はたくさん伝わっているが、それらを全て信ずると辻褄のあわぬことも多い。記録を子細に調べて『春の祭典』を著したエクスタインズは「誰の話が本当なのだ?」「どこからどこまでが作り話でどこからが事実なのか」と匙を投げる。なにしろ当日いなかったはずの者までが、見てきたような話をしているのだ。どうやら、誰もがこの歴史的事件に立ち会っていたと言いたい上、誰もが自分の参加した事件を大袈裟に語りたいらしいのだ。もはや問題は細部の真実ではない。私たちが驚くべきは、たかが舞踊の一公演が騒然たる事件となり、伝説となり、舞踊史上の一事件から近代芸術史上の事件に、そしてついには社会文化史上「近代」の始まりを象徴する「今世紀の画期的事件」とまで評されるようになったということである。
この夜、劇場の舞台では、ディアギレフ率いるロシア・バレエ団が、ストラビンスキー作曲、ニジンスキー振付の『春の祭典』を初演した。台本はストラビンスキーとレーリヒ、美術と衣装もレーリヒである。プログラムには次のような梗概が記されていた。第一幕は春の讃歌。大地は花と草に覆われ、大いなる歓喜が満ちる。人々は踊り、未来を祈る。長老たちを従えた賢者も春を祝福する。人々は一つになり、豊穰の大地を恍惚として踏み鳴らす。第二幕は犠牲。夜、丘の上に石の聖域がある。乙女たちは神秘の遊戯を行い、一人が神によって選ばれる。乙女たちはこの選ばれた者を讃える。先祖が呼び出され、気高い証人として犠牲の儀式を見守る。こうして偉大なる太陽神ヤリロに生贄が捧げられる。
客席には二つのグループがあった。ボックス席には絹の裾を曳き宝石に飾られた社交界の面々。そしてボックス席に囲まれた通路には立見の若者たち。いうまでもなく、ボックス席は保守的な芸術を愛し、立見の連中は新しい試みを好む。そしていずれのグループも振られた役を完璧に演じた。おそらく舞台のダンサーよりも熱心に。
音楽が始まると、最初の数小節で抗議の口笛が客席からあがった。ダンスが始まると怒号と口笛で音楽も聞こえないほどになった。立見の支持者からは負けじと拍手と歓呼が送られる(コクトーの言うように彼らはボックス席の連中への軽蔑を態度で示したかっただけかもしれないが)。観客の間で争いが始まり、罵声と悲鳴が飛び交った。話によれば、地震のような劇場で、貴婦人が紳士をひっぱたき、決闘の取り決めがなされ、幕間には警官が不作法者を何十人も引きずり出したという。劇場主は「とにかく聴いてください」と哀願していた。騒乱状態のなか、指揮者ピエール・モントゥーは忠実に使命を果たし、舞台の袖ではニジンスキーが椅子の上からダンサーたちに「十六、十七」とリズムを叫び、ともかくも踊りは最後まで続けられた。
幕が降りたあとについても伝説がある。コクトーの伝えるところによれば午前二時、 ディアギレフ、ストラビンスキー、ニジンスキーそれにコクトーは連れ立ってブローニュの森へ行った。そこでディアギレフは泣きながらプーシキンを呟いていたという。ストラビンスキーは別の話を伝える。公演のあと彼らはレストランへ行き、ディアギレフは満足そうにただ一言「まったく予想通りだ」と言ったという。おそらくストラビンスキーが正しい。ディアギレフがあらかじめ若者たちに無料の立見券を配っておいたのは何のためか。明らかに攻撃を予期した迎撃準備である。ディアギレフは始めから戦うつもりだったのだ。
「新しい形式が必要なんです。それがないくらいなら、いっそ何もないほうがいい」。チェホフの戯曲『かもめ』の中で文学青年トレープレフが語るこの台詞は、近代芸術の精神を要約している。貴族やブルジョアの愛する古典的・伝統的芸術形式を廃し、新しい芸術形式を発明すること。政治における革命にあたるものを芸術の領域で行うこと。それがモダニズムと呼ばれる、今世紀の芸術運動の主要動機であった。当然ながら、成功した作品はスキャンダルとなる。『春の祭典』の騒動はむしろ成功の証であった。
ディアギレフ自身は芸術家ではなかったが、芸術の革命家であろうとした。そして西 ヨーロッパにロシア芸術を持ち込んで衝撃を与えた。だがその成功は必ずしも革命によるものとは言えなかった。何よりも西欧人を驚嘆させたのは歌手シャリアピンと踊り手ニジンスキーの至芸だった。しかし腕前の見事さは芸術の新しさではない。次に喜ばれたのは豪華絢爛な装置であったが、『シェエラザード』などの異教趣味はなるほどヨーロッパ的ではないかもしないが、ヨーロッパ人の抱く「オリエント」のイメージを実現したものにすぎなかった。写実的というより装飾的な美術は、舞台美術としては斬新だったかもしれないが、既に後期印象派や野獣派を知るヨーロッパでは、美術そのものとしてはいささかも新しくはなかった。様式的な当時のバレエの中にあって演劇性を重視するフォーキンの振付は一見革新的だったが、実は一八世紀のノベールの試みの延長にすぎなかった。ただひとつ、本当に革新的であったのは、ストラビンスキーの音楽である。そのストラビンスキーが『春の祭典』のアイデアをだした。大地を割って突然生命が噴出するかのようなロシアの春。その春を讃える異教の儀式。生贄に選ばれた乙女の聖なる踊り。永遠の生のための選ばれたる者の死。この構想をきいたディアギレフとニジンスキーは興奮した。今度こそ、本当に革命的な作品ができる。問題は振付だった。「新しい形式」を生み出さなければならない。ストラビンスキーはフォーキンには無理だとみていた。彼は手紙に「必要なのは器用さではなく天才なのだ」と書いている。
ディアギレフはニジンスキーにまかせた。これは多分誰もが驚く人選だった。たしかにニジンスキーは前年『牧神の午後』を振付けてスキャンダルを巻き起こしている。しかしその理由はもっぱら自慰を暗示する所作のせいであって、バレエの動きを殺して活人画に仕立てた振付のせいではない。彼の振付家としての才能にはストラビンスキーでさえ危惧を抱いていた。だが他に誰がいただろう。ロシア・バレエ団にあって、ニジンスキーはただ一人バレエの常識を完全に無視しうる舞踊家だった。
リハーサルが始まり、ダンサーたちは疲労困憊した。まず、絶えずリズムが変動するストラビンスキーの曲に当惑した。どうやったら動きをあわせられるのか。ディアギレフとニジンスキーはリズム教育を考案したダルクローズのもとを訪れ、弟子のミリアム・ランベルクを引き抜く。彼女の仕事は団員のリズム教育だったが、そのレッスンを受けるダンサーはほとんどいなかった。さらにニジンスキーの振付は、ダンサーたちにとっては支離滅裂だった。合理的で無理なく身体を動かせるフォーキンの振付と違い、これは身体の各部分をばらばらに動かさねばならなかった。またグループに分かれたダンサーが別々のリズムで踊るように求められることもあった。動きは時にひどく複雑であり、音楽のテンポを指定よりも遅くしなければ踊れない部分もあって作曲家を怒らせた。誰もニジンスキーが何をしたいのかわからなかった。けれども彼は何かをつかんでいたようだ。思いどおりに仕上がれば『春の祭典』は観客にショックと興奮を与えるだろうと彼はストラビンス キーに書き送っている。
たしかにショックと興奮は引き起こされた。しかしそれは、ディアギレフの予想どおりではあったかもしれないが、ニジンスキーの予想したようにではなかった。パリとロンドンで八回上演されたあと、二人が別れたこともあって、『春の祭典』は長くレパートリーから外された。けれどもディアギレフは舞台装置と衣装をとっておいた。そして一九二〇年、『春の祭典』を復活する。もっともニジンスキーの振付を誰も覚えていなかったので(あるいは覚えていても誰も踊りたくなかったので)、レオニード・マシーンが新たに振付をした。彼はニジンスキー版を見たこともなかった。年の暮、再びパリのシャンゼリゼ劇場で『春の祭典』は復活した。大成功だった。鳴りやまぬ拍手のなか、ストラビンス キーは生贄の乙女の手に接吻した。
こうしてニジンスキーの『春の祭典』は死に、ストラビンスキーの『春の祭典』は永遠の生を手に入れた。
2 挑戦
『春の祭典』の音楽は振付家にとってセイレンの歌声のように誘惑的であるらしい。 ざっと数えてもベジャール、テトリー、ケネス・マクミラン、ノイマイヤー、ピナ・バウシュ、マッツ・エック。モダン・ダンスではレスター・ホートン、マリー・ヴィグマン、マーサ・グラハム。まだまだいる。『春の祭典』ほどめぼしい振付家がこぞって作品化した音楽はほかにない。こうなると、観客はどうしても振付の比較をしたくなる。振付家にしても、比較されることを承知で挑戦せざるをえない。今や『春の祭典』は、振付家の力量を問われる試金石となっているのである。
振付の出来不出来を判断するのに、私は素朴な方法をもっている。あらを捜す批評家の目で見るのではなく、無心に舞台を楽しもうとする。すると優れた振付ほど音楽が耳に入らない。なぜか振付の出来が悪いほど、音楽が立派に聞こえるのである。とりわけ『春の祭典』のように音楽自体に力がある場合、太刀打ちできなかった振付はストラビンスキーに打ち砕かれて気の毒なことになる。たとえばモリッサ・フェンレイがニューヨークの キッチンという小劇場でソロ公演したことがある。私の目はよくできた振付だと思い、半裸で熱演する彼女をよいダンサーだと思った。しかし私の耳は天井から降り注ぐ音楽の素晴らしさを再認識していた。私の意識はもっぱら音楽に向けられ、踊りの方は音楽を引き立てるための香辛料にすぎなかった。『春の祭典』をたった一つの肉体で引き受けようという決意は勇ましいが、やはり荷が重すぎたのかもしれない。
音楽と正面からぶつからず、巧みにやり過ごそうという企みもある。ポール・テイラーは設定をダンス・リハーサルに変え、ブロードウェイでもやれそうな洒落た現代劇に仕立てた。だがポテトチップスのような彼の振付はウォッカのように濃厚な音楽に浸されるとよれよれになってしまった。なぜコーラのような音楽を使わなかったのだろうと、私には不思議だった。カナダの若手クデルカはもう少しひねって、ロシアにおける春の讃歌に匹敵するヨーロッパの伝統的儀式は何かと考えた。昔から貴族も農家も血筋の存続が最重要の関心事である。そこで長男誕生を祝う儀式こそ『春の祭典』にふさわしい。というわけで、舞台ではコサックの宴会のような情景が展開されるのだが、ストラビンスキーの音楽がなければ私は眠ってしまうところだった。(このときはニジンスカの『結婚』のあとに上演するというプログラム編成上の失策もあった。この傑作に並べると、なまじ似たところがあるだけに、『結婚』の下手なパロディに見えてしまうのだ。)
私が初めて音楽に拮抗しえた振付を見たのはベジャール版である。鹿の発情の映画に示唆を得たという振付には性交を暗示する(いやほとんど明示する)シーンがあり、一九五九年の観客を仰天させた。初演はたちまちスキャンダルとなり、その後も数年は拍手に口笛が混じっていたという。当時ベジャールはバレエ界で最も前衛的な舞踊家だった。ロマンチックな愛ではなく暴力や性を表現内容とし、クラシックではなくミュージック・コンクレートを音楽に選び、役柄を表す美しい衣装ではなく何のキャラクターも与えないタイツをダンサーたちに着せて『孤独な男のためのシンフォニー』などの作品を作っていた。『春の祭典』でもやり方は変わらない。鹿の群の中の一頭を見分けられないように、私たちはダンサーを見分けることができない。なるほどリーダーとおぼしき男女はいるけれども、外見に変わりがあるわけではなく、ただ一番前にいるというにすぎない。彼らは原始的な生物の群れのように見える。それが音楽とともに目覚め、動き、衝動のままに生命と種族を維持する活動を始める。ストラビンスキーの意図したストーリーは無視されているが、振付の表現する世界は見事に音楽に一致している。踊りと音楽は互いに手を携えて疾走し、興奮と緊張をゆるめることなく劇的な終結へ一気になだれこんでゆく。「なんて鮮やかな音楽の解釈だ」と私は舌を巻いた。
だがさらに鮮やかな解釈をみせたのがピナ・バウシュである。原始生物の盲目的な欲動ではなく、人間だけの優美と残酷がそこにはあった。舞台一面に敷かれた土をはねながら薄物をまとって踊る女性たちの姿はただ美しく懐かしかった。やがて生贄が選ばれる。選ぶのは白羽の矢ではなく、モノトーンの舞台にひときわ鮮やかな赤い布である。確かめられるのは永遠の生ではなく男たちの欲望である。性は、ここでは甘美な愛でもなく動物的暴力でもなく、救いようもない残酷として現れる。男と女の関係は昔からうんざりするほど繰り返された芸術のメインテーマなのだが、これほど痛切に虚飾を剥いで見せたものはない。私は目から鱗が落ちるような思いだった。もしこれを感傷的な音楽でやれば凡庸な悲劇に落ちるだろう。クラシックの虚飾を剥いで生命の原質を告げるようなストラビンスキーの音楽だからこそ成功したのだ。私は、ようやく音楽とつりあう創造が行われたと感じていた。
新解釈を競うのではなく、ストラビンスキーの構想に忠実であろうとしたのはマーサ・グラハムである。一九三〇年、ストコフスキーは『春の祭典』をアメリカで上演しようと思い、主演にグラハムを、振付にマシーンを招いた。二人は共に不満だった。マシーンはバレエの素養に乏しいグラハムに辞任を迫り、グラハムはマシーンでは自分の力量を生かせないと思っていた。既に自分のカンパニーをもち、数多くの作品を発表していたグラハムには、ストコフスキーが自分に振付をまかせなかったのもくやしかったようだ。おそらくこの頃から、いつかは自分でと考えていただろう。そして半世紀。一九八四年、グラハムはついに『春の祭典』を世に問う。これは彼女の代表作とは言えないとしても、グラハム的舞踊の集大成とは言えるように思う。ある意味でこれは完璧な振付である。つまり春の犠牲のストーリーを正確にダンスで説明している。しかも密度は高く、様式は完成されている。グラハムはマシーンを超えたと信じたに違いない。だが別の視点から見れば時代錯誤の産物である。これを一九三〇年代の作品だと言われても誰も疑わないだろう。表現のスタイルだけでなく、そもそも物語を忠実にダンスで説明するという方法論そのものが今では古めかしいのである。とはいえ私はこの作品はグラハムの名に恥じないものだと 思っている。なぜならその振付は決して音楽に負けることなく最後まで対峙しえていたのだから。彼女はこの年九十歳だった。
3 復活
一九七九年バークレイの大学院生だったミリセント・ホドソンは常識では不可能な研究を企てた。ニジンスキー版『春の祭典』の復元である。既に関係者の多くは亡くなっていた。捜し当てた証人も、ある者は当時幼すぎ、ある者は現在老いすぎてしばしば記憶が辿れなかった。手に入れたメモを突き合わせると情報が食い違うこともあった。だがホドソンの執念は数年がかりで資料を集め、整理して、おぼろげながらもその全体像を再構成する。そして一九八七年、ついにジョフリー・バレエ団がこの復元されたニジンスキー版 『春の祭典』を上演するのである。私はこれを見る前、いささか不安があった。一つはニジンスキーの原作自体についてである。なにしろ古すぎる。二〇世紀の初めには革命的であったとしても今は二〇世紀の終わりである。もう一つは復元の正確さについてである。完全な復元には資料が不足していたとはホドソン自身認めている。とすれば残りは類推と想像によるわけだが、ホドソンとジョフリーがどの程度関与したのかがわからない。つまり昔の素朴なアイデアを現代の凡庸な舞踊家が焼き直したものを見せられるのではないかという不安である。だが幕が上がるとすぐにそんな考えは吹き飛んでしまった。それはバレエやモダン・ダンスはもちろん私の知るいかなる舞踊とも違っていた。それも技法やスタイルというより、根本的な舞踊観、身体観が違っていた。たとえば冒頭の足を踏み鳴らす人の列。スタンピングと言えば人はキリアンの出世作『スタンピング・グラウンド』を思い出すだろう。しかしキリアンのスタンピングが南太平洋の芸能を換骨奪胎したショーだとすれば、ニジンスキーのスタンピングは秘儀である。それは一挙にこの世ならぬ世界を現出させるのだ。そしてゆっくりと進む踊りの列とともに私も遠い異境に引きずりこまれてゆく。あるいは生贄となる乙女が選ばれるシーン。深夜少女たちがひそやかに遊戯を行う。そして一人が選ばれる。そのときの悲哀感を何と言えばよいのだろう。その悲しみは伝統的悲劇とも近代的心理とも違う。遊戯と宿命とが一つであるようなどこか別の世界のものである(そういえばニジンスキーはニーチェが好きだった)。これらは着想の才の問題ではない。振付家の見ている世界がそもそも私たちとは違うとしか思えない。これは、選ばれたる者の仕事なのだ。
ニジンスキーは「予想通りに仕上がれば観客にショックと興奮を与えるだろう」と書いた。彼は予想通りに仕上げたのだ。幕開きから私の正気はどこかに去ってしまった。ふと気がつくと、音楽がまったく耳に入っていなかった。聴いてみると確かに音楽は鳴っている。しかし、その音楽は息せき切ってダンスを追いかけていた! 私は初めてダンスを見ながら泣いた。頭のなかでは幾つかの言葉がぐるぐる回っていた。「この世に天才というものはいるんだ」「舞踊界はこの七十年いったい何をしていたのだ」。そして、踊り手としては伝説化されながら振付家としては無視され、「私は神だ」と言いながら狂気の内に死んだ彼の生を思った。次の夜、私は再び劇場に行き当日券の列に並んだ。
復元されたニジンスキー版『春の祭典』は最近パリ・オペラ座バレエ団のレパートリーに加えられた。マシーン版を私は見たことがないし、現在上演しているバレエ団も知らない。
参考文献
ロベール・ショアン『ストラビンスキー』遠山一行訳、白水社、一九六九
ニジンスキー『ニジンスキーの手記』市川雅訳、現代思潮社、一九七一
ロジャック・リヴィエール「『春の祭典』」富永明夫訳、『世界批評体系3』、筑摩書房、 一九七五
ロモラ・ニジンスキー『その後のニジンスキー』市川雅訳、現代思潮社、一九七七
ジョフリー・ウィットウォース『ニジンスキーの芸術』馬場二郎訳、現代思潮社、一九七七
藤野幸雄『春の祭典』晶文社、一九八二
モーリス・ベジャール『モーリス・ベジャール自伝』前田允訳、劇書房、一九八二
リチャード・バックル『ディアギレフ』上下、鈴木晶訳、リブロポート、一九八三
ダンス・マガジン、第一二号(『春の祭典』特集)、一九八六
市川雅編『ニジンスキー頌』新書館、一九九〇
市川雅『舞姫物語』白水社、一九九〇
エクスタインズ『春の祭典』金利光訳、TBSブリタニカ、一九九一
L'Avant-Scene Ballet/Dance, aout/oct. 1980.
Olive Holmes(ed.), Motion Arrested: Dance Reviews of H.T. Parker, Wesleyan, 1982
Martha Graham, Blood Memory, Doubleday:New york, 1991.
Joan Acocella, "Nijinsky/Nijinska Revivals: The Rite Stuff," Art in America, Oct. 1991