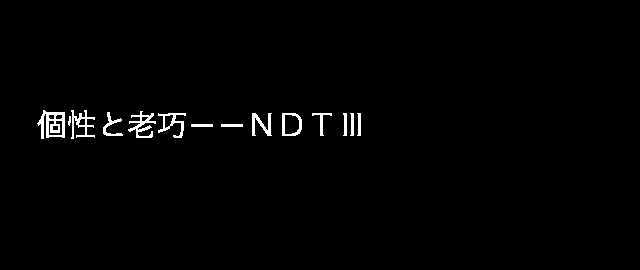ネザーランドダンスシアター(NDT)にはⅠ、Ⅱ、Ⅲと三つのカンパニーがある。Ⅰはいわば正規軍であって、3年前に来日し、あの息を呑む「ワン・オブ・ア・カインド」をさいたま芸術劇場で上演した。
Ⅱはいわば二軍であって,17歳から22歳までの青少年からなる。存分に鍛えられ力を試されて、合格すれば正規軍に編入される。とはいえこれはただの二軍ではない。昨年初めて来日し、若者ならではの圧倒的なパワーと若者とは思えない成熟した演技力で既に第一級のダンスカンパニーであることを証明した。さてここまでは、確かにたいしたものではあるにしても、実はさして驚くべきことではない。たぶん欧米のダンス関係者を驚かせたのはⅢの創設である。なぜならこれはダンスの常識への挑戦であったからだ。
Ⅰにはダンサーの定年があり、40歳で引退する。そしてⅢは40歳以上のダンサーだけをメンバーとしている。つまり欧米の常識ではもう人前で踊れないはずの中高年ばかりを集めたダンスカンパニーなのである。と、こう書くと、なにやらⅢはうば捨て山か、ご隠居たちの道楽のように見られるかもしれない。むろんそうではない。引退させるのはもったいない技量のベテランにもう一働きさせようというものである。そもそもⅢ創設のきっかけは、キリアンのパートナーであったサビーネ・クップファーベルクが40歳になったとき、彼女が舞台を去るのを惜しんだためともいわれる。さてこう書くと、今度は恋人がいつまでもスポットライトを浴び続けられるようにというキリアンの私情の産物のように見えるかもしれない。まあ最初はそんなこともあったかもしれないが、今となってはどうでもいい。とにかくⅢは、中高年のダンスという新しいジャンルへの挑戦となったのである。
もっとも日本人である私たちには、こういう話はいま一つ実感がわかない。日本の代表的舞踊家である大野一雄は90歳を越えて現役だし、武原はんも先代の井上八千代も90歳を過ぎて元気に舞っていた。なにしろ「円熟」とか「枯淡」といった50歳以下には使いにくい評語さえあり、芸道の世界では「四十、五十は洟垂れ」とまで言われたりする国なのだから。「芸は一生精進するもの」という私たちの伝統からすれば、体力が一定の水準を下回ればプロとして失格という西欧のシステムは,ダンスとスポーツを一緒にしているようで理解に苦しむものがある。荒っぽく言えば「飛んだり跳ねたりするだけがダンスじゃないだろう」というのが日本の考え方だとすれば、「飛んだり跳ねたりしなければダンスじゃない」というのが西欧の考え方であるわけだ。 欧米の一流ダンサーが大野一雄に畏敬の念を抱いているのは、単にそのダンスがすばらしいだけでなく、老年になってもなお芸術としてのダンスが可能なスタイルを試み、しかも実際に成功したということに、自分の未来の希望を感じているからである。これまで彼らにそのような可能性はないとされていたからだ (そのかわり、もう踊れないのに引退してくれないという大御所の老害もないけれども)。ネザーランドダンスシアターⅢの創設は、「飛んだり跳ねたりしなければダンスじゃない」という常識への挑戦であっただけでなく、欧米のすべてのダンサーに対して希望を与えるものであった。Ⅲを始めた以上キリアンは、これを成功させる義務を感じているだろう。
キリアンはⅠ、Ⅱ、Ⅲのそれぞれに異なった作品を与える。自分だけでなく、他の振付家にも委嘱するが、いずれもカンパニーの特質を考えた上で振り付けがなされることになる。Ⅰはとにかく最高のダンサーを想定すればいい。Ⅱは若さが売りなのだから、パワーとスピード、それに青春の哀歓なぞを加味すればいい。問題はⅢである。キリアンのとった戦略はダンサー各自の個性に焦点をあてることだった。体力は年とともに衰えるが個性は年とともに磨かれる。振付家はその魅力を最大限に引き出せばよい。だからその作品はいわばダンサーと振付家の共同制作であり、他のダンサーには踊れない(踊っても意味がない)ものとなる。さて、その成果はどうなったか。
私は昨年の来日公演を見ていないので、現在の彼らについて語るのは適任ではない。しかし97年に見た印象をいうなら、日本の枯れた老人芸を想像してたわけではないが、まず予想以上によく動くのにおどろいた。考えてみれば、鍛え抜かれた身体が40歳になったくらいでそうそう衰えるものではない。ピークの頃と同じではないにしても、たいがいの振付がこなせる程度には十分に飛んだり跳ねたりできるのだ。とはいえもはやパワーとスピードを売りものにするわけにはいかない。では何があったか。熟練したダンサーの高度な表現力、あるいは中年男のちょっと肩の力を抜いた洒脱な味わい。たしかにこれは大人のものだし(たぶんⅡにはむつかしい)、作品としても好感のもてるものだった。しかし、と私は思ったものだ。こういうものならⅠのダンサーでもできるんじゃないか、と。たしかにこれは40歳を過ぎてもダンスを踊れることを証明している。しかし40歳を過ぎなければ踊れないダンスはここにはない。それがなければⅢの意義は半減するのではないか。「お若いですね」と言うのは、言う方はお世辞のつもりなのだろうが、言われる方はあまりうれしくない。それは年の割りにはよくやってるじゃないかという意味にすぎないからだ。むしろ「やっぱり年の功ですね」と言われたいのだ。大野一雄の舞踏は老人でなければ舞えないだろう。だからこそ彼はダンサーたちに感動を与えているのである。かつて世阿弥は父観阿弥に比べて自分が劣るのは足がよく動くことだと言った。利きすぎる足に頼る芸は確かに客受けはいいかもしれないが、父の深みのある芸を実現することはできない。逆に言えば観阿弥は足がもう利かないけれども、別のスタイルで舞い、しかもそれは若い世阿弥の及ばない高さに達していたのだ。
40歳を超えたくらいでは、新しいスタイルを試みるには若いのかもしれない。まだⅢのダンサーは身体がよく動きすぎる。そしてキリアンたちは、彼らの個性に合わせて振付を考える。ダンサーの個性はこれまでのダンスのキャリアの中で形成されてきたものだから、どうしても従来のダンスの延長ないし部分的拡大になってしまう傾向がある。しかも彼らの身体能力はまだそれを実現できる。つまりまだ従来のボキャブラリーが一番彼らに向いているためにそれを使ってしまうのだ。しかし彼らが70になり、80になったとき、きっと根本からやり方を変えなければなるまい。よく動くことを断念した彼らに、キリアンはどのようなダンスを用意しているのだろうか。NDTⅢの真価はそのときに問われるだろう。
私は想像してみる。私と同年に生まれたキリアンがやがて90歳となり、90歳のダンサーに振り付けるのを。そのダンスは日本の舞踏や舞に近づくのだろうか。それともまったく新しいスタイルを開発するのだろうか。少なくともそれは、身体の不自由を振付上の制約とみなす従来の西欧の舞踊とは違った観点から作られることになるだろう。そしてそのとき、数十年の間用意してきた新しいダンスのために、キリアンは誰を踊り手に選ぶだろうか。私はさらに想像してみる。ひょっとしたらキリアンは、その新しいダンスを自身の身体で確証するために、再び自分で舞台に立つのではないだろうかと。そのときはおそらく、21世紀の舞踊史に特筆すべき光景が繰り広げられることになるだろう。
Flying Cabinet