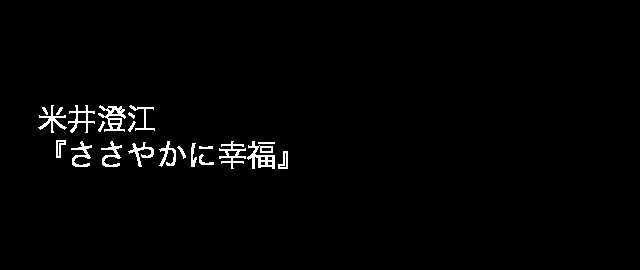ダンス・ゲーム
米井澄江の才気はあらゆるものをゲームとして組み直すことができる。彼女の作品は身体のゲームだったり、心理のゲームだったりする。だがここでは『ささやかに幸福』だけをとりあげよう。彼女の作品のなかで私がこれを一番好きだからというだけでなく、一番〈米井澄江らしい〉からだ。
舞台には十人のダンサーがいる。というより、五人の女と五人の男がいる。そしてゲームに明け暮れる。何のゲームかはいうまでもない。彼女らは野球チームの一致団結もファミコンの孤独も好まない。ただ男と女の関係だけが関心のすべてなのだ。ささやかな幸福のために。男らは「女房なんてびた一文の値打ちもない」と見得をきり、自由を求めて飛び上がったりしてはみるものの、すぐに落ちて女のゲームに巻き込まれる。もちろん、いやいやというわけじゃない。追ったり逃げたり、相手を取り替えたり。誘惑、いさかい、心変わり。わがまま、いじめ、肩すかし。さまざまな男女関係のパターンがトレンディ・ドラマのように展開する。私は柴門ふみを思い出していた。これは悪口ではない。彼女の作品が現代女性のバイブルといわれるのは、そこに描かれた恋愛が全くの等身大であるからだ。あの大時代な『べるばら』から柴門ふみまで二十年。そしてグラハムから米井澄江まで五十年。
マーサ・グラハムがモダン・ダンスを創始したとき、彼女はやはり男女の関係を作品の主題とした。ただしそれは王子さまとお姫さまの透明すぎて掴み所のない愛ではなく、愛と憎悪が表裏をなす執念である。彼女はギリシア悲劇を素材に、激しい男女の情念劇を舞踊化していった。大袈裟な身振りが〈表現〉するのは明確な理由のある明確な感情であり、古典劇だけに可能な強さと単純をそなえていた。たとえば夫に裏切られた妻は、わが子を殺したりするのである。私は日本のモダン・ダンスの現状に詳しいわけではないが、グラハムの影はいまだに小さくないように見える。「女の情念」といった大時代なものはさすがに少ないにしても、憧れや嫉妬といった単純で明確な感情の表現だけでことを済ませがちであるように思う。だが私たちの日常はもっと複雑で、もっと微細な感情の織物である。たとえば女が男を気に入り、さりげなく気をひく。男は女を値踏みして、さほどでもないと思えばとりあえず気がつかないふりをする。ところが女が他の男に視線を送ると、とたんにこいつは手を出したりなんかするのだ。これは愛とも嫉妬とも言いにくいだろう。いったい何のつもりなのか、本人にだってわからない。多分あとで男はこういうだろう。「いや、もののはずみだよ」。柴門ふみが、そして米井澄江が眼をつけるのは、こういうささいな、しかし私たちの日常を作っている男女関係である。
『ささやかに幸福』は五組の男女のささやかな満足をもとめるややこしい関係を、激しい動きと微細な演技で綴り合わせた作品である。けれども米井は関係のドラマを見せるだけでは十分とは思わなかったらしい。一人変な男を作った。こいつは、九人が白い服を着ているとき一人だけ黒い服を着る。九人が右に回るとき一人だけ左に回る。当然ながら浮き上がり、みんなとうまく関係を作れない。こういう男を相手に選んでしまった女はたいへんだ。「家庭の幸福」に興味のない男と一緒に「幸福な家庭」をつくろうとすれば、一人相撲の苦汁をなめることになる(この不運な女は米井自身が演じている)。しかしまあ、いろいろあったあげく彼もみんなに迎え入れられ、ついに十人そろって仲良くささやかな幸福にひたり始める。この時、背後で黒いきのこのようなものが次第に大きく膨らんで、何も知らない男女に迫ってくる。不吉な気配に振り返り、自分たちに襲いかかろうとしている運命に気がつくのは、この変な男一人である。だが彼も立ち尽くすだけだ。やがて全員が舞台一杯に肥大した黒い物体の下敷きになってしまう。この黒いものが原爆ないしそれに類した政治的凶事であることはすぐわかる。「そしてみんな死んでしまいました」というこの落ちはたしかに凡庸にすぎて唖然とする。しかしこれでは終わらない。いったん溶暗して終わったはずの舞台が突然明るくなり、下敷きになっていた男女が歓声をあげて跳ね起きる。黒い物体は見かけ倒しの風船だったのだ。そしてはしゃぎながら巨大風船の奥へもぐり込むように突進し、姿が見えなくなる。原爆も政治も、彼女らにとっては所詮ゲームの小道具にすぎないとでもいうように。そのしたたかな軽さになるほどとうなづきながら、私は太宰治の台詞を思い出していた。曰く「家庭の幸福は諸悪のもと」