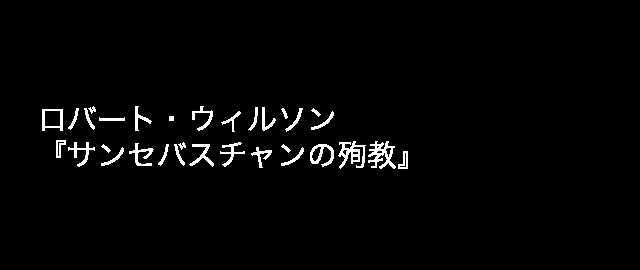バレエが現在の芸術でありつづけるためには、常にバレエの枠を破りつづけてゆかねばならない。そのことをいちばんよく知っているのは、同じ踊りを何百回も踊らされるダンサー自身かもしれない。(デュポンが、もう白鳥の湖はたくさんだといってパリ・オペラ座を辞めたのは記憶に新しい。)そのためかダンサーが運営の主導権を握るバレエ団では、時に大胆な振付家の起用が行われる。フォーサイスを抜擢したマリシア・ハイデ。トワイラ・サープを呼んだバリシニコフ。しかし依頼された方がとまどったというのはこれが初めてだろう。されたのはロバート・ウィルソン。したのはヌレエフである。「でも私は舞踊家じゃありませんよ」「ええ、でもあなたの仕事にはいつも動きが関わってるじゃないですか」。こんな会話が交わされたとニューヨーク・タイムズは伝える。おそらくヌレエフは、バレエの枠どころか、舞踊の枠さえも破る作品を期待したのであろう。ただ彼が、完全な新作ではなく、一九一一年に作られたダヌンチオ台本、ドビュッシー作曲の歌舞劇『聖セバスチャンの殉教』を指定したのは、革新は〈動き〉だけで十分で、全体の雰囲気は従来の観客も喜ぶものを、という戦略的配慮だったのかもしれない。これは皇帝と聖人の性的関係を暗示して初演時に大司教の指弾を受けたという世紀末風耽美作である。
レコードを聞いてウィルソンは頭を抱えたらしい。この大げさな愛憎劇をどうやって自分の作品に転換できるのか(浪花節の伴奏を頼まれた武満徹を想像してもよい)。彼は五時間の原作が長すぎるのを理由に削除改変の許可をとり、構成を変えた。まずプロローグを付けた。設定は初演の頃つまり第一次大戦前の、来るべき破滅を知らぬまま優雅に船旅を送る人々の姿である。水夫のセバスチャン(マイケル・ドナード)の裸に近い下半身は同性愛を暗示する。第一幕以降は三世紀ローマ時代となり、聖セバスチャン(シルヴィ・ギエム)の殉教・昇天の次第が演じられる。しかし水夫姿のセバスチャンはここでも舞台に登場し、影として皇帝にからむのである。また感傷的な歌をやめ、テキストはナレーションとした。二人のナレーターは舞台の隅で終始中央の出来事には無関心な風情で淡々と語る。彼等は現代の服装をしている。即ち聖俗二人のセバスチャン。そしてローマ時代の逸話を再解釈するダヌンチオの時代とそれを再解釈する現代という三つの時代の入れ子構造。これが原作の頽廃を括弧に入れ、再純化する戦術である。こうして舞台はウィルソン的世界となる。様式化された彼の美術は息をのむほど美しい。
振付のために彼に与えられた時間は四週間半であった。伝統的なバレエの語彙と文法を使うなら、これは短くないかもしれない。しかしウィルソンは、自分の語彙を使った。それはオペラ座のダンサーには理解を絶するものであった。彼はダンサーたちがもつ〈動き〉についての基本的な考え方を変えることから始めねばならなかった。バレエ・ダンサーたちは、体操選手なみの跳躍や回転、俳優なみのものまねや感情表現は訓練されている。しかし〈動き〉そのものを内的な緊張によって一つの〈存在〉にまで高めることを知らない。〈静止〉の持続が〈動き〉の一つとなることを知らない(これらは日本の能や舞踊では当たり前のことなのだが。たぶん彼がここ数年、花柳寿々紫を振付に起用する理由の一つはここにある。寿々紫は今回も振付家として参加している)。ヴィレッジ・ヴォイスのインタビューによれば、ウィルソンはすべての動きを自ら実演し、ダンサーはこれをビデオに撮り、その通りに動いた。新しい動きの語彙を教えるには他に方法はない。ダンサーはその動きが何かを表していると思いたがり、説明を求めた。しかし動きのための動きに理由はない。ただその動きが無意味にならないためにウィルソンが繰り返したのは「内的に」という言葉であった。結果はどうなったか。
三月パリ初演のあと、七月ニューヨーク公演がメトロポリタン・オペラハウスで行われた。皇帝役のデュポンはさすがに器用なもので、たくみにメリハリをつけて〈ダンス〉にしてしまっていた。しかしナレーターのシェリル・サットン(昔からのウィルソンの劇団員)のメリハリのないわずかな動き(たとえば両手を少し持ち上げる)がまさに内的な集中に支えられて目を離せぬ緊張感で存在しているのを見ると、デュポンの〈ダンス〉が本当にウィルソンの望んだものかどうかが疑問に思えてくる。特筆すべきはギエムであろう。あの颯爽とした、しかし色気のないギエムではなく、両性具有的なあやしさで見事に舞台の「花」となっていた。そして彼女は、誰よりも誠実にウィルソンの要請に応えようとしていた。時にバレエに流れそうになり、時に無意味な動きに陥りそうになるのを、必死に持ちこたえようとしているように見えた。何かが確実に彼女の中に植えつけられたのである。
今ロバート・ウィルソンは忙しすぎる。『シヴィル・ウォーズ』で抱えた莫大な借金を返すため、昨年は十本の新作を演出し、ニューヨークの自宅には十八日しか帰らなかったという。十分な時間をかけられぬまま送り出された『聖セバスチャンの殉教』は、しかし、当面の成果はどうあれ、クラシック・バレエの聖地ともいうべきパリ・オペラ座に、全く新しい種を植えることに成功したのであり、この意味で歴史的事件というべきであろう。ヌレエフはほくそえんでいるではあるまいか。
Flying Cabinet