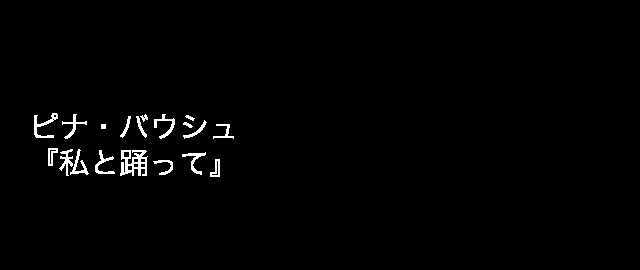たいていの人が芸術に期待するものは感動である。だから「感動しました」というのは最高の賛辞となる。しかしピナ・バウシュの作品を初めて見た感想には、感動というより衝撃を意味する言葉が多い。たとえば映画監督ヴィム・ヴェンダースはこう言う。
「世界中でダンスの公演はできるだけみてきましたが、ひっくり返されるような、椅子から投げ出され、床に叩きつけられるような体験は、それまで一度もありませんでした」
それは「感動」というなじみ深い体験ではなく、何かわけのわからない力に掴まれて自分自身を根底からひっくり返されることなのだ。ダンスをはじめ、演劇、美術、音楽、映画、文学などの芸術は人に感動を与えてきた。けれどもピナ・バウシュを見るとはまったく新しい体験である。ヴェンダースが言うように、「ピナは新しい芸術の考案者」なのだ。ピナは芸術の歴史を変えた。それも新しい芸術ジャンルを発明したというより、「芸術がなしうること」のレベルを一段階掘り下げたのである。
ピナの「新しい芸術」は一朝一夕に完成したわけではない。1976年後半からダンサーたちに多くの質問をして無意識の内面を探り始めたころから方法的な模索が始まり、1978年の『カフェミュラー』や『コンタクトホーフ』では既に完成したと見ることができる。1977年の『私と踊って』はまさにその過渡期の作品であり、後年の複雑な構成がなく、テーマも明快であるだけに、ピナの問題意識がはっきりと表れている。
『私と踊って』にはわかりやすい筋道がある。男と女が出会う。女はさりげなく男に近づき、男はあからさまに女を誘う。男は直截に距離を詰めようとし、女は恥じらいつつ間合いを計る。やがて二人の関係が進展し、男は女を支配しようとする。二人の心は行き違い、ついには傷つけあう。男はもう一度やり直そうとする。しかし女は知っている。関係を再構築することはできるけれども、それは所詮一方が他方を支配する関係でしかないことを。舞台では主役の二人の他に黒い帽子に黒いコートの男たちと優雅なワンピースの女たちが出没して古いドイツの愛の歌を次々と歌い、男女の関係を象徴するようなさまざまの振舞いをする。たとえば男が女を鞭打ったり、女がふいに男の膝に腰掛けたり。舞台空間は美しく、演出はたえず意表をついて飽きさせない。けれども観客の心に留まるのは何度も繰り返される「来て、私と踊って」という言葉である。それは初め甘い誘いだが、やがて遥かな呼び声となり、悲痛な懇願にも支配者の脅迫にもなる。単に「他者を求める」だけなら、その成就は難しくない。しかし愛を求めるとは「『自分を求める他者』を求める」ことであるなら、それは絶望しかもたらさないのかもしれない。のちに八〇年代のピナ・バウシュは愛を求める人間の悲劇を共感と悲しみの眼差しをもって多層的に描くことになるのだが、その原型が簡明な形をとってここにある。
小説や演劇などの悲劇はいつも主人公の個人的な不運だが、ピナの悲劇は人間に構造的に根ざした、それゆえに誰にも共通の宿命である。その舞台は、不可能と知りながらなお愛を求めざるを得ないという私たちの遺伝子的衝動を覚醒させ、何重にも懸けられた安全装置を破って私たちの身体を内部から揺さぶるのだ。そしてある者はただ涙を流し、ある者はヴェンダースのように椅子から転げ落ちそうになるのである。
Flying Cabinet