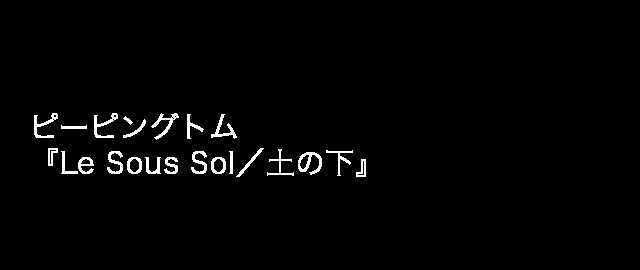暗い舞台の左端にケーキのような家の模型が光を浴びている。老婦人が闇の中から現れ、マッチ擦っておもちゃの家に灯をともす、と思ったらその家は燃え上がってしまう。舞台が明るくなるとそこは屋外ではなく、広い部屋の内部であることがわかる。けれどもなぜか床はすっかり土に覆われ、天井からは根が生えている。突然耳障りな音楽が鳴り、男が飛び跳ねる尺取り虫のようなダンスを始め、土の中からもうひとりの男が這い出し、老女がよろめき、若い女が壊れた自動人形のように倒れては跳ね起きる。そして横のほうでは太った女がメゾソプラノの美声を張り上げる。
こんなふうに始まる『土の下』は意表をつく展開の連続で、目が離せない。歌があり台詞がありキャラクターもあるけれども演劇のような筋書きはない。超現実的なシーンがつぎはぎされていく構成はピナ・バウシュのタンツテアターを連想させるが、その風合いはアラン・プラテルに似ている。親密と残酷、執着と断念、出会いの喜びと権力への怖れ。そういった私たちの誰にも身に覚えのある感覚が想像もしなかったコンテクストの中に置かれ、しかも繰り返し現れるとき、違和感はしだいに薄れてまるで懐かしいものを見ているような気になってくる。またおぼろげながら状況もわかってくる。ここは地下であり、登場人物はみな死者であり、生前の思いを引きずっている。若い女が「子どもを迎えに行かなくては」と何度も言うのは、子どもを遺してきたからだろう。
実はこの作品は三部作の第三部であり、一部と二部を知る人にはもっと細かな設定がわかる。太った女と若い女は母娘であるとか、老婦人が若い男と長い接吻をするのは若くしてなくなった夫とやっと再会できたからだ、といったことだ。けれども当日配布されるパンフレットにさえ前作の説明がないのは、物語を伝えることがこの作品の目的ではないからだろう。むしろ、観客の意識が筋書きを追うときに見失いがちなものこそが、この舞台では大事なものなのだ。
まず、演じられた役(キャラクター)ではなく、演じているパフォーマー自身の輝くような存在感がある。ピーピングトムはダンサー三人のほか、八二歳の女優とオペラ歌手の五人からなる。この作品では他に上演地のシニア・エキストラが数人加わる。老女優は少女のようにかわいらしく、歌手は威圧的な迫力をもつ。ダンサーたちの身体能力は圧倒的であり、対照的にアマチュアの日本人たちはどこまでも軽い(この性格は上演地によって変わるのだろう)。
死者を主人公にする舞台は日本人には親しい。夢幻能がそうである。生きている主人公は常に未来に向かっているが、死んでいる主人公には過去しかない。生者は富とか名誉とか正義とかを人生の目的にするが、死んでみるとそんなものは大概どうでもよくて、いつまでも気がかりなものだけが、本当に人生にとって大切だったのだと気がつく。能で妄執と呼ばれるのは、そのような愛の記憶である。『土の下』は具体的な物語を観客に伝えないが、観客は他者との関わりの記憶が凝固したような強迫的な行為や動作の中に、なまなましい身体が消しようのない哀惜を宿しているのを見る。それは枝葉を切り払って根と幹だけになった立ち木のような、漂白された人生のかけらである。一・二部の来日上演が待たれる。
Flying Cabinet