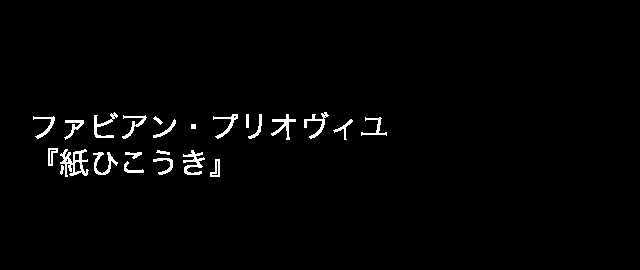紙ひこうきガールのゆくえ
1994年、平田オリザ作・演出の『転校生』は演劇界に大きな衝撃を与えた。このすばらしい舞台を演じたのがプロの役者ではなく、すべて公募で集められた女子高生たちだったからだ。しかも脚本は彼女たちとのワークショップの中で作られていったという。ある演出家は「もうプロの役者はいらない」とまで言った。そしてダンス界にもついに『転校生』が登場した。ピナ・バウシュが主宰するヴッパタール舞踊団にいたファビアン・プリオヴィユが、日本のバレエ・ノアの生徒たちと作り上げた『紙ひこうき』である。近年名の知れた舞踊家が若いダンサーとワークショップをしながら作品を作り、劇場で公開することは珍しくない。だが、たいていは発表会のレベルを超えないそれらとは一線を画し、『紙ひこうき』は舞台芸術として一級の作品に仕上がっていた。
『転校生』同様これも女子高生の世界を描いている。ダンサー自身、ほとんどが実際に女子中・高生である。そしてプリオヴィユも彼女たちとワークショップをしながら作品を作っていった。違うのは、『転校生』が結局平田オリザの世界であるのに、『紙ひこうき』はノアの生徒たちの世界であることだ。プリオヴィユは彼女たちと話し合い、その一人の話を全員に投げかけて共通の出発点としたという。そして「私は学校がすっごい嫌い」という言葉に始まる作品が生まれた。ダンスと小芝居、ユーモラスなシーンと不可解な光景などをコラージュする構成はピナ・バウシュに似ている。そして物語をなさない断片の組み合わせから全体として声にならない悲鳴が聞こえてくる。まるで昔のピナ・バウシュの仕事を見るようだった。ピナに似た手法の作品は多いが、これほど成功したケースを私は知らない。もちろん違いはある。ピナ・バウシュは個々のシーンを多義的に作り、作品のメッセージが一つに収斂しないように慎重に構成する。しかし『紙ひこうき』の象徴的表現は何を伝えたいかが明確で、作品のメッセージは一つに収斂してゆく。それはこの作品の場合必要なことであった。ワークショップは女子生徒たちが自分の抱えている問題を明確に認識していく過程であっただろう。漠然とした抑圧感が集団生活における同調の強要からきていること、堪えがたいのは暴力よりも仲間の視線であること、身を守るためには自分の顔を自分の手で消さなければならないこと、仮面は与えられるのではなく自分で択び取るように仕向けられること。そして紙ひこうきは空中で自由を得るけれども、人が空に飛び出すのは死ぬためであること。プリオヴィユは日本の女子中・高生の内部にあるものを外に引き出し、それに形を与えることに力を貸し、ほらこれが君たちのほんとうの顔だよと言おうとしたのだ。こういう場合、表現は明確でなければならない。メッセージは収斂しなければならない。
『紙ひこうき』は三つの意味で重要である。第一に作品そのものがすばらしいこと。第二に未熟なダンサーがプロを圧倒する舞台を見せたこと。第三にピナ・バウシュの手法が彼女以外によっても成功しうる普遍的な方法であることを証明したことである。
さいわいにも『紙ひこうき』は評価を得て半年を待たず今回再演の機会を得た。しかしこの作品は女子高生によって踊られるからこそ意味があるとすれば、10年後大人になった同じメンバーが上演することはできないだろう。そのときこれは伝説の名作になるのだろうか。それとも、女子高生たちの自殺を描いた如月小春の戯曲『DOLL』が今も全国の高校生によって演じられているように、高校生ダンサーたちによって踊り継がれる古典となるのだろうか。
(これはダンスマガジン2008年7月号に掲載された原稿を加筆修正したものである)