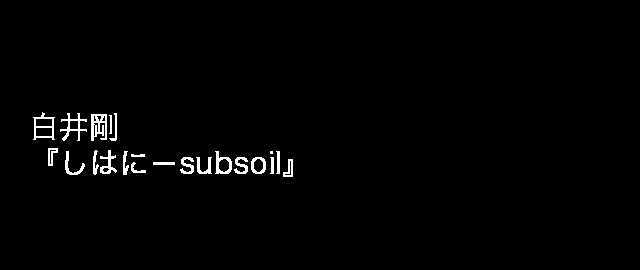3枚のシンバルが舞台右隅にある。1枚は吊られ、1枚は支柱の上に、1枚は床に置かれている。天井から水が滴ると、まず上のシンバルが鳴り、跳ね返った滴が下のシンバルを鳴らす。暗い空間に響く静謐な余韻は美しい。しかしこの音はアートなのだろうか、それとも自然の一部なのだろうか。音楽なのか、ノイズなのか。たしかにこの音は人によって仕掛けられ、人に聴かれることを待っているものだけれども、籠められた感情とか、表現された内面とか、創造された新しい表象とかいったものはここにはない。つまり、アーチストの自我という暑苦しいものがさっぱりと消えているのだ。これはそのままこの作品の特徴でもある。
白井剛は近年個人での活動が多かったが、新たにカンパニーAbsTを立ち上げ、その最初の作品『しはに』が発表された。昨年まで白井は「ダンスとは何か」という問題を「身体が動くとは何か」というところまで引き戻し、さらにそれを「身体の動きの物理的条件は何か」というところまで分解してソロ作品『質量,スライド,&』を作った。今回の新作はさらに一歩を進めて、「有機的器官の組織体である身体が動くとはどういうことか」を確かめようとする。舞台に出現するのは、機械以上、人間以下の五つの身体である。機械以上というのは、自動人形と違ってたえず状況に反応しながら動いているからだし、人間以下というのは明確な目的や意志や感情を持たないからである。
じつは身体の基礎レベルに立ち帰って新しいダンスを作ろうという試みは珍しくない。それらがたいがいつまらないのは、自分の内部感覚に頼って身体の底に降りていこうとするからだ。当人は何か新しい感覚を発見したつもりになったとしても、それは外部の観客にはさっぱり見えない。見えるのは自己満足している舞踊家の身体だけということになる。そこで反省した舞踊家は、次にこの幼い「自我」を排除する。すると方向は二つに分かれる。一つは意識のない機械としての身体、もう一つは狂気あるいは無意識の闇である。しかし白井はどちらも信用していないようだ。人は最初から状況の中で生きる有機的器官として生まれてくる。環境や他人などとの関係の中で、身体は自我などなくとも自分の動きを見つけてゆく。それは紛れもなく人間でありながら、自然の一部でもある。そういう身体のレベルにこそ、人間の最初の動きがあるだろう。それはダンスにならないだろうか。
たとえば、互いに相手の存在を認知し、わざと近づき、身体を交差させながら決して接触だけはしないという振舞い。他者の存在を明確に把握できないため寄り添おうとしては逸れてしまう、生まれたての子猫のように無器用な動き。明確なプログラムに従っているようで、じつは夢遊病者のように意志も目的もない行動。交錯する複数の刺激への反応から生まれたような所作。それらは文明の中で生活する身体でも、ダンスの様式化された身体でもない。何か自然と人間のあわいに宙吊りになったような身体である。しかも白井はそれらの身体の周囲に光と音と事物を寸分の狂いもなく構成して、緊張感の持続する時間と空間を作り上げた。このへんの白井の演出力は見事というほかはない。
今回の公演は新しい白井の作業の第一歩である。たぶん彼は今後時間をかけてこの作品の完成度を高めてゆくだろう。そのとき『しはに』は傑作となる予感がする。
Flying Cabinet