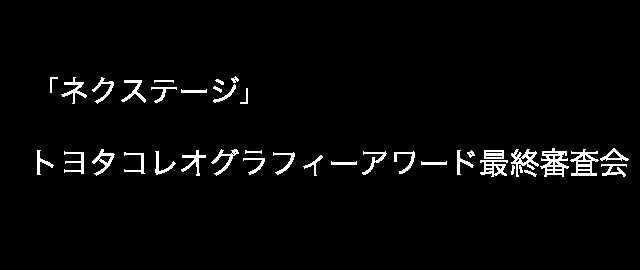「トヨタコレオグラフィーアワード」即ち「次代を担う振付家賞」は創設五年目を迎え、今年は一八六件の応募から八名が選ばれて最終審査のために自作を上演した。この公演は「横浜ソロ×デュオ・コンペティション」とともに、日本のコンテンポラリーダンスの新しい動向を占う機会ともなっている。今回特徴的であったのは、舞踊家たちが身体を異物のように扱っていることだ。かつて「表現」という言葉を掲げてモダンダンスが起こったとき、人間の身体がその内面と一体であることに疑いはなかった。しかし今、どうやら身体は自分にとって他者となった。これとどうつきあうのか、舞踊家は問い直してみなければならない。
『質量、スライド、&、』は白井の裸体が直立したまま後方へ音をたてて倒れるという劇的な光景から始まる。舞台上には身体のほかにボーリングの球や天井から吊り下がる紐などいくつかの物体がある。物体には質量があり、従って重力のために落下しようとし、力を加えれば横に滑る。白井は、質量をもつ物体が存在するとはどういうことなのかを、スリリングなやりかたで一つひとつ確かめてゆく。身体もまた質量をもつ。外部から負荷や力が加わるとき、身体は白井の意志よりも物理法則に従って動こうとする。白井は他者となった身体と交渉し、強制し、ときには迎合しなければならない。ダンスが可能であることの(あるいは不可能であることの)根拠を探るようなこのソロは、劇的な緊張に貫かれた舞台となった。
岡本のソロ『スプートニクギルー』はいくつかの小道具を回りに置いてひとり自閉的な世界を作る。まるで世界滅亡後ただ一人生き残ってしまったような孤独感だ。暗闇で何も触れるものがないとき自分の身体の境界がわからなくなるように、外部に何もつながるものがないとき人は自分の輪郭があやふやになる。彼女は身体の境界に沿って帽子や手袋や靴を身につけたり脱いだりする。自分の身体が本当に存在していることを確かめているのかもしれない。
康本雅子のソロ『メクラんラク』は徹頭徹尾ダンスである。ただきわめて短いフレーズをラジオ体操のように二、三回反復してから次の動作に移ることを繰り返す。これによって各動作は内面の表現ではなく抽象的所作にすぎないことが強調される。やがて首と手は意志によってコントロールされながらも胴体は強制されたかのようにひたすら回転し始める。身体が人間と機械に分裂するのだ。身体をさらに非人間化して自動人形にしたのが常樂泰の『広島回転人間』である。褌ひとつの男たちによる体操風絡み合いは大いに笑いを呼んでいたが、それは身体が意志を失って機械的に動くことからくる滑稽である。遠田誠の『ニッポニア・ニッポン』は正座とお辞儀などの慣習的所作を誇張したり、何かに取り憑かれた人間が操られたように跳ねるのを見せたりする。日本人の身体を自己批評するユーモアが同時に見事なダンスとなっていた。山賀ざくろの『ヘルタースケルター』はどう見てもおじさんの身体が女子高生の制服を身にまとう違和感から出発する。どう踊ってみても、女子高生になれないのはもちろん、おじさんの身体を回復することだってできない。
受賞したのは白井剛であった。その鮮明な問題意識と高い完成度を見れば、誰にも異存はない判定であろう。観客の投票によるオーディエンス賞は康本と遠田に与えられた。
Flying Cabinet