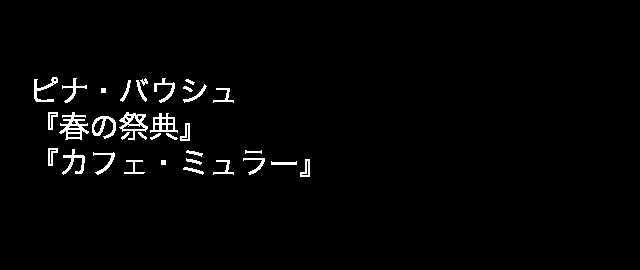二十年前『カフェ・ミュラー』と『春の祭典』をたずさえてピナ・バウシュが日本に登場したときの衝撃は今も語りぐさである。それまで新しいとされていたダンスが一挙に古く見えはじめた。従来の劇的な表現が浅薄なものに思えはじめた。同時にダンスがこれほど心を揺さぶる力を持っていたことに日本の観客は驚いた。多くの人がダンスを見る眼を変え、そして何人かは人生を変えたのである。それ以後の二十年間にダンス界は変わった。新しい試みが無数になされ、表現の幅も深さも比べ物にならない。しかしこの二作品は少しも古びない。それどころか、なんの戸惑いもなく今回の舞台を受けとめている若い観客を見ると、ようやく時代がピナに追いついてきたのだという感じさえする。
『春の祭典』はふつうのダンスを期待する人にもわかりやすい。春の訪れを喜び、やがて一人の少女が生贄に選ばれ、彼女は死ぬまで踊るのである。群舞は圧倒的な迫力があり、生贄のダンスは悲痛である。パリ・オペラ座バレエ団がレパートリーに加えたように、その完成度は二十世紀舞踊の古典のひとつと言える。いっぽう『カフェ・ミュラー』はわかりにくい。まずダンスシーンが少ない。一貫した筋もなく、登場人物が何者なのかも、彼らがなぜこんなことをしているのかも、そもそも一つ一つの行動が何を意味しているのかもわからない。けれども客席では何人もの観客が涙を流している。ここにはピナの独特の方法があるのだ。それまで誰も考えもしなかったダンスの新しい方法が。
木製の椅子とテーブルが雑然と並ぶカフェで、ヘンリー・パーセルの祈りのような音楽の中、六人の男女がとりとめのない行為を繰り返す。夢遊病のように目を閉じてさまよう女。彼女がぶつからないように椅子とテーブルを片づけるが、決して彼女を止めようとはしない男。目を閉じて女を受け止める男。人を気遣いながら何もせず、ただうろちょろする女。もしここになんらかの筋を解釈しようとしたら観客は茫然とするだろう。解釈の手掛りとなるような「意味のある行為」がまるでないのだから。舞台にあるのは、ある種の追い詰められた身体たちである。障害物にぶつかるのも構わず何かを希求する身体。他者を求める身体。気遣いつつもどうしても他者を受け止められない身体。観客はそれらに何かせっぱつまったものを感じ、胸を刺し貫かれる思いがするのだ。どうして?
人が物語に感動できるのは、登場人物が何者であり、どんな状況に陥ってどういう気持ちで何をしているのかを詳しく説明してくれるからである。小説の読者や演劇の観客はかんたんに登場人物の内面を想像し追体験できる。与えられたものをただ受け取れば感動は自動的に生まれる。これと反対に、ある種の詩歌やことわざなどはいわば白地図のようなもので、自分で内容を受肉させなければ意味をもたない。つまり自分の体験を書き込んではじめてそれは表現としての力を発揮する。たとえば「赤信号みんなで渡れば怖くない」という言葉を聞いて、なぜ人は微苦笑するのか。自分にも確かにそういうことがあったと思い当たるからだ。そのとき記憶の中には、赤信号への苛立ち、ルール無視への罪悪感、みんなと一緒という安堵、集団になると気が強くなる情けなさへの自虐などの心情が、はっきりした言葉の形はとらないけれども、いっせいに立ち上がっている。それらの実感がこの短い言葉に受肉されるからこそ、つい人は微苦笑してしまうのだ。逆に言えば、信号は絶対に守るべきであると信じ、一度も赤信号で渡ったことのない人には、この言葉のおかしみが実感できないだろう。彼が感じるのは「まったく世間にはマナーの悪い奴がいて困ったもんだ」ということであり、けっして自分のことではないのだから。
演劇という手本が身近にあったせいか、バレエもダンスも物語を説明して人の感動を誘おうとしてきた。しかし『カフェ・ミュラー』は状況を説明しない。観客が自分の内側に思い当たるものさえあればよいのだから。ピナは観客を信頼している。人は他者の物語を追わなくとも既に大事なことを知っているはずだ、と。だとすれば、心の底にあるものを拾い上げ、拡大すればよい。観客は忘れようとしていたものを思い出す。それはたいがい痛切な経験だ。むろん一人一人の人生は違うから、思い出すものも違う。反応するシーンも程度も違う。だから退屈する人だっている。そういう人はきっと幸せなだけの人生を送ってきたのだろう。けれども多くの観客は、舞台の奇妙な人物たちを見ながら、見失った自分を鏡の中に見るように思ったのである。それは安定していた自分の深層が一挙にかき乱されるような経験だ。そしてダンスにこのような力があったことに人々は驚き、それ以後たしかに世界のダンスは変わったのである。