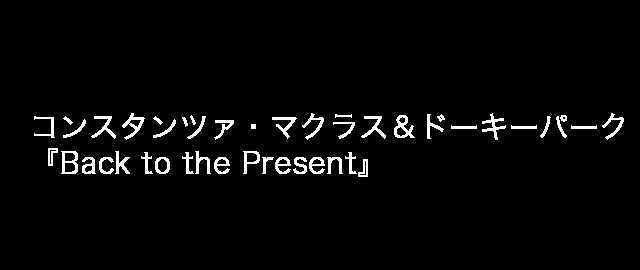「芸術は長く、人生は短かし」という常套句がある。もとは技術の習得には時間がかかるから寸暇を惜しんで勉強しろという意味だったらしいが、今では芸術賛美の格言にされている。しかし芸術が長いとは、人々の記憶に長く残るという意味か、それとも作品が何百年も保存されるということか。ベルリンのダンス・カンパニー、ドーキーパークのホームページには大きくこう書かれている。「記憶は消えやすく、ゴミは永遠である」。芸術とは所詮ゴミであるという自覚から彼らの作品は生まれるのだ。主宰者コンスタンツァ・ マクラスは、ピナ・バウシュの次はサシャ・ヴァルツだがその次はマクラスと言われるほど注目されている。その初来日公演に選ばれた『Back to the Present』を見ると、たしかに今ベルリンでは大きな変革が、それも東京とはまったく違った形で起こっているようだ。
ダンスがあり、歌があり、独白があり、映像があり、寸劇とも言えないような行為があり、それらがごちゃ混ぜにコラージュされる。その形式はおなじみのタンツテアターだ。けれどもそのテイストはピナ・バウシュの対極にある。ピナの舞台は洗練され、統一感があり、流れるような構成があり、眼を驚かせる美しいシーンや深い感銘を与えるシーンがある。しかしここにはそれらは全くない。ただ猥雑な断片がでたらめに積み上げられる。まるでゴミ捨て場のように。笑いを誘うナンセンスシーンでも、ピナの場合は一種超現実的な不条理性を帯びている。しかしこちらはひたすら馬鹿馬鹿しいだけだ。たとえば口に入れた食べ物を吐き散らしながら歌う、災難つづきの男を描く無声映画を見せる、裸になったダンサーたちの上に縫いぐるみが降りそそぐ、等々。国籍が多岐にわたるダンサーが自分について語るのも似ているが、ピナの舞台ではどの地の観客にも共感可能な内容が語られる。しかしこちらの「白人でリベラルでユダヤ人でゲイの男」が語るのは、自分と父親との関係を疑った兄が嫉妬のあまり包丁を持って自分を追いかけ回したというエピソードだ。こういう状況はなかなか想像も共感もしにくい。だから、笑うしかない。
また日本、とりわけ東京のコンテンポラリー・ダンスともある意味で対極にある。東京のスタイルが小ぎれいでカワイイとすれば、ベルリンの方は小汚く野卑だ。前者が無垢な子供の遊びだとすれば後者はヤケになった大人の愚行、ばかばかしくてやってられないけれどもやり続けるほかはないという自虐的な愚行だ。両者に共通しているのは、これまでの芸術の蓄積も規範も一切がチャラになったので完全な自由の中で何かを創らなければならないという状況認識だが、日本の若者の軽やかな疾走は何をしても手応えのない空虚感を背景にしているのに対し、ドーキーパークのまるで重しを抱えているかのような苛立ちの背後には打ち破ることのできない閉塞感がある。その重しとは、たぶん個々の現実の人生だ。だから見ているとつい「君のトラウマは何なんだ?」と精神分析をしたくなる。
政治家の偉業は野蛮であり、人類の成果はゴミでしかないという苛立ちと閉塞感。これはハイナ・ミュラーの『ハムレット・マシーン』以来、ヨーロッパの芸術家が共通にもつ背景なのかもしれない。とすれば、それは日本の背景といかに違うことだろう。
Flying Cabinet