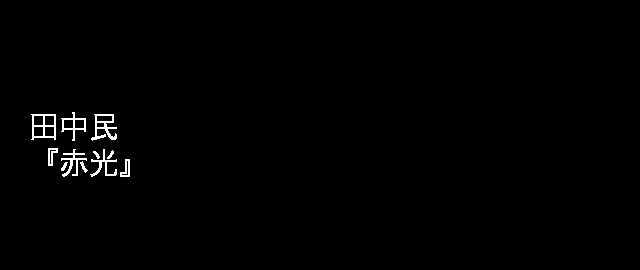『赤光』は斎藤茂吉の代表的歌集である。そこから松岡正剛が選歌した八首をスプリングボードに田中泯は三景の独舞を作った。山口源兵衛と沈娟卿の衣装、鈴木啓志の美術は簡素ながら神事の品位があり、泯は生贄のように身を差し出して舞台は一種の祭儀となった。
第一景。舞台上方には「うつそみのこの世のくにに春さりて」など三首の歌が書かれた旗が風に翻り、床には黒の丸石で埋め尽くされた庭がある。後方の闇から田中泯が白衣で登場し、細い光の中で両手を上げたりするが力がない。かすかに光る黒石のほうがよほど存在感がある。ふつうダンサーの技量は何で測られるか。人間が重い物質であることを忘れるほど、意志と力によって身体が完全にコントロールされているとき、「うまい」と見えるのである。ところがこの身体には内部の意志と力とがまるで欠けている。身体はただ外部のさまざまな力に引かれて動いているようにみえる。ではこれはだめなダンスなのか。もしダンスというものを、身体のあざやかな動作とか、美しいポーズとか、感情の表現などと考えるなら、ここにはそんなものは何もない。身体の表面にも内部にも、意味あるものは何も読み取れない。しかし驚いたことに、身体の外側に広がる空間が、舞台の主役として見えてきたのである。といっても何か目に見える形があるわけではなく、周辺は闇にとけこむ広がりにすぎない。その空間の中ににたしかに泯の身体を動かす意志と力とが感じられる。この空間は何か。森、自然、それとも宇宙? 舞台中央にそそぎ始めた雨は照明を得て闇の中で白く輝き、泯はその中に立つ。私にはやっとわかった気がした。この空間は天地なのだ。天地の間にまだ生き物以前の物体が生じ、天地によって動かされている。だから泯の身体はまだ内部を持たず、外側の天地の意志の象徴となる。一噌幸弘の能管は嵐が木の葉を吹き散らすようにメロディーのない音を闇の中に吹き散らし、大倉正之助の大鼓は時間を寸断している。ずぶ濡れの無力な身体は、その外部に広がる暗闇に力が充満しているのを感じさせる。それは造化の力である。やがて彼は服を脱いで裸体となる。仰向けになって四肢を揺らす身体は、はじめて生き物となったように見える。光の中に赤子の誕生である。
第二景。「赤光のなかの歩みはひそか夜の細きかほそきこころにか似む」他一首が提示される。両側から迫り出した木の床が黒石を覆い、ほぼ能舞台と同じ広さの舞台となる。笛の音はメロディーを形作り始める。すると泯の姿がにわかに肉体としての存在感を持ち始める。それまで空間の一部にすぎなかった存在が、空間から切り離され、内部を持つ一個の身体に結晶してゆくのだ。しだいに腰に力が生まれ、全身に力が波及する。血流が指先にまでエネルギーを運んでいくのが感じられる。そして原初の身体が立ち上がる。それは踊る身体である。けれどもそれはまだ頼りなく、行く先がわからないように見える。
第三景は「けだもののにほひをかげば悲しくもいのちは明く息づきにけり」他二首を踏まえる。客席後方から田中泯がつぎはぎのぼろ着に縄帯(『疱瘡譚』の土方を想起させる姿)で登場し、力強く踊り始める。舞台には「けだもの」のような性と生を区別しがたいエネルギーがみなぎる。腰に力が集中した安定感と力強い所作は日本の伝統芸能の身体作法に通じる。しかも時に能や相撲、歌舞伎などを思わせる形をとる。ただし最後はちょっと崩れて、型を決めない。型に至るプロセスだけを見せ、しかし終結しないまま次に移行してゆくのだ。絶えざる生成と崩壊が時間を永遠化してゆく。ちょうど一本の蝋燭が燃え尽きる前に次の蝋燭に火が移されていくように。一個の生体が死ぬ前に次の生体を産むことで生命が途切れないように。一つ一つは断片にすぎない生体の時間を鎖のように繋いで永遠化するための仕組みが性である。生体は内部に意志と力とをもつ。しかし性の仕組みは生体の内部にありながら、次の生命のために生体の意志を超えた力によって当の生体を突き動かす。第一景で身体外部の力を見せた田中泯は、ここでは身体内部にあって意志を超えた力の作用を見せる。舞台上を一直線に横切って火の手があがる。それは地水風に加わる最後の元素であり、造化の力強さを端的に示す象徴でもある。
田中泯の舞台は、私たちの生が永遠と結びつくのは精神や文化などによってではなく、身体によってなのだと教える。舞台上の身体は「入りつ日の赤き光」の中で死を迎える。けれどもそれは悲劇的ではない。その生はすでに永遠の一部であるからだ。
Flying Cabinet