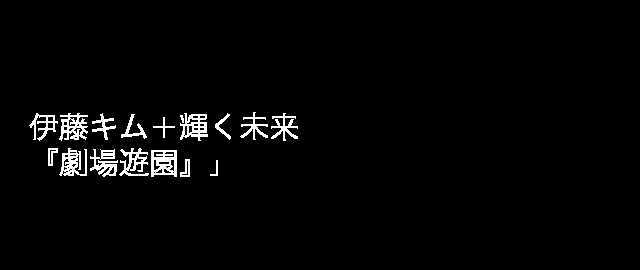劇場を遊ぼう
近頃の伊藤キムはダンスそのものよりも、ダンスという手段を使って私たちの見慣れた光景を異様なものに作り替えていくことに興味があるようだ。今年彼が各地で展開した『階段主義』のシリーズは、大階段に現れた不審な集団のパフォーマンスによって、都市の中の通路をたちまち奇妙な身体展示の場所に変えるものだった。たまたま通りかかった人はいつもの空間の劇的な変貌に眼を見はっただろう。これは日常空間の異常化だといってもいい。しかし同じことを劇場でやっても人はなかなか驚かない。劇場とはもともと非日常的なものを見せるための空間だから。では劇場空間を異常化するにはどうすればよいのか。まず「劇場」という場所の約束事を調べること。そしてそれを踏み破りながら、しかもただの日常空間に戻すのではなく、劇場でしかできないことをやってみること。これが世田谷パブリックシアターという場所を得た伊藤キムの今回の試みである。そしていかにも彼らしいのは、これを芸術的実験という肩肘張った態度ではなく、遊びの場となるようにしかけたことだ。
劇場空間は実は二重になっている。防音扉の外のロビーやホワイエは、都市の中の階段と同じく通行ないし遊歩の場所だから、観客の振舞いはまだ日常のままだ。扉の奥の場内には舞台と客席があり、ここが非日常のための空間である。けれどもここでもよく見ると、本当に見慣れぬことが起こるのは舞台の方だけで、観客は普段着のまま客席にとどまっている。そこで伊藤キムの仕掛けは二部制になった。第一部はロビーとその上の三層のホワイエで行われる。ダンサーたちは各階で同時多発的にポーズをとったり、走ったり、叫んだりとさまざまのパフォーマンスを行い、観客は事前に配られた「鑑賞マップ」を参考に「展示されるカラダのスキマを巡って、ご自由にご鑑賞ください」と指示される。第二部は場内で、着席した観客が正面のダンサーたちを鑑賞するという形式をとる。しかし座席は舞台上に仮設されたものであり、いつもの客席にはダンサーたちがいる。「通常の客席と舞台とが一八〇度反転した状況」(鑑賞マップ)なのだ。一部二部を通じて一貫しているのは、劇場空間の約束事をひっくり返して遊んでしまおうという企みである。
第一部、観客はできるだけたくさんの出来事を目撃しようと階段やホワイエをうろうろと往復する。けれども人が多くスペースが狭いので、文字通りダンサーの「カラダのスキマを巡って」いかねばならない。時には接触さえ避けられない。それは日常空間が異常なカラダを当然のように受け入れることであり、日常の私たちのカラダが異常な空間にためらいもなく入り込むことである。そしてこれはなかなか心地よい体験なのだ。さてチラシにも「舞台から客席へ、客席から舞台へ」と謳っているように、この公演の力点は第二部にある。しかし客席と舞台の機械的な反転は期待したほどの混乱を生まなかった。観客にとって座席だけがあって演技スペースがない舞台はもはや舞台ではなくただの客席だったし、ダンサーしか立ち入れない客席は目先の変わった演技空間にすぎなかった。舞台と客席の間の溝は反転以前と変わりがない。とはいえすり鉢状の斜面に椅子が林立する空間は落ちかかりそうな迫力があったし、足立智美の作曲・指揮による即興合唱は楽しかったし、伊藤キムの才気は観客のつぼを巧みに押さえて、終演時には熱烈な拍手を得ていた。奇策がアイデア倒れになる公演が多いなか、これは成功というべきだろう。さらにパワーアップした再演が期待される。