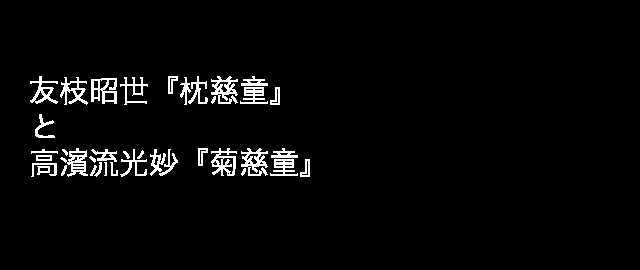二人の慈童
高濱流が創流二十五周年を迎え、記念公演で光妙は『菊慈童』を踊った。たまたまその二日前に喜多流の友枝昭世が薪能で『枕慈童』(観世流では『菊慈童』)を舞い、いずれも当代の名手であるだけに、能と日本舞踊の特徴がよく現れたように思う。
能は太平記に拠ったもので、周王の寵童が過誤を犯して人界離れた山中に追放されるが、仏法の功徳により菊の露を飲んで不老長寿の身となり、七百歳を経てなお童子の姿をしていたというものである。王の寵愛を一身に受けたというのだからよほどの美少年だったのだろう。台本にはさしたるドラマがあるわけでもなく、ただ主人公の美しい姿を見せることが主眼としか思えない。現在では「童子」や「慈童」の面をつけるけれども、ひょっとしたら中世には少年が無面で演じていたかもしれない。世阿弥の言う「時分の花」(少年であることの魅力)を発揮させるのにこれほど適した設定はない。いうまでもなく中世は美貌の稚児が美女以上に熱狂的なファンを得た時代である。
友枝昭世は夜の空間にひたすら幻想の美少年を顕現させた。その演技は物語を説明しようとするものではなかった。荒唐無稽な物語はどうせ現代の観客に説得力をもたない、ただ主人公を非現実的な存在とするための口実にすぎないというかのようだった。じっさい衣装の金糸が篝火にきらめき、背後の茂みが風にゆらめくと、慈童の姿はこの世の者とは思えなかった。
日本舞踊の『菊慈童』は能の『菊慈童』の日舞版ではない。それは観客が既に能の物語を知っていることを前提にしている。だからその詞章は、たしかに『菊慈童』であることを謡曲の引用で確認するだけで物語そのものは語らず、もっぱら恋心の諸相を語るのである。それも「浮名のな立つともこちやうれし」とか「いとし辛気の顔みたや」とか、まったく江戸趣味である。
この曲は本格的にやるならおかっぱの鬘に能風の衣装らしいが、光妙は素踊りということで大人の髷に着流しで登場した。なんともこれが粋な女の風体だった。これでは衆道の恋を表現するのに不向きなようだが、実はこれで正しい。光妙の舞台を見ていて分かったのは、慈童は遊女や芸者の仮装なのだということである。この曲は初手から菊慈童なんかどうでもよく、江戸の花柳界の色事を舞台に乗せるさいの趣向として中国の故事をちょいと借りたにすぎないのだ。
春信の浮世絵に若い女が川岸で菊を手折っている『見立菊慈童』というのがある。むろんこの絵の本質は「美人画」であって、見る者はここにめでたい長寿を見出したり山中の孤独を思いやったりするわけではない。「菊慈童」の見立てはこの絵を単なるピンアップにしないための風雅な口実にすぎない。同じように舞踊『菊慈童』の本質は色の道にある。ただ趣向として能の『菊慈童』に見立てただけなのである。この「見立て」という手法そのものがまた江戸好みである。
光妙は詞章の世界を細やかに表現してみごとだったが、それだけにこの江戸趣味が現代に通じがたいという感を覚えざるを得なかった。能の異様な美の方が、特定の時代の趣味に依存していないために、かえって現代人に驚きと感動を与えるのだ。いわば中世の能は当世ファッションとして通用するのに、江戸の日本舞踊は流行遅れに見えるのである。日本舞踊が現代芸術になるためには、この江戸趣味を脱しなければならないのだろう。