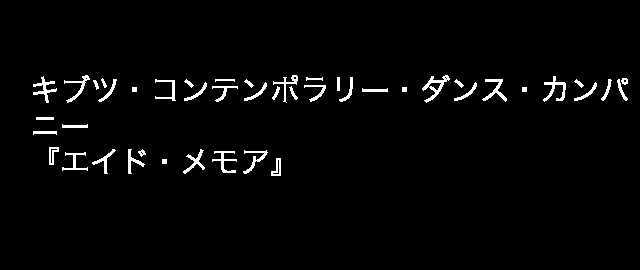アウシュビッツは踊れるか?
多くのことを考えさせられる公演だった。それもダンスにとって重大な問題を。
そもそもアウシュビッツはダンスになるだろうか? これは日本人にとってはこう言い換えてもいい。いったいヒロシマはダンスになるだろうか? 七三一部隊はダンスになるだろうか?
この夏私は北京にいた。仲間と盧溝橋を見るべくタクシーを走らせたのだが、運転手はその手前の抗日戦争記念館で車を止め、まずこれを見ろと笑顔で強要した。戦勝五十周年を記念する展覧会は勝利者の子孫で賑わっていたが、圧巻は南京大虐殺の記録写真と七三一部隊の再現模型だった。白衣を着た人形たちが中国人捕虜を生体解剖している光景を見て、私は吐き気を覚えた。人形の出来が迫真性を欠くのが救いだった。これは意図的だったかもしれない。もし真に迫っていれば、会場の床は嘔吐でぬかるんでいただろう。青ざめた私たちを笑顔で迎える運転手を見ながら、彼らはこの事件を決して忘れないだろうが、ダンスにすることも決してないだろうと思った。劇場の床が嘔吐にまみれるような作品を作ろうとは誰も思わないし、また思ったとしてもできるものではない。
不思議なことに日本にはヒロシマを主題にした舞踊作品があるらしい。確かにダンスは悲しみや苦痛を表現できるし、悲鳴をあげることだってできる。だがそれらの表現は、 ペットを失った悲しみや、虫歯の苦痛と区別がつくだろうか。その悲鳴は痴漢に襲われた時のものとどこが違うだろうか。もし観客が落ちついて座席に坐っていられるなら、違いはないのだ。表現を尽くした数時間の舞踊作品よりも、たった一枚の被爆者の写真の方が、多くのことを語り、強く心を動かし、深く記憶に残るだろう。だから心ある舞踊家なら、ヒロシマを主題にすることをためらうだろう。しかし皮肉なことに、世界は日本人に対してはヒロシマを、ユダヤ人に対してはアウシュビッツを見たいと思うらしい。暗黒舞踏がヨーロッパに進出を始めた頃、その混沌と醜悪をヒロシマの表現と勘違いされたという。
ユディット・アーノンは家族とともにアウシュビッツに収容され、出て来たときは孤児になっていた。やがてイスラエルに渡り、キブツ・コンテンポラリー・ダンス・カンパ ニーを創設し、現在なお芸術監督の地位にある。五十年の間、彼女はアウシュビッツを忘れることはなかっただろう。しかし、ついにそれを作品化することはなかった。できな かったのだ。たぶん世界がそれを期待していることを知ってはいたけれども(だからこそ、初来日公演にこの作品を選んだのだ)。
作品化したのは戦後世代の振付家ラミ・ベアである。彼はアーノンの住むキブツ(財産を共有する村規模の生活共同体)で生まれ、小さいときから彼女にダンスを学んだ。収容所の経験はないけれども、その記憶を周囲から聞かされながら育ったことだろう。なぜなら、その記憶は世代の交替とともに消えてしまってよいものではないのだから。
舞台は重々しい汽車の響きから始まる。奥には幅1m高さ3m程の板が八枚、50㎝くらいの間隔で横いっぱいに並んでいる。細い光の中に女性の姿が現れる。「よろずの事には期あり、よろずのわざには時あり・・・」という「伝道の書」の一節が英語で読まれ、次第に数を増したダンサーたちが祈りと苦悩とを身振りに表す。繊細な追憶が始まる。ラミ・ベアの振付は巧みである。十数人の身体を自在にあやつり、反復と逸脱、地と図、多数と一人とを対比させつつ空間を設計する手際は鮮やかだ。欧米のモダンダンスの最先端を抜かりなく把握しているし、構成力も、細部の工夫もある。全体のトーンは抒情的であり、いくつかのシーンは息を呑むほど美しくさえある。そして時折、荒々しい情景が挟みこまれる。たとえば「出て来い!」というドイツ語の怒号が繰り返され、その声に追い立てられるように、板と板の暗い隙間から、わらわらとダンサー達が現れる。まるで隠れていた者が見つかったように。イスラエルの舞踊団がドイツ語を用いるとき、既に政治的意味を帯びる。観客は誰もがナチスによるユダヤ人狩りを思い出すだろう。
しかし人々が「アウシュビッツ」という言葉から想像する、背筋の凍るような感覚は、ここにはまったくない。レスキスにみられるような暴力的世界への危機感さえない。ただ「アウシュビッツ物語」の挿絵があるばかりだ。それは仕方のないことなのだろう。ラミ・ベアははじめからアウシュビッツそのものを表現しようとはしていない。それは直接体験した者にしかわからないし、しかも体験してしまったものには重すぎて作品化できないものなのだ(ヒロシマのように)。彼はアーノンらから語り聞かされた「アウシュビッツ物語」の記憶を忘れないためのメモとしてこの作品を作ったにすぎない。タイトルが『エイド・メモア(備忘録)』であって、「アウシュビッツ」でも「ホロコースト」でもないのはそのためだ。たとえ外国人にとって期待外れであろうとも、おそらくこれだけがアウシュビッツを作品化できる唯一の方法なのだろう。