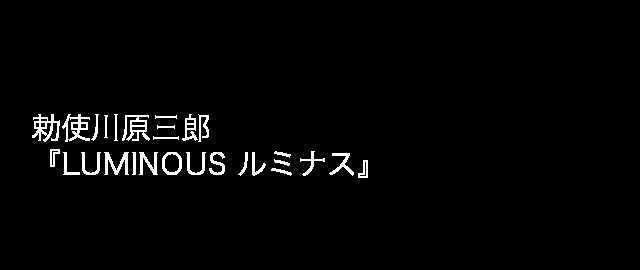光とダンス
『LUMINOUS』は一昨年初演され、その年から始まった朝日舞台芸術賞を受賞し、同時に受賞者の中から選ばれるキリンダンスサポートも獲得した。これは受賞作品の再演を財政的に援助する賞であり、優れたダンス公演が一度限りで見られなくなることが多い現在、メセナとして秀逸である。『LUMINOUS』はその後ヨーロッパ諸国で上演されていたが、今年キリンビールは約束を果たし、初演と同じ劇場で再演された。その舞台は確かに再演に値するものであった。
タイトルからもわかるように、この作品は光をテーマにしている。まず、美術家としても卓抜な勅使川原は光をさまざまに駆使して舞台に美しいイメージを構築する。それは通常の舞台照明のように舞台やダンサーをどう照らすかという工夫から生れたものではなく、舞台上で光がどう戯れるかを緻密に計算したものである。たとえばガラスは光を透過し、同時に反射する。そこで舞台上にスポットライトを置き、その光軸に沿って何枚ものガラスを置けば、透過光と反射光とがさまざまな効果を生み出すだろう。さらにダンサーの身体がその光軸に割り込んで踊れば、光と影とがさまざまなダンスをするだろう。あるいは衣装を発光塗料で覆えば、ダンサー自身が光源となって舞台上を動き回ることができるだろう。このようなアイデアを思いつくのはさほど難しくはないだろうが、このアイデアを使って大きな空間に幻想的な視覚効果を作り上げたのは勅使川原の力量である。
舞台には七人のダンサーとテキストを読む一人の役者が登場する。中で二人のダンサーが目を引く。その一人、勅使川原三郎の鋭利なダンスについては既にこれまで多くの人が賛辞を捧げているので、ここでは繰り返さない。特筆したいのはもう一人の主役、スチュアート・ジャクソンである。彼は「光」とはどういうものか知らない。先天性全盲であるからだ。盲人のダンスといえばヴィム・ヴァンデケイビュスの『あの娘は我慢できない』に前例がある。しかしそれは盲人と晴眼者に同じ舞台でダンスを踊らせ、観客からは区別がつかないということが売り物だった。盲人だって晴眼者と同じことができますよというのは、暗に晴眼者こそが正常であるということを前提にしており、私は不快を覚えたものだ。ジャクソンのダンスは逆に、私たちの知っている晴眼者のダンスとはまったく異なるものだった。晴眼者のダンサーたちは、自分のダンスが観客に「どう見えるか」を意識しながら踊る。観客は視覚情報に基づいてダンスの出来を判断するから、ダンサーは身体の形や動きの緩急など目に見える情報に心を配るわけである。けれどもジャクソンに「どう見えるか」という問題はない。彼にとってダンスとは外見の問題ではなく、内部感覚の問題である。直接に感じ取る自分自身の筋肉や神経のダイナミックな変動こそが、彼にとってのダンスなのである。驚くべきは、この内部のダンスが観客にも感じ取れるということである。たとえば最後に彼が右腕を上に伸ばす。ポーズとしてはそれだけのものである。けれども観客は彼の右腕の筋肉を伝わる緊張の波と、次第にそれが弛緩してゆく経過とを、まるでドラマを見るように見て取ることができるのだ。そして完全に緊張が解けた時、彼のダンスが終わったことを知るのだ。観客は彼に惜しみない拍手を送っていたが、そこには障害者への同情は微塵もなく、ただ新鮮なダンスへの称賛があったように思う。ジャクソンは光がないゆえに新しいダンスを発明したのだろうか。いやもともとダンスに光は要らないのだ。彼は余計なものを持ち合わせないにすぎない。ダンスとは踊り手にとっても、そして観客にとってさえ、まず肉体の内部の問題なのだということを再認識させてくれた舞台であった。