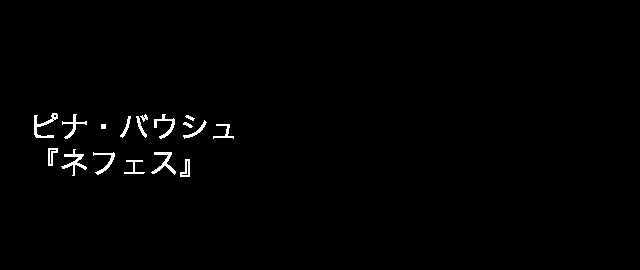青い鳥を見た夜
近年のピナ・バウシュは世界各都市の委嘱により、その地に示唆を得た作品を作る。今回はトルコのイスタンブールである。三月、その新作が例によってタイトル未定のままヴッパタールで初演された。この夜観客は青い鳥が劇場に降り立つのを見ることになった。
舞台はダンサーたちの印象的なイスタンブール経験から始まる。ハマーム、すなわちトルコ風呂である。モスクとバザールに並ぶこの歴史的名物も、今では癒しを求めて観光客が訪れたりすれば、文字通り痛い目にあうことになる。彼らが「マッサージ」と呼ぶものは、日本語では「折檻」と訳したほうがよい。ダンサーたちはいかに手荒なマッサージを受けたかをコミカルに演じ、観客を笑わせる。こうして身構える観客の緊張をすっかり緩ませたあと、ピナは突然不可解な光景を現出させる。タオルを腰に巻いてハマームの床に横たわる男性ダンサーたちの上にそれぞれ女性ダンサーが身をかがめ、ひたすら髪を梳るのだ。それは観客の意表をつくだけでなく、シュールレアリスム絵画のような不思議な魅力を湛えている。観客は茫然としてこの夢のような光景を眺める。笑劇による無邪気な興奮は消え、ただ心地よい思考停止に陥る。そして唐突に一人の女性のダンスが始まる。思考を停止した観客は、てもなくダンスに巻き込まれてゆく。構成の呼吸の見事さである。むろんこのダンスがつまらなければ全ては台無しになるだろう。このソロを引き受けた瀬山亜津咲は鮮やかに任務を果たした。いやそれ以上だった。全身のダイナミックな動きと指先の細やかな動きが組み合わされ、リズムの緩急が巧みに切り替えられ、予想外の動きが予想外のタイミングでつながって、見たことのないダンスが展開してゆく。私は舌を巻いたのだが、それでは終わらなかった。このあと次々と繰り出されるダンスの力に私は圧倒されることになった。たとえばクリスチアーナの天才的リズム感は手先をちょっと動かすだけで私の身体を内部から弾ませるし、高木賢二の超絶的スピードは特撮映画のように目を眩ますし、妖精のように跳ねるシャンタラの優雅なダンスはこれを永遠に見続けたいと思わせる。彼女が踊り終えたとき私はとても残念に感じたのだが、ピナは憎い演出を用意していた。横にいた男がシャンタラの耳もとでなにやらささやくと、彼女はほほえみ、なんともう一度同じダンスを踊って見せたのだ。彼は観客に代わって「もう一度」と言ったのだろう。シャンタラのダンスを見た観客がどんな思いを抱くことになるかピナは予期していたのだ。その自信のほども凄いが、それを予定通りに実現してしまうダンサーの力量には脱帽するほかはない。さらに特記すべきことがある。これらのソロの振付が基本的にダンサーたち自身によるということである。ピナの目を通しているとはいえ凡庸なフレーズはひとつもない。各自がそれぞれ個性に満ちたダンスを披露するのだ。もっとも女性ダンサーの動きには全体としてピナの匂いがする。つまり、自分を大きく見せようとするのでもなく、内にこもろうとするのでもなく、身体の表面のところで愛撫するような、あるいは身悶えするような動き。叫びよりもささやき。怒号よりも語りかけ。音楽に合わせるのではなく身体の内部からでてくるリズムに従う緩急など。結局この新作では十九人のダンサー全員がなんらかのソロを踊り、ヴッパタール・タンツテアターが確かに舞踊団であること、それも超一流の舞踊団であることを確認させることになった。かつてピナ・バウシュ作品にはダンスシーンがほとんどなく、「ダンスというよりボードビルだ」などと評されていたことを思うと隔世の感がある。
ヴッパタール舞踊団の様変わりの理由の一つはメンバーがすっかり若返りしたことだろう。古馴染みの顔はほとんどいない。若手たちは不条理なあるいはナンセンスな寸劇を印象的に演じる個性に乏しいが、そのかわりダンサーとしての力量は素晴らしい。それがダンスを構成の中心に置く理由かもしれない。しかしそれだけではない。
なによりピナ・バウシュ自身が変わったのだ。八〇年代のあの痛切な舞台はここにはない。人生に対するシニカルな目は苦い真実を発見するよりも、むしろユーモアを見出すために使われる。観客の安定した世界観に衝撃を与え、混乱させ、破壊する手口はもうない。むしろ痛みを癒し、幸福感を取り戻そうとしている。たとえばこんなシーンがある。一人の男が苦悩を表現するダンスを踊っている。そのスタイルは古典的モダンダンスのようで、つまりちょっと臭いのだが、技術が見事なので観客は彼の不幸を十分に説得される。すると優雅な衣装の美女が数人現れて彼をとりかこみ、微笑みながら愛撫しはじめる。とまどう彼の前に父親らしき男が現れ、にこやかに彼を迎え入れようとする。彼がおずおずと近づくと男は彼をしっかりと抱きしめ、そして再び美女たちのもとへ送り出す。彼は受け入れられたのだ。彼はてれながら、チヤホヤしてくれる女たちといっしょに舞台を去って行く。もちろんこれらはユーモラスに演じられるのだが、観客は笑いながらも救いを感じるのである。昔のピナ・バウシュなら彼は孤独へ突き落とされるか、他人にいたぶられて終わるところだ。
この素晴らしい舞台が明かしているのは、ピナ・バウシュがこのような作品を作るのはかつてのようなものが作れないからではなく、このようなものを作りたいから作っているのだということだ。とすれば彼女はもはや過去にもどることはないだろう。私たちは彼女の変化を受け入れる他はない。それは悪いことではない。一夜確かに私たちを幸福にしてくれるのだから。それも昔と同じように、世界中でピナ・バウシュにしかできないやりかたで。