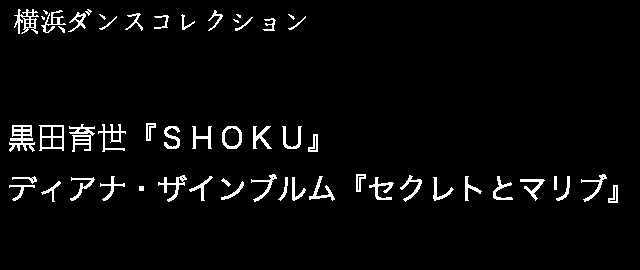バニョレ国際振付賞の本選出場者を選ぶためのプラットホーム(公開競演)からはじまった「横浜ダンスコレクション」は、今や日本のコンテンポラリー・ダンスの先端状況を示唆するイベントとなった。今年はソロとデュオのコンペティション(七七組から十組が選ばれて上演)を中心に、昨年のバニョレの受賞者から日本の梅田宏明とアルゼンチンのザインブルムの作品、また横浜プラットホーム独自の賞の受賞者から黒田育世と矢内原美邦の作品が上演された。
黒田の『SHOKU』(ミドルバージョン)は、昨年上演したショートバージョンの改訂延長版である。昨年デビューしたばかりのこの新人は,早くも独自の世界を明確に舞台に立ち上げた。これは驚くべきことだ。コンテンポラリー・ダンスの作家は、厄介なことに先人の成果を捨ててゼロから出発しなければならない。それで自分なりの世界を築きあげるのは容易ではないし、その上どこかで見たようなものになってしまうことが多い。ゼロから出発して人が思いつける範囲はあまり広くないからだ。陥りがちなのは、「私」にこだわるナルシシズム、他者との関係では性と暴力、新手法を求めてハイテクの濫用、といったあたりである。けれども黒田はこれら安易な道をとらない。
舞台は赤いワンピースを着て仁王立ちした六人の女が、金属を激しく打つリズムに合わせて上半身を大きく前後に振る光景から始まる。彼女たちは優雅でもセクシーでもない。ただエネルギーの限界を試そうとしているかのようだ。しかもユニゾンで動いている。実はコンテンポラリー・ダンスでユニゾンの振付は珍しい。というのも多数のダンサーがユニゾンで踊るのを見ると観客は生理的快感を感じるので、安直なエンタテインメントと見られやすいからだ。むろんだからこそミュージカルなどはこれを利用する(ピナも客が疲れた頃に使う)。しかしここでのユニゾンは、客席に快適なノリを与えるためでもなく、癒しをもたらすためでもない。確かに観客は一種の快感を味わうのだが、それは自己破壊へと疾走する原始的身体の興奮とでもいうべきものである。そしてこの感覚は、ときおり憑きものが落ちたように静かなシーンもあるものの、作品の全体を通じて励起され続ける。ダンサーたちは赤いワンピースという「女」の記号をまとい、スカートを持ち上げ、ついには白い下着だけになる。けれども少しもエロチックではない。観客を誘惑する能動性もなければ観客の目に傷つけられる受動性もない。ただ自分の身体に耽溺している動物的肉体があるだけだ。彼女たちは全力で自分の身体を振り回して喜ぶ巨大な幼児のようだ。もちろん実際にはみな恵まれた肢体をもった若い女性なのだが、なぜか性的分化以前の身体に見えるのだ。それどころか逆に、これらの身体が生物的にも文化的にも「若い女」という意味をまとっていることに違和感さえ覚えるのである。このジェンダーの慣習に根ざす違和感と原始的な身体の興奮との共存が、観客と舞台との間に距離化と同化の不安定な関係を作り出す。おそらくここに黒田の世界の独自性があるのだろう。
ザインブルムの『セクレトとマリブ』もまた独特の世界を作っている。南米の田舎家の庭先らしきセットを構え、二人の女の穏やかな生活が一人の男の性的な闖入によって乱されるまでをタンツテアター風に描く。一人は自然の風と光を愛し、一人は扇風機や電灯を愛する。けれども彼女たちは双子のように共同生活を楽しんでいる。それを象徴的な振舞いや、ときにピナ風ときにローザス風のダンスで示すのだが、たしかに独自の雰囲気はあるものの、個々のシーンがなまぬるくてどうもこちらの胸に届かない。最後に一人が立ったまま実際に放尿してみせるのは確かに意表をつくが、観劇後の話の種以上にどういう効果があるのかは疑問である。
Flying Cabinet