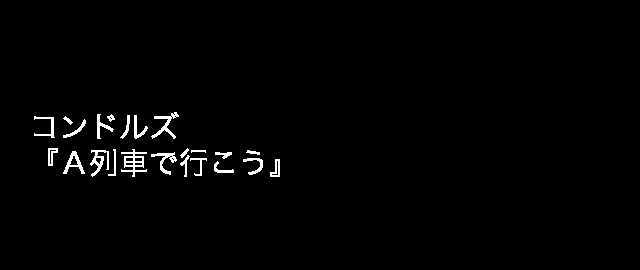ナンセンスのセンス
ニューヨークのハーレムから一直線にブロードウェイを突っ切り世界貿易センターのあったビジネス街をかすめてブルックリンへ向かう地下鉄をA線という。これを題材にしたのがデューク・エリントンの『A列車で行こう』である。コンドルズの新作タイトルはその借用だが、副題は「新世紀東アジア縦断ツアー、東京大凱旋スペシャル公演」。スケールは地下鉄より大きい。
決して少年には見えないがさりとておじさんにも見えない男たちがなぜか学生服で踊りまくるこの集団は、あっと言う間に日本の代表的コンテンポラリー・ダンス・カンパニーの一つに数えられるまでになった。近藤良平のダンスがかっこいいということもあるが、この快進撃をもたらしたのは、なんといっても舞台をつらぬく絶妙のテンポとセンスが時代に愛されたからである。例によって今回も多様な要素がとりとめもなく並べられる。ビデオ映像、コント、人形劇、楽器演奏、巨大なロボット、そしてダンス。これらがすべて快適な速度で展開してゆく。この疾走感は、常に観客の期待をはぐらかし、裏切って行く展開によってもたらされる。たとえば、教師と女子高生の列車逃避行で始まるコントがある。だが次々と奇妙な人物が現れて筋はどんどん逸れて行く。ついには「ベルばら」の世界が出現し、大袈裟な物語になるかと思えたとき、唐突にわけのわからぬ大王が登場してクイズに答えることをオスカル達に強要する。そして最後に、正解を待ち受ける観客を尻目に「答えは教えてやらない」といって引っ込んでしまう。要するに観客が期待している解決はいつも与えられないのだ。物語にオチはなく、筋書きは意味をなさない。しかしこれが受ける。観客は大声で笑う。そのナンセンスが気持ちがいいからだ。コンドルズがお笑い系といわれる理由である。けれども注意しなければならないのは、これは吉本新喜劇の笑いとは違うということである。野田秀樹の笑いとさえ違う。むしろその後の世代であるケラリーノ・サンドロビッチたちのものだ。新しい世代はもうドタバタでは笑いはしない。もう一つ例を挙げよう。かわいらしいしぐさのメルヘンチックなダンスシーンがある。踊るのは、タイツならぬ冬物の長下着を付けた男たちである。しかもある者は禿げ頭、ある者のはヒゲづら、ある者はデブである。けれどもキワモノ的に演出されるのではなく、見ている内にやさしい気分になってくるほど優美に演じられるのである。これはトロカデロ・モンテカルロ・バレエ団の、女装した男たちによるお笑いとは違う。彼らは単純なパロディをやっている。だから大袈裟に演ずる。しかしコンドルズの笑いはナンセンスから来ている。メルヘンの世界のパロディではなく、「メルヘンというナンセンス」を演じているというスタンスがある。ひとつ間違えば恥ずかしいパロディになってしまうのを、軽いアソビに昇華してしまう。その絶妙なセンスは現代のものだ。だから観客の年齢層は若い。
地下鉄A線の駅を降りるとニューヨークのさまざまな顔が現れるように、コンドルズの舞台はさまざまな光景を出現させては、惜しげもなく見捨てて次へ進む。ダンス以外のシーンの多さからもう舞踊作品ではないと言う人もいるかもしれないが、ダンスの枠が気軽に超えられていくのを見るのは気持ちのいいことだ。その構成は巧みである。反復、ずらし、ミスマッチ、引用、自己批評(自分へのツッコミ)、オチのないブラック・ユーモア。多様な手法が利用され、舞台は緊張と弛緩、ノリのいいダンスと意表をつくコントを交替させつつ、終点まで客を降ろさず疾走する。強いてアラを探すなら、毎回同じように面白いのはマンネリの一種ではないか、というくらいだ。