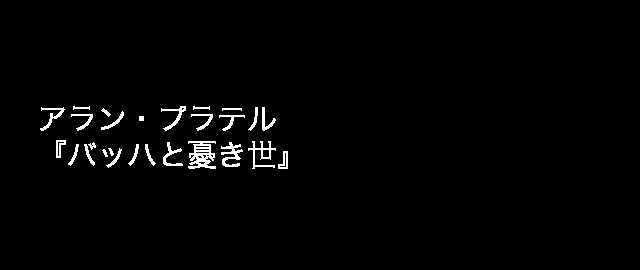愛と冷徹
衝撃的な舞台だった。作品として素晴らしいだけでなく、舞台芸術はこまできたのかという思いを抱かせる先鋭さがあった。
作品とは何だろうか。私は退屈な舞台を見ながら、こんな作品でも上演に至るまでは大変だったんだろうなと想像することがある。無から有を生み出す作家の苦悩。稽古場での生臭い葛藤。本番の舞台裏で繰り広げられているスタッフたちの修羅場。こぎれいにまとめられた作品よりも、まとめようもない現実のドラマを見せてくれた方がきっと面白いのになと思ってしまうのだ。
人の生活があるところには必ずドラマがある。高みから夜の町を見下ろすと無数の窓の灯が見える。その一つひとつに異なる生活とドラマがあるのだと考えると気が遠くなる。むろんこの光景はまだ芸術でも作品でもない。だがその人々が家を出てたまたま同じ車両に乗り合わせたら、そしてそれぞれに思いの丈を吐きはじめたらどうだろう。悲喜と愛憎、ささやきと怒声が入り混じり、ろくに聞き取れないとしても、それはたいがいの作品より面白いのではないだろうか。とりわけその声から背後のドラマを想像できる人にとっては。例えばアラン・プラテルはそういう人だ。
彼は基本的にオーディションをしないという。偶然に出会った人の中でこれはと思う者に声をかける。稽古場で彼らの自己表現を選択し拡大し凝縮して、車両ならぬ舞台に一緒に並べる。観客は性別年齢国籍さまざまな人生のドラマを同時に眺めることになる。ただしドラマは物語のように明確に与えられるわけではない。ただ印象的な断片として提示されるだけだ。けれどもそれは、無数の窓の灯の背後のドラマが、想像ではなくいきなり現実のものとして眼前に迫って来たような迫力がある。
幕が開くと廃墟になりかけた空間を背景に、男が頭から血を流して立ち尽くしている。いったい何があったのか、と思うまもなくさまざまな男女が登場して思い思いのことを始める。叫びもあればすすり泣きもある。サーカス芸もあればダンスもある。子供は無邪気に歩き回り、婚礼の日にレイプされたという白いドレスの女の股間は赤く染まってゆく。個々のシーンは卑俗でありながら、全体としては無常の色を帯びている。プリンスの音楽で一時的に無理やり高揚したりするのだが、その後はかえって虚しさが増すのだ。そして全体を覆うバッハの生演奏は、あまりにも世俗の感情を超越していて、まるで一切の人間の悲喜劇は所詮何万年も繰り返されてきた些事にすぎないというかのようだ(英語の作品タイトルは『バッハの音楽に付けられた小さなこと』という)。この音楽のおかげで観客は登場人物たちに共感することができない。醒めた目で憐れみと愛情とをもって見ることになる。たとえば演じられるサーカスの芸は背後に過酷な修練があったに違いないのだが、そのわりには何とも見栄えがしない。けれどもその愚かさと真剣さとは見るものに苦い感動を与えるのだ。バッハは、すべてのドラマは塵であり、かつすべての塵は美しいと教えているかのようだ。
プラテルはいったいどんな眼差しで世界を見ているのだろう。底知れぬ冷徹と愛。私は同じような目をした芸術家がもうひとりいたことを思い出した。ピナ・バウシュである。プラテルのタンツ・テアトルはピナ・バウシュのタンツ・テアターの後継と位置づけられているという。確かに手法にも印象にも似たところがある。しかし無数にいるピナの模倣者の一人に彼を位置づけるべきではない。ピナ・バウシュの舞台はどの瞬間をとってもピナ自身の世界が現れるのに対し、プラテルの舞台では個々の出演者のリアルな存在感が前面に出ている。出演者の選択眼と、彼らに自分を解放させる技術において元セラピストのプラテルは傑出している。私たちが目撃するのは、芸術家の作品というより、実際の人生の傷ましさであり、それらが無数に居合わせるこの世の姿そのものである。舞台芸術はここまで来たのだ。