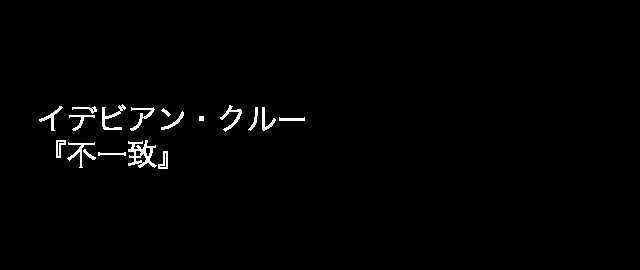イデビアンといえばまず連想される形容詞は「笑える」だった。なにしろトレードマークがブリーフである。男女の別なく全員がタイツの上に男物のブリーフを穿いて出てくる。しかも後ろを向けば、尻のところにマジックで大きく当人の名前を手書きしてある。これはもう、品位がどうとかいうものではなく、あまりの馬鹿馬鹿しさに笑うしかない。振付の特徴は集団の配置と視線を利用した心理的関係の表現にあった。たとえば仲間外れにされた者が再び集団に迎えられるまでのいきさつを巧みなドタバタマイムに仕立てて演じたりする。客席はいつも笑いに包まれる。もっともそれは、ありがちな人間関係の滑稽を抽出したコントのおかしさであって、珍しいキノコ舞踊団やコンドルズらのようなナンセンスの笑いではない。ナンセンスは波長が合わなければ笑えないけれども、イデビアンは誰にも分かりやすい笑いだったといえる。
こう書くと下ネタもケレンもいとわない受け狙いのグループのように聞こえるかも知れないが、イデビアン・クルーが送り出してきた作品はいずれもダンス作品として見事なものであった。そして今や、正統的なダンス・カンパニーへと舵を切ろうとしているように見える。今回の『不一致』ではもはやブリーフは見せない。集団の心理関係を表すシーンも一部あるけれども、長丁場の単調を避けるための気分転換程度であって、以前のしつこさはない。笑いは抑制され、代わって構築への志向とダンスそのものへの志向が前面に出てきている。
暗闇の客席に陽気なラテン音楽が響き出す。明るく軽い舞台を予想しているところへ幕が開くと、喪服姿の男女十数人が客席に向かい一列に並んでいる。舞台の奥と左右の三方は白黒の幕で覆われ、床は畳敷き。意表を突いた葬式のしつらえである。もっとも整列は完全ではない。一人欠けたようなすき間がある。やがて遅れてきた者がその穴をふさぎ、ようやく厳粛な列が完成したと思ったとたん、端の男がぶざまに態勢を崩す。だがその動きは奇妙なことに、先程から鳴っているラテンのリズムにぴったり合っているではないか。思わず笑いかけた次の瞬間、列は砕け散って全員が音楽に合わせて激しく踊り始める。それが喪服と似合わないのでまた笑いかけ、ふと気がつくと一人だけ、初めの位置で身じろぎもせず立ち尽くしている者がいる。とまあ、こんな風に始まるのだが、『不一致』という名は体をよく表しているだろう。普通の作品は要素を一致させて舞台上に秩序を作り出そうとする。しかしこの作品は常に不一致があってその秩序を完成させないのだ。混沌や混乱があるわけではない。舞台上の秩序はとてもわかりやすい。だからこそ仕込まれた異物やずれが目に立つ。そしてしばしば、その異物が次のシーン展開への呼び水となる。観客は、万華鏡のような変化に意表をつかれながら、その変化が一種の必然性を伴った流れであるように感ずる。井出茂太の構成の巧みさは、対位法を参照したというケースマイケルの数学的緻密さに匹敵するだろう。
今の東京の若者たちには「カッコつけたものはカッコ悪い」という美意識がある。イデビアンもまたバレエやモダンダンスがカッコいいとみなす動きだけはやるまいと決意しているかのようだ。彼らのダンススタイルはすでに一つの個性を確立しているが、今回井出茂太自身がダンサーとして加わったことで、その特徴はいっそうはっきりした。天性のリズム感と俊敏な動作に恵まれた彼の身体は、どんなに動きを崩しても音楽に乗っている。一見間の抜けたような姿態もダイナミックな動きに貫かれると目を奪うダンスになる。惜しむらくは、他のダンサーが井出の域に達していない。けれどもカンパニーとしてダンスで観客を楽しませるレベルには成長している。だからこそ今回はダンスを中心にしたのかもしれない。下ネタやコントの笑いは一回目こそ面白いが二回見る気にはならない。けれども『不一致』はもう一度見たいと思わせる作品である。
Flying Cabinet