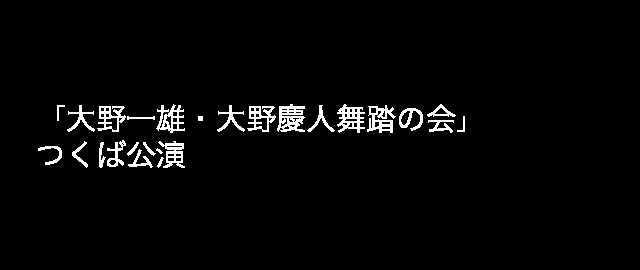一期一会。
大野一雄の公演のときは、いつもそんな気持ちで家を出る。むろんすべてのパフォーマンスは厳密に言えば一度限りだ。だからこそ記録技術がどれほど進歩しようと、あのライヴの緊張感はかけがえがない。けれども実際には、たいていの舞台芸術は「作品」の完成をめざして稽古を重ね、本番を迎えれば毎晩同じ「作品」を再現しようとする。演者が同じなら日々の出来不出来は誤差の範囲とされ、「作品」は基本的に同じだということになっている。たとえばミュージカル『キャッツ』について語りあう人たちは、いつどこで見たのかを問題にしない。彼らが経験したのは、ある時ある場所で起こった特定の事件ではなく、まるで映画のように同じ姿を繰り返す「キャッツという作品」なのだ。
一方、大野一雄の舞踏は事件である。その時その場に居合わせた者しか見ることができない。たしかにそれらは『私のお母さん』とか『アルヘンチーナ頌』といったタイトルがあるけれども、あらかじめ完成された「作品」の再現なんかではない。私たちが見ているのは大野が舞踏によって表現する何かではなく、舞踏によってあらわになる大野その人なのである。彼が遠くを見れば神への祈りが現れる。手を差し伸べれば愛する死者が現れる。90年余を持ちこたえた彼の身体はすでに老残といってもよい。その身体に私たちは希有の魂の90年の経歴を見るのだ。私は狂言師善竹弥五郎の『月見座頭』を思い出す。彼は虫の音に聞き入る盲人を演じていた。その姿にひとりの老座頭の人生の総てが凝縮され、私は涙を抑えることができなかった。神品の演技術である。しかし大野は演技によって誰かの人生の幻影を作りだすのではない。彼が女装して誰かを演じているときでさえ、私たちは彼自身の情念を見てしまうのだ。
大野一雄はできるだけ間近で見るほうがよい。カピオホールが舞台上に観客を上げ、鼻先で大野の肉体が舞うようにしたのは正しい。降り注ぐ音楽が大野の身体に染み込み、一瞬ごとに舞踏となって新たに生み出されていくさまを、私たちはこの身に触れるように感じとった。予定のプログラムが終わると彼は舞台を降り、無人の観客席を抜けて出口に向かった。舞台に残された観客は拍手で彼を送っていた。そしてついに出口に辿り着いたとき、突然彼は踵をかえし、客席の最後尾で舞い始めたのだ。それは雲の切れ目から去ろうとしていた天女が最後の別れの舞をしているようだった。これほどの無垢な優しさと愛に包まれた時間を私は知らない。やがて大野は彼を愛する人々を舞台に残し、手を振りながら視界から消えた。この日の「事件」を私は忘れることはないだろう。
Flying Cabinet