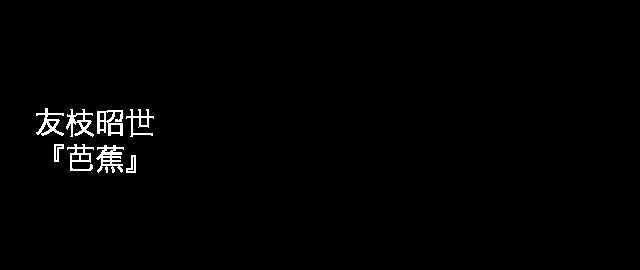花と草
中世の日本では人間ならぬ草木までも成仏するという奇妙な説が広く世間に流布した。その理論は天台本覚思想と呼ばれるが、どうやら日本独自のものらしい。金春禅竹の『芭蕉』はこの教説の劇化で、芭蕉が成仏するという話である。私は昔ざっと一読して、なんだか抹香臭い能だなと思った。まるでテキストが読めていなかったのだ。だが友枝昭世の演能を見て、目から鱗が落ちた。『芭蕉』は抹香臭いどころか、選ばれた美男美女の恋物語などよりはるかに深く、今もなお古びない感動的なドラマだった。
日本人はなんと「花紅葉」を愛してきたことだろう。とりわけ桜は、今や遅しと開花を待たれ、咲けば色香を賛嘆され、散ってゆくのを惜しまれる。これを日本人の自然愛好の証とする人がいるが、そういう人は桜の周りにある草木が見向きもされないという事実を忘れている。花紅葉に目を奪われることを人は風雅と呼ぶけれども、草木を無視することを誰も無情とは言わない。無視されるだけでなく、無視されるのを当然とされること。これほど残酷なことがあるだろうか。誰からも愛される桜に対し、見捨てられた草木の代表として芭蕉は登場する(実は芭蕉にも花はあるのだが、詞章に「花もなき芭蕉」とあるように花はないものとみなされている)。芭蕉が桜とかわらないのは死の訪れることである。散りやすい桜の花と裂けやすい芭蕉の葉は、はかないものの象徴とされてきた。死を前にしてはじめて芭蕉は桜と同じ場所に立つことができる。
はじめ芭蕉は里の女に化身して現れる。彼女は荒涼たる山陰に誰にも知られず住み暮らし、年老いてゆく身の哀れを語る。いまや念頭にあるのは、なんとかして命ある内に真理を悟り生死を超えること、即ち成仏することのみである。だが仏法は男女を差別する。男は成仏できるが女人はできない、まずは来世で男に生まれるのを待てという。まして非情の(魂のない)植物は成仏できるはずがない。ところがここに「草木国土悉皆成仏」を説く経を読誦する僧がいる。芭蕉は毎夜庵室の外で読経を聞き、ある夜女の姿となって僧と対面し、「女人非情草木の類ひまで」成仏する理法を問いただしてゆくうちに、ついに真理を悟得する。
「ただそのままの色香の草木も、成仏の国土ぞ、成仏の国土なるべし」
この繰り返しは「そうなのだ、まさにそうだったのだ」という突然の覚醒を実感させる。その地謡の声に合わせて、友枝昭世の両手がゆっくりと合掌した。それは意志によってというより、感動のあまりひとりでに手が動いたようであった。草木の人生は無価値ではなかった。私には女の両手の間からこぼれる涙が見えたような気がした。
「何疑ひか有明の、末の闇路を晴るけ」(もはや何の疑いも残らない。闇夜の道が月光を受けたようにすべての真実がはっきりと見える)。
願いを達した芭蕉の精はいったん僧の前から身を隠し、姿を変えて再び現れる。「花も無き芭蕉」の詞とともに友枝昭世が両袖を広げると、眼前に巨大な葉が左右に開き、まざまざと芭蕉が立ち現れた。雌雄のない芭蕉の精が女の姿であるのを見て、僧は愚かにもなぜ「女体の身をば受け」たのかと問う。これは僧自身が人に教えるほどの学識はあっても、じつはまだ悟得していないことを示している。男女の差別にこだわる僧に、芭蕉の女は「その御不審は御誤り」と一蹴し、男女の差別も有情非情の差別も根拠のないこと、さらに春の花から秋の草まで「諸法実相隔ても無し」と説く。そして白い月光のもと、秋風の音に死を予感しつつ、無量の思いを抱きながら白鳥の歌ともいうべき最後の舞を始める。
「しのに物思ひ立ち舞ふ、袖暫しいざやかへさん」
しかし友枝昭世の序の舞は優美というより、かぼそく侘しかった。肺を病む若い女が自ら死へと踏み出すような脆さと切なさとがあった。私はようやく気がついた。これは女の姿を借りた芭蕉なんかではない。芭蕉の名前を借りた女なのだ。芭蕉はいわば隠喩にすぎない。ここで舞っているのは、桜の容姿に恵まれなかったために男たちから無視され、おそらくは人生の花をことごとく拒まれたまま、日陰で草木の人生を送ってきた女だ。その彼女が死に臨んで自分の生の価値を確認している姿なのだ。これは中世の宗教劇ではない。現代なお普遍性をもちつづけるドラマである。花と草の人生を分けるものは美醜に限らないだろう。男女の性、家の貧富、才能の有無、頑健と病弱、当人に責任のない天与の運が残酷な差別をもたらす。不運を割り当てられたものはただ身の不幸を歎くしかないのだろうか。そうではない、と舞う女の姿は告げている。
「草の袂は久方の、天つ少女[おとめ]の羽衣なれや、これも芭蕉の葉袖をかへし」
彼女の眼に、もはや桜と芭蕉、天女と自分の間の差異はない。そして風が吹き始める。
「庭の浅茅生[あさじう]、女郎花[おみなえし]苅萱[かるかや]、面影うつろふ露の間に、山颪[やまおろし]松の風吹き払ひ吹き払ひ」
庭にも花と草とがある。いうまでもなく和歌の伝統では「女郎花」は美女の隠喩である。だが吹き荒れる山颪、すなわち無常という死の風は花も草も隔てなく襲う。
「花も千草も散り散りに、花も千草も散り散りになれば、芭蕉は破れて残りけり」
友枝昭世は広げた両手をしぼむように下ろした。西洋の古典絵画ではだらりと垂れた手が死体を表す。葉を破られて立ち尽くす芭蕉の姿にも生気がなかった。なんという無残な終わり方だろう。夢や幻のように消えてゆくのではない。芭蕉は死に、この場に残骸をさらしているのである。けれども月光の下の残骸は、差別の世界を超えて永遠に入ったように見えた。