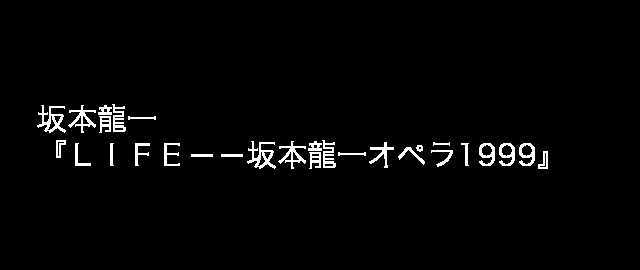とにかく壮大なオペラである。まず空間が大きい。オペラ劇場ではなく日本武道館である。望遠鏡がなければ私は字幕を読めなかった。当然肉声には向かないから、拡声装置を駆使することになる。視覚装置も大きい。広さが平均的マンション三戸分くらいありそうなスクリーンが十六面に分割され、プロジェクターの群が精密な技術に制御されて一つの映像を合成する。スタッフとキャストも豪華である。コンセプト・デザイナーに浅田彰、インターネット顧問に村井純を迎え、テキストは村上龍、衣装は山本耀司、映像はダムタイプの高谷史郎、身体表現はフランクフルト・バレエのアントニー・リッツィ、CGは原田大三郎があたる。スクリーンでは、ホセ・カレーラス、ローリー・アンダーソン、ロバート・ウィルソンらが朗読し、ピナ・バウシュが語り、ついにはダライ・ラマ14世までが出演する。だが何よりも壮大なのは坂本龍一の構想と気宇である。オペラといえばたいがいは私的な恋の挫折かなんかを大げさに歌いあげるものだが、彼はそんなものには目もくれず、人類の歴史と地球の生命について語ろうとする。第一部は20世紀の総括である。坂本は今世紀を人口爆発ではなく大量殺人によって特徴づけ、技術革新を医療ではなく戦争によって代表させる。映像は第二次大戦や湾岸戦争などの破壊と殺戮の記録を枚挙し、それにアウシュビッツやヒロシマを語る文学者や思想家の言葉を重ね、並行して音楽はドビュッシーからミニマル音楽までの様式史をおさらいする。やがて原子爆弾を開発したオッペンハイマーの顔が大写しとなり、「世界の破壊者」という彼の言葉が執拗に繰り返されて、第一部が終わる。第二部は坂本の生命観の提示である。生命の進化と地球の歴史を映像によって鳥瞰しつつ、生命体は互いに依存する「共生」関係にあることを言葉によって訴え、地球自身が一個の生命体であるというガイア仮説を紹介する。音楽はアフリカ、モンゴル、沖縄などから来た歌手がそれぞれの唱法で歌い、クジラの歌など自然から集められた音が流れ、合唱団は今世紀に絶滅した種の名前をラテン語で美しく朗唱する。第三部は救済を主題とする。しかしいまどきこのような問題に救済を提示できるのはカルト宗教くらいだろう。坂本も、『エヴァンゲリオン』や『もののけ姫』と同じく、安易な救済を語らない。芸術に希望を見出しつつ、ただ死者を鎮魂する。最後は「彼らをいつまでも光で照らしたまえ」というレクイエムと「彼岸に往ける者」をたたえる般若心経を荘厳に歌い、会場を光の洪水で満たすのである。
1976年ロバート・ウィルソンが身体表現・音楽・美術を複合しつつ物語のない舞台『浜辺のアインシュタイン』を作りこれを「オペラ」と呼んだとき、人々はまだ抵抗があったとみえてこれを「パフォーマンス」という新ジャンルに分類した。しかし近年「オペラ」の概念は拡張され、たとえばタン・ドゥンの『マルコ・ポーロ』は西欧とモンゴルの唱法を共存させ、スティーヴ・ライヒはビデオ映像と生演奏とを組み合わせた「ドキュメンタリー・ビデオ・オペラ」を始めている。マルチメディア・パフォーマンスである『LIFE』はこのような新しいオペラの一つとして認知されるだろう。
最後にダンスに触れよう(プログラムには「ダンス」ではなく「身体表現」とあるが)。テキストや映像や音楽がわかりやすいメッセージ性を備えていたのに対し、ダンスはむしろそれを避けるように曖昧だった。ダンスは三つの層で提示される。生身の身体、それをビデオで撮影したスクリーン上の映像、そしてインターネットを通して送られてくるニューヨークとフランクフルトのライヴ映像。リッツィのしなやかな身体はすばらしいが、このような巨大空間ではどうしてもスクリーン映像のほうが印象が強くなる。高谷の洗練された映像は賞賛に値するが、彼にとってダンサーの身体は映像素材の一つにすぎなかったようだ。インターネットからの映像は東京の音楽やダンスと密接にかみ合うわけでもなく、なぜこんなことをするのかわからなかった。地球の裏側のダンスがライヴで見えることは、既にオリンピックの同時中継を見慣れた私たちにとって驚くべきことではない。あるいはこの作品が壮大であるために、どうしても地球規模の同時参加者、いや共生者が必要だったのだろうか。
Flying Cabinet