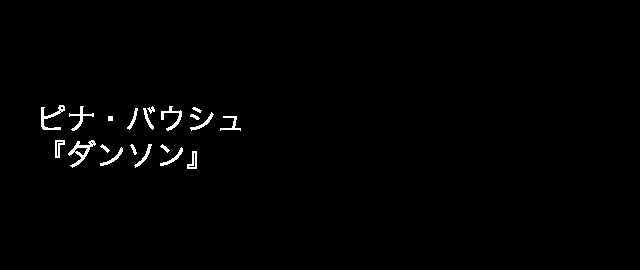心ゆくまでダンスを
五月の終わりから六月にかけての四週間、続けてピナ・バウシュの公演があった。『タウリスのイフィゲネイア』『ヴィクトール』『フェンスタープッツァー』『ダンソン』と四本のプログラムを見るため毎週(時には連夜)彩の国さいたま芸術劇場に通いながら、私は一カ月つづく祝宴に出ているような軽いめまいと興奮の中にいた。全てが終わった今、その後遺症に苦しんでいる。困ったことに、ふつうのダンスやバレエを見ると、あまりのナイーヴさに退屈でしかたがないのだ。「ダンス」という既成の形式を信頼しきっている舞踊家の素朴さが、単なる鈍感さに見えてしまうのである。ある者は美しい姿や形を作ろうとしている。ある者は身体をメディアにして感情や思想を表現しようとしている。ある者は超人的な妙技を見せようとしている。だがそれらが見事に成功しているときでも、私は「ああ、頑張ってるね」「よくやったね」という感想しか持てないのである。私の舞台の見方が素直じゃないのだろうか。私はべつに斜に構えて客席に座っているつもりはないのだが。ただ作り手の期待とは違った見方をしているのは確かだろう。私はどうやらピナ病にかかってしまったのだ。
ふつう舞踊家は自分の仕事の成果である「作品」を見せようとする。そこで「ダンス」という形式の枠の中で、工夫を凝らし心血を注いで舞台の上に人工の作品を作りだす。ところが私はそうやって「ダンスとして作り出されたもの」よりも、「ダンスをしていること」「ダンスをしている人」の方を見てしまう癖がついてしまったらしい。だから作り笑いをしながら精一杯に予定のポーズを決めるプロのダンサーよりも、『ヴィクトール』でエキストラに起用された地元の老紳士たちがヴッパタールの女性ダンサーたちと社交ダンスを踊るのを見る方が気分がいいのだ。うまい下手など関係ない。だって彼らは本当に楽しそうなんだもの。私はそこに彼らの悠々たる余生を、そして終わりよければすべてよしの人生を見てしまう。むろん私は錯覚しているだけだろう。彼らの人生の実情などわかるはずもない。けれども私は彼らの屈託のないダンスに、長い波瀾のあとの穏やかな日々を感じてしまうのだ。こういう経験をすると、社交ダンスのプロの鮮やかなデモンストレーションの方がなにやら空しい作業に見えてくる。
『ダンソン』では久しぶりにピナ・バウシュ自身のダンスが見られる。なんでも、ダンサーたちが「ピナも一緒に踊ってくれなくては私たちも踊らない」と迫ったのだという。ピナは要求に応え、ソロのダンスを披露した。ただし、主役でなければ気のすまない多くの舞踊団主宰者とは違い、自分にスポットを当てることはしなかった。それどころか、わざと照明を暗くして自分が誰かわかりにくいようにした。舞台開口部の全面を巨大なスクリーンがふさぎ、水中の魚たちを映し出す。高さ数メートルの熱帯魚が明るく輝きながら身をうねらせて疾走し、ダイナミックに反転する。その右下隅で暗い小さな人影がゆったりと動き出す。両足は動かさず、ただ上体がファドの抒情的な音楽に乗って、単純なしぐさを繰り返すだけだ。けれどもそれはまぎれもなくダンスだった。素晴らしいダンスだった。もっと正確に言えば、ピナのダンスが素晴らしいというより、ダンスをしているピナが、そして彼女が今日ダンスをしていることが素晴らしかった。うまい下手は重要ではない(もちろん下手ではないけれども)。私はこの時間が永遠に続いてほしいと思っていた。こう書くとなんだかアイドルを前にしたミーハーのようだけれども(じっさい私はピナのファンであるけれども)、初めてピナ・バウシュの作品を見た人でさえ、同じような印象をもったようだ。つまり観客は彼女のダンスに見事な技芸や深い表現などを見出すのではなく、ただ彼女の優しさをその繰り返されるしぐさから感じとり、心地よい気分に浸っていたのである。
ダンサーたちの求めに応じてピナは踊った。ダンサーたちも皆ピナのために踊らなければならない。『ダンソン』とは「ダンス狂」という意味であるという。この作品はダンスに満ち満ちている。もともとダンスの嫌いなダンサーなどいないにしても、『ダンソン』のダンサーたちは楽しげだ。しかし、そのダンスのほとんどはふつうのダンスではない。いや、ダンスなのかどうかさえあやしい。たとえば、正装した男が女物の靴をはいて出てくる。足が大きすぎて、親指が靴の外にはみ出している。舞台中央に進み出ると、微笑みながら両足を揃えたまま、彼は音楽に合わせて二つの足の親指を動かし始める。そう、これは足指のダンスなのだ。いや、これは「ダンス」といっていいのだろうか。動いているのは足の親指だけで、彼の身体はちっとも動いていないのだから。彼はまだ踊っていないというべきではないのか。けれどもリズミカルに動くその指は確かに踊っているとしか見えない。人形遣いが人形を踊らせるとき、踊っているのは人形であって人形遣いではないというならば、確かにこの場合も踊っているのは彼の足指であって、彼ではないということができる。だがそんなことを言うなら、彼がふつうに踊っているときも、踊っているのは彼の身体であって彼ではないということになってしまう。やはり彼は踊っているのだ。たとえ指しか動いていると見えなくとも、彼の身体の内部には音楽と同じリズムが脈打っているにちがいない。彼は両手で身体を抑えて動かないようにしているけれども、その先端で、靴からはみ出した指がつい動いてしまうのを止められないのだ。これは身体の最小部分だけによるダンスである。
またたとえば、およそダンサーらしくない野暮ないでたちと不格好な体型の(たぶんセーターの下にいろいろ着込んでいる)女性が出てくる。彼女は歩きながら、両手や足をふとダンスっぽく動かして見せる。鼻唄というのがあるけれども、それのダンス版と思えばよい。いい加減で、中途半端で、そもそも元はどんなダンスなのかもわからない。けれども、鼻唄でさえそのリズムや音程の正確さから、きっとまともに歌えばうまい歌手にちがいないとわかることがあるように、彼女の動きのタイミングはつぼにはまっていて、うまいダンサーであることがわかる。それどころか、うまいダンスを見ているのと同じ快感さえある。見て楽しいダンスであるために美しい肢体も大げさな身振りも完璧な動きも必要がない。ぐうたらな身体と動きの途上で、ただほんの少しのしぐさが時々ぴたりと決まればよいのだ。とすれば、多くの振付家がダンスを作るために苦心惨憺しているあの努力はいったいなんなのだろうか。これは人の所作がダンスになるための最小限の要素でできているダンスなのだ。
ではこんなのはどうだろう。椅子に横座りにかけた女性が、観客に流し目を送りながらスカートをめいっぱいたくし上げる。むき出しになった太腿にライターを近づけ、火をつける。熱いんじゃないか、と心配した次の瞬間、彼女は微笑みながらふと腰を浮かし、ライターの上に腿を落とす。火は消える。あまりの馬鹿馬鹿しさに客席に笑いが起こる。セクシーな誘惑かと見えた振る舞いが自己処罰の行為に転じ、次の瞬間ナンセンスなギャグになる。この一連の所作は面白いけれども、決してダンスには見えない。ところが彼女はこの同じ所作を繰り返し始める。それどころか、他の女性ダンサーたちも椅子をもって現れ、彼女の横にならんでラインダンスのように同じ所作を始めるのだ。一人の演者が同じ所作を反復するとき、あるいは複数の演者が同じ所作を同時に行うとき、観客の眼にはその所作が一つの「型」として見えはじめる。つまり演者は意味ある行為を表現しようとしているのではなく、決められた動作の型を再現しようとしているのだと見えはじめる。だが人の振る舞いを「行為」としてではなく「動作の型」として見るとは、それをダンスとして見ているということである。実際、同時に数個のライターに火がつき、同時に数本の太腿が動き、同時に火が消える一連の所作は、まるでラインダンスを見ているような快感があった。ここには、私たちが人の動作をダンスとして見るための最小条件がある。
「ダンスとして見る」ということをもっとはっきりと問題にするシーンが冒頭近くにある。優雅な薄物をまとった女性が登場し、観客に日本語で語りかける。「私はこちら、あなたがたはそちら」。演者と観客とが二つに別れるとき、ダンスは自分で踊って楽しむものではなく、ただ「見るもの」(観客にとって)、そしてただ「見られるもの」(ダンサーにとって)となる。両者の間には深い溝がある。しかし彼女は続いて驚くべきことを行う。客席の老婦人(実は男性ダンサー)を舞台の上に招き、自分はその空いた座席に座って老婦人に言うのだ。「私たちはこちら、あなたはそちら。何か素敵なことをやって見せてください」と。見る者と見られる者はいつでも逆転可能だし、しかも舞台の上に立ったものはいつでも「なにか素敵なこと」をやる義務があるということだ(ヴッパタールのダンサーたちは稽古場でピナから課題を与えられるたびにそれを感じているだろう)。しかし足もともおぼつかないこの老婦人に何ができるというのだろう。満場の観客が見まもる中、彼女はぎこちなく、けれどもうれしげに自分のもっとも晴れがましい記憶を再現して見せる。片足を引き身をかがめるその所作は、かつて高貴な人の前で行ったお辞儀である。われわれの眼にはただの西欧風のお辞儀にすぎない。しかし彼女にとっては人生でもっとも華やかな注目を浴びた一瞬のパフォーマンスである。そのとき彼女は「見られる者」であったし、そのお辞儀は細心の注意をもって行われた「観衆に見せるための所作」だったのだ。身をかがめながらそのとき彼女は確かに舞台に立つ者、観客から見れば「そちら側」、ダンサーからみれば「こちら側」の人だったのである。人に見せるための優雅な所作は、すでにダンスと同じではないだろうか。これはあるしぐさが「見られるダンス」として成立するための最小条件を示している。
これらの例はみな普通の意味ではダンスではない。というか、ダンスと呼ぶのをたいていの人はためらうだろう。いわばこれらは、ダンスが生まれようとしているその寸前の姿である。それだけにダンスの基本条件がむき出しになっているし、「ダンスとは何か」を考えるには絶好の事例でもある。ではこれは、あのポストモダニズムの時代に流行った「ダンスについてのダンス」、「ダンス批評としてのダンス」つまりメタダンスなのだろうか。そして「ダンスとは何か」を問いなおそうとしているのだろうか。いやそうは思えない。ピナ・バウシュはたぶん人がなぜ踊るのかに興味があっただけなのだ。彼女はかつて「私は人がどう動くかよりも、人を動かしているものに興味がある」と言った。人がなぜダンスをするのか、その理由がこれらを見ればわかるではないか。たとえば人は音楽に、あるいはリズムに合わせて身体を動かすのが好きなのだ。またたとえば、何かのために身体を動かす行為よりも、ただ動きのための動きをすることが好きなのだ。そしてそれをみんなで一緒にやればもっと楽しいのだ。そういう動きをしている身体を見るのが人はまた好きなのだし、しかも多くの人の前でそういう身体を見せることも好きなのだ。要するに、人はダンスが好きなのだ。
もっともこれは、あまりにもダンスの意味を拡大することになるかもしれない。たとえば海辺で裸の男女が楽しげに走り回るのも、山の中のキャンプで身振りを交えて漫談するのも、赤ん坊が意味もなく石を転がすのも、それどころか男が女の服を脱がせたり着せたりするのさえゲームとして行われれば、それはダンスになってしまうのではないか。だがそう考えて何が悪いだろう。実はこれらはみな『ダンソン』の舞台で行われたことだ。そして嬉々として行われたこれらは、少なくともダンスと同じ理由で生まれたのだ。人々はこれらの行為を、何かの意味があるからではなく、ただしたいから、することが好きだからしているのだ。さらに言えば、茶人が茶を淹れるのも、旅人が山を越えるのも、詩人が詩を書くのも同じ理由からだ。そしておそらく、人が人生を生きるのも同じことだ。『ダンソン』のなかほどでは茶人の手紙が朗読され、最高の茶を淹れるさいの次第を絢爛たる戴冠式の実況のように物語る。また最後ではあるゲーテの詩をめぐるエピソードが語られる。三十歳のゲーテは『旅人の夜の歌』と題する詩を山小屋の壁に記した。五十年後、人生の最後の誕生日に山小屋を訪れた彼は、この詩を読んで涙したという。
すべての峰を静寂が覆う
すべての梢に風は止み
森の鳥も口を噤んだ
もうすぐだ
お前も休息を得るのは
山小屋に辿り着いた旅人はただ満足して夜の休息を得るだろう。そして人生の終わりに辿り着いた詩人はやはり満足して最後の休息を得るだろう。なぜなら、彼は心ゆくまで踊ったのだから。舞台からひとり客席にお辞儀をした老婦人のように。また『ヴィクトール』の舞台に招かれた老紳士たちのように。