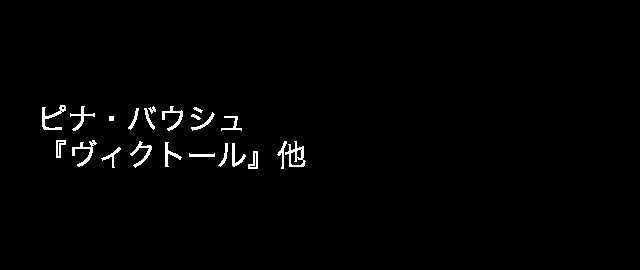極北のダンス
ピナ・バウシュとヴッパタール舞踊団が3年ぶりに来日し、さいたま芸術劇場で五月から六月にかけて4作品を上演した。舞踊や演劇についての私たちの強固な常識をたった一人で覆してしまった天才の作品をこのようにまとめて見られるのは世界でも稀な幸運である。しかもプログラムは代表作『ヴィクトール』を含めて初期作品から近作までを並べ、彼女の全体像が見えるように配慮してある。
20世紀の後半、アメリカに生まれたモダニズムというイデオロギーが芸術界を風靡した。それは芸術各ジャンルの自己批評こそ前衛の道だという考えで、作品は美術についての美術、ダンスについてのダンスであることを要求する。50年代のカニングハム、60年代のミニマル・ダンス、70年代のポストモダニズムのダンスなどはこの文脈で評価された。しかし70年代の半ばに登場し80年代に世界の舞踊界の頂点に立ったピナ・バウシュは、その流れに無縁というより、むしろそれに逆らうもののように見えた。そこでアメリカのモダニズムに対するドイツ表現主義の逆襲という図式が語られたりもした。ピナ・バウシュ自身は表現主義と呼ばれることを拒否していたにもかかわらず。
1974年のダンスオペラ『タウリスのイフィゲネイア』を見るとき、やはりドイツ表現舞踊の伝統を思わずにはいられない。その美しさや完成度の高さにおいてモダンダンスの到達点であるとしても。だが86年の『ヴィクトール』になると、もはや表現舞踊ではなく、モダンダンスですらない。ピナ・バウシュ独自のタンツテアターというほかはない。作品は多数のシーンのコラージュから成る。ダンスシーンは僅かしかない。ほとんどは演劇の断片のような、さまざまな振る舞いや台詞でできている。だが演劇の常識からはほど遠い。ふつう芝居は筋がわかるからこそ面白く、言いたいことがわかるからこそ感銘を受けるのだが、これはどちらもまるでわからない。といって視覚的に美しいだけの「イメージの劇場」ではない。観客は話もわからぬままに劇的なものを感じ、わけもわからぬまま涙を流す。ここには優れた演劇を見たときと同質の感動がある。だからこそ私たちは「演劇の領域が広がった」と思ってしまうのだ。演劇の極北なのかもしれない。10年後の『フェンスタープッツァー』(97年)も同じ方法で作られている。これはピナ・バウシュの一般的な作法なのである。最後に上演された『ダンソン』(95年)はある意味で大部分がダンスシーンである。ただ普通のダンスはほとんどない。人の動作がダンスとして成立するぎりぎりの場面をつぎつぎと送り出す。見慣れたダンス形式がほとんどないのに、私たちは確かにダンスを見ているのと同じ快感を覚える。これはダンスの極北と言ってもいい。
ピナ・バウシュはけっしてモダニズムの人ではない。しかし彼女の仕事は演劇や舞踊の成り立つ限界を探り、その領域を拡張し、その概念を変革した。これが演劇についての演劇、舞踊についての舞踊でなくてなんだろうか。