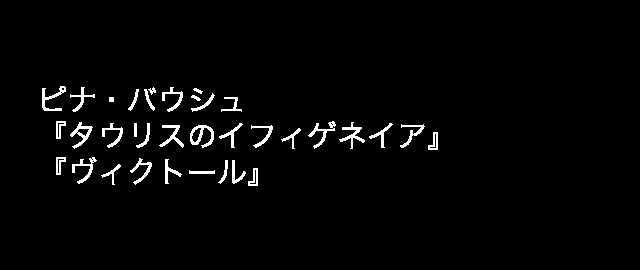怖がらないでピナをごらん
東京に住む私がひとつだけパリを羨ましいと思うのは、毎年ピナ・バウシュの公演を見られることだ。その舞踊団が三年ぶりに日本にやってきた。それも四本の作品を携えて。
ピナ・バウシュがヴッパタール・バレエの監督を引き受け、ヴッパタール・タンツテアターと改名して世に問うた最初の作品『フリッツ』はあまりに新奇であったためか一九七四年の観客や批評家に冷たく扱われたという。だが三カ月後、格調高いグルックのオペラに振付けた次作は大成功を収めた。今回の最初のプログラム『タウリスのイフィゲネイア』がそれである。ピットにはオーケストラが、左右の二、三階の客席には歌手たちが配され、高雅な歌声が教会のように降りそそぐ中、視覚的に計算され尽くした舞台の上で細部まで完成されたダンスが展開される。保守的な観客といえども、この張りつめた美しさには圧倒されただろう。たしかにこれは今の私たちが知っているピナの作風ではない。ダンサーは踊るだけだし、そのダンスはオペラの筋書きを無言で説明するものだし、動きはモダンダンス的である。けれどもこれは今なお傑作である。そして既に後のピナ・バウシュの特徴が見られる。たとえば三幕では舞台中央部の床がなく、額縁のような四辺しかダンサーたちに残されていない。激しく動く彼らが巨大な墓穴に落ちてしまわないかと、観客は不安を感じながら見守ることになる。ピナは観客にいつも落ち着かない気分でいるように仕向けるのだが、その仕掛けがわかりやすい形でここにある。
二つ目のプログラム『ヴィクトール』(一九八六年)はピナ・バウシュの代表作の一つである。左右と奥の三方を高さ数メートルの土壁で囲まれた舞台は、遺跡の発掘現場か巨大な墓穴の底のように見える。上演の間、壁の上では一人の男がシャベルで土をすくっては舞台に投げ下ろす。穴を埋め戻しているのだ。これだけで私たちは不安になる。この穴は一体何なのか。登場人物たちはみな亡霊なのか。穴が埋め戻されたとき彼らはどうなるのか。彼らが泣いたり笑ったりできるのも、穴がふさがるまでの短い間のことなのだろうか。この作品はいつものように無数の断片のコラージュから成るが、そのひとつひとつがやはり私たちを落ち着かない気分にさせる。両腕のない美女が真っ赤なドレスでこの世の勝利者のように婉然と微笑むのはなぜなのか。しかも彼女にコートを着せ掛ける男が悲しげな眼をしているのはなぜなのか。花嫁のように白い布を身にまとう女が前に進みながら上半身は身悶えるようなダンスをしているのはなぜか。しかもその裾をかかげて付き添う二人の男が煙草を吸いながらにやにやしているのはなぜか。すべてが私たちの知る紋切り型を外れているため、その意味を解釈して安心することができない。愛の神話やフェミニズムの図式を持ち出して解釈することは簡単だが、それで安心すると肝心の何かが見えなくなってしまいそうだ。私たちは不安に耐えて見続けるしかない。するとそれぞれの断片が、実はよく知っていたものであるような気がしてくる。ただ触れたくないだけなのだ。誰だってせっかくふさがった傷口のかさぶたを剥がすようなことはしたくない。うっかり剥がしてしまった観客は涙が止まらなくなるだろう。私はこれほど生きることの傷ましさを形象化してみせた作品を知らない。むろんここにあるのは傷ましさだけではない。笑いを誘うシーンもたっぷりある。爽やかな解放もある。たとえば吊り輪にぶら下がった女たちが長いドレスの裾を翻しながら楽しげに空中を往来するのを見るとき、その軽やかさと優美とに胸がいっぱいになる。見終わったとき、私たちの感情の仕組みはすっかりかきまわされて、以前とは別のものになってしまったような気がするだろう。
だがどんな説明もピナ・バウシュには追いつかない。「音楽を聞いて踊る子供は、音楽の凡庸な解説者より遥かに正しい」と小林秀雄は言ったけれども、初めてピナ・バウシュを見た私の友人の反応はどんな解説よりも正しいだろう。十数年実直にフランス文学を研究してきた彼女は『ヴィクトール』を見たあとでこう言ったのである。
「明日から私は、生きたいように生きるわ」