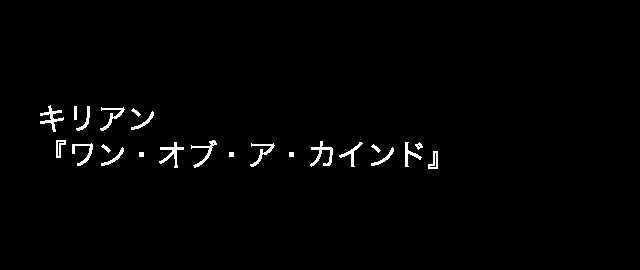舞台空間のオデッセイ
身体というこの上なく具体的なものをメディアとするダンスは、観念のこね上げた作品にはうんざりした現代人に、ある種魔術的な魅力をもっている。その得意とするのは私たちの衝動や欲望を引きずり出すことだ。その代わり形而上学はもっとも不得意とする。だが彩の国埼玉芸術劇場でイリ・キリアンの『ワン・オブ・ア・カインド』を見た時、はじめてピラミッドを目の当たりにした時に似た驚きがあった。形而上的な意志が具体的な形をとって現れていたからだ。
キリアンはかつて東京の建築を見て回ったとき、好きなものがみな北川原温の設計であるのに気がついたという。オランダ政府から憲法記念事業の一環として大作を委嘱されると、彼はその舞台美術を北川原に依頼した。作品は三幕から成りそれぞれ空間が異なる。第一幕は白色と鋭角の世界である。暗闇に稲妻型の白い道が現れ、それを辿るダンサーの彼方に氷山のようなセットが現れる。初めかすかな光の図形にしか見えなかった氷山は、照明によって相貌をさまざまに変え、やがて傲然たる姿をとる。第二幕は左手後方に菱形の、右手前に円錐のいずれも巨大なオブジェが尖端を下に向けて宙に浮いている。原始的な烈しい音楽とともにダンサーは疾走しつつ身体を躍らせる。モノリスの前で立ち騒ぐ猿人のように。やがて円錐がゆるやかに回転を始めると、たちまち安定した宇宙はゆらぎ、ダンサーたちの卑小さが強調される。第三幕では舞台いっぱいに縄のれん状のスクリーンが降りて来る。ダンサーは紐を分けてスクリーンを出入りする。このスクリーンは紗幕のように背後に光を当てれば後ろの光景を透かし見ることができる。前から光を当てれば、反射率の高い材質なのだろう、舞台全面が輝く光の洪水となる。その効果は圧倒的だった。
この作品の中心は刻々と変わる舞台空間にある。シンプルなオブジェと空間とが光によってさまざまに表情を変える。北川原のほとんど崇高といってよいデザインにミヒャエル・シモン(フォーサイス作品でも照明を担当している)は息を呑むような照明を与えた。キリアンは、いつもの音楽の解説のような振付も、これでもかとばかり凝った振りを繰り出すこともやめた。ただ北川原とシモンに存分に世界を作らせ、それを緊迫したダンサーの身体という糸で貫いた。セットに比べて小さな人体が、制約された宿命をを生きねばならぬ人間を象徴するように見え、それが舞台を劇的な空間にしている。逆に、この身体が緊張感を失うと舞台は要を失った扇のようになり、形而上的空間は安っぽい紙細工に見えてしまう(昨年パリで見たときにはそれが起こっていた)。休憩時間さえ舞台に留まりつづけるソロダンサーの役割はきわめて重い。この作品は、美術・照明・振付・ダンスなどが高度なレベルで共振してはじめて成功するというあやうい作り方をしている。だが埼玉の公演はたしかにこれが成功したし、それを目撃することができた私たちは幸運だったといえるだろう。