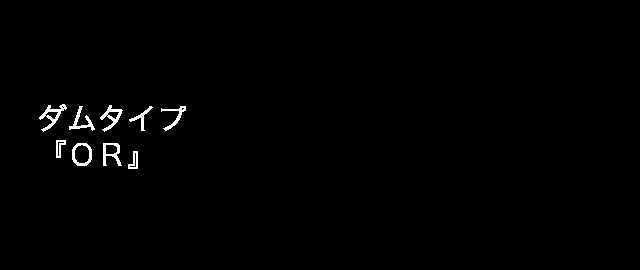身体への爆撃
会場に入るとひたすら白い空間が広がっていた。舞台は奥にふくらんだ半月形のスペースで、その曲線に沿ってシネラマのスクリーンのような壁が立ち上がっていた。床も壁も特定の光源に照明されているように見えず、全体がほのかに発光しているかのようだった。このミニマルといってもよい単純な舞台は、精密な照明技術によって床や壁という物質を感じさせず、ただ茫漠たる白い空間を作りだしていた。やがて三台のビデオ・ブロジェクターが作動し、壁の上を光の線が走り始める。このとき私は新しい感性の世界が開かれていくのを予感していた。
あらかじめ観客に対してはストロボと重低音を多用するので承知してほしいという注意がなされていた。生理的に耐えがたいことがあったとしてもそれは意図的な演出だという宣言である。はたしてストロボの閃光はそのつど私の眼を眩まし、断続する重低音は床もろとも私の肉体を震わせた。ストロボの光は視覚的情報を与えるものではない。むしろあらゆる視覚的情報を一瞬遮断し、何も見えなくしてしまう。これが繰り返されると、視覚の捉える光景は幻のように存在の不確かなものになり、むしろ自分の住み込んでいる空間そのものが光とともに振動しているかのように感じられてくる。重低音もまた聴覚的情報というよりは身体そのものへの衝撃であり、外部からやってくる音として知覚するというより、内臓の振動という私の内部での出来事として知覚される。従来のダンスはもちろんたいていの芸術が視聴覚の情報という形で観客に届けられるのに対し、ストロボと重低音はむしろ直接に身体で経験されるものである。『OR』の観客になるとは、そのような身体的経験の持続に付き合うことなのだ。このことは後半のビデオ映像にも言える。それは疾走する自動車の運転席から見た高速道路の光景を前面のスクリーンいっぱいに延々と映したものである。ゲームセンターでカーレースをやれば、あたかも自分自身が虚像の道路を疾走しているような錯覚をおこすことがある(いわゆるヴァーチャル・リアリティ)。ちょうどそのような身体感覚をもたらすことを意図しているのだろう。ひたすら道路を疾走する単調な空間感覚に身を委ねていれば、やがてそれは一種のめまいにも似た酩酊感を生むかもしれない。むろん『OR』は総合的パフォーマンスであるから、生身の身体によるダンスや寸劇もあれば、散文のテキストも投影される。しかし登場する身体たちはなぜかひどく希薄であり、テキストはそもそも英語だから日本人の観客が読むことは期待されていない。結局この作品の戦略上の特徴は、たいていの舞台が観客の明晰な意識に情報を送って何事かを理解させようとしているのに対し、これは身体へ反復される直接的刺激によって観客が時間と空間の明確な分節を失い、茫漠たる世界の中で酩酊した身体に陥るという点にあるのだろう。
劇場の中へ入るとき、人々は日常の自分自身を捨てて「観客」という抽象的な存在になる。だから実生活では自分の娘に虫がつくのを許さない親も、『ロミオとジュリエット』の純愛に感動したりする。ダムタイプの前作『S/N』が挑発的だったのは、観客がいつものように「観客という名の別人」に安住してはいられなかったからだ。明確な政治的メッセージと問いかけとがあり、観客は感動よりも共感を、称賛よりも同意を求められていた。しかもその共感と同意とは「その場かぎりの観客」としてではなく、実生活の中の自分自身として行わねばならなかった。これは観客を具体的な一人の人間へとまるごと回復しようとする戦略だったといってもよい。しかし『OR』では、「観客」という抽象的な存在に戻らせることはしないけれども、ただ「身体」という生理的存在に追い込もうとしているようだ。脳死者の心臓が動き続けるように、明晰な意識が停止したあとも刺激の受容器官だけがとめどなく疾走し、薄明のなかで夢のような映像が明滅し、意志とは関わりなく皮膚や内臓がリズミカルに踊る。たしかに身体が白い空間に溶けだしたようなこの浮遊感は心地よいと言ってもいい。問題は、この感覚が持続しないことである。というのも、人間の生理は、持続する刺激に対してしだいに感応しなくなってしまうようにできているからだ。閃光の目つぶしにも重低音の爆撃にも、人は数分で慣れてしまう。
舞台芸術の外では、身体への直接刺激によって一種の陶酔状態へ誘導するというのは珍しいことではない。かつてニューヨークで新しいディスコを設計した磯崎新は、そのコンセプトを「音と光のシャワー」という言葉で言い表した。そのディスコ『パラディアム』は八〇年代中期の最先端空間だった。ただしディスコは踊るための場所である。『OR』の観客は踊らない。これは決定的な違いである。ディスコで人々がいつまでも興奮を失わないのは自ら踊っているからだし、ゲームセンターの客がカーレースに飽きないのは自ら運転しているからだ。能動的な身体は決して退屈しない。しかし『OR』の観客は椅子に縛られて受動的に刺激を受け取るだけである(ロック・コンサートのように総立ちしてタテノリでもすればともかく)。酔いは醒めてしまう。すると目の前にあるのは平板なサウンドと希薄な身体と単調な映像だけということになる。冒頭部の身体経験が素晴らしいだけに、膨らんだ期待との落差も大きい。もしこの公演が二十分で幕を下ろしていたら、「未完の傑作」として長く記憶に残ったかもしれないのだが。