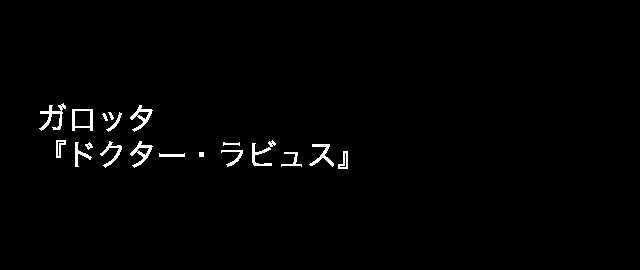深夜の政治学
薄暗い舞台をふらふらとひとつの人影が横切るところから、この作品は始まる。寝起きのこうもりのような足取りのその姿こそガロッタ、いやドクター・ラビュスである。どうやら彼は昼間に眠り夜になると起き出して、獲物、いや患者を探して歩くらしい。これから彼は四組の男女の愛の形態を観客に見せようというのだが、まじめな研究成果なのか、病的な妄想なのか、誰にもわかったものではない。
まず登場するのはアンナ・カリーナのような女とジャン=ポール・ベルモンドのような男である。いかにも「現代風の女」と「現代風の男」であり、彼ら自身も「いい女」と 「いい男」を演じようとしているのかもしれないが、ゴダールの映画と同様、物語は成り立たず、辻褄の合わぬ愛の形の断片が積み重ねられてゆく。
次に出てくるカップルは、フェリーニの名作『道』のジュリエッタ・マシーナとアンソニー・クインを彷彿とさせる。無垢でけなげな薄幸の少女と、野蛮で自己本位で腕力だけが自慢の男である。少女は無私の愛しか知らず、男は他人を支配する愛しか知らない。コミュニケーションの手段は暴力だけだ。はたして舞台では残酷でいたましい関係が演じられる。ところがこの二人の関係はしだいに奇妙な様相を帯びてくる。関係を続けようと切望し哀願しているのはむしろ男の方であり、されるがままの女の方が実は男を支配しているように見えてくるのだ。
三番目は、五十年代のアメリカの青春映画に出てくる元気いっぱいの高校生である。まだベトナム戦争を迎えていないあの時代のアメリカは、本当に明るかった。最大の関心は卒業パーティーで誰と踊るかであり、当面の欲望は恋人と抱き合うことだ。何と健康なことだろう。はつらつと登場した二人は、まずひたすら舞台を走る。駅伝のように、一人が倒れるまで走るともうひとりが交替し、えんえんと走り続ける。そして十分に汗とエネルギーとを発散したあと、二人はさわやかにじゃれあい、さわやかに交歓する。異常なまでに健康な彼らにとって、愛と性とスポーツに何の区別もないのだ。
最後に中国風の衣装で現れたのは、当夜もっとも印象的なカップルである。黒い髪と長い脚を強調するように首からくるぶしまでを真っ赤なパンツスーツでくるんだ女はスパイのように妖艶なのだが、その相手はどうみても幼児退行した中年男なのだ。いやこれは中年のダンサーが少年役を演じているのだろう。とすれば、彼は年上の女と政略結婚した幼い皇帝、すなわち『ラストエンペラー』にちがいない。昆虫採集にしか興味のない少年が姉に遊びをねだるように、彼は彼女にまとわりつく。彼女は彼の気を引き、しりぞけ、愛撫する。要するに手玉にとって、性の手ほどきをする。必要とあらば、彼の尻だってなめてやる。あらゆる倒錯が彼にとっては無邪気な遊び、彼女にとっては老獪な調教として行われる。
ここに展開された愛の形の種々相は、あまり見慣れたものではない。しかし胸に手を当てれば多分誰もが知っているものだ。ただし昼ではなく夜の時間に。居間ではなく寝室で。つまりドクター・ラビュスが私たちに見せたのは、ロマンチックな物語としての恋愛の四つの形ではなく、一種の格闘としての性愛の四つの形なのだ。ベッドの上では、昼間の安定した人間関係が壊れ、もうひとつの人間関係が現れる。権力関係も、愛情表現も、すべてが昼間とは違った形になる。人々はしばしば「性」を軽視するあまり、ベッドの上では知性を置き忘れた肉体が獣のように単純な行為をするだけだと思っているが、実はそこには十分にやっかいなもう一つの人間関係があり、別の政治学によって動いているのだ。 ベッドの上で昼間の政治学は役に立たない。支配者が嘆願し、皇帝が玩具になり、あらゆる倒錯が正当になる。それは朝の光と共に消えてしまうけれども、夢ではない。人々が夢だと思い込みたがっている現実である。精神分析が意識の下に押しこめられた真実を明るみに出すように、ガロッタは人々が昼間忘れている深夜の人間関係を舞台照明の下にさらすのだ。こういう作業は精神科医か芸術家の仕事である。
とはいえこのような人間関係を演劇で写実的に表現するのはむつかしいだろう。ダンスだからこそできるのだともいえる。最後に幕を引くようにもう一度舞台を横切るドクター・ラビュスはこう言っているようだ。「昼間の政治学は演劇にまかせておけばよい、夜の政治学こそダンスの領分なのだ」と。ドクター・ラビュスを演じたのはガロッタ自身である。