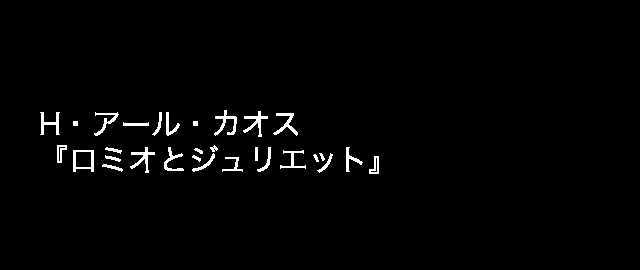劇的な電影少女
白河直子の独舞『ロミオとジュリエット』は、劇的な空間、劇的な構成、劇的なダンスによって印象的な公演となった。
彩の国さいたま芸術劇場は、ネーミングの野暮ったさとはうらはらに優れた劇場だが、とりわけ小ホールは空間の密度の高さにおいて東京圏では際立っている。演出の大島早紀子はこの空間を縦横に利用して、劇的な空間を提出した。たとえばすり鉢状の観客席からは、ステージの床に落ちる照明の形がよく見える。そこで光は人物を照らすためよりも、舞台平面を分割するために用いられる。暗い床の一部が矩形に輝けば、そこに島のような空間が立ち上がる。矩形の光面がいくつもできれば、その数だけの島ができる。その光の島はそれぞれが、異なる空間となり、異なるパソコンのウィンドウとなり、そして異なる女にもなるだろう。鉄製の階段はバルコニーになり、巨大な背後の扉は異界に通じ、可動の床はジュリエットを沈め、高い天井から吊られたワイヤはロミオを風の中で泳がせる。さらに床と壁に並べられたコンピュータ・ディスプレイが、視線の行方を複雑にする。これだけでも観客を飽きさせない。
大島はこれまでもよく知られた物語、「人魚姫」や「白鳥の湖」などから抽出した構造を現代の状況に置き直してみることで作品を構想してきた。それは現代の少年少女の内面を表現することと現代の風俗を表層に取り込むことの二面をもっていた。今回もその方法は変わらないが、重みはやや風俗に傾いたようである。今回の趣向は、お伽話のようなシェイクスピアの恋物語をTVゲームの世界に重ね合わせたことである。考えてみれば、お伽話あるいはロマンチックな物語が恥ずかしげもなく語られるのは、今日ではゲームとアニメの世界くらいかもしれない。ロミオはゲームの世界を現実以上に愛する少年となりジュリエットは彼に選ばれた理想のキャラクターとなる。仮想現実の少女はセーラームーンの姿をとり、ラムちゃんの姿をとって彼の前を疾走する。ここまでならばありふれたキワモノにすぎない。大島の着眼は、失敗して死んだ主人公がリセットキーを押せば何度でも生き返り、人生をやり直すことができるという能天気な電子ゲームの制度と、いったん死んだと見えたジュリエットが生き返り、新しい人生を始めるはずだったという原作との間の類似にある。原作の悲劇は、この計画が情報伝達の手違いで狂うことから生ずる。同様にコンピュータ・ゲームでは、しばしば予測できない情報計算の狂いによって、できるはずのやり直しがきかなくなる。かくて電子世界のロミオとジュリエットは、コンピュータ・ウィルスによって再生不能となるのである。大島はこの物語を、家制度による悲劇としてではなく、情報処理の悲劇として捉え直したのだ。この解釈は新しい。
ロミオとジュリエットの二役を演じた白河直子のダンスも見事なものだった。たった一人で一時間余を持ち堪えることができるだろうかという心配は杞憂だった。鏡とディスプレーに映る我が身にうっとりし、ドラッグとゲームにはまる蕩児ロミオ。あるときは遊び命のコギャル、あるときは見るも楽しいアニメ・キャラ、またあるときは恋する処女と七変化する電影少女ジュリエット。これらを衣装やポーズなどでは演じ分けつつも、ダンスの動きそのものは強靱な白河風で一貫していた。動きの質に男女の別くらいはつけてもいいのではという意見もあろうが、それをやっては白河らしくなくなってしまうのだろう。これは演劇ではなく舞踊公演なのだし、誰も白河になよなよしたダンスを期待してはいない(いわゆる「女らしさ」が必要なら大島は他のやり方をとっただろう)。むしろ白河の硬質な動きと劇場のハードな空間とが一つになることで、このダンスは劇的となったのである。