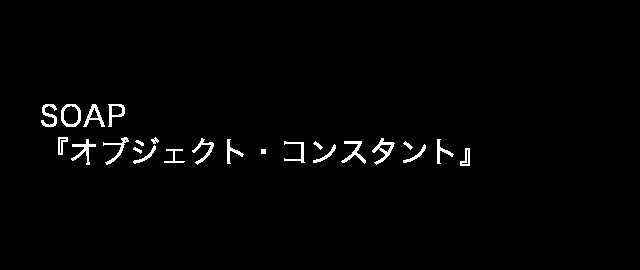ポスト・メロドラマ・ダンス
劇場に着くとロビーは混雑していた。開演時間の直前、ようやく閉ざされていた扉が開き、観客は薄暗い空間に入ることができる。見ると舞台には煙が立ちこめ、光の筋の他は一切が茫漠としている。舞台前端の右隅には底から光を発するガラスの水槽があり、誰かが髪を浸している。朝霧の立ちこめる神社で信者がみぞぎをしているような静謐な雰囲気である。そこへ軽薄そうな男が現れ、立見の客に向かって「全日本立見競争かい」といったつまらぬ冗談をマイクで喋りだす。押し付けがましいが調子のいいお喋りに続けて、彼はノートを開いて朗読を始める。意外にもそれは、昔を振り返る抒情的な詩である。「東からは、とうもろこし畑がいっそう緑に見えた。僕はこの緑の畑の真ん中に青い家を建てたいと、ずっと夢見ていた・・・」音楽までが抒情的になる。突然、心臓も止まるほど凶暴な大音響がする。まだ煙る暗い舞台に眼を凝らせば、逃げまどう男めがけて次々に速球が投げられ、彼のよけたボールが背後の薄い金属板を強打しているのだ。これはいじめなのか処刑なのか。空間は悪意に満ちる。逃げる男は舞台に円を描いて走り出し、そこへ女が加わって走り始め、二人はいきなり絡み合うとデュエットのダンスになり、いつのまにかダンサーが増え・・・。
さまざまなシーンをコラージュした舞踊作品は、今日珍しくない。しかしSOAPのようにその展開が息もつかせぬ疾走感を与えるものは少ない。その特徴は、シーンとシーンとが合理的につながらないことにある。一つのシーンは、常に攻撃的に切断され、全く別の世界に乗っ取られるのだ。たとえば、右の冒頭の数分で観客が経験するものは何か。ざわめくロビーの日常から、薄暗い通路を抜けると、いきなり半透明な美しい空間に出会う。殆ど宗教的な雰囲気は、ありきたりの司会者の饒舌に切断され、低俗な笑いにくつろぐ。だが不意に彼はノスタルジーの世界に入り、観客も美しい田舎の空と野とを思い浮かべ、甘い気分になる。突然の耳障りな衝撃音は、差し迫る危険の前兆のように生理的不安を生み、犠牲者を襲う悪意は恐怖を呼び起こす。こうして観客は一つの波に乗せられては、たちまちそれを断ち切られて別の波に攫われるということを繰り返すのである。それも、 まったく雰囲気もテンポも違う波に。観客の前に展開される世界は実に多様である。ユーモアあふれるマラカスダンスがあり、はらはらするストリップがある。椅子の下から重低音のビートが響けばディスコにいるようだし、奇妙に対話がすれ違えば不条理劇を見ている気分になる。そしてむろん、ダンスがある。ほとんど何でもありのこの作品で、ないものはおそらく一つだけだ。それは今世紀前半の(そして現在の日本の)モダンダンスに多い感傷的物語、すなわちメロドラマである。
次々と鎖のように繋がれてゆく断片は、互いに差異を際立たせるばかりで、何の統一もないのだろうか。少なくとも、表面的にはない。しかし、実はルイ・ホルタは明確な主題をめぐって断片を作っている。それは見ることの不確実性ということである。「オブジェクト・コンスタント」とは心理学用語であり、知覚対象の恒常性を意味する。見たはずのものが現実にはないなら、人の生きる世界はあやふやな夢にすぎない。同じものを見たはずの二人の記憶が違っていれば、コミュニケーションは成り立たない。見ているつもりのものと実際に見ているものが違うとき、人は自分が何を見たのかを自信をもって言えない。冒頭の煙幕は、知覚の不確実性を観客に強制する。先の詩は第二幕で次のように言い直される。「東からは、とうもろこし畑は緑がかって見えた。しかし実際は陽にさらされて黄色っぽかった。緑の畑の真ん中に青い家を建てたいという僕の夢は実現しなかった」。対話が不条理劇風になるのは、二人の知覚の記憶が違うからである。また上半身を脱いだ女性ダンサーが一心不乱に激しいダンスを踊っているとき、横のマイクを持った男が観客に問いかける。「あんたたち何を見てるの?ダンス、それともダンサー?」そして彼女たちのダンスが終わると、もう一度駄目をおす。「ダンスを見てた・・よね?」観客は自問する。「ダンスを見てた・・かな?」
緑と見えた光景が次の瞬間黄色になり、横から作者が「どっちも錯覚だよ」と解説を付け足すような、自己否定し続ける舞台。これがなぜ心地よいのだろう。多分これが現代を生きる私たちの生活感覚を的確に再現しているからだ。もはや世界を統一的に説明する 「大きな物語」はなく、混沌とした断片の海を浮遊するしかない。しかもその時々に見る現実の断片は、ほんとうに現実の姿なのかどうかもさだかではない。インターネットの厖大な情報の海を、真偽もわからぬまま少しずつ面白そうな話題を拾いながら渡ってゆく、ネットサーフィンこそが新しい世代の生活だとすれば、メロドラマに感動を求めた旧世代はこのような時代に違和感を持つかもしれない。しかしSOAPは、まぎれもなくポスト・メロドラマ世代のためのダンス・カンパニーなのである。