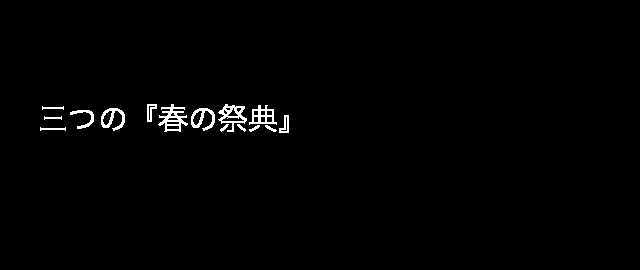「三つの『春の祭典』」は、公演前から成功が約束されているようなものだった。企画がいい。理由は四つある。第一に三月末という季節。春の桜が日本人にとって最大の自然の祝祭であるとすれば、その前夜祭に『春の祭典』ほどふさわしいものはない。なにしろこれは、偉大なる春を迎えるための儀式を舞踊化したものなのだから。第二に『春の祭 典』という音楽。ストラビンスキーのこの曲ほど、多くの振付家を誘惑した音楽はない。初演のニジンスキー以来いったい何人がこれに挑戦したことか。そして玉砕したことか。この曲は恐るべきことに、振付家の能力の限界を引き出してしまう。凡庸な振付家の場合、その無能さが露骨に現れてしまうのだ。そのかわり才能ある作家からは、時に本人さえ知らなかった力を引き出し、眼のさめるような新境地を開かせることがある。ニジンスキーの振付の革新性は当時のヨーロッパでは理解されなかったが、ベジャールの画期的な振付はモダン・バレエ史を転回させたし、ピナ・バウシュの振付は天才の出現を誰にも確信させるものだった。だからこそ『春の祭典』を見にゆくときはいつも心躍るのだ(たいていは落胆して帰ることになるのだけれど)。第三に競作という趣向。観客は個々の作品をダンスそのものとして楽しむことができるだけでなく、三人の作家が同じ課題にいかに対処したかを比較できる(その課題が『春の祭典』だとは何という試練!)。しかもこの比較はしぜん作品の出来の、従って作家の能力の比較になるから、作家たちは手を抜くことができない(何というプレッシャー!)。こういう趣向は、やる側から言えば、高円宮殿下の至言の如く「悪魔も落涙する」企らみである。しかし見る側から言えば、滅多に見られないデス・マッチである。所詮劇場の観客とは、その昔ローマのコロシアムで剣闘士の殺し合いを楽しんだ市民たちの末裔なのだ。そして第四に選ばれた舞踊家の顔触れ。現代日本の舞踊界ではなぜか若い女性の元気がいい。旧世代のモダンダンサーたちが二十世紀前半の米独のモダンダンスを、まるで伝統舞踊のように受け継ぐことに満足しているのに対し、二十代から三十代前半の女性舞踊家たちが次々と個性的なダンスを試み、(技術的には未熟なことがあるにせよ)世界の舞踊界の最前線と同じ土俵で語ることができるような作品を披露している。この現象に注目した榎本了壱氏は、これをまとめて「変態少女舞 踊」と名付けた。そして「H・アール・カオス」と「レニ・バッソ」とは、この「変態少女舞踊」の代表選手なのである。一世代上の江原朋子を変態少女グループに入れるのはおかしいかもしれないが、その前衛的経歴をみれば、彼女こそ元祖変態少女であると言ってもよい。とすれば、この公演は「変態少女舞踊フェスティバル」という一面をも持っているのである。これだけの条件が揃えば天下の舞踊ファンの注目を浴びるのは当然である。今回の企画の唯一の欠点は、公演が一日しかなかったということであろう。切符を買えずに涙を呑んだファンに成り代わり、来春は少なくとも二日は公演するようにとお願いしておこう
「レニ・バッソ」の舞台は、ごちゃごちゃと物を置いた空間に一人の少女が現れ、ラジカセのスイッチを押すところから始まる。流れて来たのは英語版の『スキヤキ』である。堂々たるストラビンスキーを期待していた観客は肩透かしを喰う。振付の北村明子は『春の祭典』という巨人と正面から格闘するのではなく、いわば巨人をポラロイド・カメラで撮ってその画像を画鋲で部屋のあちこちに張り付けるという戦略をとったのである。その部屋には他にもいろいろな家具があり、照明器具があり、音があるだろう。そこで少女たちは気儘に動き回るだろう。そこにあったのは、緊密で重厚なストラビンスキーとは対極の世界であった。
江原朋子もまた重々しい音楽に肩透かしを喰わせる。幼児のようないでたちで登場するのだ。どうやら彼女は猛獣のような音楽と格闘するよりも、熊と遊ぶ金太郎になろうとしたらしい。『春の祭典』は雛祭となり、音楽は白酒のように観客を酔わせ、一人遊びをする子供のように、江原は無邪気にソロダンスを踊っていた。
この日、「H・アール・カオス」の大島早紀子は果敢にもただ一人ストラビンスキーの『春の祭典』と正面から対決した。そして見事に成功した。白河直子が白い下着姿で犠牲となる女を演じ、宇佐美道子ら四人の女性ダンサーが黒いスーツで男たちを演じる。ワイヤで身体を支えて踊る技法は洗練されて、あるときは優雅であり、あるときは危険なほどに過激である。白い浴槽から現れ同じ浴槽で死ぬ女は、白河の技量で観客を魅了し大島の演出で観客の息を呑ませる。また一つ『春の祭典』の名作が誕生したことに、この夜私は祝杯をあげたのだった。
Flying Cabinet