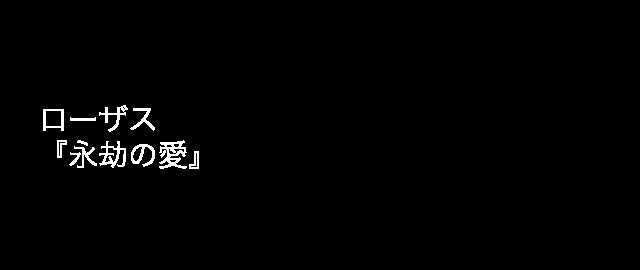二月二三日から三月四日まで、パリの市立劇場でローザスの最新作「Amor constante mas alla de la muerte 」が上演された。このスペイン語の題名は、悪漢小説で名を残した一七世紀スペインの作家フランシスコ・ケベードの詩からきており、その意味は「死の後までも変わらぬ愛」だという。題名だけをみるとひどくロマンチックだが、ケベードは奇想と諧謔で知られたバロック詩人であり、額面通りにはとらないほうがよい。
ブログラムを見ると、振付はいうまでもなくケースマイケル。音楽はローザスの出世作『ローザス・ダンス・ローザス』のティエリー・ド・メイ。そして構想・演出は二人の連名となっている。舞台にはローザスの一五名のダンサーとアンサンブル・イクトゥスの一一人の奏者が登場するが、ダンスと音楽の比重は対等である。両者は互いに相手に合わせるよりも、相手を出し抜こうとしているように見える。両者に共通するスピードの早い展開と緻密な緊張感とは、互いに相手を意識することによって生み出されたものだろう。ここにはダンスと音楽の決闘がある。そして打楽器を中心とするド・メイの作曲は素晴らしく、しばしばダンスの方が音楽の背景に見えるほどである。
舞台の床は二重になっている。元の舞台の上に星型を作り損ねたような、鋭角の出入りをもつ上置き舞台が載せられているのだ。高さはひと足でなんとか登れるほど。つまりダンサーは上下二つの舞台を自由に行き来することはできるが、滑らかな動きで繋ぐことはできず(助走をつけて飛び上がるといった場合はともかく)、どうしても境界で動きの断絶を伴うことになる。ということは、二つの舞台が別の空間であり、別の世界であることを観客に意識させるということである。ケースマイケルはときにこの差異を強調し、利用する。たとえば、上の舞台で踊っていたダンサーが下に降りると素に帰る。あるいは素に帰った下のダンサーが上で踊っているダンサーを見物するといったように。この構造は、上の舞台でのダンスが、意図的な作り物であることを強調する効果をもつ。観客は、作られたダンスとそれを冷たく見据えるメタレベルの視線とを同時に見ることになるからだ。こうしてケースマイケルは、舞台に性質の異なる二つの身体・二つの場所を置くのだが、これを単純に対置するだけなら既に多くの演出家が(例えばメタフィクションの演劇で)やってきたことだ。彼女はこの両者を対置させた上で、その差異を不意に埋めようとする。たとえば、上から落ちかかったダンサーを下のダンサーが支えるといったように。ただしこのときも、上の女性ダンサーはあくまでもダンスの型として倒れかかるのだが、下の男性はまるで日常の作法として女性を支えているようにも、ダンスの型に従っているようにも見える。レベルの境界は曖昧になり、その曖昧さから何かが生まれてくるのをケースマイケルは期待しているのかもしれない。というのも、これが本作品の一貫した狙いのようであるからだ。
まず幕開きがどんなふうに始まるかを紹介しよう。といっても舞台に幕はない。客席のざわめくなか、突然左手奥から暗い舞台に一条の光が射し、その細い光の中に一人の女が現れる。彼女は左手奥で身体の片側だけを照らされながら、ひとり鋭いダンスを始める。その技術は見事であり、千人の観客の目を十分に引きつける。同時に右手からも一人の男が現れるのだが、こちらは照明がないため、陰の中を動いているだけで、よく見えない。左の女に気をとられているかなりの観客は、男の存在にさえ気がつかないかもしれない。やがて客席の照明が落ち、音楽が始まる。薄暗い中、十数人の男女が上の舞台に現れ、毛布らしきものを枕に仰臥する。彼らは足だけを使って頭の向く方向へ滑り、まもなく上舞台の右端にマグロのように並ぶ。そして口々に何かを喋りはじめる。彼らの顔の上には一本のライトが低く吊られており、一人のダンサーがこれを引っ張って手を離すと、それは振子のように揺れて、床に並んだ顔を次々と照らしては行き過ぎてゆく。このライトにはマイクが仕込まれており、照らし出された顔の声だけが一瞬のあいだ拡声器から投げ出される。聞けばそれは愛の詩であり、ちょうど歌舞伎の割台詞のように、一語ずつをさまざまな声で朗読しているような具合いになる。通過する光。点滅する顔。断片化された声と詩。鋭い動きと寝そべった身体。そして光と闇の中の見えるダンスと見えないダンス。冒頭の数分でケースマイケルは方法論をさらけ出す。私たちは、利用可能な舞台言語の全てが、断片化され、不完全に組み直されてゆくことになるだろうと予感する。『ローザス・ダンス・ローザス』では禁欲的なまでに要素を制限していたのに、ここではあらゆるものが利用されるだろう。だが問題は、どのような原理でそれを組み合わせてゆくのかである。
『ローザス・ダンス・ローザス』では、同じ種類に属する動きを、ずらしながら組み合わせ、対比するという対位法的構成をとった。今回もその基本は変わらない。対立項を同時並行させ、それらを組み合わせるのである。たとえば、歩く者と走る者と踊る者と三つのグループが同時に舞台にのぼり、それぞれのルールに従って動く。これは対立項の並行である。しかしその各項は交換可能であり、突然歩く者が踊る者のグループに加わったり、踊る者が突然走り出して踊る者のグループを抜けたりすることで、その構成は一定のルールに従っているという印象を与えながらいくらでも複雑になることができる。だがこれだけなら、動きの組み合わせを追求する現代の振付家たちがみんなやっていることだ。ケースマイケルの個性は、ここに文化的記号や意味を持ち込んだことである。たとえば同じ上下を着た男たちが登場しながら、そのなかの一人だけが上着がなく、また一人だけがズボンがないとき、なぜかズボンのない男は間が抜けて見える。しかし彼らが一つのグループとして一定のルールで群舞をすれば、彼らの衣装もまた一定の組み合わせのルールに従っているだけだと思わざるをえない。とはいえ、それが順列組み合わせという抽象的ルールに過ぎないとわかっていても、やっぱりズボンのない男は間抜けに見えざるをえない。意味がないはずのところに意味が生じるのを避けることができない。この意味は何かを表現しようとするものでないのはもちろん、パロディなどのように何かを否定するものでもない。いわば目的もなく偶然に虚空に発生した意味である。次のシーンではたちまち消えて忘れられてしまう意味である。同様のことが女性ダンサーでも行われる。お世辞にもスタイルがよいとは言えない小太り短躯の女がボディコンのスーツを着て現れ、同時にファッション雑誌から抜け出したような美女がスリップ姿で現れるとき、私たちはそこに「二枚目のヒロインと三枚目の脇役」というおきまりの役柄を想起せざるをえない。しかし彼女たちが全く同じ抽象的な振付を踊るとき、彼女たちの身体はカニングハムのダンサーのように抽象的な動きのための媒体であって、なんの役柄も与えられてはいないと理解する。頭では理解するのだが、この対比からはどうしてもある種の意味が発生せざるをえない。実際小太りの女性のテクニックは素晴らしく、観客の目を引くという意味では事実上の主役であり、ソロでは火の玉小僧となって踊りまくるのだが、その動きは抽象的であって何の表現も目指していないにもかかわらず、ときに「レディらしからぬ姿勢」になってしまうとき、観客は笑いをこらえることができないのだ。このような、虚実皮膜に発生する意味をこそ、ケースマイケルは大切にしようとしているかのようである。
なかでも印象的だったのは、この女ともう一人の男とがE・E・カミングスの詩「may i feel said he」を語りながら踊ったデュエットである。これは男が女を口説いて性行為に及ぶ次第を対話形式で綴ったもので、四畳半襖の下張り的内容と簡潔で見事に韻を踏んだ詩的形式との対比が粋であり、昔ロイヤル・シェイクスピア劇団の朗読劇でも台本に採用されたことがある。たとえば冒頭はこうである。「may i feel said he / i'll squeal said she (触れてもいいかいと彼は言った/叫ぶわよと彼女は言った)」。この対話詩を二人で交互に暗唱しつつ、複雑な動きを踊るのである。ただし二人は詩の内容とはうらはらに、決して絡み合うことはなく、むしろ遠く離れて自分の世界に浸っているように見える。その動きは激しいけれども抽象的であって、いさかも性的ではない。にもかかわらず、詩行が進み、「cccome?said he / ummm said she (いいいくかと彼は言った/うううんと彼女は言った)」というあたりでは、彼らの激しい動きが性交の暗喩に見えてしまうのだ。現代の舞踊を説明するのに、表現的なものと抽象的な動きによるものとに分けるやり方が近頃行われているが、ここでは抽象的なはずの動きが意味をもってしまうという現象が起きている。むろんケースマイケルの場合、それは何かを表現するためではないから、たちまち次の動きではぐらかされてしまう。そして複雑な動きと記号の対位法に見とれている観客は、その隙間からチラリと覗く禁断の意味に興奮し、これはすごいと思った瞬間、彼女の術中に陥るのである。カミングスの詩は前述のクライマックスの後、次のように終わる。
you're divine!said he / you are Mine said she (君はすごい!と彼は言った/あなたは私のものよと彼女は言った)
Flying Cabinet