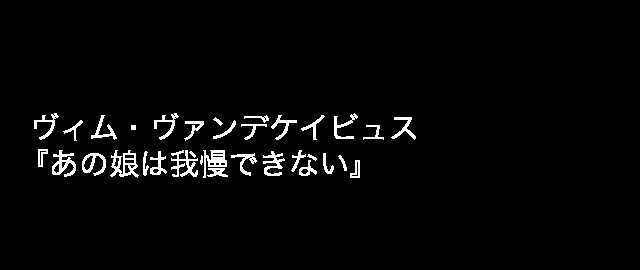心身不適合シンドローム
前の座席にいた私は気がつかなかったが、後方で見ていた人によると、途中で席を立つ客が少なくなかったという。確かに小細工だらけの作品だが、私は前回の東京公演よりはましだと思ったし、見るべきものがないわけではない。
ヴィム・ヴァンデケイビュスに振付師としての才能があることは疑いない。ダンサーたちは猛烈なスピードで走り、跳び、回り、倒れては起きる。それだけなら珍しくもないが、しばしば彼らは互いにぶつかりそうになり、蹴飛ばしそうになる。それを間一髪ですりぬけるのは、京劇の殺陣ほどではないにしても、結構スリリングである。この組み立ての巧みさは評価してもよい。問題は、これだけでは一時間半の作品はもたないということである。観客も飽きるし、だいいちダンサーの身体がもたない。古典的な解決は物語を導入し、お話に沿ってさまざまなシーンを作ることだが、現代作家としてはいくらなんでもこれはできない。そこで周囲を見回せば、ピナ・バウシュやフォーサイスといった恰好の手本がある。即ち、様々な種類の断片を、脈絡もなく組み合わせること。そこでこの舞台でも、映画やコントや朗読が行われ、ノイズを拾って拡大したり、意味不明の言葉をえんえんと喋り続ける男が歩き回ったりするということになる。だが、統一的に作品を構成することは多少の修業をつめば誰にもできるが、意図的に不統一な構成を取る場合には、作家の内部に「自分は何をしているのか」についての明晰な理解が必要になる。たとえば新しい構成の原理的思索、あるいは身体についての独自の眼差し。それは振付師としての才能とは別のことである。
この作品は映画から始まる。盲人の姿が次々に映し出され、一転して同居する男女の朝の日常が映される。ハリウッド風の劇的な映像構成とは逆に日常生活を延々と映し出す手法はウォーホルによって極限まで実験されたが、少し手を加えてゴダールからジャームッシュまでこのアンチ・ドラマティックな様式は「芸術派」の手法として受け継がれ、今なおスノッブな映画少年の好むところである。ヴァンデケイビュスは男女が目覚めてから歯を磨き、髭を剃り、服を着て出掛けるまでを(順序を前後させながら)描写する。これ自体はありふれた手法だが、普通の映画と違うのは、いずれこの映画がダンスの実演に取って代わられることを観客が知っているということである。興味は、その転換がどのように行われるかに向けられる。やがて画面の中の男はなぜかベッドに帰り、窓の光が明るくて眠れないといったそぶりで、黒い紙で窓を塞ぎはじめる。私は「おいおい」と言いかけた。これは見え透いているではないか。全ての窓を塞ぎ了れば画面は暗くなり、都合よく映画を終わることができるというわけだ。しかしそれには何分かかかる。わかりきった段取りをじっと待つのは退屈なことだ。果たして暗くなった銀幕が片づけられ、おもむろにダンサーが登場したとき、私はこの作家がかなり気楽な人であることを理解した。
ヴァンデケイビュスの素材の集め方は二元論であるらしい。冒頭の映画は盲人を映したあと、髭剃りのために鏡を覗く、パチンコで狙う、窓の光の眩しさといった、視覚に関わる素材を拾う。あるいは、夢では切れた林檎が現実では切れないといった文章を朗読する。かつて黒人が「白さ」について語った言葉を舞台で白人が喋る。だがこの対立図式はいかにも観念的だ。
この作品の最大の話題は二人の盲人の出演である。たしかに盲人が晴眼者に立ち混じって踊り、見分けがつかないというのは、驚くべき事である。しかし盲人がハンデキャップを乗り越えて、晴眼者と同じことができたというだけなら、メディア向きの美談にはなるかもしれないが、作品の価値とは無関係である。視覚の有無に関わらず優れたダンスであるか(この場合盲人であるかどうかを言う必要はない)、晴眼者には難しいことができるのでなければ、彼らを起用した意味はないだろう。たとえば普通のダンサーは「見せる」ために踊る。しかし盲人が踊るとき意識するのは、自分の姿が外からどう見えるかではなく、周囲の空間と身体の感覚であるだろう。彼らの空間感覚は晴眼者と異なるだろうし、身体内部への感覚はより鋭敏なのではないか。だがヴァンデケイビュスは彼らに他のダンサーの真似をさせるだけだ。晴眼者と区別がつかないことをウリにするのは、志が低すぎるのではないか。
原題は「彼女の身体は心と合わない」であり、身体と心のずれがテーマなのだそうだ。作家が何も考えていないとは言わないが、少なくとも考えていることは見えなかった。多分彼の身体表現が心中の意欲と合わなかったのだろう。この不適合は観客にも伝染する。身体を座席に置きながら、心はどこかへ、たとえば夕食へ行ってしまう。ずれに「我慢できない」者は、席を立って一致に向かうことになるわけだ。