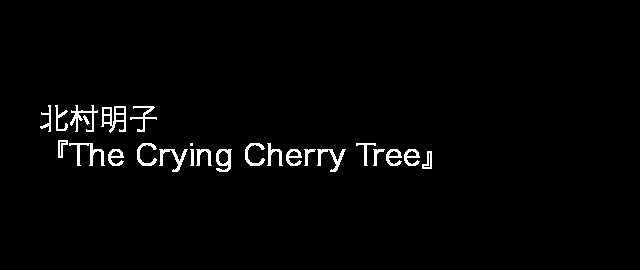痙攣の制御
入口を抜けると、薄暗い倉庫のような空間に五枚のスクリーンが吊られ、満開の桜を映している。座席の代わりに緋毛氈を敷いた雛壇が所々に置かれ、観客は思い思いに座る。花見客の見立てらしい。やがて闇の中から、酔客なのか精霊なのか、ぼろきれのような衣装をまとった正体不明の女たちが現れ、客の前や後ろで動きはじめる。そしてそれだけのことである。
北村明子にジャズダンスを使ったエンタテイメントを作らせれば、一時間ほど観客の鼻づらを引き回して拍手喝采を受けるくらいわけもない。しかし最近の北村は、意志的に自分の得意技を封じて、独自の動きを創りだすことに挑戦している。そして早くも「北村明子様式」とでもいうべきものが、おぼろげながら姿を見せはじめている。二十三歳という年齢を考えれば、これは驚くべきことかもしれない。
ある動きがダンスとして見えるためには、その動きの過程がある様式の下にコントロールされていると見えなければならない。実際、リズムを刻むジャズダンスであれ、所作の優美なバレエであれ、微速を保つ舞踏であれ、プロの舞踊家なら動きの過程は意識的にコントロールされていると見える。逆に日常の動きはコントロールされているように見えない。ふつう私たちは、歩こうとか水を飲もうと思えば、ただちにそれを「行為」として行う。「目的」は意識するが「動き」の過程の細部など意識しない。意識されないものはコントロールできない。「行為」は無造作に遂行されるのである。しかし歩行さえ「動き」そのものを意識してコントロールし、しかるべき形式を与えれば、それはダンスと見えるだろう。つまり、ある動きがダンスになるかならないかは、それがコントロールされているか無造作であるかの違いなのである。ここから、ダンスの領域を拡張しようとする舞踊家たちは、日常の無造作な行為を取り入れようとする。それは六〇年代から始まり、今なお続いている。だが人間にはもう一種類の動きがある。それは行為の意志にもよらず、意識的コントロールからも外れた動き、たとえば痙攣やくしゃみである。あるいは泣き叫ぶ子供の地団駄や神がかりした人間の四肢の暴発である。どうやら北村が飼い馴らそうとしているのは、これらの動きである。
ダンサーたちの動きの特徴は、一見コントロールがないほどの暴発性にある。まるで何かが取り馮いて、彼女たちの身体をオモチャにしているようだ。彼女たちは全力で肢体を振り動かす。一挙手一投足が高校野球のように全力疾走全力投球だ。動きはコントロールされるよりも、ただ激しくあろうとしている。筋肉は適度に収縮し適度に膨張することを許されない。瞬時に精いっぱい収縮し膨張しなければならない。これが全ての動きを一種の「痙攣」に見せるのである。問題はこういう動きをどうやってダンスに仕立てるかだ (パンフレットにパフォーマーと書いてダンサーと書いてないのは、もうダンスではないというつもりかもしれないが)。たとえばカウントに合わせて痙攣するなどという芸当はできない。できたらそれはコントロールされた動きであって、痙攣ではない。当然ながら、リズムにも音楽にも乗らない。複数の人間がタイミングを合わせて痙攣することもありえない。しかし北村はこれをやろうとする。たとえば、ばらばらに動いていたダンサーたちが、突然同じ所作を同じタイミングでやってみせることによって。それは彼女たちが厳密な振付に従って動きをコントロールしていることを証明するだろう。
痙攣する身体とコントロールされた身体という、およそ矛盾するものを調停しようという試みは、当然ながらそう簡単に解決できるものではない。またこのやり方はダンサーにとっても過酷な試練だろう。だからこの作品は過渡期の作品である。さらなる北村の試行錯誤とダンサーの成長とを待たなければならない。だが、その目標はすでに射程に入ったというべきだろう。
この作品は身体のパフォーマンスの他に、視覚的・聴覚的・空間的な仕掛けも売り物とされている。しかしこれらは衣装を含め、振付に見合うだけの努力がなされていたとは思えなかった。多彩な工夫は、それ自体が自立できるほど魅力的であるか、明確なコンセプトのもとに統一されていなければ、小細工の印象しか与えない。勝手を言わせてもらえば、北村にはエンタテインメントに陥ることを恐れるなと、スタッフには過激にすぎることを気遣うなと言いたい。