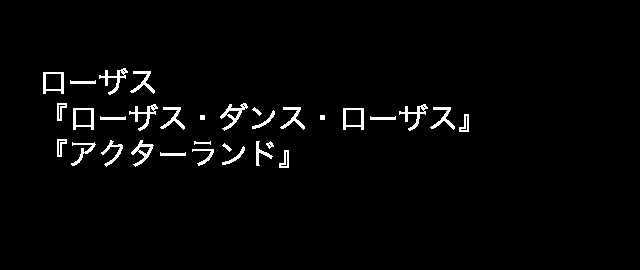スカートを脱いだ脚は美しいのに、なぜズボンを脱いだ脚は滑稽なのだろう。『アク ターランド』(一九九〇)を見ながらそんなことを考えていた。
『ローザス・ダンス・ローザス』(一九八三)は傑作である。たとえ初めの無音の四〇分が睡魔に付きまとわれるとしても、後の一時間は息もつかせぬ傑作である。たった四人の女性はみな似たような服装をしている。ゆったりとしたシャツ。動きやすそうなスカート。ソックスに踵の低い靴。それはいかにも無造作な女性の普段着だ。だが総ての衣装は文化的意味をもつとすれば、この選択は無造作ではない。古典バレエの王子や妖精の衣装は想像上の役柄を表現する。逆に抽象舞踊のレオタードは身体から意味を剥ぎとって単なる動きの媒体に還元しようとする。たいていの舞台はその中間にあって、特定の性質を強調する。レヴューの誘惑的衣装は性的身体を、ピナ・バウシュのドレスとハイヒールは文化的な「女らしさ」を表すだろう。だがこのローザスの無造作な衣装は、舞台にいるのが抽象的身体ではなく「女」であることを示しはするけれども、なんの「女らしさ」も意味しない。この意味と無意味の中間の曖昧な領域が、ケースマイケルのダンスの世界である。
『ローザス・ダンス・ローザス』は本人も認めるように対位法によって振付けられている。単純な動きと少ない語彙を反復とずらしによって構造化し、動きの力強さと速度によてめくるめくような効果を生み出している。時間は幾何学的に分割されてエネルギーの噴出と抑圧をコントロールし、そのジグザグの疾走を観客は息を切らせて追いかける。動きは単純であるからこそ力強くなり、語彙は少ないからこそ予期を外された観客の驚きは大きくなるのだ。だが対位法的構成や疾走する振付だけなら他にも例がある。ケースマイケルの独自性が現れるのは、ときおり動きが止む瞬間である。そのときダンサーたちは「動かない身体」になるのではない。あるときは脚を組み、あるときは肘をつき、「ポーズをとった女」になるのだ。反復される単位にすぎない音譜が突然意味の表情を帯びる。観客は驚いて眼差しを切り換える。しかし次の瞬間、再び身体は動きだし、抽象的な構造の中に編み込まれてしまう。けれども観客の眼は元に戻らない。四つの身体に微細な表情を見出そうとする。すると四人のほどけた髪が、激しく揺れているのに気がつくだろう。身体の動きは性的意味を抑圧している。しかし髪は意に反して「女」を現してしまう。そして四人の髪には長短があり、それが髪の表情に差異を与えていることに気がつけば、中の一人に東洋人を起用するのも意図的なものではないかと思えてくる。同じように脚を組んでも、その表情はわずかながら違うからである。こうして急展開する禁欲的身体の対位法と、その間から恰も意に反したものであるかのように零れ出て明滅する「女」の記号との組み合わせが、観客に眩惑的な効果を与えるのである。
先年横浜で上演された『ミクロコスモス』(一九八七)ではこの手法がさらに徹底された。「女」の記号は一層露骨になり、ふとミニスカートを捲くるダンサーたちは無意識に中年男を誘惑する少女のようだった。そして『アクターランド』である。女は五人になる。男も五人登場する(うち二人はヴァイオリニストとピアニストだが)。衣装もいろいろと着替える。ボディコン風スーツやハイヒールも使われる。道具立ては増えたが、仕掛けの基本は変わらない。滑らかではなく、破線のような動き。単純な語彙の反復とずらし。そして「女」の記号。たとえば五人の中で最も脚の長い女性ダンサーが、上半身にシャツ、脚の先にハイヒールをつけただけの姿で進み出る。観客の眼は脚に釘付けになる。観客は(少なくとも男どもは)その脚を美しいと思う。ダンサーは腰を振ったりして単純な踊りを見せる。だがそれはいわゆるセクシーな動きではない。「女らしさ」を動きには表さないのだ。むしろ「女」を意味することだけはしたくないとでもいうかのように無機的に動いてみせる。たとえ観客が「誘惑する性」を見出したとしてもそれは踊り手の意図に反したことであるかのように。魅力的な脚を見せてくれたケースマイケルに感謝しながら、しかしこれは余りにも露骨ではないかと私は思った。ダンサーは全ての視線が自分の脚に集中していることを知っているだろう。やがて今度は男のダンサーがシャツと靴だけの姿で現れる。だがその剥き出しの脚はけっして「男」の記号とならない。ただ間抜けなだけだ。ケースマイケルも彼をパロディにするほかはない。シャツの色は下品な赤であり、どた靴は紐がほどけている。彼が腰を振れば笑いが起きる。これもまた別の意味で観客へのサービスではある。だがギャグとしてさほど上等とは言いにくい。作者が「男」を扱いあぐねていることはよくわかったが、それにしてもこれは余計ではないかと私は思った。
『アクターランド』が『ローザス・ダンス・ローザス』からの前進であることは間違いない。だが周囲の反応を聞くと、評価は真っ二つである。「道具立てが増えて面白くなった」というものと、「そのために凡庸になった」というものと(私自身は後者に属する)。現代の舞踊界でケースマイケルは希有の創造力の持主だが、その才能は『ローザス・ダンス・ローザス』で早くも十全に開花してしまった。この奇跡的な傑作を乗り越えねばならぬという課題がどれほど困難なものか、私たち凡人には想像もつかない。ただ、彼女が立ち止まることに耐えられない作家であることは確かであり、それゆえ彼女が再び驚嘆すべき作品を携えて来日することを信じてもよいであろう。
Flying Cabinet