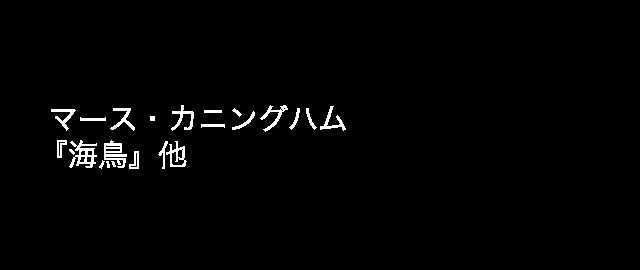最後の前衛
舞台では十余のダンサーが複雑な動きを展開している。その速度、強さ、いずれも訓練された身体だけがもつしなやかさを見せている。そこへ一人の老人が片足を引きずるようにして登場し、踊りはじめる。その動きは、七十五歳という年齢を考えれば驚異的だが、周りの若いダンサーたちとはむろん比べるべくもない。だが大劇場の観客の目は一斉に彼に釘付けになる。いささか不自由と見える動作の異質さが目立つからだろうか。年寄りのソロという物珍しさのせいか。いや、観客は多分動き以上のものをそこに見ているからだ。それは「マース・カニングハム」という現代芸術における一つの神話である。
二〇世紀の芸術は「前衛」と呼ばれる一連の運動によって主導されてきた。それは美術なり音楽なりの各ジャンルが、自らの定義を問い直し、玉葱の皮を剥くように一枚また一枚と慣習的条件をはぎ取ってゆく過程であった。舞踊が舞踊であるためのぎりぎりの条件が身体と動きであるなら、カニングハムほど純粋にその条件だけを追求した者はいない。半世紀に及ぶ彼の作業は、身体の動きの可能性を問い、確かめることだけに終始していた。この不器用なまでの一貫性は彼の志の強さと確信の深さを示している。最近彼は振付にコンピュータを使い始めたというが、作品の本質は何も変わっていない。変わったのは周囲である。ポストモダニズムは前衛に引導を渡したと言われ、そのポストモダニズムさえ今や死語となった。しかしカニングハムは相変わらずだ。いまや彼は「伝統的前衛」という逆説的存在となったのである。
七年ぶりの日本公演では八タイトルから成る三つのプログラムを全て近年の作品で編成した。これは瞠目すべきことである。七十歳を越えてなお新作を生み続ける精力にではない。このくらいの有名な舞踊団が八本も上演するのなら、一つや二つは古典となった代表作を入れて観客を喜ばせるのがふつうの編成であるだろう。たとえばエイリーなら必ず 『リベレーションズ』を入れる。だがカニングハムは最新作だけを見てくれというのだ。そして考えてみれば、百数十の彼の作品の中に、彼の代表作とか古典とか呼べるものは一つもない。一般に代表作になるには二つのケースがある。一つは特に出来のよい傑作である場合。もう一つはその作家の特徴が典型的に表れている場合。しかし、彼の作品は感動や美を基準にした価値尺度を受け付けないため、傑作の判定ができない。またどの作品にも確実にカニングハムの刻印が押されているため、とくに典型的といえるものがない。おそらくカニングハムは傑作を作ろうとしたことはない。ただ動きの問題を一つ一つ解決してきただけだ。過去の作品は振り返る必要もない足跡にすぎない。彼は同じ歩幅で歩いてきたし、今もなお歩き続けている。観客に報告すべきは最新の成果だけである。そしてカニングハムにとって一番重要なのは、常に次の作品である。
カニングハムは動きそのものに興味があると言う。身体ばかりでなく、木の葉のそよぎのような動きでさえ、いつまでも見ていて飽きないと言う。風に木の葉が揺れるとき、計画された構成もなく、表現された内容もない。偶然にまかせ、物理と生理の枠の中であらゆる動きをとるだけだ。それをただ見つめ続けることが、起承転結の構成に納得したり、激しい表現に共感したりするよりも面白いと思ったとき、カニングハムは自分の仕事を自覚したのだろう。彼は身体に可能な限りの動きを考案し、骰子で構成をきめて舞台に乗せる。背後には、舞踊と無関係に作られた音楽と美術とが在る。身体は、自然の中の木の葉のように、偶然の環境の中で偶然の指令に従って、生物的限界の中であらゆる動きをとる。観客は、この動きをただ見つめ続けるしかない。物語の展開にも感情の流れにも身を委ねることなく、ただ静かな眼となって、木の葉を見続けたカニングハムのように、動きの観察に耐える他はない。
不謹慎ながら私は、カニングハムの死後この舞踊団はどうなるだろうと考えた。常に新たな動きを提示することを存在理由にしている舞踊団は、新作ができなくなれば存続の理由がない。といって誰かがカニングハムの役割を継ぐことは意味がない。誰かの手法をそのまま別人が継承するのは「古典芸能」であって、もはや「前衛」ではないからだ。そして彼の成果は既に別人が別のやり方で受け継いでいる(たとえばフォーサイス)。むろんいくつかの舞踊団は、この偉才を記憶するために彼の作品をレパートリーに入れるだろう。しかし均質な彼の作品には代表作というものがないから、誰もが知る古典という作品はのこりそうもない。
ただジョン・ケージとの最後の共同作品である『海鳥』(一九九一)は異例だった。音楽は波の音を想わせ、衣装は鳥を想わせ、動きは鳥の動作を想わせた。しかも全体には叙情的な雰囲気さえ漂っていた。「海鳥」というタイトルで全てが理解できた気になってしまう。これは古典になるかもしれない、と私は思った。しかしこれがカニングハムの傑作としてさまざまな舞踊団で上演され、ひとびとがこれによってカニングハムを判断するならば、それは不幸なことだろう。カニングハムの偉大さは、まさに理解の対象となるような作品を否定することに一生を賭けたことにあるのだから。
ときおり彼が今シーズン限りで出演を辞めるという噂が流れる。最終日、ニューヨークの観客は総立ちで彼に別れの拍手を送る。だが次のシーズンになるとやっぱりカニングハムは登場するのだ。おそらく彼は動くことができる間は舞台に現れるだろう。私は想像してみる。いずれ木の葉が散るように、ある日自然の指令によって彼の身体は舞台に倒れるかもしれない。そのとき観客はどうするだろうか。たぶん私たちはみな立ち上がり、最後の前衛にいつまでも拍手をおくるだろう。