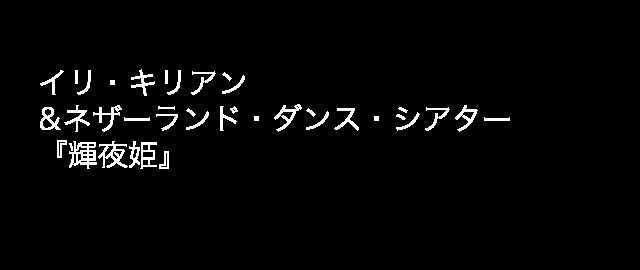白鳥・天女・宇宙人
「かぐや姫=宇宙人」説をキリアンに教えたのは石井真木らしい。
「性的な美女」に飽き足らない男たちの願望は「この世ならぬ美女」の物語を生み出した。物質を感じさせない白い肌。重力も捉えられない身の軽さ。そしてまだ男に汚されていない身体。こうして未知の美女実は白鳥の化身という物語が生まれる。人類学者が白鳥処女伝説と名付けたこの説話は世界中で見出されている。これをバレエにしたものが「白鳥の湖」であり、オペラにしたものが「夕鶴」である。鳥ではなく、人間の形のまま空から舞い降りれば、これは天女になる。たとえば美保の松原の羽衣伝説がそうだ。かぐや姫の物語もその一つに数えてよいだろう。ただ他の「この世ならぬ美女」たちが、結局は地上の男と恋に落ちたり結婚したりしているのに、かぐや姫だけは恋する男たちを不幸にするだけで、決して交わることなく立ち去ってしまう。だからかぐや姫はもっとも純粋な 「この世ならぬ美女」である。
十年ほど前、石井真木は上演のあてもないまま何かに駆られるようにバレエ音楽の構想を練ってい。それは打楽器と雅楽によってかぐや姫の物語を表すものだった。一九八五年スターダンサーズ・バレエがこれを『輝夜姫』として上演し、三年後キリアンがネザーランド・ダンス・シアターのために新たな振付を行った。ヨーロッパ各地で好評を得たというこの作品が日本に登場するにはさらに五年を要した。タイトルはそのまま『KAGUYAHIME』である。
キリアンの卓抜な構成演出力は、この世ならぬ美女をめぐるおとぎ話を、スケールの大きなスペクタクルに仕立てあげた。垂直に伸びる竹林は水平に揺れる鉄梯子の群に置き換えられ、不安の中で輝夜姫はこの世に現れる。白い肌どころか夜さえも輝かせるという彼女の身体は銀色のタイツで表される。まさか身体に電球を巻き付けるわけにもいかない。石井の作曲は輝夜姫のために雅楽を、地上の人間には打楽器を割り当てた。さらに体制的貴族には西洋の打楽器、農民たちには日本の打楽器を割り当てた。キリアンはこの対立を衣装でさらに明確にした。ダンサーばかりか打楽器奏者まで舞台に上げ、左右に分けた上一方に黒衣、他方に白衣を着せた。そして帝が登場すると舞台は権力の象徴たる金ピカの布に覆われる。何てわかりやすいんだろう。ところで雅楽奏者はといえば、あの豪奢で非日常的な伝統衣装で、周囲のけたたましい騒ぎをよそに悠揚迫らぬ演奏を行う。初めて見る西洋人には、この扮装と音楽はほとんどSFの世界かもしれない。
戦いのシーンはウェストサイド・ストーリーを彷彿とさせる図式的肉弾戦で表現され、キリアンの振付術がブロードウェイでも通用することを示した。懐かしい盆踊りの鳴りひびく祝宴のシーンでは、バレエ風フォークダンスという平凡な方法を洗練されたショーに仕上げて、凡庸な振付家とは一線を画した。だがキリアンが一番苦労したのは輝夜姫の動きだろう。世俗の人間たちは何の新鮮味もない凡俗な動きでもよい。しかし輝夜姫はそうはいかない。なにしろ「この世の人」ではないのだから。さて、その結果だが、この動きを音楽なしで見たら、昔ながらのモダンダンスとどこが違うのかといった話になったかもしれない。だが綿々とうねり続ける雅楽の音楽と共に聞くとき、確かに輝夜姫だけには、打楽器で踊る周りの人間とは違った時間が流れていた。工夫は、動きの形ではなく、動きの時間にあった。メトロノームによって刻まれる時間ではなく、波のようにたゆたう時間である。
竹取物語によれば、かぐや姫が月に帰るとき、あたりは昼間をしのぐ光に満たされたという。はたして舞台は光に満ちた。いや舞台ばかりか光の洪水は客席にまで溢れかえった。そのただなかを輝夜姫は歩み、光源の中に消える。私はこれを以前にも見たことがあるような気がした。のっぺりとした宇宙人が光輝く宇宙船の中へ消える。
「そうだ。これは『未知との遭遇』のラストシーンだ!」
私は舞台の上で異彩を放っていた日本車の意味をやっと理解した。あれは宇宙船だったのだ。