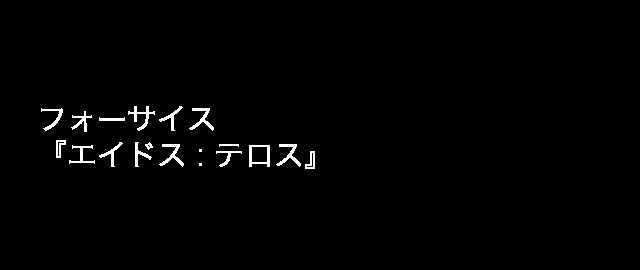桜の森の蜘蛛の糸
フォーサイスの舞台はいつも刺激に満ちていて、終演後は混乱した頭を鎮めるために居合わせた誰かと話したくなる。不幸なことに上野の東京文化会館の近くには手頃な店がなく、いつも場所定めに苦労するのだが、四月初旬の今回は違った。誰かが「花見をしよう」と言ったのだ。それはぴったりの思いつきだった。満開の夜桜の下でそれぞれのグループが自分たちの宴会に熱中している光景は、美しい空間の中で銘々のダンサーが自分だけの世界を勝手に動いているかのようなフォーサイスの舞台になんと似ていることだろう。
日本人・韓国人・ベルギー人からなる私たちは公園の隅で今見たばかりの舞台について意見を交わし始めた。解釈の糸を縒り合わせて一つの結論を紡ぐためではない。結論はフォーサイスを貧弱にしてしまう。むしろどれほど多くの要素があり、どれほど多様な解釈が可能かを知るために他人の言葉を聴きたいのだ。彼の作品は複雑巨大な事件であって、目撃者によって見たものが違う。その豊かさを味わうためには互いに手に入れたものを交換しなければならない。そしていつも私たちは、むやみに広がった解釈と感想の網の目にますます頭を混乱させて帰ることになるのだ。
興味深いことに今回は、誰もが同じ印象を受けたことがあった。それは登場人物たちがみな死者だということである。フォーサイスの作品で主役らしき人物がいることは稀なのだが、『エイドス:テロス』ではダナ・カスパーセンだけがはっきり他のダンサーたちと区別されている。いわば彼女だけが人間でほかはみな亡者に見える。しかし彼女が「こちら蜘蛛の声・・」と独白を始めると、どうやらこれも冥界をさまよう死者らしいとわかる。この蜘蛛女は何者なのか。オルフェウスを待っているエウリディーケだろうか。初演時のプログラムには、冥界の王ハデスにさらわれてその王妃となり亡者に君臨したペルセフォネの物語が引用されているから、ペルセフォネなのかもしれない。いや、この作品を作るとき亡妻のことが念頭にあったと、ぽろりとフォーサイスが洩らしたというから、実は彼の愛した妻なのかもしれない。いずれにせよ、フォーサイスにはしてはわかりやすい設定がここにはある。けれども、むろん物語を語ることには彼の興味はない。この物語は、いわば舞台でおきる出来事の装飾音のようなものだ。あるいは、理解できる物語がなければ落ち着かない観客のためのサービスのようなものだ。
サービスはダンスにもある。三幕からなるこの作品の、二幕の終りに、突如優雅なワルツが始まる。男も女も長くて軽いスカートの裾をひるがえしながら、旋回しつつ行き交う。それまでの観客を拒絶するような舞台が、一転してノスタルジックな優しさに満たされる。私たちは陶然として、この時間がこのまま永遠に続いてほしいと願う。これは多分、古典的舞踊を愛する観客のためのフォーサイスからの贈り物なのだ。
しかし全体としてフォーサイスがやっているのはおそるべき実験である。これまでのダンス、いや芸術作品の基本ルールを否定してなお芸術が成立するための新しい方法を開発しようとしているのだ。そしてこの『エイドス:テロス』は、それが確かに成功したことが誰の眼にもわかるという、とんでもない作品なのである。近代の芸術観では、芸術作品の条件は「多様の統一」であった。むろん要素の多様と全体の統一とは矛盾する条件だ。そこで芸術家は、あらかじめ要素を慎重に選択しなければならず、全体を綿密に構成しなければならないとされた。ところがフォーサイスは、要素の選択をダンサーの即興にまかせ、構成を偶然にまかせるのだ。舞台は焦点もなく拡散し、進行は不意に幕が下りて終わる。翌日同じプログラムを見に行けば、進行の大枠はともかく、細部のダンスはまったく別物になっている。ふつうこれでは作品にならない。しかし『エイドス:テロス』は傑作である。奇跡が起こっているのだ。
近代芸術は創造や構成を制作原理としてきたが、これに反逆する前衛芸術は破壊を原理としたり、そもそも原理というものを否定したりしてきた。ところがフォーサイスは「消滅」という言葉を用いる。これは破壊でも否定でもない。普通とは逆方向で制作の原理を作ったのである。たとえば彼は自分のダンサーたちに、動きを「置く」のではなく「離れる」ことを求める。ふつうダンサーが踊るときは、まず頭の中に振付家から教えられた動きの形を思い描き、それを決められた時間と空間の中に置いてゆく。始められた動きは、予定された通りに完結されなければならない。だがフォーサイスが求めているのは、既に始められた動きを完結させるのではなく、そこから離れてゆくことである。ダンサーが意識しなければならないのは、これから実現すべき動きではなく、捨て去るべき動きである。ある動きを捨てるだけなら、静止するなり目茶苦茶に動くなりすればいいと思うかもしれない。そうはさせないためにフォーサイスは一定の枷をはめる(たとえば腕を九十度曲げたままで動けとか)。困難な条件の中で動きながらダンサーは常に自分の全身を意識しなければならない。いったい自分は今どんな動きに向かっているのか、それを実現してしまわないためにはどうすればよいのか。アクセルが働けば直ちにブレーキがかけられ、直線の動きにはカーブが割り込み、滑らかな動きをとろうとする関節と筋肉に対しては絶えずずらしと崩しの圧力が加えられてゆく。このようなダンスを行う身体は決して美しい形をつくることはない。また何かを表現することもない。ただ身体の内に満ちている恐るべき力と緊張だけは観客にも感じられる。というより、そこにはあらゆるイメージや目的から離れ、なおかつ生きている身体がある。それは日常生活にも、たいていのダンスにも見られないものだ。このような身体を維持するのは、実はむつかしい。フォーサイスはさまざまのルールや偶然を利用して、これを維持する。こういう舞台は突然幕を下ろすよりほかに終わらせようがない。
古代ギリシア語の「エイドス」と「テロス」は今日哲学用語としてのみ生き残り、ふつう「形相」と「目的」と訳される。たとえば職人が椅子を作るとき、かれはまず作ろうとする「椅子」の完成した形を思い浮かべる。これが「形相」である。次に彼は材料を集め作業を始める。その作業はすべて椅子の完成という「目的」に向けられている。つまり形相と目的とは、何か物を(芸術作品を含めて)作るさいの条件なのである。古代の哲学者はこれを「形相因」と「目的因」と呼んだ。しかしフォーサイスがやっているのは、まさに形相と目的なくして作品を作ることである。ではタイトルの「エイドス:テロス」とは反語なのだろうか。いや「エイドス」には見える物、像といった意味があり、「テロス」には完了、死という意味がある。この舞台は確かに見える物はある。というより、何の表現もない舞台は、ただ見えている物を見続けるほかに観客にできることはない。そしてまた完了もある。それは作品が完成したがゆえの完了ではなく、突然の死のような強制終了なのだけれども。とすれば、この作品の制作原理はエイドスなきエイドス、テロスなきテロスである。フォーサイスが創造したのは作品そのものというより、この新しい制作原理なのだ。
この舞台を見続けるのは異様な体験である。目の前に展開されるのは洗練された支離滅裂、流れるような混乱だ。その中を流星のように悲痛な蜘蛛女や優雅なワルツが通り過ぎる。それは夜の公園で時折流れる酔客の奇声や唱歌を聞きながら、ひたすら降りしきる桜を見続けるのに似ていたような気がする。