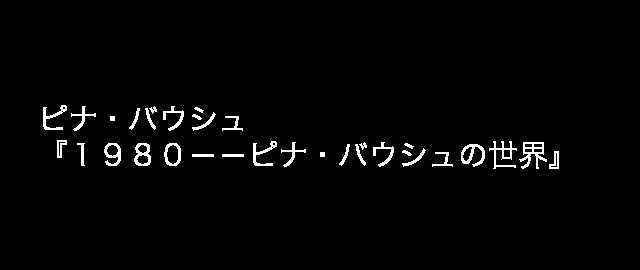着飾った孤独
緑の芝生は、西欧文明の生み出した最も美しい人工環境の一つである。広い舞台の全面をその芝生が覆うさまを想像してみよう。人工芝ではない。土がつき、露に濡れ、草いきれする本物の芝である。目に鮮やかな緑はどれほど豪奢であることだろう。この芝生の上で演じられる劇は、鮮烈な緑のおかげで、悲哀はいっそう深く、皮肉はいっそう辛辣になるだろう。さて想像をやめて現実を見よう。舞台一面に広がる芝生は埃っぽい古畳のように白茶けていた。東京の四月は寒すぎたのだ。「緑のはずだったのに」とピナは嘆いた。豪奢な背景を失った公演は音楽なしの『白鳥の湖』のようにいささか索漠たるものとなった。だが仕方あるまい。この手の誤算はよくあることだ。それにピナの官能的な魔術に巻き込まれにくくなった分だけ、ピナの世界がはっきり見えたような気もする。
舞台の奥では一頭の剥製の鹿がこちらを見つめている。こいつだけは冷静に、これから起こる悲喜劇の一部始終を見届けるのだろう。舞台の中央にスーツの青年が金属の大鉢を抱えて現れる。彼は椅子に座り、背中を丸めてスープを口に運びながら呟く。一杯目「ママのために」。二杯目「パパのために」。彼の成長は幼児のまま止まったのだろうか。それともしあわせだった幼児期の夢を見たいのだろうか。突然音楽が鳴り渡り、着飾った紳士淑女が一列になって現れる。彼らは官能的に我が身を撫で回し、観客に微笑を投げかけつつ行進する。夢が始まったのだ。やがて芝生の上ではパーティーや遊びや日光浴や脚線美のコンテストなどが繰り広げられることになる。だがそれらはいずれも人々が普通期待するような楽しいものではない。たとえばある女性は独り蝋燭に火をつけて歌う。「ハッピー・バースデー・トゥ・ミー」。また別の女性は語る。「今日パーティーを開きました。たった三人の小さなパーティーでした。参加者は、私と、自分と、私自身でした」。楽しげな歌とともに始まったハンカチ落としは、これから盛り上がろうという矢先に一人二人と立ち去り、熱中している者は取り残される。人と人との絆を確かめる場であるはずの パーティーはここでは孤独を確かめるための機会でしかない。パーティーだけではない。断ち切られた人間関係のさまざまな形が、ほとんど象徴ともいうべき単純な断片となって提出される。たとえば一人の女が「抱き止めて、抱き止めて」と叫びながら男に向かって走り、男の名を呼んで飛びつく。女の四肢は男を強く抱き締めようとするのだが、男は無表情に立っているだけだ。女は再び「抱き止めて」と叫びつつ別の男に向かって走り、その名を呼んで飛びつくのだが、これも同じことだ。女はまた別の男に向かって走り出さねばならない。あるいはこんな場面もある。去り行く者に他の全員が一人ずつ心からの別れを告げる。その言葉は少しずつ違うのだけれども、十人も聞いているとうんざりして皆同じ紋切り型に思えてくる。こうして他人に向かう言葉と行為はたっぷりあるのだけれど、心は決して届かないし、身体は決して抱き止められないのだ。
特定の他人ではなく、社会へと自分を投げかける者もいる。市場社会における成功者とは自分を高価な商品として売ることに成功した者のことである。能力を競うのも美貌を競うのも、市場原理に基づく商品の売り込みという点では変わりがない。そこで芝生の上では「コーラス・ライン」のように男女が一列に並び、脚をむき出して売り込みを競う。はじめは能力や容姿が競われる。やがてプライバシーが、ついには不幸な人生そのものが商品としてさらされる。成功するためには全てを売り渡さねばならない。この無残な競争を観客は笑って見ている。観客とは消費者、つまり商品の買い手だから。
人が着飾るのは何のためか。他人に見せるためだ。集まるのは何のためか。他人との絆を結ぶためだ。しかし全ての努力は孤独を確かめることにしかならない。自分の商品化の成功は、自分という存在を気まぐれな消費者の手に委ねることでしかない。こうして登場人物たちは結局みな同じ言葉を呟いているように見える。「人生は緑のはずだったのに」。
一九八〇年、ピナ・バウシュは人生の伴侶を失った。この作品はその直後に作られたものである。鹿のように醒めた諦念と、にもかかわらず希望を捨てぬ者への共感とがここにある。その最後の台詞はこうである。「誰かいるかい?」